
2019年における働き方改革関連法の施行により、フレックスタイム制のルールが一部変更されました。
具体的には、自由に労働時間を調整できる期間(=清算期間)について、最大1ヵ月から3ヵ月まで延長することが可能になりました。しかし、延長するためにはいくつかの決まりがあるため、ルールを十分に理解したうえでフレックスタイム制を導入・運用することが大切です。
今回は、フレックスタイム制の「清算期間」に着目して、労働時間の考え方や実務上のポイントについて解説します。
フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説
フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. フレックスタイム制の清算期間とは

清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が働く時間を調整できる期間のことです。労働者は、清算期間の中で定められた総労働時間に達するように日々の労働時間を調整します。
1-1. 清算期間は最大3ヵ月まで
2019年の法改正までは、フレックスタイム制の清算期間は最大1ヵ月まででしたが、同年4月以降は、最大期間は3ヵ月となりました。3ヵ月に延長することで、より各個人の都合に応じた労働時間の調整が可能です。
たとえば、清算期間が7月~9月の3ヵ月のAさんに小学生の子どもがいたとします。8月は子どもが夏休みで家にいる時間が長いため、7月と9月は長めに働き、8月は早めに退勤することで、子どもと過ごす時間を増やすことができます。
このように、3ヵ月の清算期間とすることで、従来よりも柔軟に労働時間を調整できるでしょう。
1-2. 過重労働を防ぐような労働時間の設定が必要
先ほど、清算期間を最大3ヵ月まで延長することで、各個人の都合に応じて働き方を調整できるメリットがあることを解説しました。しかし、同時に労働時間が一定期間に集中しすぎて健康被害が高まるリスクもあるため、清算期間が1ヵ月を超える場合には、以下の2つの条件を満たす必要があります。
①清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
②1ヵ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
このルールがあるため、繁忙期・閑散期の差が大きかったとしても、繁忙期に偏った長時間労働をすることができない仕組みになっています。
フレックスタイム制の清算期間を1ヵ月を超えて設定する場合は、労働時間の上限に注意しましょう。
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
1-3. 清算期間が1ヵ月を超える場合は、労使協定の届出が必要
清算期間が1ヵ月を超える場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。清算期間が1ヵ月以内の場合、フレックスタイム制を導入するためには
- 就業規則などへの規定
- 労使協定で所定の事項を定めること
の2点が必要でした。しかし、清算期間を延長する場合は、この2点に加えて労使協定の届出が必須になります。違反すると30万円以下の罰金が科せられる場合もあるので、清算期間を決める際は注意しましょう。
【ひな形付】フレックスタイム制の労使協定の結び方と届け出が不要なケースを解説
2. フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月以内の場合

フレックスタイム制では、まず清算期間中の法定労働時間の総枠を計算して、その中で総労働時間を決定します。この法定労働時間の総枠は、下記の計算式で算出しましょう。
【清算期間の暦日数 ÷ 7】×【40時間(1週間の法定労働時間)】
たとえば、清算期間の暦日数が31日の場合、下記のように計算します。
法定労働時間の総枠 = 31日 ÷ 7 × 40時間 = 177.1時間
法定労働時間の総枠は、下表の通り、清算期間の暦日数によって異なるため注意しましょう。
| 清算期間 | 法定労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
| 7日 | 40.0時間 |
この総枠に収まるように、総労働時間を設定する必要があります。
3. フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月を超える場合

清算期間が1ヵ月を超える場合も、基本的に計算方法は一緒です。実際に法定労働時間の総枠を計算すると次の表のようになります。今回は3ヵ月の場合を掲載します。
| 清算期間 | 法定労働時間の総枠 |
| 92日 | 525.7時間 |
| 91日 | 520.0時間 |
| 90日 | 514.2時間 |
| 89日 | 508.5時間 |
しかし、清算期間が1ヵ月を超える場合、この法定労働時間の総枠のみを守れば良いわけではありません。先程も解説した通り、法改正では過度な労働を防ぐための下記のルールが新設されました。
①清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
②1ヵ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
フレックスタイム制で1ヵ月を超えて清算期間を設定する場合、これらの規定を遵守する必要があります。
フレックスタイム制の残業時間の計算は複雑で、文面だけだと理解しにくいという方もいるのではないでしょうか。そのような方のために、当サイトでは、フレックスタイム制の概要から残業の考え方まで、わかりやすく図解した資料を無料で配布しております。フレックスタイム制の清算期間の仕組みや残業代計算の方法を正確に把握したいご担当者様は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。
4. フレックスタイム制の清算期間において過不足が出た場合の考え方

ここまで、清算期間の仕組みやフレックスタイム制の新しいルールについて説明しました。
次に、フレックスタイム制において残業や労働時間の不足が発生した場合の考え方を解説します。
4-1. 清算期間が1ヵ月以内で過不足が発生した場合の考え方
総労働時間より実労働時間が長かった場合は残業となるため、超過分の賃金を割増して支払います。一方、総労働時間より実労働時間が短かった場合は、以下のいずれかの方法で対応しましょう。
- 不足時間分を賃金から控除する
- 不足時間分を翌月の総労働時間に加算して処理する
上記のいずれかの方法で、不足分を相殺します。なお、翌月に不足分を繰り越す場合、当該清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠におさまっていなければならないので注意しましょう。
4-2. 清算期間が1ヵ月を超える場合に過不足が発生した場合の考え方
では、清算期間が1ヵ月を超えた場合、時間外労働はどのように考えるのでしょうか。
まずは、不足分についてです。総労働時間より実労働時間が短かった月は、複数月内での相殺が可能なため、直ちに賃金から控除しなくても問題ありません。複数月内で総労働時間と実労働時間を比較して不足が出ないように調整しましょう。
一方、超過分は考え方がやや複雑になります。清算期間が1ヵ月を超える場合、総労働時間と実労働時間の過不足は、月を跨いでの処理が可能です。総労働時間より実労働時間が長くても、以下の2つの条件を満たす場合、時間外労働(法定外残業)には該当せず、清算期間内で調整することができます。
①清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
②1ヵ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
つまり、上記の条件を満たしていれば時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、時間外労働に対する割増賃金は、清算期間全体だけでなく、各月ごとにも算出する必要があります。そのため、清算期間が1ヵ月を超える場合は以下のように計算します。
①各月内で週平均50時間を超過した時間数を求める
②清算期間内で法定労働時間を超過した時間数から①の時間を差し引いた時間数を求める
③②で求めた時間数に割増賃金を加味した残業代を計算する
少し複雑ですが、ルールをしっかりと把握しておきましょう。なお、フレックスタイム制の残業代の計算方法はのちほど解説します。
フレックスタイム制で残業代は減るの?残業時間や残業代の計算方法を解説!
4-3. 総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまう場合の対処法
法改正前は、完全週休2日制の場合、1日8時間労働だとしても曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうことが起こり、問題視されていました。
そのため現在は、週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者を対象に、労使協定によって、清算期間内の所定労働日数×8時間を労働時間の限度とすることが可能になりました。
限度の範囲内であれば、対象期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えること自体には問題ありませんが、労使協定は必須となるため、注意しましょう。
5. フレックスタイム制で残業が発生した場合の計算方法

フレックスタイム制は通常の勤務とは異なり、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働が残業にあたるとは限りません。また、清算期間が1ヵ月以内か1ヵ月を超えるかによって、残業時間の計算方法も異なるので注意が必要です。
5-1. 清算期間が1ヵ月以内の場合の残業時間の計算方法
清算期間が1ヵ月以内の場合は、残業時間の計算方法は非常にシンプルです。この場合、残業時間は、清算期間中の実労働時間から総労働時間(所定労働時間)を引くことで求められます。
その結果、法定労働時間の総枠を超えた部分は時間外労働(法定外残業)となり、割増賃金の支払いが必要です。なお、法定労働時間の総枠を超えない部分であっても、総労働時間を超えていたら、法定内残業代の支払いが必要になるので注意しましょう。
5-2. 清算期間が1ヵ月を超える場合の残業時間の計算方法
清算期間が1ヵ月を超える場合も、清算期間中の実労働時間から総労働時間を引くことで残業時間は計算できます。清算期間全体で、法定労働時間の総枠を超えた実労働時間が時間外労働(法定外残業)となります。また、清算期間1ヵ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間も時間外労働に該当し、割増賃金の支給が必要になるので注意しましょう。
5-3. 【具体例】清算期間が1ヵ月を超える場合の残業時間の求め方
ここからは、具体例を交えて清算期間が1ヵ月を超える場合の残業時間の求め方を紹介します。清算期間を3ヵ月として考えてみましょう。なお、総労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間の総枠と同じと仮定し、法定内残業代は発生しないこととしています。
実労働時間が週平均50時間を超えているか確認する
まずは、清算期間における各月の実労働時間が週平均50時間を超えているか確認しましょう。各月の実労働時間は下表の通りとします。
| 労働月 | 実労働時間 |
| 4月 | 230時間 |
| 5月 | 170時間 |
| 6月 | 150時間 |
| 合計 | 550時間 |
たとえば4月の場合、週平均50時間に収めるためには、月の実労働時間を214.2時間に収める必要があります。計算式は以下の通りです。
「50時間」×「各月の暦日数 ÷ 7」=「週平均50時間となる月の実労働時間」
4月の暦日数は30日であるため、以下のように計算できます。
50時間 × 30日 ÷ 7 = 214.2時間
5月と6月についても同様に計算すると、下表のようになります。
| 労働月 | 週平均50時間となる月の実労働時間 |
| 4月 | 214.2時間 |
| 5月 | 221.4時間 |
| 6月 | 214.2時間 |
上記の表をもとに、4〜6月の実労働時間が週平均50時間を超えているかを確認します。
| 労働月 | 実労働時間が週平均50時間を超えた労働時間 |
| 4月 |
15.8時間(230時間 – 214.2時間) |
| 5月 | 0時間(170時間 – 221.4時間) |
| 6月 | 0時間(150時間 – 214.2時間) |
つまり、週平均50時間を超えたのは4月のみとなり、残業時間は15.8時間となります。
実労働時間が法定労働時間の総枠を超えているか確認する
次に、清算期間中の実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えているかを確認します。
4月~6月の暦日数の合計は91日であるため、法定労働時間の総枠は以下の計算式を用いて求めましょう。
「法定労働時間の総枠 = 40時間 × 91日 ÷ 7日 = 520時間」
清算期間中の実労働時間が法定労働時間を超えているかは、下記により求められます。
「清算期間の実労働時間」-「週平均50時間を超えた労働時間」-「清算期間の法定労働時間の総枠」=「残業時間」
実際に計算すると、残業時間は24.2時間となります。
550時間 – 15.8時間 – 520時間 = 14.2時間
上記の時間は、最終月の残業時間として集計します。
残業時間を合計する
最後に、これまでに算出した残業時間を合計します。
- 週平均50時間を超えた時間:15.8時間
- 清算期間中に法定労働時間を超えた実労働時間:14.2時間
- 週平均50時間を超えた時間 + 清算期間中に法定労働時間を超えた実労働時間:15.8時間 + 14.2時間 = 30時間
| 労働月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 残業時間 | 15.8時間 | 0時間 | 14.2時間 |
今回のケースでは、清算期間中の残業時間は30時間となり、この時間に対しては時間外労働の割増賃金の支払いが必要です。
このように、清算期間が3ヵ月を超える場合、残業時間の計算方法はかなり複雑でミスが生じやすくなります。そのため、計算方法を正しく理解し、正確に割増賃金を支給しなくてはなりません。
フレックスタイム制の導入を検討する場合は、労働時間の管理や給与計算の方法を見直すとよいでしょう。
6. フレックスタイム制の清算期間に関する注意点

フレックスタイム制の清算期間については、以下のような点に注意しましょう。
6-1. 適切な勤怠管理をする必要がある
フレックスタイム制に限りませんが、従業員の勤怠状況はしっかりと管理しなければなりません。とくにフレックスタイム制のように従業員ごとの労働時間が異なる仕組みを導入すると、勤怠管理が複雑化します。また、前述のように残業計算の方法も複雑です。
紙のタイムカードでは管理が難しく、担当者の負担が増加するケースも多いため、必要に応じて勤怠管理システムの導入を検討しましょう。勤怠管理システムを活用すれば、労働時間や残業時間の集計を自動化したり、給与計算システムと連携したりして、業務を効率化することが可能です。
6-2. 繁忙期だけ清算期間を3ヵ月とすることもできる
繁忙期だけ、清算期間を3ヵ月に設定することもできます。たとえば、通常は清算期間を1ヵ月としておき、一定期間のみ、清算期間を延長することも可能です。
ただし、清算期間を頻繁に変更すると従業員が混乱したり、勤怠管理が複雑化したりします。事前に労使間で協議をおこない、ルールを明確にしたうえで制度を導入しましょう。また、制度に合わせて労使協定を締結することや、就業規則を変更することも重要です。
6-3. 清算期間の途中で清算が必要なケースもある
フレックスタイム制においては清算期間が終了したタイミングで、労働時間や賃金を清算するのが基本です。ただし、1ヵ月を超える清算期間を設定している企業において、従業員が清算期間の途中で退職した場合などは、そのタイミングで清算しなければなりません。
清算期間中の労働時間を平均して、週40時間を超える部分については割増賃金も支払う必要があるため注意しましょう。
7. 自社に合わせたフレックスタイム制の清算期間を設定しよう
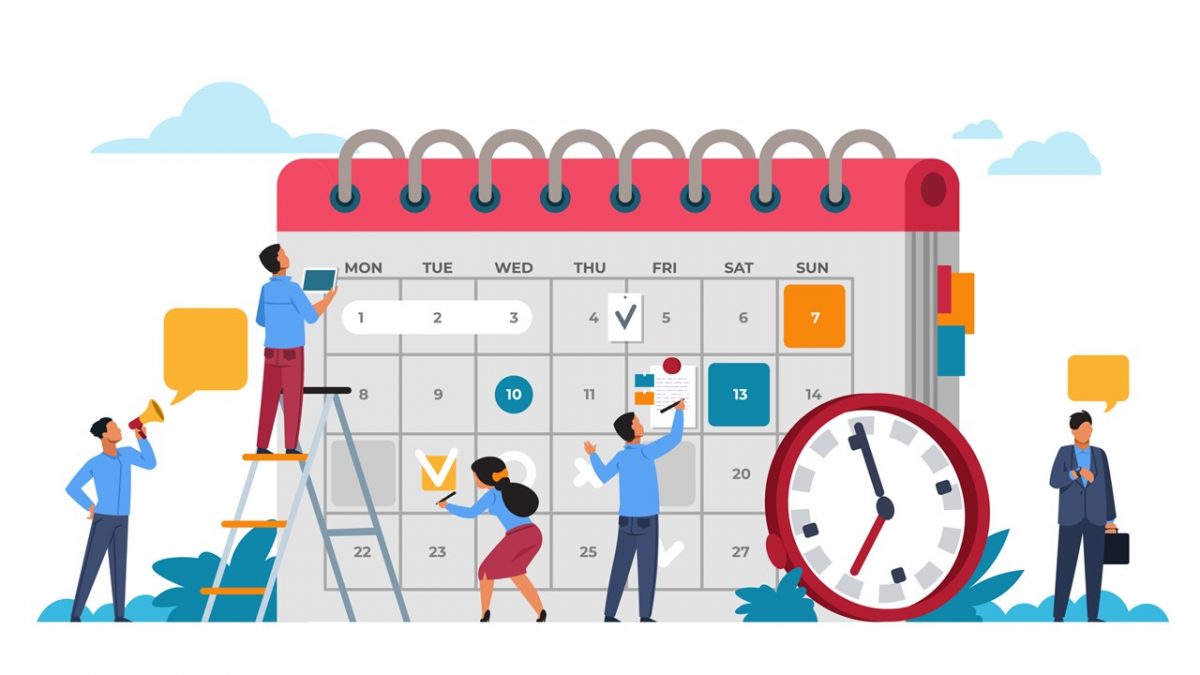
今回は、フレックスタイム制における清算期間について解説しました。法改正により、より自由な働き方ができるようになりましたが、その分必要な手続きが増えたり、残業時間の計算が複雑になったりと、運用が難しくなるといった側面もあります。清算期間が1ヵ月を超えると、運用方法がより複雑になるため注意しましょう。
また、自社に適したフレックスタイム制を取り入れれば、従業員のパフォーマンスが上がることや優秀な人材が集まることなどが期待できます。ぜひ、本記事を参考に、自社の勤務形態を見直してみましょう。また、同時に労働時間の管理や給与計算の方法も検討してみてください。








