
社会の変化により目標管理(MBO)のトレンドは変化しており、アップデートしなければ時代遅れや意味ないと言われることがあります。この記事では、なぜ目標管理がくだらないと言われるのか、その理由や背景を解説します。また、目標管理がくだらないと言われないための対策や、目標管理に役立つフレームワーク・システムも紹介します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 目標管理がくだらないと言われる理由
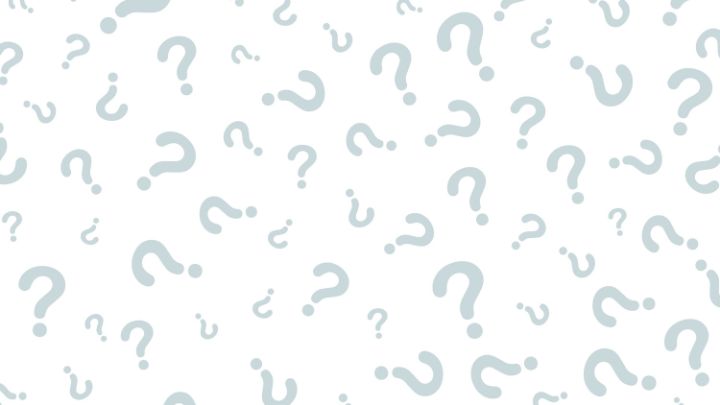
目標管理(MBO:Management By Objectives)とは、従業員が決めた個人やチームの目標の進捗や達成度によって評価する人材管理手法の一つです。目標管理は組織や個人の目標を達成するために重要な役割を果たします。
しかし、会社から一方的に従業員の目標を設定している場合や、達成可能性を考慮していない非現実的な目標を設定している場合、目標が正しく機能せず、その管理も形骸化し、目標管理がくだらないと言われてしまいます。ここでは、なぜ目標管理がくだらないと言われるのか、その理由について詳しく紹介します。
1-1. 目標をトップダウンで決めることが多い
目標は従業員自身で決めることで、責任感が生まれ、成し遂げようとモチベーションが高まります。しかし、目標をトップダウンで決めることもまだまだ少なくありません。目標に従業員の意思が反映されていなければ、当事者意識が生まれず、仕事に対する意欲も高まりません。
また、目標を押し付けられたと感じると、会社に対する不満につながり、生産性の低下や離職率の上昇の原因にもなります。このように、目標管理がくだらないと言われる理由の一つとして、トップダウンにより目標が設定され、従業員の意見は含まれていないことが挙げられます。
関連記事:目標設定の押し付けは従業員のモチベーションを下げる!よい目標設定の特徴やポイントを解説
1-2. 目標に対するプロセスが非現実的になっている
目標を立てても、行動に移し、実現しなければ意味を成しません。しかし、目標を立てたことに満足してしまい、その行動プロセスが無視されていることも多いです。目標に対する行動プロセスが非現実的だと、行動を起こそうとならず、目標達成に近づきません。このように、目標が単なる形式的なものとなり、目的を果たすことに役立っていないために、目標管理がくだらない、意味ないと言われることがあります。
1-3. 運用管理に手間がかかる
目標を立てたら、進捗状況を把握し、常に達成状況をチェックすることが求められます。運用管理に時間や手間がかかってしまい、目標達成に向けた行動の時間が削られ、目標管理が意味ないものとなっているケースもあります。目標管理がくだらないと言わせないためにも、管理を効率化する仕組みを構築することが大切です。
1-4. 定性的な目標が評価されにくい
目標は数値化して定量的に管理することで、進捗状況が把握しやすくなり、客観的に評価もしやすくなります。営業職やサービス職などで売上や利益を目標に設定すれば、数値化して目標を設定することが可能です。一方、事務職の場合、定量的な目標を設定するのが難しいケースもよくあります。
そのため、定性的な目標を設定して、目標管理することもあります。しかし、定性目標を達成したけれど、評価基準が曖昧なため、正しく評価されず、目標管理がくだらないと言われてしまうこともあります。
1-5. 目標を修正する機会がない
近年ではビジネス環境が目まぐるしく変化しており、時代や社会の移り変わりとともに、目標が変わってもおかしくはありません。しかし、半年・1年単位で目標管理がおこなわれている場合、途中で目標を修正したいと思っても、人事評価につながるため変更できないケースがあります。このような場合、目標を修正するまでに時間を要し、自分の成長につなげられず、目標管理がくだらないと言われる原因になります。
2. 目標管理が意味ない・時代遅れとなっている背景

目標管理がくだらないと言われる大きな理由の一つに、目標管理が時代遅れ、意味ないものとなっていることが挙げられます。ここでは、目標管理が意味ない・時代遅れとなっている背景について詳しく紹介します。
2-1. 多様な働き方の推進
昨今では働き方改革の影響により、裁量労働制やフレックスタイム制、時短勤務、ダブルワークといった多様な働き方が推進されています。また、ネットワーク技術の発展により、テレワークが社会に定着しつつあります。
オフィスに出社することが一般的であった従来であれば、紙の目標管理シートでも問題なく管理することができました。しかし、出勤・退勤時間や働く場所が多様化している現代では、紙の目標管理シートでは共有が難しく、運用管理に時間や手間がかかり、時代遅れになりつつあります。
2-2. 考え方や価値観の多様化
最近ではグローバル化やダイバーシティ推進により、多様な考え方や価値感を持った労働者が組織に集まっています。年功序列・終身雇用が当たり前であった時代であれば、トップダウンによる画一的な目標管理でも、十分に評価や育成をおこなうことができました。
しかし、人材が多様化している現代では、従業員一人ひとりのキャリアやなりたい姿にあわせた目標管理が求められています。そのため、従来の組織が一方的に従業員の目標を定めるやり方は、意味ない・時代遅れと言われています。
2-3. ビジネス市場の急速な変化
近年では人工知能(AI)やIoTなどのIT技術の進歩が目覚ましく、ビジネス市場は急速に変化しています。このような時代では、変化に対して柔軟に対応することが求められます。そのため、リアルタイムで評価する仕組みがトレンドとなりつつあり、従来のような時間をかけて目標達成を目指す管理方法は時代遅れとなっています。
関連記事:評価制度のトレンド10選!各手法の特徴を詳しく紹介
3. 目標管理をする意味や目的とは?

目標管理はくだらないと言われることがよくありますが、目標管理自体にはメリットも多くあります。ここでは、目標管理をする意味や目的について詳しく紹介します。
3-1. 経営理念を浸透させられる
目標管理を実施する際、組織の求める姿を事前に伝えることで、従業員は会社からどのようなことが求められているのか理解したうえで、目標を設定するようになります。これにより、経営理念の浸透につながり、すべての従業員が同じ方向を目指して働くようになり、組織に一体感が生まれます。結果として、意思疎通や情報共有が円滑になり、組織全体の生産性向上も期待できます。
3-2. 人事評価がしやすくなる
目標を明確に定めることで、評価基準も明確になります。たとえば、「売上20%アップ」という目標を設定し、結果が「売上10%アップ」だった場合、目標達成率は50%と算出でき、過去や他者と比較することで、数値データに基づき客観的に評価をおこなうことができます。
また、目標管理を実施することで、目標到達までのプロセスも管理できるため、努力や頑張りも評価に加えることが可能です。このように、目標管理は人事評価をしやすくするために役立ちます。公平で納得いく評価は、従業員エンゲージメントを高めることにもつながります。
関連記事:従業員エンゲージメントとは?向上施策や調査方法とその手順をわかりやすく解説!
3-3. 人材配置に役立つ
目標管理を通じて、現状の従業員のスキルを客観的に把握することが可能です。また、目標に取り組む過程も記録に残せるので、従業員がどのような考え方や価値観を持っているかも理解することができます。従業員のスキルや価値観を踏まえて適性のある部署や業務に配置すれば、個人の持っている力を最大限に発揮できるようにしてパフォーマンスを最大化したり、組織に不足している人材の早期育成につなげたりすることが可能です。
3-4. 従業員のモチベーション向上につながる
目標を定めることで、やるべきタスクが明確になり、次の行動につながりやすくなります。また、自分で立てた目標に向かって努力し、それを達成することで、大きな達成感が得られ、自信にもつながります。このように、従業員の仕事に対するモチベーションを高めるために、目標管理は重要な役割を果たします。
3-5. 従業員のスキルアップにつながる
目標を設定する際、スキルマップなどを用いて現状の自分の能力やスキルがどの程度か可視化します。その後、自分に足りていないスキルを明確にし、それに到達することを目標に設定して、進捗管理を実施すれば、効率よくスキルアップを目指すことができます。また、目標の振り返りを通じて、自分の成長を実感でき、よりスキルを伸ばそうと努力を促すことも可能です。
4. 目標管理を効果的に実施する手順

目標管理はくだらないと言われることもありますが、意味や目的はきちんとあります。意味ない・時代遅れと言われるのは、やり方が間違っているからです。ここでは、目標管理を効果的に実施する手順について詳しく紹介します。
4-1. 組織の方向性や目標を明確にする
まずは組織の方向性や目標を明確にすることが大切です。組織の求める姿が明らかにならなければ、会社がどのような人材を必要としているのか、従業員に正しく伝えることができません。経営理念やビジョンを参考に、組織の理想像を明確にし、目標管理を運用する前に従業員にきちんと周知するようにしましょう。
4-2. チームや個人の具体的な目標を設定する
組織の方向性や目標が定まったら、それと結びつく形でチームや個人の具体的な目標を設定しましょう。目標は具体的でなければ、何を成し遂げるのか曖昧になり、目標管理がくだらないと言われる原因になります。目標を達成した後、どのような姿になっていたいかをイメージし、言語化することで、具体的でわかりやすい目標を定めることが可能です。
4-3. 目標達成に向けた具体的な行動を明確にして実行する
目標を設定しただけで行動に移さなければ、目標は意味ないものとなり、目標管理がくだらないと言われる原因になります。そのため、目標を設定する際、同時に具体的な行動も定めておきましょう。目標に到達するまでのプロセスが具体化されることで、次何をすべきか明確になり、行動を起こしやすくなります。目標とその行動プロセスが具体化できたら、実際に目標管理を運用し始めましょう。
4-4. 目標に対する進捗状況を定期的にチェックする
目標管理を開始したら、進捗状況を定期的にチェックすることが大切です。また、市場環境が目まぐるしく変化する現代では新たなトレンドが次々と登場するため、目標を変える必要性が生じるケースもあります。そのため、目標自体の見直しも検討できるような仕組みを整備しておきましょう。
4-5. フィードバックや改善を実施する
定期的に目標の達成状況をチェックし、進捗が思わしくないのであれば、目標および行動プロセスを見直して、原因を追究し、改善に努めましょう。また、上司や同期などの第三者からのフィードバックをもらうことで、新たな気づきが得られ、成長につながることもあります。
なお、あらゆる関係者に評価してもらう360度評価は、特定の人だけで評価しないため、主観を減らし、公平で納得いく評価がしやすくなります。定性評価を取り入れている場合は、360度評価を制度として導入してみるのも一つの手です。
関連記事:360度評価とは?メリット・デメリットや評価方法を紹介
5. 目標管理の有効性を高めるポイント

目標管理がくだらないと言われる事態を招かないためにも、目標管理のポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、目標管理の有効性を高めるポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 目標設定で従業員の自主性を尊重する
目標管理はトップダウンで決めてしまうことで、従業員の意見が反映されず、モチベーションが下がってしまい、目標管理がくだらないと言われる理由につながります。そのため、目標設定はボトムアップで定めるようにしましょう。従業員が自分で目標設定をおこなうことで、目標に対する責任感が生まれ、主体的な行動につながりやすくなります。
5-2. 組織目標と個人目標をリンクさせる
目標をボトムアップで決める場合、個人に目標設定を任せっきりにしてしまうと、組織の目標と乖離してしまう目標が立てられる可能性もあります。この場合、目標を達成しても、個人の成長につながるかもしれませんが、組織の成長につながりません。そのため、あらかじめ組織の求める姿を明確にし、従業員にきちんと周知することが大切です。組織目標と個人目標がリンクすることで、従業員と会社の両者の成長につなげることができます。
5-3. 従業員の負担が少ない運用管理方法を採用する
目標管理に時間や手間がかかるため、コア業務に集中できないことから、目標管理がくだらないと言われるケースもあります。そのため、できる限りシンプルな目標管理を採用しましょう。目標の進捗状況の把握や、情報の共有を効率化するため、目標管理システムを導入してみるのも一つの手です。目標管理システムであれば、目標に関するデータを一元化してリアルタイムで管理することができます。また、システム上でやり取りできるので、在宅勤務の際や移動中でも情報共有が可能です。
5-4. 定量的かつ具体的な目標を設定する
公平な評価ができないために、目標管理がくだらないと言われることもあります。まずは定量的で具体的な目標を設定することを心掛けましょう。数値化して管理できれば、目標の達成状況を客観的に把握し、ブレない評価を実現することができます。また、あらかじめ目標を達成するためのアクションプランの策定もしておくことで、次の行動につながりやすくなり、効率よく目標達成を目指すことが可能です。
5-5. 変化に応じた修正の機会を設ける
目標は定期的に見直し、従業員や組織の成長につながるものかどうかチェックすることが大切です。目標に対する行動プロセスを改善することはあっても、目標自体の見直しは人事評価などに影響するため制度上できないことになっているケースもあります。ビジネス市場が目まぐるしく変化する現代では、最初に立てた目標が時代の移り変わりとともに必要性が薄れている可能性もあります。そのため、環境の変化に応じて目標の修正機会を設けることも推奨されます。
6. 目標管理に活用できる手法やフレームワーク

ここでは、目標管理に活用できる手法やフレームワークを紹介します。
6-1. OKR
OKR(Objectives and Key Results)とは、日本語に訳すと「目標と主要な成果」で、目標設定手法の一つです。目標達成のための具体的な成果指標を定め、進捗状況を測定し、評価することを繰り返すことで、効率よく目標達成を目指します。OKRでは、組織と個人の目標を紐づけて管理する点が特徴です。組織と個人の目標がリンクするので、企業全体の目指すべき方向性を一致させて目標に向かって取り組むことができます。
関連記事:OKRとは?意味や目標・評価の設定、導入企業の具体例を紹介
6-2. アジャイル目標管理
アジャイル目標管理とは、アジャイル思考に基づく目標管理の新たな手法の一つです。通常の目標管理では半年や1年単位で目標を設定して振り返りを実施しますが、アジャイル目標管理では短期的な目標を具体的に設定します。その後、目標を可視化して組織全体に共有したうえで、目標に取り組みます。チームの同意を得ながら、短期間でPDCAサイクルを素早く回すことで、目標の早期達成を目指すことが可能です。
6-3. KPI管理
KPI(Key Performance Indicator)とは「重要業績評価指標」と訳され、最終ゴール(KGI:Key Goal Indicator)を達成するために設けられる中間指標のことです。KPIは数値化して管理されるため、目標の達成状況を把握しやすいというメリットがあります。KPIを達成するためにリソースを注ぎ、定期的に振り返りをして改善することで、効率よく目標達成を目指すことが可能です。
関連記事:KPIとは?メリット・デメリットや設定のポイントをわかりやすく解説!
6-4. ベーシック法
ベーシック法とは、「目標項目」「達成基準」「期限設定」「達成計画」の4つのから構成される目標設定フレームワークです。最も基礎のフレームワークとよばれることもあり、あらゆる目標設定フレームワークの基となっています。目標管理を初めて導入する場合、ベーシック法を基に目標管理シートを組み立ててみるのもおすすめです。
関連記事:目標設定シートの書き方は?職種別の記入例やフレームワークを解説
6-5. SMARTの法則
SMARTの法則とは、「Specific(具体性)」「Measurable(計測可能性)」「Achievable(実現可能性)」「Relevant(関連性)」「Time-bound(期限)」の5つの英単語の頭文字を取って名付けられた目標設定フレームワークです。
SMARTの法則を用いることで、定量的でわかりやすい目標を設定することができます。また、実現可能性を考慮しているので、実現不可能な目標の設定を避けることが可能です。さらに、期限を決め、関連性を取り入れることで、目標を成し遂げようという意欲を高めることもできます。
関連記事:SMARTの法則とは?目標設定に活用するメリットと方法・注意点を解説
7. 時代や組織のニーズにあった目標管理を実現しよう!

目標管理は時代や社会の変化により、適したやり方が変わってきています。従来のまま目標管理制度を放置していると、目標管理がくだらない、時代遅れ、意味ないと言われる原因になります。目標管理を効率よく実施するため、目標管理システムの導入も検討してみましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。









