
360度評価制度とは、組織や企業の全従業員がお互いに評価し合う制度です。上司や部下などの役職を超えて評価するため、多角的な視点からの意見を得られるなどのメリットがあります。しかし一方でデメリットがあることも事実です。
本記事では、360度評価とはどのような評価方法なのか、メリット・デメリットにはどのようなものがあるのか、評価方法はどうするのかまで詳しく解説します。
目次
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
1. 360度評価とは?

360度評価とは、被評価者である従業員を複数の関係者が評価する仕組みです。一般的な評価制度においては、ほとんどが上司だけに評価されるため、大きく異なる評価方法といえます。
360度評価では上司はもちろん、同僚や、普段は部下として働いている従業員、異なる部署の従業員などから多面的に評価されます。
1-1. 360度評価の目的
360度評価は、上司だけでなく同僚や部下、異なる部署の従業員からも評価されることで、被評価者である従業員の納得感を得やすい制度です。上司1人では理解しきれていなかった面も含めて多面的にデータが集まるため、より公平に評価を下すことができます。
さらに各従業員が「周囲の大勢の人が自分を見ている」「評価してくれている」と感じるようになり、安心感や信頼感を持って業務に励むようになる点も、360度評価の魅力のひとつです。
それぞれの従業員が自己の改善点や長所を把握できるのはもちろん、上司も適切に指導しやすくなるため、人材育成にも大いに役立つでしょう。
1-2. 360度評価が注目されている背景
360度評価に注目が集まっている理由としては、成果主義における公平な評価が求められていることや、新しい働き方が浸透してきたことなどが挙げられます。
成果主義における公平な評価が求められている
従来は年功序列型の評価制度が一般的でしたが、近年は成果主義による評価制度を実施する企業が増えてきました。成果主義においては、従業員ごとの成果や保有する能力を公平に評価して、給与や役職を決定しなければなりません。上司だけが評価すると、どうしても偏った見方になってしまうため、360度評価によりさまざまな角度から評価することが求められているのです。
新しい働き方が浸透してきた
新しい働き方を取り入れる企業が増えてきたことも360度評価が注目されている理由のひとつです。在宅勤務やリモートワークを取り入れている場合、従業員が離れた場所で働いているため、従来のような方法では勤務態度を正確に評価することはできません。
そこで、同僚や部下など関わっている複数の従業員からの意見をもとに、評価を決定しようとする企業が増えてきました。
2. 360度評価のメリット

360度評価にはさまざまなメリットがあります。内容ごとに確認してみましょう。
2-1. 評価に客観性を持たせる
上司が部下を評価する方法では、上司がどれだけ部下である従業員を見て理解しているか、どれだけ評価能力があるかが重要です。従業員自身の評価と上司の評価が乖離していることもあり、評価結果の公平性に疑いや不満を感じる部下は珍しくありません。
360度評価の場合は、上司の主観や心象の影響が薄くなり、多方面の関係者から評価されることで客観性も補えます。上司が見落としていた部分もほかの人の評価から見えてくるため、従業員も納得しやすくなる点は大きなメリットです。
2-2. 従業員が評価に納得しやすくなる
360度評価は客観性が強いため、従業員も納得しやすくなります。数による信用の補填がされているため、評価そのものの信頼度が上がるのです。場合によっては顧客や取引先の意見も取り入れられるため、評価の客観性は上司だけのものとは比較になりません。
公平に評価されていると感じれば、従業員の職場への信頼感が増します。評価内容に納得して受け入れてくれるだけでなく、さらによい評価を得ようとモチベーションを引き上げることも可能です。
2-3. 主体的に改善点と向き合える
360度評価では、被評価者自身も評価をすることになります。自己評価と他の従業員からの評価を比較検討できるのです。
360度評価は客観性が数で担保されているため被評価者も納得しやすく、自ら改善点と向き合うようになります。他の人の評価がこれまで気付いていなかった部分を明確にし、従業員自身が考えて行動できるようになるでしょう。
2-4. 被評価者自身の特性を客観視しやすい
被評価者は、360度評価の結果から自分のことを再認識できます。自己の強みや弱みといった特性をより客観的に認識できるのです。評価を受けた従業員は、どこを伸ばしてどこを改善するべきか取り組むべきことが明確化します。
各従業員が自ら考え行動するようになり、組織や企業全体の活性化につながるでしょう。
また、管理職を含めた上司が部下からの評価を受け、自身の行動を客観的に振り返る機会を得られる点も大きなメリットです。
2-5. 従業員同士の人間関係を把握しやすい
360度評価では多くの人間が関係するため、普段は見えにくい従業員同士の人間関係も見えてくることがあります。人間関係がうまくいっていなかったり、いじめやパワハラなどを受けたりしている場合、不当に低い評価をつけられることがあるためです。職場内のこれらの問題点が、360度評価によって浮き彫りになるケースもあります。
2-6. エンゲージメントの向上につながる
360度評価をうまく運用すれば、従業員のエンゲージメントが向上します。エンゲージメントとは、企業に対する愛着や思い入れのことです。360度評価では多くの関係者から評価を受けるため、とくに高い評価を得た場合は、組織全体から必要とされていると感じられ、会社に貢献したいという気持ちが強くなるでしょう。
エンゲージメントが向上すれば、生産性の向上や離職率の低下なども期待できます。
3. 360度評価のデメリット
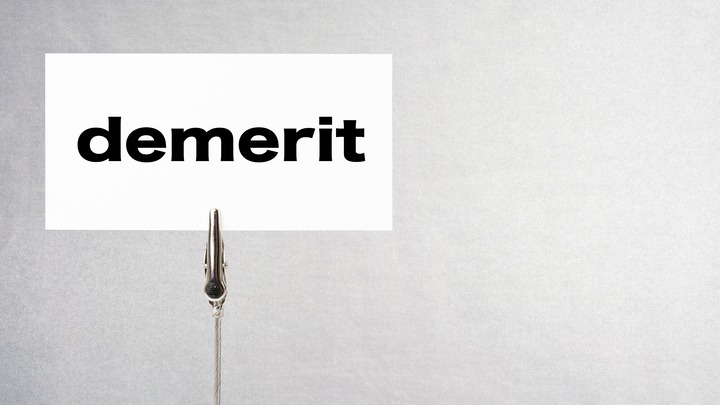
全ての評価制度には、メリットと同時にデメリットもあります。360度評価も例外ではありません。続いてはデメリットを確認してみましょう。
3-1. 評価に主観が入りやすい
普段から評価をすることに慣れている上司と異なり、一般の従業員は評価すること自体に慣れていません。全従業員に360度評価の目的や具体的な方法を周知しておくことが重要です。
各従業員が360度評価に慣れるよう、しっかり研修を繰り返し、正しく評価できるようにする機会を持つことが重要になります。
3-2. 管理職が評価を意識した行動に陥りやすい
部下である従業員は、普段上司が何をしているのかわかっていないことも珍しくありません。そのため評価基準が少なく、印象だけで評価をしてしまいがちです。
とくに厳しい上司と思われると、マイナス評価をされることが多くなります。また、近年では叱られることに慣れていない従業員が増加していることもあり、簡単に会社を辞めてしまうケースもあるでしょう。
上司の評価の際は項目を限定したり、部下とのコミュニケーションを密にしたりすることで、なぜ厳しく指導されるのか真意が伝わるよう取り組んだりするなどの工夫をするとよいでしょう。
3-3. 評価になれ合いが生まれる
同僚同士など従業員同士が評価をし合うときに、なれ合いが起こることがあります。お互いに相談して高評価をつけ合ったり、関係性のよい相手に甘い評価をつけたりするのです。
逆のケースも考えられます。仲が悪い相手や自分に低評価をつけた相手を低評価にするといったケースです。
いずれもさまざまな思惑や感情が入り交じっているため、評価内容は実態に即したものではありません。しっかり評価者研修をおこなって、なれ合いを未然に防ぐ努力が必要です。
3-4. 工数と時間が必要となる
360度評価は、全従業員が評価をおこなうため仕事量も当然増えます。集めた評価を取りまとめる人事担当はさらに多くの仕事を抱えることになりかねません。単なる作業だけでなく研修の時間も必要です。
多くの時間や労力が必要となるため、本来の業務に支障をきたすようになる可能性もあります。360度評価を取り入れる際には、負担を軽減するためのツールを検討するなどの工夫も必要です。
3-5. 慣れるまでに時間がかかる
運用に慣れるまでに時間がかかることも360度評価のデメリットのひとつです。ほとんどの従業員は他人を評価したことがないため、どのような部分に注目すればよいのか、どのような基準で評価すればよいのか、といった点に悩んでしまい時間がかかるケースも多いでしょう。
また、評価制度を取りまとめる側も評価を実施するタイミングに迷ったり、集計に時間がかかったりすることも考えれられます。360度評価を導入する際は、事前に運用ルールをしっかりと決めておくことが大切です。
4. 360度評価における評価方法
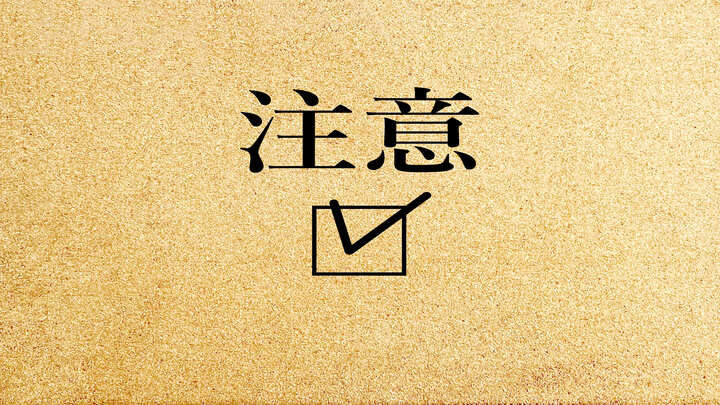
360度評価を実施するには、評価項目と評価方法を理解しておくことが重要です。360度評価を取り入れるための注意点でもあります。項目別に確認していきましょう。
4-1. 全ての従業員を対象する
360度評価を実施するときは、その組織や企業に所属する「すべての従業員を対象にすること」が重要です。評価する側もされる側も特定の従業員のみでは、公平性や客観性が失われてしまいます。
360度評価のメリットである部分が失われてしまっては意味がありません。必ず「すべての従業員」を対象として客観性や公平性を追求しましょう。
4-2. 執務態度を中心に評価項目を作成する
360度評価では、人事評価項目である「成果」「発揮能力」「執務態度」の3点のなかでも「執務態度」に絞ることが望ましいです。日常の業務に取り組む姿勢を可視化するのみにとどめ、処遇にかかわる評価は避けます。
評価項目には「どちらでもない」「わからない」といった曖昧な項目も用意しましょう。被評価者のなかには、普段見ないため評価ができない従業員が含まれるケースもあるためです。評価者が評価を付けやすいよう配慮するようにしてください。
4-3. 評価得点は平均値にする
360度評価では、全従業員の評価を集計すると必ず大きなばらつきが出ます。被評価者と身近な直属の上司や同僚と、関わりが薄い別部署の従業員とでは、評価が異なるのは当然です。
評価に公平性を持たせるためには、平均値を評価得点とします。最高値や最低値で評価しないようにしましょう。
4-4. フィードバックも忘れずにおこなう
360度評価で出た結果は各従業員に伝え、被評価者自らも自己を顧みる機会につなげます。フィードバックをおこなうことで従業員自身が気付いていなかったよい点や悪い点を知らせ、自己を伸ばしたり改善したりする題材として活用させましょう。
4-5. 評価の反映先を明示する
360度評価で出た結果の反映先は事前に周知しておきます。360度評価で何がわかり、どう活用したらよいのかを明示しておきましょう。
なぜ評価されているのかや評価結果がどう反映されるのかがわかっていないと、従業員側が受け止めきれません。納得できない従業員がいるまま実施しても、不満が募るばかりか効果そのものが得られない危険性もあります。
360度評価を実施する前にしっかりと目的やルールを周知し、全体が納得した状態で始めましょう。
4-6. 匿名性を確保する
360度評価では匿名性の担保は欠かせません。とくに部下が上司を評価する際に、忖度する可能性もあります。また、自身に低評価をつけた相手にやり返すようなことが起こり得る状態では、公平性や客観性を維持できません。
フィードバックを実施する際にも誰の評価なのかわからないよう、慎重な運用を心掛けましょう。
他にも目標面談の際に逆にメンバーにどうフィードバックをしていくのか、そもそもどのように人事評価を策定すれば良いかを悩んでらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「人事評価の手引き」という資料を無料配布しております。本資料では、人事評価の策定から、人事評価を実際に導入したあとの振り返りの方法やフィードバックの仕方、またフィードバック時の注意点も紹介しており、これ一つで人事評価の策定から運用まで適切に進められます。参考になる資料ですので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。
5. 360度評価の失敗を避けるポイント

360度評価の導入に失敗しないよう、以下のポイントを把握しておきましょう。
5-1. 導入目的を明確にする
360度評価を成功させるためには、導入目的を明確にしておくことが必要です。人事評価や人材育成に活用する、評価の公平性を確保するなど、目的を明確にしておく必要があります。既存の評価制度における課題を把握したうえで、なぜ360度評価を導入するのかを把握にしておきましょう。
また、導入目的について従業員に周知しておくことも大切です。360度評価の意義を理解しておいてもらうことで、より導入効果が高まります。
5-2. ガイドラインを作成する
360度評価をうまく運用していくためには、ガイドラインを作成しておくことも重要です。他人を評価することに慣れておらず、評価に時間がかかったり、間違った評価をしたりするケースもあります。
評価の対象となる従業員や評価を実施するタイミング、評価の基準などを明記したガイドラインがあれば、運用がスムーズに進むでしょう。
5-3. アフターフォローを徹底する
360度評価を導入するなら、アフターフォローを徹底しましょう。評価を実施して終わりではなく、面談をおこない評価結果について詳しく話し合うなどの対応が重要です。
自分がどのような評価をされているのか、今後はどのような努力をしていくべきなのか、評価結果をもとに丁寧なフィードバックをおこなうことで、モチベーションアップや人材育成につなげましょう。
6. 360度評価はメリット・デメリットを理解したうえで導入しよう

360度評価は組織や企業の全従業員がどのような性質を持っているか、業務に対してどのように取り組んでいるかを、客観的かつ公平に把握するのに向いています。役職に関係なく評価できることから、上司や部下との関係改善や管理職の育成にもつなげられるシステムです。
ただし、360度評価は全従業員が目的やメリットを理解していないと効果が下がってしまいます。リスクを回避するためには、評価方法に関する研修や学習が必要です。
リスクを回避できれば風通しのよい社風をもたらしてくれるメリットもあるため、まずは自社に合うかどうか検討してみみましょう。
人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。









