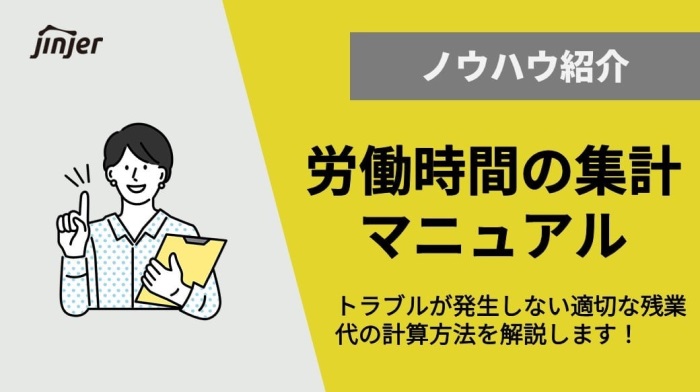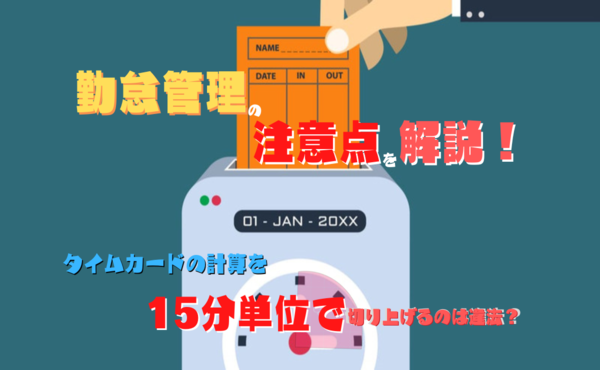
タイムカードはシンプルで誰でも使いやすいので、多くの企業で使われています。ただし、使い方によってはトラブルが発生したり、法律違反に該当したりするため、正しい運用ルールを設定することが重要です。
本記事では、タイムカードの仕組みや利用するうえでの注意点について解説しつつ、勤怠管理を効率化する方法についても紹介します。
「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?
当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。
「打刻まるめでの正しい集計方をが知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードに15分単位で記録するのは違法!

原則として、タイムカードに15分単位で記録したり、15分単位で給与計算をしたりすることは違法です。下記の通り、労働基準法第24条には、従業員が働いた労働時間に対し、企業側は賃金を全額支払わなければならないと定められています。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
正確な賃金を支払わない場合、労働基準法違反として罰則を受けるケースもあるため注意しましょう。
このように、今まで自社でしていた勤怠管理が実は違法だったといったケースもあります。当サイトでは、打刻まるめが違法となるケースや、適切な労働時間の集計方法を解説した資料を無料でお配りしています。こちらからダウンロードして、労働時間の集計方法や自社の運用方法が適切かどうかの確認にご活用ください。
1-1. 勤怠管理は1分単位でおこなう
タイムカードを活用する場合に限らず、勤怠管理は1分単位でおこなうのが基本です。労働時間を15分単位などで管理すると、従業員が働いた分の賃金を全額支払えない可能性があります。
たとえば8時間14分の労働が発生した場合に、15分以下の部分を切り捨て8時間と記録してしまうと、14分の労働時間に対する賃金を支払えません。労働基準法第24条の全額払いの原則に違反してしまうため、労働時間の切り捨ては避け、1分単位で記録しましょう。
1-2. 1カ月単位での勤務時間の切り上げ・切り捨ては合法
前項では、勤怠管理・給与計算は1分単位でおこなう必要があると解説しました。しかし、全ての従業員の労働時間を1分単位で計算するとなると、多大な時間がかかってしまいます。
そのため、1カ月の残業時間の集計で、1時間に満たない場合は下記のように処理することが許容されています。
- 30分未満→切り捨て
- 30分以上→1時間に切り上げ
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 月の残業時間が34分だった場合、1時間として給与計算をおこなう
- 月の残業時間が30時間23分だった場合、30時間として給与計算をおこなう
以上のように、基本的には1分単位での勤怠管理が必要ですが、1カ月単位であれば簡略化して給与計算をすることは可能です。
また、タイムカードによる勤怠管理は、ここで紹介した注意点以外にもさまざまな課題を抱えています。たとえば、集計作業に工数を取られることや、リモートワークに対応できないことなどが挙げられます。必要に応じて、上記のような課題を解決できる勤怠管理システムの導入を検討するとよいでしょう。
2. タイムカードを15分単位で計算することで発生するトラブル
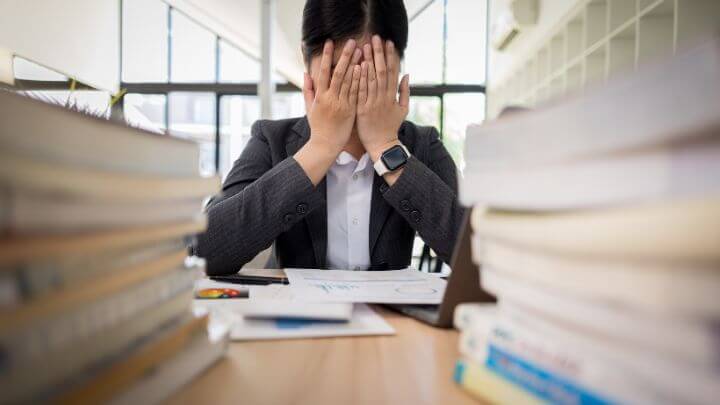
前述の通り、タイムカードを15分単位で計算することは違法です。また、以下のようなトラブルにもつながるため注意しましょう。
2-1. 労働基準監督署に指摘される
労働時間を15分単位で記録するなど、適切な勤怠管理をおこなっていない場合、労働基準監督署に指摘されるかもしれません。労働基準監督署は、従業員が安全に働ける職場環境であるかどうか、賃金が正しく支給されているかどうか、といったポイントを随時チェックしています。
定期的な調査のほか、従業員が労働基準監督署へ問題を報告することで調査が実施されるケースもあります。もし、15分や30分単位で労働時間を管理しているなら、調査時に指摘を受けるでしょう。すぐに改善すれば大きな問題には発展しませんが、指導を無視すると処罰されるケースもあります。
2-2. 未払いの残業代を請求される
労働時間を15分単位で記録すると、賃金を正確に支払うことができません。たとえば、20分の残業が発生したのに15分の残業とカウントすると、5分の残業時間が無視されてしまいます。
仮に15分の残業と記録したとしても、従業員が働いたという事実は残るため、後で未払いの残業代を請求される可能性もあります。そもそも働いた分の賃金を1分単位で支給することは企業の義務であるため、しっかりと対応しましょう。
2-3. 社会的なイメージが悪化する
法律に従った形で勤怠管理をおこなわないと、社会的なイメージ悪化につながります。正しく賃金を支払わない会社というイメージが広がると、新しい人材の確保に苦労したり、取引先との関係性が悪化したりするケースもあるでしょう。会社にとって大きなダメージとなるため、適切な勤怠管理を心がけることが重要です。
3. タイムカードによる勤怠管理の仕組み

ここでは、タイムカードによる勤怠管理の仕組みについて解説します。
関連記事:タイムカードとは?仕組みや使い方、メリット・デメリットを徹底解説
3-1. そもそも勤怠管理とは?
勤怠管理とは、従業員の出退勤や休日休暇の取得状況といった日々の労働が、就業規則や労働基準法に沿っているかを管理することです。自社の労働環境を把握することで、現在抱えている課題を早急に見つけ、解決に向けて取り組むことができます。
日本では、長時間労働や過労死が社会問題となっており、企業に勤怠管理の徹底がより一層求められています。
3-2. タイムカードで打刻してエクセルで記録する企業が多い
実際に勤怠管理をおこなう方法として、タイムカードを利用している企業は非常に多いです。タイムカードによる勤怠管理の方法は、以下の流れでおこなわれています。
↓
②打刻された情報をエクセルで記録・計算
↓
③計算された内容をもとに給与を支払う
タイムカードはシンプルで誰でも使いやすいという反面、勤怠情報をエクセルに移す際に入力ミスの恐れがあるため、十分注意する必要があります。
関連記事:タイムカードの情報をエクセルで計算する方法|メリットや注意点も
4. タイムカードによる勤怠管理に関するよくある疑問

ここでは、タイムカードで勤怠管理をするなかでの「よくある疑問」について解説します。
4-1. 始業前の朝礼や終業後の終礼は労働時間に含む?
結論、始業前の朝礼や終業前の終礼は労働時間に含まれます。そもそも労働時間とは「従業員が使用者の指揮命令下にある時間」のことです。始業前や終業後であっても、原則として朝礼や終礼は参加が義務付けられているため、労働時間に該当します。
会社によっては、「朝礼や終礼は労働時間には含まない」と就業規則で定めている場合があります。しかし、労働時間に該当するかどうかは客観的に判断されるため、就業規則などの影響を受けません。そのため、たとえ3分であっても、適切に労働時間を計算する必要があります。
4-2. 閉店時間を終業時間とみなしても問題ない?
飲食業界などでは、閉店時間を終業時間とみなしている企業が多く見られます。しかし、実際には閉店後であっても、店の締め作業や着替えの時間などの業務が発生しています。そのため、閉店時間を終業時間とみなし、労働時間を計算することは労働基準法違反に該当するでしょう。
ここまで、「15分単位で労働時間計算をおこなっている場合」や「閉店時間を終業時間とみなしている場合」など、労働時間に関する疑問について解説しました。
ここからは、タイムカードによる勤怠管理をおこなううえで、注意すべきことを解説します。
4-3. 適切な勤怠管理を怠るとどうなる?
適切な勤怠管理をおこなわないことには、次のようなリスクがあります。
労働基準法に違反してしまう
労働基準法に違反することは、企業にとって重大なリスクです。懲役や罰金などが科せられるだけではなく、社会的なイメージの悪化にもつながるため注意しなければなりません。
たとえば、労働時間の上限は労働基準法によって定められています。勤怠管理を怠ると、知らないうちに上限を超過してしまう可能性もあるでしょう。
また、労働時間に応じた休憩時間を付与することや、勤続年数に応じた有給休暇を付与することは法律によって定められた企業の義務です。以上のように多くのルールがあるため、勤怠管理を徹底することで労働基準法を遵守した形で事業を展開していきましょう。
従業員の健康を維持できなくなる
勤怠管理を怠ると、従業員の健康を維持できなくなる可能性もあります。過剰な長時間労働や休日出勤は、従業員にとって大きな負担です。心身の健康を維持できなくなると、モチベーションや生産性が低下したり、休職したりする可能性もあります。
従業員の健康を守るためには、勤怠管理を徹底し、長時間労働を是正したり適切な休暇を付与したりすることが重要です。
5. タイムカード以外の勤怠管理の方法

タイムカード以外の勤怠管理の方法としては、勤怠管理システムの活用が挙げられます。ここでは、タイムカードの問題点と勤怠管理システムがおすすめの理由を紹介します。
5-1. タイムカードによる勤怠管理の問題
タイムカードで勤怠管理をおこなう場合、打刻ミスや打刻漏れが発生しがちです。遅刻しそうなときに同僚に頼んで打刻してもらう代理打刻が発生することもあるでしょう。
また、集計作業に時間がかかることも大きなデメリットです。タイムカードを回収して、従業員ごとの労働時間や残業時間を計算しなければならず、担当者が負担に感じることも多いでしょう。
5-2. 勤怠管理を効率化したいならシステムの導入がおすすめ
勤怠管理システムは、打刻・労働時間計算・記録を連動しておこなうことができるため、タイムカードに比べ、手作業による入力ミスの恐れがないことが魅力です。
また、スマートフォンやICカードというように、打刻方法が多様なのでリモートワークが導入されている企業や現場仕事の多い建設会社などに、幅広く受け入れられています。
さらに、勤怠システムであれば、労働時間の上限に近づくとアラートを自動で出すなど、労働基準法に遵守した環境づくりを自動でおこなうことができるため、人事担当者の業務を大幅に減らすことができます。
関連記事:効率的なタイムカードの集計方法とは|人事・経理から個人管理まで
関連記事:アプリ対応の勤怠管理システム8選|タイムカードに代わる勤怠管理手法の導入メリットとは
6. タイムカードを15分単位で計算するのは違法!正しい勤怠管理をおこなおう

本記事では、タイムカードによる勤怠管理の仕組みや規則などについて、法律上のルールに沿って解説しました。労働時間を15分や30分単位で記録することは違法です。働いた分の賃金を正しく支払えるよう、従業員ごとの労働時間は1分単位で管理しなければなりません。
また、タイムカードに限らず勤怠管理・給与計算を正しくおこなうことは、労働基準法を遵守するだけでなく、従業員が健康的に長く働ける職場を作ることにつながります。今回解説した内容を踏まえて、適切に勤怠管理・給与計算をおこないましょう。
「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?
当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。
「打刻まるめでの正しい集計方をが知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。