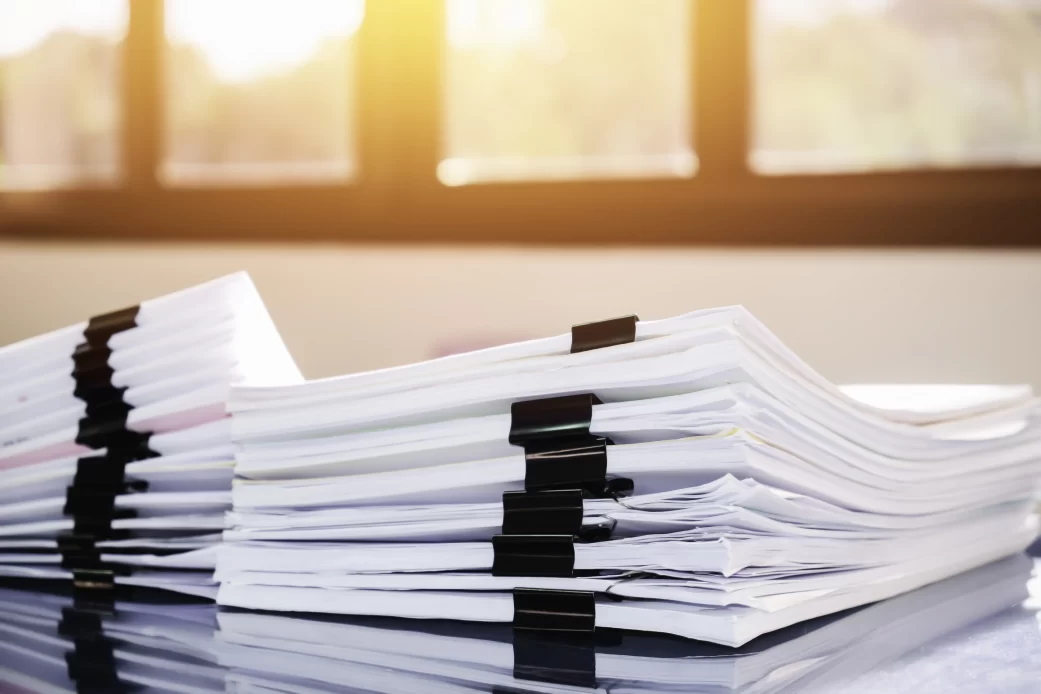
退職手続きに必要な書類は数多くあります。手続きの抜けや漏れを発生させないためにも、事前に必要となる書類をチェックしておくことが大切です。本記事では、退職手続きに会社側が準備すべき書類を一覧で紹介します。また、従業員から受け取る書類や、退職者に渡す書類のチェックリストも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 退職手続きに会社側が準備すべき書類一覧

退職手続きの際に必要になる書類は数多くあります。従業員の状況に応じて、必要な書類を正しく用意することが大切です。ここでは、退職手続きに会社側が準備すべき書類を一覧で紹介します。
1-1. 退職届
退職届は、労働者が退職を申し出る際にその記録を証拠に残すために必要な書類です。期間の定めがない無期雇用契約の場合、民法第627条により、退職の申し出から2週間を経過することで、その労働契約は終了します。つまり、後任や業務の引継ぎをおこなう時間を考えず、法律上の話だけで言うと、退職届を退職する日の2週間前までに提出してもらえば、契約を終了させることが可能です。
しかし、期間の定めがある有期雇用契約の場合や、やむを得ない事情がある場合は、法律で定められたルールが異なります。そのため、就業規則に退職のルールを細かく記載し、退職届をいつまでに提出すべきか明確にしておきましょう。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(省略)
関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介
1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険に加入していた労働者が退職した場合に、雇用保険の資格喪失手続きをおこなうために必要となる書類です。雇用保険被保険者資格喪失届は、資格喪失日(退職日の翌日)の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。提出方法は「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?入手方法や提出方法を解説!
1-3. 離職証明書
離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは、離職票の交付を受けるために必要な書類です。離職証明書は、雇用保険被保険者資格喪失届に添付して提出します。
なお、退職者が離職票の交付を希望しない場合、離職証明書の提出は不要です。ただし、退職日に59歳以上に該当する労働者については、希望に関係なく離職票を交付しなければならないので、離職証明書の添付が必須です。また、離職証明書を提出する場合、賃金支払状況を確認できる書類(賃金台帳や労働者名簿、出勤簿など)と離職理由を確認できる書類(退職届や解雇通知書など)の添付も必要なため気を付けて準備しましょう。
1-4. 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していた労働者が退職した場合に、社会保険の資格喪失手続きをおこなうために必要となる書類です。健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届は、資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に日本年金機構(および健康保険組合)に提出する必要があります。
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入している場合、健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きを同時におこなうことが可能です。ただし、資格確認書や健康保険証、高齢受給者証などの添付書類も手続きに必要となります。
一方、組合健保(組合管掌健康保険)に加入している場合、厚生年金保険の資格喪失手続きは、被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することで添付書類不要で手続きができます。しかし、健康保険の資格喪失手続きは、所属している健康保険組合によって異なる可能性もあるので、事前に手続き方法をチェックしておきましょう。
関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の書き方や提出先を解説
1-5. 退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書とは、退職金を支給する場合に、退職金にかかる税金を正しく計算・徴収するために必要な書類です。退職所得の受給に関する申告書は、退職予定者に交付し、退職金を支給するまでに会社へ提出してもらう必要があります。
退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、退職金に対して一定の税率(20.42%)を掛けて源泉徴収することになり、退職所得控除は反映されません。そのため、税金の納め過ぎとなり、還付を受けるためには、退職者自身で確定申告をしてもらわなければならなくなるので注意しましょう。
関連記事:退職金にかかる税金(所得税・住民税)の仕組みや計算方法をわかりやすく解説!
1-6. 源泉徴収票
源泉徴収票(給与所得)とは、その年に会社から支払われた給与と支払った所得税の税額が記載された書類です。従業員が退職した後、支払うべき給与を確定させたら、所得税法第226条に則り、退職後1カ月以内に給与所得の源泉徴収票を交付する必要があります。また、退職金を支給する場合、退職所得の源泉徴収票も、退職後1カ月以内に交付しなければなりません。
給与所得の源泉徴収票は、同一年内に退職と転職があった場合に転職先で年末調整を受けるために必要になります。一方、退職所得の源泉徴収票は、年末調整に不要なため転職先への提出は不要です。また、自分で確定申告をおこなう場合、給与所得と退職所得両方の源泉徴収票が必要になる可能性もあるため、退職者に正しく保管しておくように伝えましょう。
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
関連記事:退職所得の源泉徴収票とは?書き方や提出期限、確定申告の必要性について解説!
1-7. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書とは、従業員の退職に伴い、給与から住民税を徴収できなくなったときに提出する書類です。給与所得者異動届出書は、退職した月の翌月10日までに、退職者の居住地の自治体へ提出する必要があります。なお、例外的に従業員が住民税を普通徴収している場合には、給与所得者異動届出書の提出は必要ありません。
転職前の会社で特別徴収している場合で、すぐに転職するのであれば、「特別徴収」を継続することができます。この場合、転職先が給与所得者異動届出書を提出することになります。そのため、転職前の会社は給与所得者異動届出書に必要事項を記載したうえで、退職者に退職する際に渡し、転職先に提出するよう伝えましょう。
一方、すぐに転職しない場合は、原則として「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えをして、退職者自身で住民税を納めてもらうことになります。ただし、退職時期によって、住民税の納付方法が次のように変わることもあります。
- 1月1日~4月30日に退職:原則一括徴収
- 5月1日から5月31日に退職:通常通り納付
- 6月1日~12月31日に退職:普通徴収もしくは一括徴収
1月1日~4月30日に退職した場合は、原則一括徴収により住民税を納付することになります。しかし、残税額が支払予定の給与支給額の合計額を超える場合、普通徴収に切り替えることも可能です。このように、住民税の手続きは複雑であるため、最寄りの自治体などに相談し、手続き方法を細かく社内マニュアルにまとめておくことが推奨されます。
1-8. 退職証明書
退職証明書とは、従業員が退職したことを証明する書類です。退職者の転職先の企業にて、提出が求められる場合があります。また、国民健康保険の加入手続きなども、退職証明書でできるケースがあります。
退職証明書は、労働基準法第22条に基づき、退職者から求められたら必ず交付しなければなりません。また、労働者が希望しない事項を記載してはならないので、あらかじめ記載事項について労働者に確認し、速やかに交付しましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)
関連記事:退職手続きで会社側がすべきこととは?必要な業務の流れを一から解説!
2. 退職手続きの際に返却してもらう書類のチェックリスト

退職手続きでは、会社側が用意する書類のほかに、従業員から返却してもらう必要のある書類もあります。ここでは、退職手続きの際に返却してもらう書類などについて詳しく紹介します。
2-1. 社員証
社員証とは、自社に在籍している労働者であることを証明するために交付される私的な身分証明書のことです。会社から退職する場合、社員証は不要になるため、退職する際に返却してもらいましょう。
2-2. 名刺
名刺には、会社が支給したもの、従業員が自分で作成したものに大きく分かれます。どちらにせよ、会社の情報が記載された名刺は退職後不要になるため、退職前に早めに回収しましょう。
2-3. パソコンやスマートフォン
ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの電子機器を貸し出している企業も少なくないでしょう。これらの備品も会社に所属するものであれば、退職前に必ず返却してもらう必要があります。返却された後は、電子機器に含まれているデータをチェックし、必要に応じてバックアップを作成してから初期化をおこないましょう。
2-4. 制服・作業着
制服や作業着も会社に所属するものであるため、退職する際に返却してもらう必要があります。制服・作業着のクリーニング代を福利厚生として会社で負担している場合、混乱を招かないためにも、その旨を退職予定者に伝えておきましょう。
2-5. 健康保険証(資格確認書)
健康保険証(資格確認書)は、資格喪失日(退職日の翌日)から使えなくなります。そのため、退職日に返却してもらうのが一般的です。社会保険の資格喪失手続きをする際に、健康保険証(資格確認書)を添付しなければならないので必ず返却してもらいましょう。また、退職者に扶養家族がいる場合、その扶養家族の分の健康保険証(資格確認書)も返却してもらわなければならないので注意が必要です。
2-6. 業務上の書類
業務で作成した書類も、個人情報や顧客情報などの社外秘の情報が含まれているため、退職後に外部に漏れないよう、退職前に回収することが大切です。やむを得ない事情があり、回収が難しい場合は、退職者に自分で破棄してもらうよう伝えましょう。
関連記事:退職手続きで会社側がすべきこととは?必要な業務の流れを一から解説!
3. 退職手続きの際に従業員に渡す書類のチェックリスト

退職する際や、退職した後に、従業員に渡さなければならない書類もあります。ここでは、退職手続きの際に従業員に渡す書類について詳しく紹介します。
3-1. 離職票
離職票とは、従業員が退職した事実を証明するための書類です。退職者が再就職するまでの期間に失業手当を受け取るには、ハローワークへ離職票を提出しなくてはいけません。そのため、退職者が失業給付の受給を希望する場合、スムーズに手続きできるよう、会社は離職票の発行手続きをおこなう必要があります。
雇用保険の資格喪失手続きをすると、後日、ハローワークから会社に「離職票1」と「離職票2」が送付されます。なお、離職票1と2の役割は次の通りです。
- 離職票1:失業給付金を振り込む銀行口座の申請用
- 離職票2:離職理由や離職前の賃金状況を把握するための書類
会社に離職票が届いたら、2通とも退職者へ速やかに送付することが大切です。
3-2. 健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書とは、健康保険の資格を喪失したことを証明するための書類です。従業員が退職後に国民健康保険に加入する場合や、転職先で新しく健康保険に加入する場合などに、健康保険資格喪失証明書が必要になります。
健康保険資格喪失証明書は、社会保険の資格喪失手続きをした後に、発行申請をすることで受け取ることが可能です。所属している健康保険組合によって手続きの仕方は異なるので注意が必要です。健康保険資格喪失証明書も退職する際に渡すようにしましょう。
なお、健康保険資格喪失証明書の交付義務はないため、退職時に渡さなかった場合、後に退職者から請求を受ける可能性もあります。その場合は、速やかに対応するようにしましょう。
3-3. 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入者であることを証明する書類です。雇用保険被保険者証は、転職先で雇用保険に加入する場合や、失業手当などの手続きをする場合に必要になります。そのため、会社で雇用保険被保険者証を預かっている場合は、必ず退職者に返却しましょう。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?発行方法や再発行のやり方、退職日・転職の際の手続きを紹介!
3-4. 基礎年金番号通知書(年金手帳)
基礎年金番号通知書とは、基礎年金番号を証明するための書類です。2022年4月から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が発行されるようになっています。なお、従来通り、年金手帳も証明書類として有効です。
そのため、従業員によって、基礎年金番号通知書と年金手帳のどちらかを預かっている場合もあるでしょう。国民年金保険の手続きの際や、転職先で社会保険に加入する際にこれらの書類が必要になるため、必ず退職時に返却するようにしましょう。
3-5. その他の書類
退職手続きの際に会社側で準備した書類のうち、次のように、退職者に交付しなければならないものもあります。
- 給与所得の源泉徴収票(※退職後1カ月以内)
- 退職所得の源泉徴収票(※退職後1カ月以内、退職金を支給する場合)
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(※すぐ次の職場へ転職する場合)
- 退職証明書(※希望を受けた場合)
期限が定められているものや、希望者や転職者のみに交付すればよいものもあるので、あらかじめ正しく整理しておきましょう。
4. 【雇用形態別】退職手続きの書類の注意点

ここでは、パート・アルバイトや派遣社員の退職手続きの書類に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. パート・アルバイト
パートやアルバイトであっても、通常の従業員と同様の退職手続きをおこないます。しかし、社会保険に加入していない人もいるため、その場合は、健康保険証(資格確認書)の回収や、社会保険の資格喪失手続きが不要です。
4-2. 派遣社員
派遣社員は、派遣先でなく、派遣元と労働契約を締結しています。そのため、派遣社員から退職の申し出があった場合、退職手続きをするのは派遣元企業です。また、派遣社員であっても、社会保険に加入している場合は、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。健康保険証(資格確認書)の回収などを忘れずにおこないましょう。
5. 退職手続きの書類に関するポイント

ここからは、退職手続きの書類に関して注意すべきポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 書類の内容や受け渡しに抜け漏れがないように入念に確認する
退職手続きでは、会社と退職者との間で書類の受け渡しが頻繁に発生することが想定されます。返却漏れが発生すると、郵送や再度出社してもらうなど、二度手間が生じてしまう恐れがあります。無駄なコストや作業を発生させないためにも、あらかじめ必要な書類のチェックリストや退職手続きマニュアルを作成しておくのがおすすめです。
5-2. 遅延がないようスケジュールに余裕をもって手続きをする
退職手続きを期限内に実施できなかった場合、失業手当の申請ができなかったり、転職先での社会保険の加入手続きができなかったりするなどのトラブルが生じる恐れがあります。また、法律に違反すると、罰金などの罰則が課せられるリスクもあります。このような事態を生じさせないためにも、あらかじめスケジュールを調整し、余裕を持って手続きを進めましょう。
5-3. 郵送する場合は追跡可能な方法で送付する
退職手続きの書類のなかには、個人情報が含まれた書類や、再発行に時間や手間がかかる書類もあります。万が一紛失すると、大きなトラブルにつながる恐れもあります。退職手続きの書類は郵送することもできますが、退職者にきちんと届いたかチェックするため、必ず追跡可能な方法で郵送するようにしましょう。
6. 退職手続きに必要な書類を事前にしっかりと確認しよう!

退職手続きには、さまざまな書類が必要になります。退職手続きのなかには、期限が定められているものもあり、スピーディーかつ正確におこなわなければなりません。退職手続きを効率よく実施するためにも、必要となる書類は事前に集めておきましょう。また、退職手続きの内容をマニュアル化したり、必要な書類のチェックリストを作成したりすると、無駄なく手続きができます。







