
社会保険に加入する従業員が退職した場合や、契約変更により被保険者の資格要件を満たせなくなった場合は「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」の提出が必要です。社会保険への加入手続きと同様に、脱退の手続きも事業主が実施の義務を負います。
原則として、社会保険の加入・脱退を申請する際はその事由が発生してから5日以内に手続きを済ませなければなりません。退職等により従業員が被保険者資格を喪失する際は速やかに手続きをおこないましょう。
本記事では健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届について、書き方や手続きの流れを解説します。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届とは、自社の従業員が健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際に事業主が提出する書類です。被保険者資格を喪失する事由としては対象従業員の退職や死亡、契約内容の変更等が挙げられます。
なお、保険制度からの脱退手続きは原則として資格喪失日から5日以内に済ませなければなりません。手続きが遅れた場合は「納める必要のない保険料が計算されてしまう」「被保険者資格がないにもかかわらず保険給付を受けてしまう」等の問題が生じる可能性があります。
自社の従業員が健康保険・厚生年金保険いずれかの被保険者資格を喪失した際は、速やかに被保険者資格喪失届を提出しましょう。
1-1. マイナ保険証の義務化で手続きは変わるのか
マイナンバー法の改正により2024年12月2日から、現行の保険証発行が終了、医療機関へ受診する際はマイナ保険証か資格確認書の提示が必要になります。
※ 猶予期間の間(最長で2025年12月1日まで)は、現行の保険証でも受診可能
それに伴い、保険証の交付はなくなりますが、資格取得・喪失の届け出は依然として必要となるため、注意しましょう。
また、2025年12月2日以降に資格喪失する場合は、保険証を企業で回収せず、個人で廃棄してよいとされています。
法改正により保険証の扱い方が変わるため、12月付近には従業員からの問い合わせが増えることが予想されます。あらかじめ変更点を理解しておき、対応方法や問い合わせ窓口を用意しておくと良いでしょう。
変更スケジュールは当サイトで無料配布している「社会保険手続きの教科書」の資料でも解説しているので、参考にしてみてください。
2. 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出が必要となるケース

本章では健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースを紹介します。なお、資格喪失日は事由により考え方が異なるため、十分注意しましょう。
2-1. 従業員が退職・死亡した場合
社会保険に加入する従業員が退職した場合は被保険者資格喪失届の提出が必要です。退職の場合は「退職日の翌日」が資格喪失日となります。
また、社会保険に加入する従業員が在職中に死亡した場合も被保険者資格の喪失手続きが必要です。在職中に死亡した場合は死亡日が退職日とみなされるため、その翌日が資格喪失日となります。
関連記事:社員が退職したときの社会保険手続きについて徹底解説
2-2. 契約変更により保険の適用要件から外れる場合
契約変更により保険の適用要件から外れてしまった従業員も被保険者資格喪失届による手続きが必要です。この場合は「新たな契約での勤務を開始する当日」が資格喪失日となります。
なお、パートやアルバイトの従業員のような短時間労働者は、従業員数が101人以上の企業で勤務する場合、以下の条件にあてはまると加入の対象となります。
<短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件>
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
時短勤務への意向やパートタイマーへの雇用区分変更など勤務形態が大きく変化する従業員については労働時間を確認のうえ、必要に応じて被保険者資格喪失の手続きをおこないましょう。
2-3. 従業員が70歳に到達した場合(厚生年金の資格喪失)
70歳以降も勤務を継続する従業員は強制的に厚生年金保険の加入資格を喪失し、以降は「70歳以上被用者」として扱われます。なお、現在では日本年金機構において70歳到達の手続きをおこなうため、原則として事業主による届出は必要ありません。
ただし、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる場合は、「被保険者資格喪失届 70歳到達届」の提出が必要です。なお、「厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の書式を使えば、1枚でまとめて手続きをすることができます。
なお、70歳到達による厚生年金の資格喪失日は「誕生日の前日」です。
2-4. 従業員が75歳に到達した場合(健康保険の資格喪失)
75歳に達した従業員は健康保険から後期高齢者医療制度への切り替えが必要です。後期高齢者医療制度への加入手続きは各自治体がおこないますが、健康保険の資格喪失手続きは事業主側でおこないます。75歳到達による健康保険の資格喪失日は「誕生日当日」です。
なお、後期高齢者医療広域連合により「一定の障害がある」と認定された場合に限り、65歳から74歳までの従業員も後期高齢者医療制度に加入できます。その際も同様に事業主による健康保険の資格喪失手続きが必要です。この場合の被保険者資格の喪失日は「障害者認定を受けた日」となります。
3. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の手続きの流れ

本章では、従業員の被保険者資格喪失に伴う健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の手続きの流れを解説します。書類の提出は資格喪失日から5日以内が目安となるため、手続きが必要となった際は速やかに対応することが大切です。
3-1. 被保険者証を回収する
被保険者資格を喪失する従業員がいる場合は、まず資格喪失日までに被保険者証の回収を依頼して確実に回収できるようにしておきましょう。
保険証の回収が不可能な場合は、回収困難な理由や状況を記載した「被保険者証回収不能届」を添付することで手続きを進められます。また、本人が保険証を紛失してしまっている場合は「被保険者証滅失届」の添付が必要です。
協会けんぽ以外の保険組合に加入している場合は、原則として被保険者資格喪失届以外の書類は必要ありません。ただし、被保険者証は資格喪失後に各保険組合に返却するため、必ず本人から回収しておきましょう。
3-2. 被保険者資格喪失届を作成する
次に手続きに必要な書式である「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を用意しましょう。最新の書式は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
上記の書式では1枚で複数の被保険者の手続きも可能です。被保険者ごとに「被保険者整理番号」や「被保険者の氏名」「生年月日」「基礎年金番号」など記入し、書類を完成させましょう。
詳しい書き方や記載例は日本年金機構のホームページで公開されています。以下のリンクから確認できるので、参考にしてみてください。
3-3. 必要な添付書類を揃える(協会けんぽの場合)
自社が加盟する保険組合が全国健康保険協会(協会けんぽ)である場合、被保険者資格喪失届に以下の書類の添付が必要です。
- 被保険者証
- 高齢受給者証※
- 健康保険特定疾病療養受給者証※
- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証※
※2~4は交付を受けている場合
必要書類に抜け漏れがないかしっかりと確認したうえで、提出をおこないましょう。
3-4. 資格喪失日から5日以内に書類を提出する
被保険者資格喪失届および添付書類は「資格喪失から5日以内に提出」がルールです。書類を封筒にまとめて管轄の年金事務所に提出しましょう。提出方法は郵送、もしくは窓口への持参です。管轄の年金事務所の所在地はあらかじめ確認しておきましょう。
健康保険などの社会保険手続きは届出が遅れたり、抜け漏れがあったりすることで、最悪の場合、法律に触れる可能性があります。
しかし、手続きの書類や方法が複雑で正しいかどうかがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、社会保険手続きを正しくおこなうことができるよう、必要な手続きや書類をまとめたガイドブックを無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして、社会保険手続きの確認にご活用ください。
4. 被保険者資格喪失届の手続きは電子申請も可能
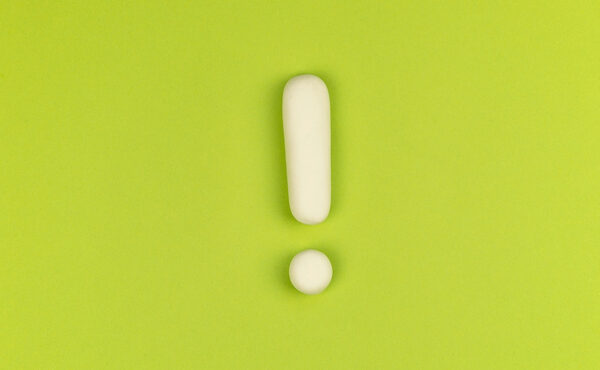
健康保険・厚生年金の被保険者資格喪失届は電子申請も可能です。電子申請であれば届出の際に郵送手続きや窓口に出向く必要がなくなります。
時間や場所を問わず手続きが可能なため、リモートワークへの対応という意味でも利用を検討してみましょう。
4-1. 被保険者資格喪失届の電子申請の方法
被保険者資格喪失届の電子申請の方法は以下の3通りあります。
①総務省が運営する各種行政手続きの窓口「e-Gov」を利用して電子申請する
②届書作成プログラムを利用して電子申請する方法
③労務管理システムを利用して電子申請する方法
それぞれの方法で電子申請する場合の手続きの流れは以下の電子申請ガイドブックで詳しく説明されています。
確認しながら、手続きを進めることで、ミスを防ぐことができるでしょう。
電子申請での届出に慣れると、手続きにかかる時間を短縮できるため、積極的に活用する企業も増えています。
なお、以下の条件にあてはまる法人は2020年4月から社会保険にかかわる一部手続きを電子申請でおこなわなければならない「電子申請義務化」が適用されているので、提出の際には注意しましょう。
- 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
5. 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届のルールを理解し正確な手続きをしよう

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届は、退職等により従業員が被保険者資格を喪失した際に提出する書類です。事業主は資格喪失日から5日以内に書類を作成し、年金事務所への郵送か持参、もしくは電子申請により手続きを済ませなければなりません。
もしも被保険者資格喪失の手続きが遅れた場合、被保険者が保険から脱退できていないことによるトラブルが生じるリスクがあります。事業主に対する法的な罰則はないものの、被保険者資格喪失届の提出が必要なケースでは適切に手続きを実施することが大切です。
関連記事:社会保険喪失証明書とは?発行方法や記載事項について詳しく解説
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









