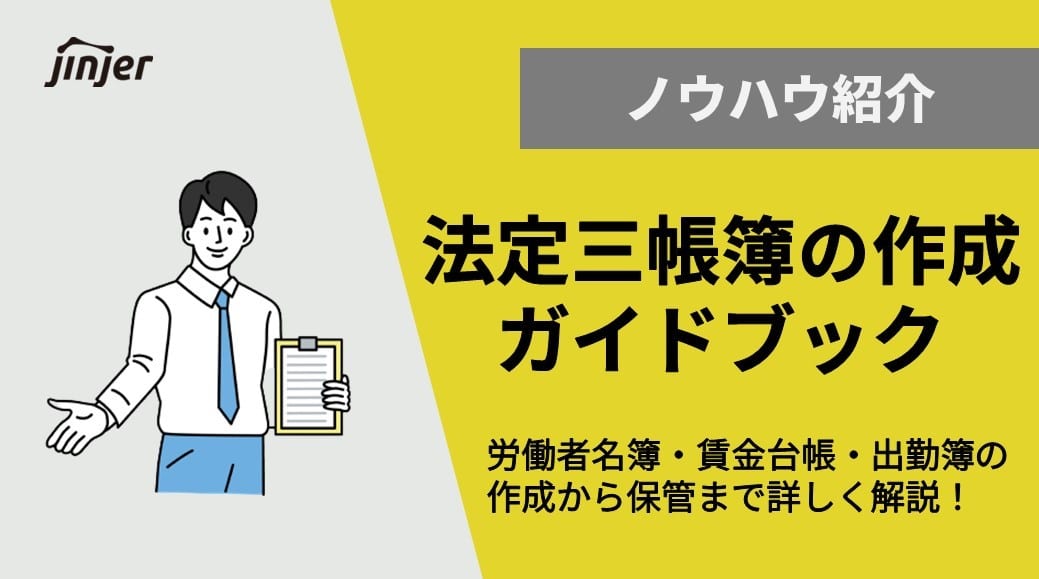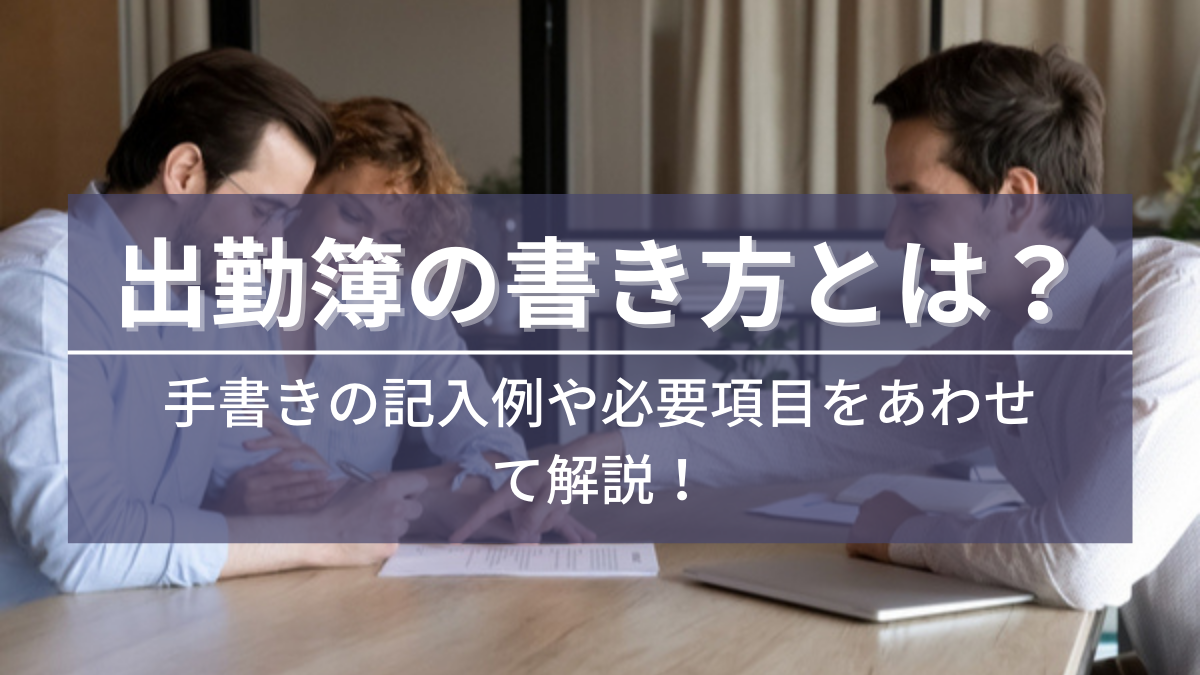
出勤簿は従業員の労務管理をおこなうために必要な帳簿ですが、厳密なフォーマットが設けられているわけではありません。そのため、どのような項目について記載すべきか、きちんと把握できていないというケースもあるでしょう。
本記事では、出勤簿へ記録する方法や出勤簿に記載するべき項目・書き方、出勤簿に記入する際の注意点などについて説明します。
「法定三帳簿の作成ガイドブック」を無料配布中!
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3種類の帳簿のことです。
いずれも、雇用形態に限らず、従業員を雇用する際には必要となるうえ、労働基準法で保存期間や記載事項などが決められているため、適切に調製しなければなりません。
当サイトでは、『法定三帳簿の作成ガイドブック』を無料で配布しており、作成から保管の方法まで法定三帳簿の基本について詳しく紹介していますので、「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「法定三帳簿の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 出勤簿とは?

出勤簿とは、従業員の出勤・退勤時刻を記録し、労働時間や労働日数を把握・管理するものです。「賃金台帳」「労働者名簿」に並んで、法定三帳簿の一つに該当し、5年間保存することが義務付けられています(当分の間は3年)。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
1-1. 出勤簿に記載すべき従業員
企業は、すべての従業員の情報を出勤簿に記載しなければなりません。正社員だけではなく、パートやアルバイト、契約社員なども対象となるため注意しましょう。
また、2019年4月の労働安全衛生法の改正により、管理監督者についても労働時間の把握が義務付けられました。以前は管理監督者の勤怠情報を出勤簿に記載する必要はありませんでしたが、ルールが変わっているため注意しましょう。
1-2. 出勤簿とタイムカードの関係性
従業員の出勤・退勤時刻を記録するために、タイムカードを導入している企業も多いでしょう。タイムカードは便利な機器ですが、従業員が自分で記録をおこなうため、必ずしも正確な時刻を管理できるとは限りません。
出勤簿は、正確な勤怠情報をもとに作成する必要があるので、タイムカードそのものを出勤簿の代わりにすることはできないのです。タイムカードの情報をもとに、作業日報や残業申請書などの補足資料と照合しながら、出勤簿を作成する必要があります。
また2019年4月以降、自己申告制による勤怠管理は原則として禁止されているため、ICカードによる打刻や勤怠管理システムの導入を検討するとよいでしょう。
参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準|厚生労働省
2. 出勤簿へ記録する方法

厚生労働省が発表しているガイドラインでは、従業員の労働時間を把握する方法として以下のいずれかである必要があるとしています。
- 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する
- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する
出勤簿は労務管理をおこなうために必要な書類なので、使用者が自ら確認・記録することが理想的ではあります。ただし、現実問題としてそのような運用は難しいことが多いため、従業員が出退勤の時刻を出勤簿へ直接記載することがほとんどでしょう。
従業員の自己申告による労働時間の把握は推奨されていませんが、自己申告で対応せざるを得ない場合には、既定の措置をとる必要があるため注意しましょう。講じるべき措置の内容は、後述します。
参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準|厚生労働省
3. 出勤簿に記載するべき項目や書き方
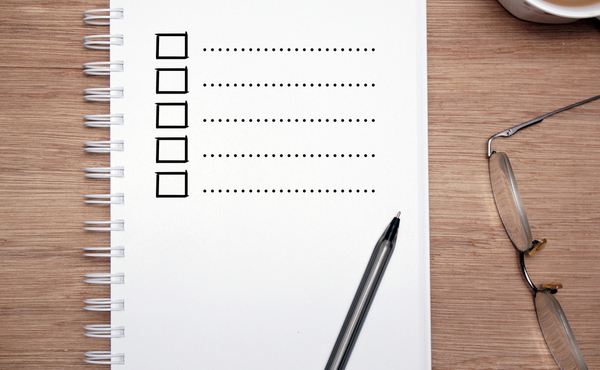
出勤簿に記載するべき項目としては、以下のようなことが挙げられます。
- 従業員の氏名
- 出勤日および出勤日数
- 日別の労働時間数と始業・終業時刻と休憩時間
- 時間外労働をおこなった日付・時刻・時間数
- 休日出勤をおこなった日付・時刻・時間数
- 深夜労働をおこなった日付・時刻・時間数
それぞれの項目および書き方について、説明します。
3-1. 従業員の氏名
従業員の氏名については正確に記載しておく必要があります。必要に応じて社員番号や所属部署などを記載しておくと、わかりやすいでしょう。
3-2. 出勤日および出勤日数
出勤簿であるため、出勤日や出勤日数は当然記載しておかなければならない項目の一つです。
最近では在宅勤務やテレワークといった形で働くことも増えてきていますが、そのように出社せずに働いている日も記録する必要があります。
3-3. 日別の労働時間数と始業・終業時刻・休憩時間
出勤した日ごとの労働時間数も記載する必要があります。労働時間数は「始業時刻」と「終業時刻」および「休憩時間」がわかれば算出することが可能です。
たとえば、始業時刻が8時45分、終業時刻が17時45分、休憩時間が12時~13時の1時間という場合は、労働時間は「9時間 – 1時間 = 8時間」ということになります。
3-4. 時間外労働をおこなった日付・時刻・時間数
時間外労働(法定外残業)とは、基本的に「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超える部分のことを指します。
ただ、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用している会社の場合、時間外労働の算出方法が異なる可能性もあるので、それぞれの会社の体制に即した形で算出しましょう。
関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説
3-5. 休日労働をおこなった日付・時刻・時間数
出勤簿に記載をおこなう際の「休日」とは、「週1日」もしくは「4週間を通じて4日」の法定休日のことを指します。所定休日の労働は、休日労働にあてはまらないため注意しましょう。
関連記事:所定休日の割増賃金とは?法定休日や割増賃金の計算方法も詳しく紹介
3-6. 深夜労働をおこなった日付・時刻・時間数
深夜労働は「深夜22時~翌朝5時」の時間帯の労働のことで、この時間帯においては裁量労働制や管理監督者であっても、割増賃金の対象となります。そのため、労働時間を適切に把握できるように、漏れなく記載しなければなりません。
関連記事:夜勤とは何時から働いた場合のこと?労働基準法上の定義とは
3-7. 出勤簿の記入例
出勤簿を作成する際には、上記の項目を漏れなく記録する必要があります。
ただし、出勤簿のフォーマットについては、法律で規定されていないため、手書きの場合は以下の厚生労働省が公開している資料の記入例(2ページ目)を参考に作成することをおすすめします。
その他にも出勤簿のひな形や見本はWeb上で複数公開されているので、必要事項がそろっていることを確認のうえ、ダウンロードして活用してもよいでしょう。
参考:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう |厚生労働省
出勤簿を含む法定三帳簿は適切に調製して保管しておく必要があります。作成に不安のある方は、当サイトで無料配布している「法定三帳簿の作成ガイドブック」もご確認ください。資料では、法定三帳簿の記入項目とその書き方を解説しているほか、それぞれのフォーマットもご確認いただけるため、適切に法定三帳簿を調製したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
4. 出勤簿の管理方法

出勤簿の管理方法は、出勤簿の媒体により異なります。紙媒体で出勤簿を作成している場合にはキャビネットにまとめるほか、エクセルにデータを入力し電子化して保存するなどの方法が考えられます。
エクセルで出勤簿を作成している場合には、USBメモリやハードディスクなどにデータを写すなどして保存するケースが挙げられるでしょう。勤怠管理システムで出勤簿を作成する場合は、エクセルに出力することも可能なほか、給与計算と連動しているシステムであれば自動で給与計算までしてくれます。
出勤簿を紙媒体やエクセルで作成すると、記入ミスや抜け・漏れ、改ざんなどが起こりうるため、客観性のある適正な勤怠データを得られないこともあるかもしれません。法律に沿って効率的に出勤簿の記録・作成をおこなうには、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
4-1. 出勤簿の保管期間
前述の通り、労働基準法に従って出勤簿は5年間保管しなければなりません。賃金請求権の時効が5年に延長されたことに伴い、出勤簿の保存期間も変更されました。当面の間は3年間でも問題ありませんが、いずれは経過措置が終了するため、5年間保管できるよう仕組みを整えておきましょう。
関連記事:出勤簿の保存期間は7年?5年?法改正の内容・適切な保存方法も解説
5. 出勤簿に手書きで記入する際の注意点

出勤簿に記入する際は、労働時間を客観的に把握できるデータをもとにする必要があります。ただし、場合によっては従業員の自己申告によって始業・終業時刻などを把握しなければならないこともあり、そのようなケースでは以下に挙げるような点に注意することが必要です。
- 従業員に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告をおこなうことなどについて十分な説明をおこなう
- 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査をおこない、所要の労働時間の補正をおこなう
- 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定しない
以下、それぞれの注意点について説明します。
5-1. 労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告をおこなうことなどについて十分に説明をする
従業員に労働時間を申告してもらう場合、人によってどこからどこまでを労働時間と認識しているか異なる可能性があります。また、使用者が労働時間として認識している時間ともずれが生じる可能性もあるため、対象となる従業員に対しては、適正に自己申告をおこなうことなどについて、十分な説明をする必要があります。
5-2. 把握した労働時間が実労働時間と合致しているか、必要に応じて実態調査をおこない、所要の労働時間の補正をおこなう
従業員からの自己申告によって労働時間の把握をおこなう場合でも、使用者側で労働時間に関して、執務室への入退室時間など、ある程度客観的なデータを有している場合もあります。
そのようなデータから把握できる労働時間と、従業員自身が申告している労働時間に大きな乖離がある場合、必要に応じて実態調査をして、場合によっては労働時間の補正をおこなわなければなりません。
5-3. 労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定しない
上述したように、従業員自身に適正に自己申告をおこなってもらわなければ、労働時間を適切に管理することはできません。そのため、労働時間の適正な申告を阻害する目的で、時間外労働時間数の上限を設定するようなことは避けましょう。
会社が出している措置などが従業員による適正な申告を阻害する要因になっていないか確認し、要因となっていると認められる場合は、改善措置を講じる必要があります。
6. 出勤簿の書き方に関してよくある質問

ここからは、出勤簿の書き方に関してよく生じる疑問について解説します。出勤簿に有給、産休、休業、欠勤を書く具体的な方法を紹介しているので、確認しておきましょう。
6-1. 有給休暇の書き方は?
従業員が有給休暇を取得した日の出勤簿は、備考欄に「有給」の旨を記すことが一般的です。月あたりの「有給取得日数」の合計欄があれば、そちらに従業員が取得した有給の日数も記載しましょう。
有給休暇とは、労働の義務を免除して給与を支給する日のことです。そのため、始業・終業時刻欄に定時を記すか記さないかは、各企業の出勤簿作成の目的・方針によって異なります。自社にとって最適な方法で記載する認識で問題ないでしょう。
関連記事:有給休暇の金額はいくら?給料として支払う際と買取の際の計算方法
6-2. 産休の書き方は?
従業員が産休を取得した日の出勤簿は、欠勤として扱わず、「産前産後休業(休暇)」と記載するようにしましょう。また、出産手当金の受給には、出勤簿と賃金台帳の写しを提出書類に添付する必要が生じるため、正確に記載することが大切です。
6-3. 休業の書き方は?
休業がある際には、休業日は「休業」などと記載することが一般的です。また、企業が休業をする際には、出勤簿を雇用調整助成金の申請に用います。従業員一人ひとりの出勤時刻・労働日数などに漏れがないか確認することが重要です。
6-4. 欠勤の書き方は?
従業員が欠勤した日には、始業・終業時刻は記さず、所定の欄に「欠勤」と記載しましょう。所定の欄がない場合は、備考欄に「欠勤」と記載することが一般的です。月あたりの「欠勤日数」の合計欄があれば、その欄に日数も記載しましょう。
7. 出勤簿の記入を効率化する方法

出勤簿の記入を効率化した場合は、エクセルや勤怠管理システムを活用するとよいでしょう。
7-1. エクセルを活用する
紙の出勤簿よりは、エクセルを活用したほうが勤怠管理を効率化できるでしょう。エクセルの大きなメリットは、誰でも簡単に使えることです。会社のパソコンにインストールされていることも多く、費用を抑えて勤怠管理を効率化できます。
また、関数を設定しておけば、労働時間や残業時間の合計を自動で計算することも可能です。計算ミスなどを減らせるため、出勤簿のペーパーレス化を検討している場合はエクセルを活用してみましょう。
7-2. 勤怠管理システムを導入する
従業員の出勤・退勤時刻や残業時間の管理をより効率化したい場合は、勤怠管理システムの導入がおすすめです。とくに従業員数が多い企業においては、エクセルによる管理に限界を感じることも多いでしょう。また、エクセルの場合は、不正なアクセスや書き換えにも注意しなければなりません。
勤怠管理システムであれば、勤怠情報を一元管理し、不正アクセスなどを防止することも可能です。労働時間の自動集計や給与計算システムとの連携なども可能なため、勤怠管理に関する業務を大幅に効率化できるでしょう。
8. 出勤簿の書き方をしっかりと理解しておこう!

今回は、出勤簿の書き方や管理方法などを解説しました。出勤簿は労務管理をおこなうために必要な書類であり、出勤日や出勤日数などの所定の項目を記載しなければなりません。客観的な記録をもとにして記入をおこなうのが原則ですが、従業員の自己申告によって始業・終業時刻などを把握する必要がある場合もあります。そのような場合は、従業員に対して適正に自己申告をするよう十分な説明をおこなうことなどを、意識しましょう。
また、紙の出勤簿を使っていると管理や集計の手間がかかるので、必要に応じてエクセルや勤怠管理システムを活用するのがおすすめです。業務を効率化して担当者の負担を軽減するためにも、便利なシステムの導入を検討しましょう。
「法定三帳簿の作成ガイドブック」を無料配布中!
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3種類の帳簿のことです。
いずれも、雇用形態に限らず、従業員を雇用する際には必要となるうえ、労働基準法で保存期間や記載事項などが決められているため、適切に調製しなければなりません。
当サイトでは、『法定三帳簿の作成ガイドブック』を無料で配布しており、作成から保管の方法まで法定三帳簿の基本について詳しく紹介していますので、「法律に則って適切に帳簿を管理したい」「法定三帳簿の基本を確認しておきたい」という担当者の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。