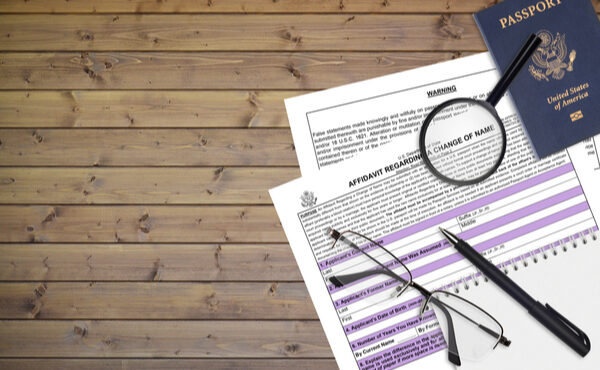
マイナンバー制度の進展により、従業員が市区町村の窓口で手続きをすれば、連動して社会保険の名義変更もおこなわれるようになりました。しかし、従業員の扶養者の名義変更など、現在でも一部の名義変更は会社での手続きが必要です。本記事では、結婚や離婚などによって、従業員の氏名に変更があった場合に必要な社会保険の名義変更手続きについてわかりやすく解説します。また、事業所の名義変更手続きについても紹介します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険の名義変更が必要なケース

結婚や離婚などにより、従業員の氏名に変更があった場合、社会保険の名義変更手続きが必要です。また、従業員だけでなく、事業所の名称などに変更があった場合も、社会保険の名義変更手続きをしなければなりません。なお、名義変更が必要になる社会保険の種類は、次の通りです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険(事業所のみ)
ここでは、従業員の氏名が変更になった場合に、社会保険の名義変更が必要になるケースについて詳しく紹介します。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
1-1. 健康保険・厚生年金保険
マイナンバー制度の導入により、2018年3月から、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている被保険者に関しては、氏名変更手続きが不要となりました。そのため、従業員が各自治体の窓口で、婚姻届や離婚届、転入届を提出すれば、原則として、その情報に紐づいて自動的に社会保険に関する情報も変更されます。ただし、従業員で次のいずれかに該当する場合、健康保険・厚生年金保険の名義変更手続きが必要です。
- マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない従業員の氏名変更(訂正)
- マイナンバーを保有していない海外居住者の氏名変更(訂正)
- 短期在留外国人労働者の氏名変更(訂正)
70歳を超えて健康保険(協会けんぽ)にのみ加入している従業員については、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合でも、社会保険の名義変更手続きが必要です。また、健康保険組合(組合健保)に加入している場合、健康保険組合によって手続き方法が異なるので注意しましょう。
なお、従業員(被保険者)でなく、その家族(被扶養者)の氏名が変更(訂正)になる場合、マイナンバーを有しているかどうか、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいているかどうかに関係なく、「健康保険被扶養者(異動)届」にて手続きをおこなうことになります。
1-2. 雇用保険
2020年1月から「雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止されたため、雇用保険に関しては、従業員の氏名に変更があった場合でも、名義変更単独での手続きは不要です。名義変更が必要な際は、以下の手続きと合わせておこないます。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用継続交流採用終了届
- 雇用保険被保険者転勤届
- 個人番号登録・変更届
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
- 高年齢再就職給付金の支給申請
- 育児休業給付金の支給申請
- 介護休業給付金の支給申請
それぞれの届書に氏名変更記入欄があるため、記載して変更します。
関連記事:【雇用保険がわかる】人事担当者が知るべき雇用保険を徹底解説
2. 社会保険の名義変更手続きの流れと必要書類
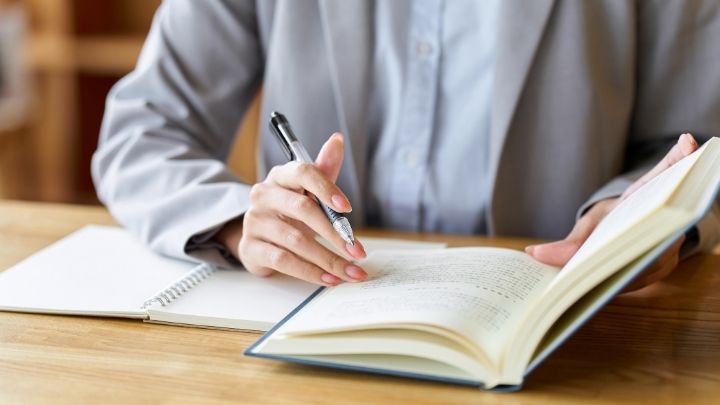
ここでは、結婚や離婚などによって氏名が変更された場合の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の名義変更手続きの流れと必要書類について詳しく紹介します。
2-1. 従業員(被保険者)の名義変更の方法
従業員(被保険者)の社会保険の名義変更手続きをする場合、「被保険者氏名変更(訂正)届」を使って届出をおこないます。協会けんぽに加入している場合、被保険者氏名変更(訂正)届を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)に提出することで、健康保険と厚生年金保険の両方の名義変更手続きを一括しておこなうことが可能です(組合健保に加入している場合については後述)。
書類の提出方法には、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類があります。提出期限は明確に定められていませんが、速やかに手続きすることが求められます。また、次のような添付書類も必要になるので注意しましょう。
- 資格確認書
- 健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 特定疾病療養受療証
- 健康保険限度額適用認定証等
- ローマ字氏名届(外国人従業員のみ)
なお、保険者氏名(漢字)が書類に記載されることから、被扶養者の資格確認書や健康保険被保険者証の添付も原則必要です。ただし、フリガナのみの名義変更になる場合は添付不要です。
2-2. 従業員が扶養する者(被扶養者)の名義変更の方法
従業員(被保険者)の社会保険の名義変更手続きをする場合、「被扶養者(異動)届」を用いて届出をおこないます。協会けんぽに加入している場合、被扶養者(異動)届を日本年金機構に提出することで、扶養に関する名義変更手続きが可能です(組合健保に加入している場合については後述。)。
書類の提出方法は、従業員の名義変更の場合と同様で、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類です。提出期限も明確に定められていませんが、速やかに手続きしましょう。また、被扶養者に交付されている資格確認書や健康保険証などの添付も必要になるので注意が必要です。なお、被保険者の資格確認書や健康保険証の添付は不要です。
2-3. 健康保険組合に加入する会社の場合
協会けんぽに加入する会社は、健康保険と厚生年金保険について、どちらも同一の届出で手続きが完了します。しかし、健康保険組合(組合健保)に加入する会社では、厚生年金の手続きとは別に、各健康保険組合で名義変更の手続きが必要です。
各健康保険組合により申請書の様式や必要書類は異なります。氏名変更にどのような手続きが必要か、担当窓口に確認し対応しましょう。
3. 事業所の名義変更があった場合の社会保険手続き

従業員の氏名だけでなく、事業所の名称や事業主の氏名などが変わった場合も、社会保険の名義変更の手続きが必要です。ここでは、事業所に関する名義変更があった場合の社会保険手続きについて詳しく紹介します。
3-1. 雇用保険・労災保険
雇用保険や労災保険について、事業所の名称や所在地が変わる場合、「労働保険名称、所在地等変更届」を所轄の労働基準監督署もしくは公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を所轄の公共職業安定所にそれぞれ変更のあった日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。手続きの内容によって、添付書類も変わるため注意が必要です。なお、法人事業所の事業主のみが変わった場合であれば、手続きは不要です。
また、事業所の移転などにより、管轄する公共職業安定所自体が異なるときは、移転後の住所を管轄する事務所へ書類を提出します。これらの書類を提出しただけでは、ハローワークの求人票の情報は変更されません。求人を出している場合、「雇用保険事業主事業所各種変更届」が受理された後、交付された「事業主控」を求人担当者に提出し、登録内容を変更しましょう。
関連記事:被保険者住所変更届が必要なケースや手続き方法を解説
3-2. 健康保険・厚生年金保険(事業所の名称・所在地が変わる場合)
健康保険・厚生年金保険について、事業所の名称・所在地(管轄内)が変わる場合、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を事実発生から5日以内に日本年金機構へ提出する必要があります。
提出方法は、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類です。また、変更内容に応じて、次のような添付書類も必要になります。
- 法人(商業)登記簿謄本のコピー(法人事業所で名称・所在地を変更する場合)
- 個人番号が記載されていない事業主の住民票のコピー(個人事業所で所在地を変更する場合)
- 公共料金の領収書のコピー等(個人事業所で名称を変更する場合)
なお、法人(商業)登記簿謄本や住民票の写しは、提出日から遡って90日以内に発行されたものに限られます。また、他の都道府県へ事業所が移転する場合、従業員の資格確認書や健康保険証に記載されている記号が変更になる可能性もあり、その場合は一度回収し、再交付が必要になるので注意しましょう。
3-3. 健康保険・厚生年金保険(事業所の登録内容が変わる場合)
事業主の変更など、事業所として登録している内容に変更があった場合、「事業所関係変更(訂正)届」を事実発生から5日以内に日本年金機構へ提出する必要があります。提出方法は、他の手続きと同様で「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3種類です。また、変更内容に応じて、次のような添付書類が必要になることもあります。
- 法人(商業)登記簿謄本のコピー(会社法人等番号に変更・訂正があった場合)
- 法人番号指定通知書のコピー(法人番号に変更があった場合)
なお、事業所の名称変更などをする際、協会けんぽでなく、組合健保に加入している場合、各健康保険組合に届出が必要になる可能性もあるため注意しましょう。
4. 社会保険の名義変更に関する注意点

ここでは、社会保険の名義変更に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 社会保険では旧姓の使用が認められない
結婚や離婚などにより姓に変更があった場合でも、働きやすい環境を整備するため、旧姓の使用を認める企業も増えています。そのような会社で働く場合、名刺やメールアドレス、社員証などを旧姓のままにしている人もいるかもしれません。
しかし、社会保険に関しては、旧姓のままにしておくことができません。国や行政機関は戸籍名によって管理をおこなっているため、社会保険を含め、源泉徴収簿や労働者名簿などの法的な根拠を求められる書類については名義変更をする必要があります。
4-2. 名義変更をしていない保険証は使用できない
社会保険の名義変更手続きをしない場合、健康保険証の記載が旧姓のままとなります。旧姓のまま健康保険証を使用することは認められていないため、社会保険の名義変更手続きをして、新しい健康保険証の交付を受けましょう。
なお、協会けんぽに加入する会社の場合、氏名変更後の健康保険証は自動的に事業所へ送付されます。古い健康保険証は回収した後、日本年金機構へ返送が必要です。従業員個人で返送したり、会社側で勝手に破棄したりしないようにしましょう。
また、2022年9月から健康保険証に戸籍名と旧姓の両方を記載できるように変更されました。併記を希望する場合、申請すれば、戸籍名の横に括弧書きで旧姓が記載されます。
Q:結婚して、会社では旧姓を使用しています。保険証も旧姓を使用できますか?
A:保険証には旧姓は使用できませんので、氏名変更の手続きが必要となります。手続きが完了した後、新たな保険証を交付します。
参考:被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い|全国健康保険協会
4-3. 従業員の住所や生年月日に変更・訂正がある場合も社会保険手続きが必要
従業員の氏名だけでなく、住所や生年月日に変更・訂正がある場合も、原則として社会保険手続きが必要です。住所に変更があった場合は「被保険者住所変更届」を、生年月日に訂正があった場合は「被保険者生年月日訂正届」を速やかに日本年金機構(および健康保険組合)に提出します。なお、被扶養者に関する変更については、「被扶養者(異動)届」を用いて手続きをします。
5. 従業員の名義変更に伴う社内の必要業務
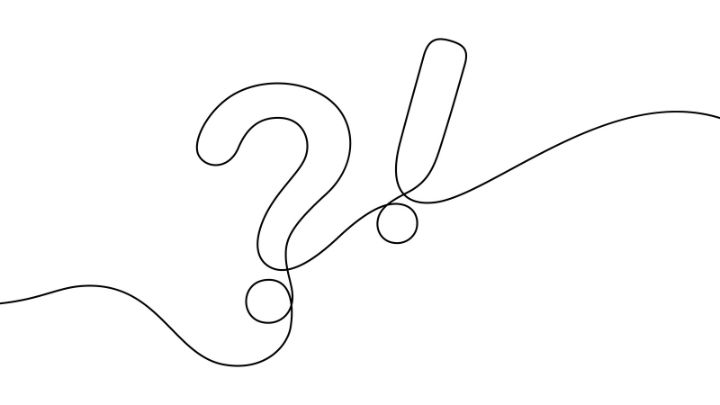
従業員の名義変更があった場合、社会保険関係の手続きのほかにも、社内でさまざまな手続きが必要です。ここでは、従業員の名義変更に伴う社内の必要業務について詳しく紹介します。
5-1. 労働者名簿の修正
労働者名簿には、戸籍上の氏名を記載しなければなりません。仕事上での呼称を旧姓のままにする場合でも、忘れずに更新しましょう。また、緊急連絡先名簿など、関連する書類についても更新が必要です。従業員の配偶者の氏名が変わる場合も更新を忘れないようにしましょう。
5-2. 「扶養控除等(異動)申告書」の変更
結婚や離婚により配偶者が扶養親族となる場合、社会保険の扶養・名義変更手続きだけでなく、所得税の控除に関する手続きも必要です。扶養親族に増減があった場合、「扶養控除等(異動)申告書」を再度提出してもらう必要があります。
この書類を基に、月々の給与から天引きする源泉所得税を調整します。また、年末調整では、配偶者控除(配偶者特別控除)を考慮したうえで、所得税を計算する点にも注意しましょう。
5-3. 各種手当の見直し
会社のルールによっては、結婚したことにより家族手当が追加されたり、引っ越しに伴い通勤手当が変更されたりするケースもあります。正しい手当を支給できるよう、すぐに変更手続きを進めましょう。
また、各種手当は固定的賃金に該当するため、大きく賃金額に変更が生じた場合、月額変更届(随時改定)の提出が必要になる可能性もあるので気を付けましょう。
関連記事:社会保険の随時改定はいつから必要?おこなうための条件や手続き方法を紹介
6. 社会保険の名義変更が必要かどうかを把握しておこう!

マイナンバー制度の導入により、社会保険の名義変更手続きは圧倒的に削減されました。しかし、現在でも外国人従業員や扶養家族の名義変更などについては、会社にて手続きが必要になります。また、事業所や事業主の名義変更は個別の手続きが必要です。
社会保険の名義変更手続きに遅れが生じると、健康保険証が利用できないなどのトラブルが生じる恐れもあります。手続き漏れが発生しないよう、どのような社会保険の名義変更手続きが必要なのか、事前にマニュアルとしてまとめておくことが推奨されます。









