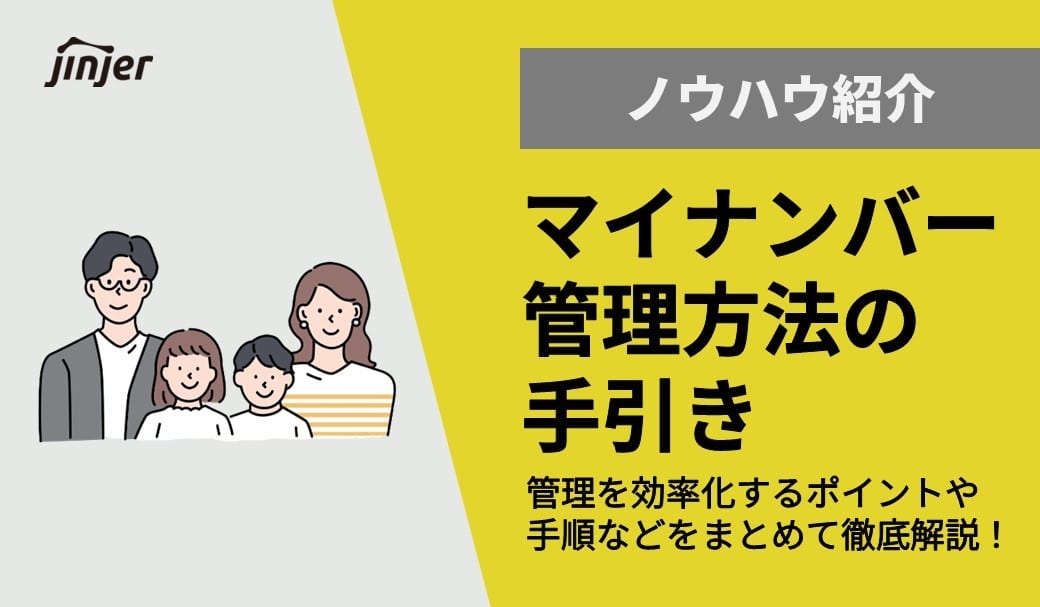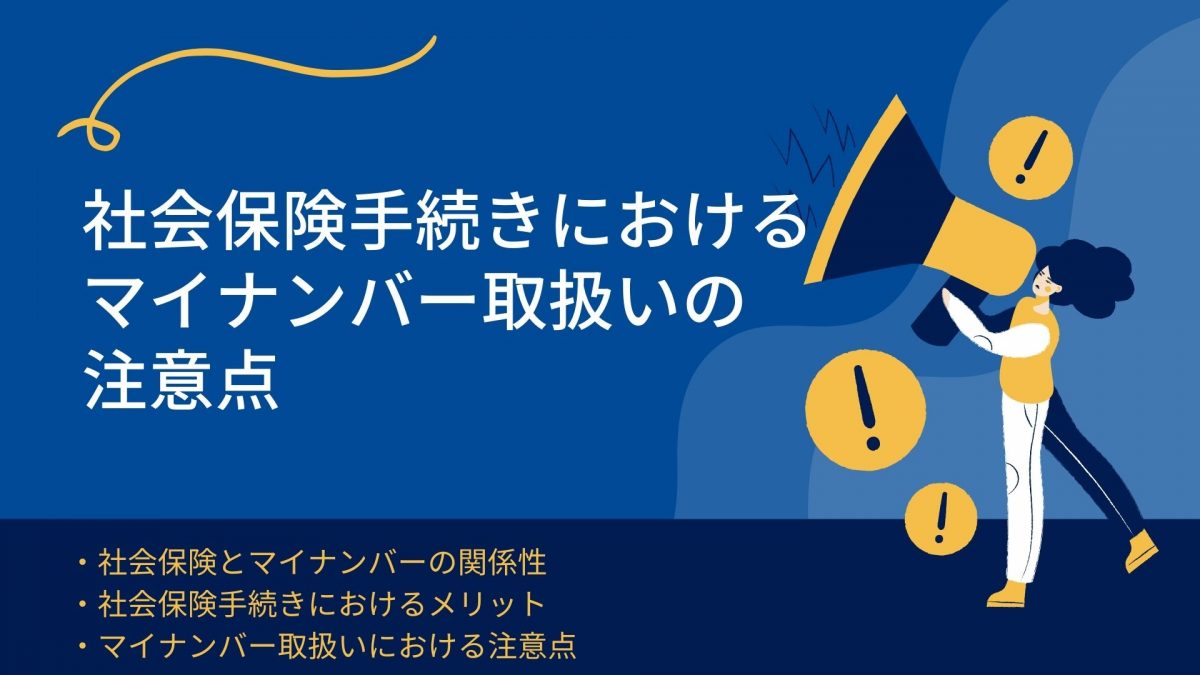
マイナンバー制度の導入により、社会保険手続きの方法も変更されました。企業では、従業員のマイナンバーを管理する必要がありますが、マイナンバーの保管方法に頭を悩ませている担当者も多いでしょう。
マイナンバーは従業員の各種手続きに必要になることもあり、人事担当者が把握をしなければならない重要な情報です。労務管理をする際に社会保険とも紐付ける必要があり、マイナンバーでの管理が従業員の老後の年金などに大きく関わってきます。
そこで今回は、マイナンバーと社会保険がどのような場面で連携しているのか、またマイナンバーの取扱いにおいて注意したいことを紹介します。
非常に複雑で手間のかかる、従業員のマイナンバー管理。
誤ってマイナンバー情報を流出させてしまった場合、個人情報保護委員会から勧告を受ける可能性もあります。多忙な中でそのような事態になることを防ぐためには、万全なセキュリティ体制やルールについてしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
当サイトでは、マイナンバーの収集から保管、廃棄まで段階ごとの対応と、安全な管理方法について細かく解説した資料を無料で配布しています。人事や総務の担当でマイナンバー管理にお困りの方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. マイナンバーとは?

マイナンバーとは国民全員が持つ12ケタの番号のことで、税や年金、雇用保険などの行政手続きに使用されます。
マイナンバーの普及により、税や年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった書類が削減され、これらの手続きの利便性が高まるといわれています。また、行政事務の効率化や公平な各種給付の確保などを実現することも、マイナンバー導入の大きな目的です。
1-1. マイナンバーの仕組みとは?
マイナンバーは、住民票を有する全ての国民に割り振られ、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報を一元管理するために活用されています。社会保障や税の公平化を実現することを大きな目的として、マイナンバー制度が導入されました。
マイナンバーの仕組みは、まず住民登録している各市区町村より個人番号通知カードという紙のカードが届きます。その後、希望者のみ各市区町村にて個人番号カードへ切り替えることができ、同カードを身分証明書として扱うことが可能です。
通知カードを個人番号カードへ切り替える手間はかかりますが、保険証として利用できるなど、利便性は高まりつつあります。
1-2. マイナンバーは何に使われるのか?
マイナンバーの導入目的は上記で述べた通り、行政手続きの利便性向上と社会保障の公平化です。マイナンバーが導入されたことにより、今後さらに行政関連の情報や銀行口座にも紐付けされる可能性があり、生活保障の不正受給や各種税金の未納など、公平な社会保障が実現すると考えられます。
1-3. マイナンバーカードは保険証として利用できる
マイナンバーカードは、保険証と紐付けることが可能です。手続きをおこなうことで、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。この機能は「マイナ保険証」と呼ばれており、利便性や医療サービスの向上を目的として2021年から導入されました。
2024年12月からは現状の保険証は廃止されるため、マイナ保険証に変更する必要があります。マイナ保険証に変更すると、就職や転職の際に保険証を切り替える必要がなくなるため、手続きが効率化されるでしょう。
参照:健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料|全国健康保険協会
2. マイナンバーは社会保険手続きで利用される
 マイナンバーが導入されたことにより、社会保険の手続きにおいてマイナンバーを記載する必要があります。雇用保険、健康保険、厚生年金など、いずれの手続きにおいてもマイナンバーを使用するため、しっかりと管理したうえで適切な手続きをおこないましょう。
マイナンバーが導入されたことにより、社会保険の手続きにおいてマイナンバーを記載する必要があります。雇用保険、健康保険、厚生年金など、いずれの手続きにおいてもマイナンバーを使用するため、しっかりと管理したうえで適切な手続きをおこないましょう。
2-1. マイナンバーは社会保険とどのような関係なのか?
従業員を雇用する場合、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、といった多くの社会保険に関する手続きが発生します。マイナンバーは上記全ての手続きにおいて必要です。
ハローワーク、年金機構、税務署など、手続きを担当する管轄はそれぞれ異なっており、必要な書類にはマイナンバーを記載しなければなりません。また、生命保険の受給の際にもマイナンバーが必要となる場合もあります。
2-2. マイナンバーの記入が必要な社会保険関係の書類
マイナンバーは、以下のように個人および企業における各種手続きにおいて必要です。
- 雇用保険 資格取得届、資格喪失届、高年齢雇用継続給付申請書、育児休業給付金支給申請書など
- 健康保険・厚生年金保険 資格取得届、資格喪失届、被扶養者異動届、傷病手当支給申請書など
- 所得税 扶養控除申告書、支払調書、源泉徴収票、給与支払報告書など
個人においては、確定申告や失業給付などの場面があり、企業においては、健康保険や厚生年金の資格取得・喪失届、年末調整などの手続きに必要となります。
関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介
3. マイナンバー導入による社会保険手続きにおいてのメリットとは?

マイナンバーの管理にかかるコストを考えると、なぜ導入されたのか疑問に思う人も少なくないでしょう。情報漏洩が心配だという人もいるかもしれません。
しかし実際には、情報管理の効率化や手続きの簡略化などのメリットがあります。以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
3-1. 従業員の情報管理を効率化できる
従業員に関する情報管理を効率化できることは、マイナンバー導入による大きなメリットです。従業員ごとに異なる番号を使って情報を管理することで、社会保障や雇用情報の管理の正確性が高まります。社会保険に関する手続きもスムーズにおこなえるようになり、業務の効率化を図れるでしょう。
3-2. 手続きを簡略化できる
マイナンバー導入により、以下のような手続きが不要となります。
- 被保険者の住所・氏名変更届が不要
- 年金手帳確認が不要
- 資格取得届に住所が不要
- 一部の届出・申請で住民票や所得証明が不要
ペーパーレス化を図れるのはもちろん、作業工数やコストの削減にもつながるでしょう。
4. マイナンバーの取扱いで注意することは?

マイナンバーは、特定個人情報という個人情報より重要度の高い分類です。とくに企業においては、昨今の情報漏洩問題もあるので、厚生労働省のガイドラインには、マイナンバーを扱う専用ルームや専用PCなどの設置が案内されています。
ここでは、マイナンバーに対する管理の姿勢について解説します。
4-1. マイナンバーは厳重管理が必要
前述の通り、マイナンバーは特定個人情報であるため、厳重に管理しなければなりません。今後、マイナンバーが普及するにつれ、マイナンバーの闇市場における価値も上がり、個人および企業は今以上にマイナンバーを保護する必要があります。
個人でマイナンバーを取り扱う際に注意する点は、安易に公表しないことです。生命保険の受給手続きにマイナンバーが必要となるケースもあると説明しましたが、本当に必要なのかを自分で考え、確認する必要があるでしょう。
とくに高齢者は現役の社会人と比べると、マイナンバーの重要性を認識していない可能性もあります。家族や親族、友人へ周知するとともに、安易にマイナンバーを公表しないことを意識しなければいけません。
また、企業においては、マイナンバーを保護することにはコストがかかります。しかし、企業は従業員のマイナンバーを保護する義務があります。コンプライアンスの観点からも指定した者しか閲覧できないルールを作り、マイナンバーの収集や専用PCへの入力、指定場所への保存、といったマイナンバー管理方法を改善していくことが重要です。
現在は、マイナンバーを安全に管理するためのシステムもあります。専用ルームやPCを準備するための手間やコストを省くことができるため、導入を検討してみてください。
4-2. マイナンバーの利用目的を明示する
従業員からマイナンバーの提出を求める際は、利用目的を明示しなければなりません。健康保険や厚生年金保険の手続きのために必要であるなど、具体的な利用目的を伝えたうえで提出を求めましょう。
従業員のなかには、マイナンバーの必要性を理解していない人もいるかもしれません。無理に提出を求めると従業員が疑問を感じる可能性もあるので、丁寧に説明しておくことが大切です。
4-3. マイナンバーの提出を拒否されたときの対応
健康保険や厚生年金保険の手続きにおいてマイナンバーの記入が必要な場面はあるものの、従業員がマイナンバーを提出する義務はありません。マイナンバーの提出を拒否された場合、強制的に提出させることはできないので注意しましょう。
従業員に提出を拒否されたときは、まずはマイナンバー制度の趣旨や利用目的をしっかりと説明します。それでも提出してもらえない場合は、基礎年金番号を記入する、届出先に事情を説明したうえで受け付けてもらうなどの対応が可能です。対応に悩んだときは、管轄の届出先に相談してみましょう。
5. 社会保険におけるマイナンバーの取扱いに注意しよう!

今回は、社会保険におけるマイナンバーの取扱いについて解説しました。マイナンバー制度の導入により、社会保険手続きを簡略化できる、従業員に関する情報管理を効率化できる、といったメリットを得られます。
一方で、企業側は従業員から提供されたマイナンバーを厳重に管理しなければなりません。情報漏洩が発生すると、従業員に迷惑がかかるのはもちろん、社会的なイメージが低下してしまうため十分に注意しましょう。