
社会保険に加入している人であれば、どのような条件で家族が扶養になるのか知っておく必要があります。
社会保険で扶養に入るためには条件があり、この条件から外れると扶養からも外れてしまうからです。
当記事では、社会保険の扶養を外れる条件やタイミングについて解説します。また、社会保険の扶養から外れる際の手続きや注意点についても紹介します。
関連記事:>社会保険の扶養範囲や扶養の手続き方法についてわかりやすく解説
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 「扶養」には2つの種類がある
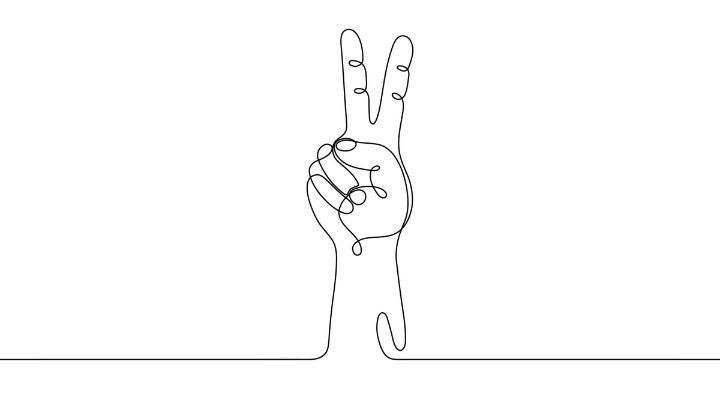
そもそも「扶養」とは、未成年者や無職など、自身の稼ぎで生計を立てられない家族・親族に対して、経済的な援助を行う仕組みです。
この扶養には、2つの種類があります。
1-1. 税制法上の「扶養」
税制法上の扶養とは、所得税法に基づいて扶養控除を受けられる扶養のことです。
税制法上の扶養控除を受けるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。以下の条件を全て満たすことで、納税者の所得税が軽減されます。
- 扶養親族の合計所得金額が48万円以上であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
1-2. 社会保険制度上の「扶養」
社会保険制度上の扶養とは、健康保険や年金の被扶養者と認定されることです。被扶養者になるためには、「被保険者との関係」と「収入の基準」の2つの条件を満たしていなくてはなりません。
「被保険者との関係」では、被保険者と同居していなければならない場合と、被保険者との同居が必要ない場合があります。被扶養者となりうる範囲は以下の通りです。
①同居か別居かを問わない人
- 配偶者(内縁関係も可)
- 子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居していることが条件になる人
- 上記の①以外の3親等内の親族(甥・姪・叔父・叔母など)
- 被保険者の配偶者(内縁関係も含む)の父母・連れ子
- 配偶者(内縁関係も含む)死亡後の父母・連れ子
直系尊属には、養子縁組をおこなったケースも含まれます。
続いて、「収入の基準」です。
社会保険制度上の被扶養者になれるかどうかは、被扶養者の収入も関係してきます。収入の基準には、被保険者との同居の有無が影響します。
被扶養者を同居する場合、被扶養者になる人の年収は、一部を除き、年間収入130万円未満(60歳以上の方や障がい者の場合には年間収入180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
一方、同居していない場合には、年収が130万円未満(60歳以上の方や障がい者の場合には年間収入180万円未満)かつ被扶養者の収入が被保険者からの仕送りよりも少ない場合に、扶養が適用されます。
1-3. 社会保険の加入範囲が段階的に拡大している
法改正により、社会保険加入の範囲が段階的に拡大しています。これまで扶養者に該当していたケースであっても、勤務先の規模や雇用期間などによっては、扶養を外れ、勤務先の社会保険に加入しなければならないケースが増えることが予想されます。
社会保険加入の範囲拡大に伴う要件の変更は以下の表を参考にしてください。
| 項目 | 2024年9月30日まで | 2024年10月1日から |
|---|---|---|
| 従業員数 | 101名以上 | 51名以上 |
|
労働時間 |
週20時間以上 | 週20時間以上 |
| 月額賃金 | 月額88,000円以上 | 月額88,000円以上 |
| 雇用期間(見込み) | 2か月を超える | 2か月を超える |
| 適用除外 | 学生 | 学生 |
2024年10月からは、51人以上の事業所も社会保険の加入対象となる点に注意してください。
2. 社会保険の扶養を外れる条件
 ここまでで、社会保険の加入条件について解説しました。
ここまでで、社会保険の加入条件について解説しました。
社会保険の扶養を外れるということは、加入条件を満たしていないことになります。ここからは、社会保険の扶養を外れる条件について詳しく紹介します。
2-1. 106万円以上の収入がある場合
社会保険の扶養を外れる可能性があるのは、配偶者や子どもなどの扶養家族に106万円以上の収入がある場合です。パート・アルバイトなどで働いている場合でも、1月から12月までの1年間の収入が106万円以上になると、社会保険への加入が求められます。ただし、この場合の社会保険への加入条件は、下記のように収入以外にもあるので注意が必要です。
- 従業員数101人以上(2024年10月1日からは51人以上に変更予定)
- 1ヶ月の賃金8.8万円以上(1年で106万円以上)
- 週所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが2カ月以上
- 学生以外(休学中の学生や夜間学校に通う学生は対象)
また、2024年10月からは従業員数の条件が「51人以上」に変更になります。知らないうちに社会保険の対象になっていることがないよう、自分や家族の状況をよく確認しましょう。
関連記事:『106万円のライン』社会保険の適用拡大でパートは増える?減る?
2-2. 130万円以上の収入がある場合
年収130万円以上になると、自分自身で社会保険に加入しなければならないため、自動で社会保険の扶養から外れることになります。目安としては、毎月の給料が10万8,333円を継続して超えている場合です。なお、勤務先の社会保険に加入しない場合、自分で国民年金や国民健康保険の手続きが必要になります。
関連記事:社会保険料の扶養とは?条件や扶養範囲について詳しく解説
2-3. その他のケース
年収が106万円、年収130万円というケースでは、社会保険への加入が必要になるため、それほど複雑ではありません。しかし、これに該当しない場合でも、社会保険に加入しなければならないケースがあります。
たとえば、1月から6月までの収入が65万円を超えているような場合です。このケースでは、年収106万円、年収130万円に達していないですが、年間に換算すると収入が130万円を超えます。そのような場合、社会保険に加入しなければならないと判断されることがあるのです。
また、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上になった場合、社会保険に加入する義務が発生します。扶養を外れるかどうかの判断は難しいケースもあるので、詳しく知りたい人は勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。
2-4. 【補足】「年収の壁」一覧
社会保険の扶養だけでなく、税金に関する年収の壁もあります。下記の表が「年収の壁」一覧になります。
|
年収 |
住民税 |
所得税 |
社会保険料 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
100万円以下 |
– |
– |
– |
対象 |
– |
|
100万円 |
かかる |
– |
– |
– |
|
|
103万円 |
かかる |
– |
– |
対象 |
|
|
106万円 |
場合によってかかる |
– |
|||
|
130万円 |
かかる |
– |
|||
|
150万円 |
– |
対象 ※収入増加に伴い控除額減少していく |
|||
|
201万円 |
– |
– |
年収100万円を超えると住民税、年収103万円を超えると所得税がかかるようになります。ただし、適用できる控除によってはかからない可能性もあります。
また、年収150万円を超えると、配偶者特別控除は受けられるものの、段階的に控除額が引き下げられます。年収201万円を超えると、配偶者特別控除も受けられなくなり、税金における扶養の対象にならなくなります。
関連記事:「年収の壁」に対する政府の支援制度|ポイントをまとめて解説
3. 社会保険の扶養から外れるタイミングはいつ?

勤務先の社会保険に加入する必要がある理由は理解できても、いつのタイミングで社会保険料の扶養を外れなければならないのか判断に迷う人もいるかもしれません。
社会保険の扶養から外れるタイミングは、原則として見込み年収が130万円以上と判断されたときです。また、勤務先の社会保険の加入条件に当てはまる場合も見込みで判断するので注意が必要です。
従業員の扶養が外れてしまった場合は、企業が社会保険加入手続きをする必要があります。手続きには必要書類や守るべき法律・ルールがあり、複雑に感じるご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、そのような方に向けて、社会保険手続きの必要書類や手続きの手順を一冊にまとめたガイドブックを無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして、ご活用ください。
4. 社会保険の扶養を外れる際の手続き

配偶者や子どもなどが社会保険の扶養から外れる場合、勤務先と従業員それぞれが手続きをおこなわなければなりません。ここでは、事業主と従業員それぞれの手続きについて詳しく紹介します。
4-1. 事業主
事業主は、社会保険の扶養に関する手続きをおこなう場合、扶養から外れた事実が発生してから5日以内に「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出しなければなりません。扶養から外れる被扶養者の健康保険証は勤務先で回収し、必要に応じて返却しましょう。
4-2. 従業員(扶養者)
従業員(扶養者)は、まず社会保険の扶養から外れる家族・親族がいることを会社に伝えましょう。その後、会社の指示に従って必要な書類を提出する必要があります。また、健康保険証を返却しなければならないため、扶養から外れる人から受け取って勤務先に提出しましょう。
5. 社会保険の扶養を外れた後はどうする?
 年収106万円、年収130万円といった「年収の壁」を超えてしまったら、社会保険の扶養から外れる必要があります。社会保険の扶養から外れた後は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
年収106万円、年収130万円といった「年収の壁」を超えてしまったら、社会保険の扶養から外れる必要があります。社会保険の扶養から外れた後は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
ここでは、社会保険の扶養から外れた後の対応について詳しく紹介します。
5-1. 勤務先の社会保険に加入する
勤務先の社会保険の加入条件を満たす場合、会社の社会保険に加入することができます。勤務先の社会保険に加入できれば、「健康保険」「厚生年金保険」に加入することが可能です。なお、社会保険料は自分と会社で折半になります。
社会保険の扶養から外れ、勤務先の会社の社会保険に加入するのであれば、会社を通して「被保険者資格取得届」を提出します。提出先は日本年金機構、提出期限は事実があったときから5日以内です。
5-2. 国民年金・国民健康保険に加入する
被保険者の扶養を外れた後、勤務先の社会保険に加入しないのであれば、扶養を外れた日から14日以内に自分で国民年金と国民健康保険への加入手続きをおこなう必要があります。なお、国民年金と国民健康保険の保険料は、自分で全額負担することになります。
社会保険の扶養から外れる前に、所属している市区町村に必要な書類を確認しましょう。また、扶養から外れた証明としての「健康保険資格喪失証明書」は、被扶養者の勤務先などで受け取ることができます。
関連記事:社会保険における健康保険は国民健康保険と何が違うのか?|切り替え手続きについてもご紹介!
6. 社会保険の扶養を外れるときの注意点

社会保険の扶養を外れる場合、いくつかの注意点があります。ここでは、社会保険の扶養を外れる際の注意点について詳しく紹介します。
6-1. 世帯の収入が減る可能性がある
社会保険の扶養を外れると、世帯全体の収入が減る可能性があります。社会保険の扶養は、扶養家族の年収が130万円以上になると強制的に扶養から外れることになります。
扶養から外れると、扶養に入っている間は支払う必要がなかった社会保険料を支払わなければなりません。勤務先の社会保険に加入する場合でも、自分で国民年金・国民健康保険に入る場合でも、保険料の負担が大きくなります。そのため、世帯全体としての収入は減ってしまう可能性があります。
6-2. 被保険者の税金が増える
社会保険の扶養を外れたために、パート・アルバイトで大きく稼ぐようになると、年収150万円、年収201万円といった「年収の壁」を超えるケースがあります。年収150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減少します。また、年収201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられるなくなります。配偶者特別控除の控除額が減ることで、所得が大きくなり、被保険者の税金が増える可能性もあります。
6-3. 手続きの手間がかかる
先述の通り、年収が130万円を超えて扶養を外れることになった場合、勤務先で社会保険に加入するかするか、国民健康保険に加入するかのいずれかを選択しなくてはなりません。特に後者の場合は、自身で役所に出向いて手続きを行う必要があります。
また、勤務先の社会保険に加入する場合、保険料は毎月の給与から天引きされまずが、国民健康保険の場合は、後日役所から届く納付書を持参して自身で保険料を納付しなくてはなりません。
扶養から外れることにより、金銭面以外の負担が出てくることも覚えておきましょう。
6-4. 健康保険の保障内容が変わる
社会保険の扶養から外れると、被保険者の健康保険から、勤務先の社会保険もしくは国民健康保険に加入しなければなりません。健康保険組合によって保障内容が異なるケースもよくあります。また、健康保険では傷病手当金や出産手当金の支給対象ですが、国民健康保険ではこれらの支給対象となりません。このように、健康保険の補償内容が変わることも事前に押さえておきたいポイントです。
6-5. 将来の年金額が変動する
社会保険の扶養に入れば、配偶者は第3号社会保険者に該当し、社会保険料を支払わずとも国民年金に加入することができます。
社会保険の扶養から外れて、勤務先の社会保険に入る場合は、厚生年金保険に加入することになります。社会保険料の負担は大きくなるかもしれませんが、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
一方、国民年金に加入する場合、国民年金保険料の免除制度などを利用しなければ、将来の年金額はほとんど変わりません。ただし、自分で国民年金保険料を支払わなければならないので、金銭的な負担は大きくなります。
関連記事:人事担当者向け|厚生年金の手続きやその他の年金の違いを解説
6-6. 年収を増やせる可能性もある
これまで解説の通り、年収が増えたからといって必ずしも手取り額が増えるとは限りません。勤務先で社会保険に加入したり、被保険者の税金負担が増えることで支出が増え、扶養を外れる前と後では収入にほとんど変化がないというケースも出てくるでしょう。
しかし、労働時間が増えたりキャリアアップしたりすることで収入を増やすことも可能です。
扶養を外れる場合は、収支のバランスと今後の働き方を考えることが必要となるでしょう。
7. 社会保険の扶養の条件や仕組みを正しく理解しよう

社会保険の扶養を外れる条件の一つとして、年収106万円、年収130万円という収入の条件があります。ただし、年収だけではなく、労働時間や勤務日数なども考慮に入れる必要があります。
知らないうちに扶養から外れる条件を満たしてしまっていたということがないよう、自分の収入や勤務日数などには十分注意しておきましょう。社会保険の扶養から外れる前に、どのような対応が必要なのかを事前に整理しておくことが大切です。









