
社会保険に加入している従業員が結婚した際や子どもが生まれた際には、社会保険の扶養対象となる場合があり、その場合には事業主経由で扶養の手続きをおこないます。
配偶者が扶養になることで、納めるべき税金が減る、単独で健康保険や国民年金に加入せずに済むなどのメリットがあります。
本記事では社会保険の扶養範囲や条件について解説していきます。
関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 社会保険の扶養に入るための条件
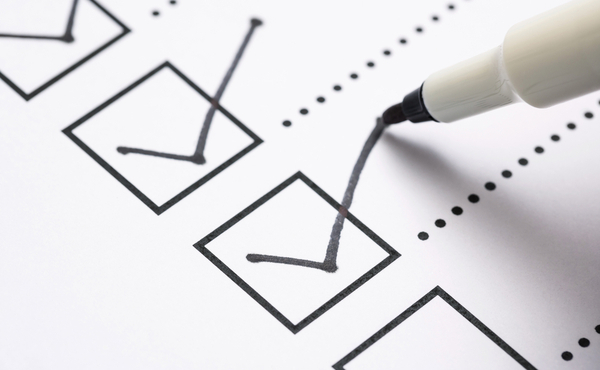
そもそも「扶養」とは、未成年者や高齢者、失業などを理由に収入が少なく、1人で生計を立てることが難しい家族・親族を経済的に援助する仕組みを意味します。
また、扶養には「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」の2種類があり、それぞれ扶養条件が異なります。
今回解説するのは「社会保険の扶養」です。まずは、被扶養者になった人が、自分自身で社会保険に入らなくても保険を受けられる加入条件について紹介します。
関連記事:社会保険の加入条件とは|保険の種類別に条件を詳しくご紹介
1-1. 扶養範囲の条件:「被扶養者の範囲」
社会保険の扶養に入れるかどうかは、被扶養者の範囲に入っているか、さらに同居しているかどうかが関係してきます。
被扶養者の範囲には、被保険者と同居していなければならない場合と、被保険者との同居が必要ない場合があります。
被扶養者の範囲は以下の通りです。
①同居か別居かを問わない人
- 配偶者(内縁関係も可)
- 子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居していることが条件になる人
- ①以外の3親等内の親族(甥・姪・叔父・叔母など)
- 被保険者の配偶者(内縁関係も含む)の父母・連れ子
- 配偶者(内縁関係も含む)死亡後の父母・連れ子
直系尊属には、養子縁組をおこなった場合も含まれます。
被扶養者になるためには、被扶養者の範囲内であることに加えて、収入の条件も満たさなくてはなりません。
続いて収入の条件を紹介します。
1-2. 扶養範囲の条件:「扶養に入るものの収入」
被扶養者になれるかどうかは、被扶養者の収入も関係してきます。
収入の条件を考える際には、同居の場合と別居の場合で条件が異なります。
被扶養者が同居の場合、被扶養者になる人の年収は、一部を除き、年間収入130万円未満(60歳以上の方や障がい者の場合には年間収入180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
扶養とは、経済的に自立していない親族に経済的援助をする制度のことなので、被扶養者の収入を中心に生計を維持している場合には扶養は適用されません。
同居していない方の場合には、年収が130万円未満(60歳以上の方や障がい者の場合には年間収入180万円未満)かつ被扶養者の収入が被保険者からの仕送りよりも少ない場合、扶養が適用されます。収入の金額によって被扶養者になれるかどうかが変わってくるので、注意しましょう。
なお、この年間収入には以下のようなものが含まれます。ちなみに、収入は見込みで計算しますが、退職など特別な事情がない限りは前年の所得及び直近3ヶ月の収入をベースに計算します。
| 条件に含まれる収入 | 収入の種類 |
| 給与収入 |
|
| 年金 |
|
| 事業収入 |
|
| 不動産収入 |
|
| 利子収入・投資収入 |
|
| 仕送り |
|
| その他 |
|
一方、以下のような一時的な収入は条件に含まれません。
| 条件に含まれない収入 | 収入の種類 |
| 一時的な収入 |
|
1-3. 2024年10月からの社会保険適用拡大で扶養範囲も変わる
2024年からの社会保険適用拡大に伴い、社会保険の加入対象となる短時間労働者の条件も変更される予定です。
| 項目 | 2024年9月30日まで | 2024年10月1日から |
|---|---|---|
| 従業員数 | 101名以上 | 51名以上 |
|
労働時間 |
週20時間以上 | 週20時間以上 |
| 月額賃金 | 月額88,000円以上 | 月額88,000円以上 |
| 雇用期間(見込み) | 2か月を超える | 2か月を超える |
| 適用除外 | 学生 | 学生 |
変更点は以下の2点です。
①特定適用事業所の範囲拡大
これまで、短時間労働者を社会保険に加入させる義務のあった社会保険の特定適用事業所は短時間労働者を除く従業員数が501人以上の事業所でした。しかし、従業員数は段階的に変更され、2022年10月からは短時間労働者を除く従業員数が101人以上のすべての事業所が社会保険の特定適用事業所となり、2024年10月からは51人以上となります。
②短期労働者の雇用期間の要件
2022年9月までは、短期労働者の社会保険適用要件のひとつに「雇用期間が1年以上見込まれること」という条件が含まれていましたが、2022年10月から「雇用期間が2ヵ月以上みこまれること」に変更されました。2024年10月以降もこの雇用期間に変更はありません。
この社会保険適用拡大によって、新たに社会保険に加入する人もいるでしょう。そのような人は扶養からは外れることになります。
社会保険の被保険者となっている人は被扶養者になることができないため、社会保険の適用拡大によって扶養から外れるなどの変更が発生する場合があります。
2. 社会保険の扶養となるメリット・デメリット
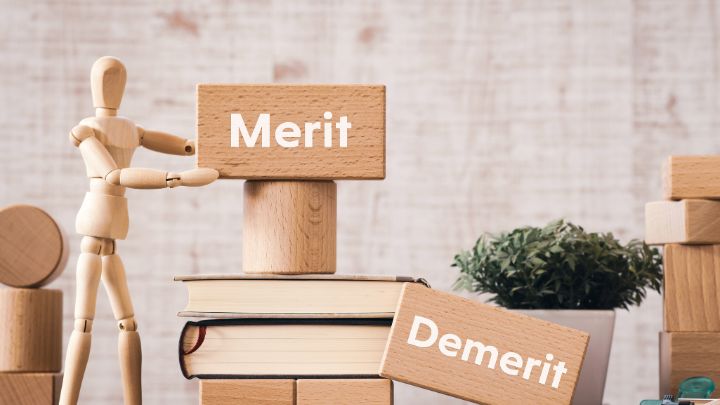
社会保険の扶養に入るメリット・デメリットとはどのようなものなのでしょうか。
2-1. 社会保険の扶養に入るメリット
社会保険の扶養に入るメリットには以下のようなものがあります。
- 年金や健康保険料を支払う必要がない
- 収入の手取り額が増える
- 被保険者に配偶者控除が適用される
社会保険の被扶養者は人は、年金や医療保険を支払う必要がありません。給与から社会保険料が引かれないため、扶養に入っていないときよりも手取り額が増えます。また、被扶養者がいると被保険者には「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用されるため、税金の負担が軽減されます。
2-2. 社会保険の扶養に入るデメリット
社会保険の扶養に入るデメリットには以下のようなものがあります。
- 将来受け取る年金額が減る
- 扶養条件を超えないように収入を調整しなくてはならない
社会保険の扶養に入ると、厚生年金加入者に比べて年金の受給額が少なくなります。被扶養者は「第3号被保険者」に該当し、受け取る年金が国民年金のみになってしまうためです。
また、扶養に入るには収入条件があるため、月々の収入や年間の収入額を管理し、場合によっては仕事をセーブをしなければならないケースも出てくるでしょう。
3. 社会保険の扶養に入る手続き方法

配偶者や親族が社会保険の扶養に入る場合は手続きが必要です。
できるだけスムーズに手続きをおこなうために、どんな手続きが必要か確認しておきましょう。
3-1. 必要書類を揃える
社会保険の扶養に入る手続きをおこなうためには、必要書類を揃えなくてはなりません。
まず、手続きに必須の書類が「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」です。
従業員の被扶養者に変更があった事実が発生してから5日以内に届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
さらにこの書類に添付する必要書類があります。
一つ目は、被保険者と被扶養者との続柄を確認するために必要となる被保険者の戸籍謄本、もしくは住民票の写しです。被保険者と被扶養者が同一世帯で生活しているのであれば、それを証明するために住民票が必要です。
ただし、被保険者と被扶養者の両方のマイナンバーが届出に記載されていれば、戸籍謄本や住民票を添付する必要はありません。
二つ目に必要な書類は、社会保険の扶養に入るためには、年収の条件があるため、被扶養者の収入がいくらなのかを証明する書類です。もし、被保険者の父母などが退職して扶養に入るのであれば退職証明書、そうでなく自分の収入がある場合には確定申告書の写しなどを添付する必要があるので、従業員がもれなく準備しているかどうかを確認しましょう。
関連記事:国民年金第3号被保険者関係届とは?電子申請の方法についてもあわせて解説
3-2. 特殊なケースで必要な添付書類
被扶養者になるための手続きで必要な書類は基本的に被保険者の戸籍謄本や住民票、被扶養者の収入を証明できる書類です。
しかし、特殊なケースでは別途書類が必要になることがあります。
まず、被扶養者が被保険者と同居していない場合です。
被扶養者が被保険者と別居しているのであれば、被保険者からの仕送りなどが確認できる預金通帳のコピーや現金書留の控えを提出しなければなりません。
さらに、被扶養者と被保険者が婚姻関係にはないものの内縁関係にある場合、双方の戸籍謄本または双方の住民票が必要です。
これらの添付書類が必要になる場合、従業員から添付されているかを確認したうえで届出をおこないましょう。
3-3. 提出期限内に書類を提出する
必要書類を揃えたなら、提出期限内に書類を提出しましょう。基本的には、扶養に入った事実があった日から5日以内に書類を提出しなければなりません。
しかし、健康保険組合などによって提出期限が異なることもあるので注意が必要です。提出期限を過ぎると、被保険者や被扶養者が不利益を被ることもありえます。
提出期限を確認して、スムーズに手続きをおこなうようにしましょう。
このように、社会保険には必要な書類が複数あり、提出期限が設けられているものもあります。提出に遅れが出てしまうと、法律に抵触する可能性もあるため、期限を守った適切な手続きをおこないましょう。
当サイトでは、社会保険に必要な手続きと書類一覧などをわかりやすくまとめた資料を無料で配布しています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてミスのない手続きにお役立てください。
3-4. 健康保険被扶養者(異動)届けの書き方
社会保険の扶養に入るためには、「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」が必要です。各項目や書き方は以下を参考にしてください。
| 記載項目 | 記載内容や注意点 |
| 事業所整理記号 |
|
| 事業主確認欄 |
|
| 被保険者整理番号 |
|
| 収入 |
|
| 提出日 |
|
| 被扶養者(第3号被保険者)になった日 |
|
| 収入 |
|
| 備考 |
|
4. 従業員の扶養が外れるときの手続き方法

会社に勤務している従業員が扶養から外れる場合、会社側にも手続きが求められます。
では、従業員の扶養が外れる時にどんな手続きが必要か見ていきましょう。
4-1. 従業員の扶養が外れるタイミング
まずは、従業員の扶養が外れるタイミングにはどのようなものがあるのかを確認しましょう。従業員が別の人の扶養に入った、従業員が離婚・死亡したなどのタイミングで従業員の扶養が外れることが考えられます。
また、被扶養者の従業員が75歳以上になり、後期高齢者の保険証を持っている場合も扶養が外れます。
加えて、被扶養者であるための条件である130万円を超える年間収入を得ている場合にも扶養を外す手続きが必要です。
4-2. 会社がおこなうべき手続き
従業員自身の扶養を外す場合、必要に応じて会社が手続きをおこなう必要があります。
従業員が扶養から外れて、社会保険の加入をする必要がある場合には、会社がすみやかに「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出しなければなりません。その際に、配偶者や子どもなど被扶養者とする人がいる場合は、「健康保険被扶養者届」、配偶者を第3被保険者とする場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」をあわせて年金事務所に提出します。
届出が完了したら、健康保険被保険者証が交付されるので、すぐに本人に渡しましょう。
従業員本人が扶養から外れて社会保険に加入しない場合は、社会保険に関して会社がおこなうべき手続きは特にありません。
4-3. 従業員側にも手続きが必要
従業員が扶養から外れた場合、従業員側にも手続きが求められます。扶養から外れた場合、健康保険への加入を考えなければなりません。
被保険者の扶養を外れると、国民健康保険に加入するか、自分が勤務する会社の社会保険に加入するか決定することになるでしょう。
どちらにせよ、無保険状態になることがないよう、扶養を外れたならすぐに手続きの準備を始めなければなりません。
5. 従業員の家族が扶養から外れる時の手続き方法
 次に、従業員の家族が扶養から外れる時の手続き方法を解説します。
次に、従業員の家族が扶養から外れる時の手続き方法を解説します。
どのようなタイミングでどのような手続きが必要になるのか本章でみていきましょう。
5-1. 従業員の家族の扶養が外れるタイミング
従業員の家族の扶養が外れるタイミングには以下のようなものがあげられます。
- 配偶者や子どもの収入が増えて、扶養範囲の条件が適用されなくなった場合
- 配偶者や子どもが就職・転職などで社会保険に加入した場合
- 結婚などで別の家族の扶養家族になった場合
- 離婚や死亡などで被扶養者ではなくなった場合
- 被扶養者が雇用保険(失業給付)を申請して受給するようになった場合
- 被扶養者が75歳以上になり、長寿医療制度の保険証を受け取った場合
このようなタイミングでは、会社が手続きをおこなう必要があります。
次節で会社がおこなうべき手続きを具体的に解説します。
5-2. 会社がおこなうべき手続き
従業員の家族の被扶養者に変更がある場合、まず被保険者から被扶養者の保険証を預かります。何らかの理由で被保険者の保険証を回収できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能(滅失)届」を代わりに提出しなければなりません。
また、被保険者に健康保険被扶養者異動届を記載してもらい、会社が年金事務所に提出します。
これらの手続きは扶養が削除される日から5日以内におこなわなければなりません。
扶養が削除される日は以下のいずれかです。
- 就職した場合は就職日または被扶養者の健康保険資格取得日
- 収入が要件を超えた場合はそれが発生した日
- 離婚・死亡した際は発生日の翌日
- 雇用保険の受給を開始した場合は失業保険の受給開始日
被扶養者異動届は扶養から外れた日から5日以内に被保険者の所属する会社が提出しなければならないため、これらの手続きをできるだけ早くおこないましょう。
従業員の家族の扶養が外れたのに被保険者異動届を提出しない場合、通院や入院などで空白期間に発生した医療費や給付金を返還するよう求められるなど、トラブルが発生する可能性があります。
わずかな金額であればそれほど大きな問題にはなりませんが、入院や手術といった多額の費用がかかった場合には労使間で大きなトラブルになる恐れがあるため、注意しましょう。
関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介
6. 社会保険の扶養範囲をしっかり理解しておこう

社会保険の扶養の範囲は、同居の有無や年間収入によって変わってきます。
社会保険の扶養の範囲は2024年10月からの社会保険適用拡大によっても変わるため、従業員が扶養の範囲内なのかどうかを確認しておきましょう。扶養に入る場合も外れる場合も、手続きが必要となる点に注意が必要です。
社会保険に関する手続きは、従業員の生活や金銭面の問題に直結することなので、ミスや滞りのないように進めましょう。









