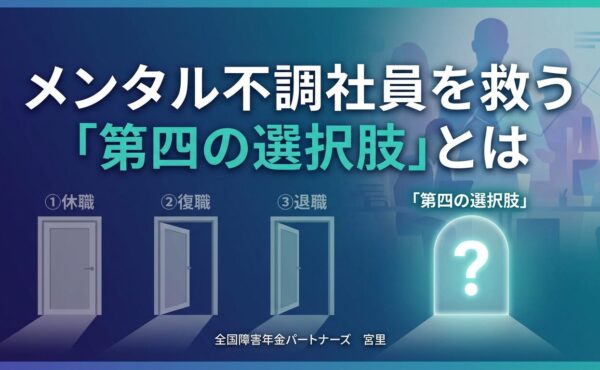裁量労働制とフレックスタイム制は、働き方の自由度が高いという点で似ているため、混同されやすい制度です。しかし、2つの制度は根本的に異なり、対象範囲や残業代の取り扱いなども大きく違うので、正しく理解しておく必要があります。
この記事では、裁量労働制とフレックスタイム制の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
関連記事:裁量労働制とは?適用職種や改正のポイントを簡単にわかりやすく解説!
フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、おこなうべき手続きが存在します。
また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。
「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 裁量労働制とフレックスタイム制の違い
 裁量労働制とフレックスタイム制の違い理解するために、それぞれの制度の特徴を紹介します。
裁量労働制とフレックスタイム制の違い理解するために、それぞれの制度の特徴を紹介します。
まず、裁量労働制とは、労使間で定めたみなし労働時間を労働時間とみなす制度です。たとえば、みなし労働時間を8時間と決めていた場合は、何時間残業をしたとしても8時間働いたとみなされます。反対に、仕事が早く終わり7時間で退勤できた場合でも、8時間とみなされるのです。
そのため、裁量労働制においては実労働時間ではなく、仕事の成果が重視されるといえるでしょう。裁量労働制は、大きく分けると専門業務型と企画業務型の2種類に分類されます。
続いて、フレックスタイム制とは、労働者自身で勤務の開始時間と終了時間を自由に決められる制度のことです。
フレックスタイム制では、清算期間のなかで定められた総労働時間を守らなければなりませんが、その範囲であれば、日々の労働時間は自分で決められます。会社によっては、必ず業務をおこなわなければならないコアタイムや、労働者が働く時刻を選べるフレキシブルタイムなどを設けている場合もあるでしょう。
裁量労働制とフレックスタイム制の特徴について説明しましたが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。以下、それぞれの制度の違いについて詳しく解説します。
1-1. 適用範囲が異なる
2つの制度の大きな違いとしてまず挙げられるのが、適用範囲の違いです。フレックスタイム制は対象の職種や人に制限がありません。フレックスタイム制を導入している会社に勤めている労働者であれば、誰にでも適用できます。
対して裁量労働制は、厚生労働省が定める職種・業務にのみ適用される制度です。専門業務型裁量労働制を適用できる具体的な職種としては、研究者・開発者やプロデューサー・ディレクター、弁護士、税理士などが挙げられます。対象業務は2024年4月から「M&Aアドバイザーの業務」が追加され、現在は全部で20業務に定められています。企画業務型裁量労働制は、経営や調査などに関する業務に限って適用できます。
また、定められている職種・業務であれば必ずしも適用されるわけではありません。裁量労働制として認められるには、業務の遂行や労働時間の配分などが業務の性質上、労働者本人に任せる必要性がある場合に限ります。
関連記事:裁量労働制の適用職種は?2024年4月からの職種拡大や企業対策も併せて解説
1-2. 時間や給料の扱い方が異なる
フレックスタイム制は前述の通り、出退勤時間を自由に決められ、実労働時間に応じて給料が支払われるものです。そのため、清算期間で定めた総労働時間を満たしていない場合は、賃金が減額されることもあります。
また、総労働時間を超えた分は残業扱いになるため、労働者には残業代を支払わなければなりません。
一方、裁量労働制は基本的に仕事の成果で評価されるので、労働時間は関係なく、遅刻や早退の概念もありません。設定されているみなし労働時間が法定内であれば、残業代の支払い義務はないものとされています。
関連記事:裁量労働制は残業代が出ない?計算方法や休日出勤・深夜労働についてわかりやすく解説!
1-3. 導入のための手続き方法が異なる
フレックスタイム制は就業規則に記載し、労使協定を締結するだけで比較的簡単に導入できます。具体的な導入手順は以下の通りです。
- 必要・任意事項の決定(対象となる労働者範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、1日の労働時間、コアタイム、フレキシブルタイムなど)
- 就業規則への記載
- 労使協定の締結
- 労働基準監督署長への届出の提出(清算期間が1ヵ月を超過する場合のみ)
- 従業員の雇用契約書の更新
一方、裁量労働制を導入する場合は、より複雑な手続きが必要になります。裁量労働制のうち専門業務型においては、労使協定を締結して労働基準監督署に届出が必要です。以下のような手順で進めましょう。
- 労使協定の締結
- 届出の作成
- 就業規則への記載
- 労働基準監督署長への届出の提出
- 従業員の雇用契約書の更新
もうひとつの企画業務型に関しては、労使委員会を設置し、4/5以上の多数による議決で決議をして、対象労働者から個別に同意を得なければなりません。具体的な手順は以下の通りです。
- 労使委員会を設置・決議
- 就業規則への記載
- 労働基準監督署長への届出を提出
- 対象労働者本人からの同意を得る
- 労使委員会で決定した措置の実行・定期的に所轄労働基準監督署へ報告
このように、フレックスタイム制と裁量労働制にはいくつかの異なる部分があるため、それぞれの仕組みを理解して自社にあった制度を採用することが大切です。当サイトでは、1冊でフレックスタイム制と裁量労働制のそれぞれの制度について理解ができる資料を無料でお配りしています。フレックスタイム制・裁量労働制の成功事例や導入方法を知りたい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。
2. 裁量労働制のメリット・デメリットや適している企業
 柔軟な働き方が魅力的な2つの制度ですが、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。それぞれ確認してみましょう。
柔軟な働き方が魅力的な2つの制度ですが、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。それぞれ確認してみましょう。
2-1. 裁量労働制のメリット
裁量労働制の主なメリットは以下の通りです。
従業員が自分のペースで働ける
裁量労働制は、時間の拘束がなく自分のペースで働ける点が大きなメリットです。仕事を効率良く進めれば、みなし労働時間より早く終えることもできます。出退勤のタイミングも自由に決められるので、生活スタイルに合わせた働き方が可能です。
生産性向上を期待できる
裁量労働制においては、仕事の質や成果が評価されるので、生産性の向上が期待できます。自己管理能力が高い従業員には向いている働き方かもしれません。
人件費の管理がしやすい
会社側のメリットは、残業代の支払いを見込んでみなし労働時間を決めているケースが多いため、人件費の管理がしやすくなることです。残業代計算の手間を省け、労務負担の軽減にもつながります。
また、どの程度の人件費が発生するのか、目安を把握できるため、長期的な予算も立てやすくなるでしょう。
2-2. 裁量労働制のデメリット
一方で、裁量労働制には以下のようなデメリットもあります。
残業代が支給されない
裁量労働制の場合、みなし労働時間が決められているため、いくら労働をしても残業代が出ないことは、労働者にとってデメリットでしょう。日常的にみなし労働時間を超えて働いている場合は、メリットを感じられない可能性があります。
導入のハードルが高い
企業側のデメリットは、導入のハードルが高いことです。導入の手続きをしても認められるとは限りません。労使協定で決議をしたり、場合によっては労使委員会を設置したりする必要もあります。
無事導入できたとしても、働き方が大きく変わるため、制度に即した新しい人事評価を取り入れる必要があるでしょう。
長時間労働が常態化する可能性もある
自己管理ができない労働者が多いと、裁量労働制のメリットが活かされず、長時間労働が助長されることも懸念されます。裁量労働制においては自由な働き方を認めるのが基本ですが、勤怠管理を徹底し、実労働時間がどの程度なのかを把握したり、必要に応じて仕組みの改善を図ったりすることも重要です。
2-3. 裁量労働制が適している企業の特徴
裁量労働制はどのような企業に向いているのでしょうか。仕事の進め方や時間配分の自由度が高い裁量労働制なら、フレックスタイム制よりも柔軟な働き方を実現することができます。
裁量労働制は次のような企業に向いています。
- 従業員の創造性やイノベーションを引き出したい企業
- 従業員に業務上の指示をほとんど与えず、仕事の進め方やスケジュールを委ねている企業
- 労働時間の長さにかかわらず、業務上の成果を求める企業
厚生労働省による裁量労働制で働く人を対象としたアンケート調査では、制度を利用した理由として、44.0%の人が「仕事の裁量が与えられていることにより仕事がしやすくなると思った」、32.3%の人が「自らの能力の有効発揮に役立つと思った」と回答しています。[注1]
たとえば、税理士や弁護士、大学教員、研究開発職などの専門業務をおこなう事業所では、裁量労働制のメリットを効果的に活かすことが可能です。
3. フレックスタイム制のメリット・デメリットや適している企業

次に、フレックスタイム制のメリット・デメリットや、適している企業の特徴について見ていきましょう。
3-1. フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制の主なメリットは以下の通りです。
仕事とプライベートを両立しやすい
フレックスタイム制は、仕事とプライベートが両立しやすくなるメリットがあります。出退勤の時間を自由に決められるため、通勤ラッシュの時間を避けたり、子どもの送迎や通院がしやすくなったりなど、ワークライフバランスを確保しやすくなるでしょう。
また、仕事量が多い日と少ない日にムラがある場合、フレックスタイム制であればその日の仕事量に合わせて労働時間を調整できます。総労働時間の範囲内であれば調整は自由なので、業務負荷を分散させられるでしょう。
優秀な人材を確保できる
現在、多くの業種で人材確保の難しさが問題となっていますが、柔軟性のある働き方が可能なフレックスタイム制を導入していることは、会社にとってアピールポイントになります。
なお、厚生労働省の就労条件総合調査によると、令和6年調査時点でのフレックスタイム制導入率は、7.2%となっています。また、企業の規模が大きいほど導入率が高い傾向にあるようです。[注2]
3-2. フレックスタイム制のデメリット
一方で、フレックスタイム制には以下のようなデメリットもあります。
社内の連携が難しい
フレックスタイム制のメリットである出退勤の時間を自由に決められる点は、デメリットにもなる可能性があります。出退勤の時間が個々で違うことによって、社員同士のコミュニケーションが取りづらくなったり、会議の調整が難しくなったりするからです。
会社は、フレックスタイム制を利用する労働者に、コアタイム以外で勤務時間を指定することは原則できません。
勤怠管理が複雑になる
労働者の勤怠管理が複雑になるため、労務担当者の負担が増えてしまう可能性もあるでしょう。必要に応じて勤怠管理システムを導入するなど、労働時間の管理を効率化する方法について検討しておくことも重要です。
生産性が下がる可能性もある
時間にルーズな人は、フレックスタイム制の自由度の高さが裏目に出て、生産性を下げてしまうことも考えられます。コアタイムを設定するなど、ある程度の強制力がある仕組みにすることで、労働者の働き方をうまくコントロールしていきましょう。
3-3. フレックスタイム制が適している企業の特徴
裁量労働制と違って、フレックスタイム制には職種の制限がありません。そのため、ほとんどの事業所でフレックスタイム制を導入することができます。
裁量労働制より仕事の進め方やスケジュールの自由度が低いものの、出社時間を柔軟に選べるフレックスタイム制にもさまざまなメリットがあります。
フレックスタイム制が向いているのは、次のような特徴を持った企業です。
- 通勤ラッシュを避けるため、オフピーク通勤を導入したい企業
- 従業員のワークライフバランスを改善し、育児や介護と仕事を両立できるようにしたい企業
- 出社日や出社時間の制限をなくし、従業員の生産性を高めたい企業
- 働き方改革を推進したいが、職種の制限によって裁量労働制を導入できない企業
関連記事:フレックスタイム制とは?目的や制度の仕組み・メリットデメリットをわかりやすく説明
4. 裁量労働制やフレックスタイム制を導入している企業の割合

働き方改革をきっかけとして、裁量労働制やフレックスタイム制の導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。
ここでは、厚生労働省の就労条件総合調査をもとに、国内での裁量労働制やフレックスタイム制の導入状況を解説します。
4-1. 裁量労働制の導入率
厚生労働省の令和6年就労条件総合調査によると、裁量労働制などのみなし労働時間制を導入している企業の割合は次の通りです。
| – | 事業場外みなし労働時間制 | 専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 |
| 令和6年 | 13.3% | 2.2% | 1.0% |
| 令和5年 | 12.4% | 2.1% | 0.4% |
| 令和4年 | 12.3% | 2.2% | 0.6% |
裁量労働制の導入率は、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制をあわせて3.2%です。過去の数値と比較すると、裁量労働制の導入率は増加傾向にあることもわかります。
また、同調査によると、従業員規模が大きい企業ほど裁量労働制の導入率は高くなっています。[注2]
4-2. フレックスタイム制の導入率
一方、フレックスタイム制をはじめとした変形労働時間制の導入率は次の通りです。
| – | 1年単位の変形労働時間制 | 1ヵ月単位の変形労働時間制 | フレックスタイム制 |
| 令和6年 | 32.3% | 25.2% | 7.2% |
| 令和5年 | 31.5% | 24.0% | 6.8% |
| 令和4年 | 34.3% | 26.6% | 8.2% |
フレックスタイム制の企業全体の導入率は7.2%です。令和5年の調査と比較すると、フレックスタイム制の導入率は0.4%増加しています。
また、裁量労働制と同様に、従業員規模が大きい企業ほどフレックスタイム制の導入率が高くなっており、従業員数1,000人以上の大企業では導入率が34.9%に達しています。[注2]
5. 裁量労働制とフレックスタイム制に関してよくある疑問

ここからは、裁量労働制とフレックスタイム制に関してよく生じる疑問について解説します。裁量労働制とフレックスタイム制の併用が可能であるかや、移行方法などについて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
5-1. 裁量労働制とフレックスタイム制は併用可能?
裁量労働制とフレックスタイム制を併用することはできません。裁量労働制とは、労働者へ労働時間に関する裁量を一任する制度です。また、導入可能な職種は限定されています。
一方で、フレックスタイム制は従業員が始業・終業時刻を自由に選択できる制度です。フレックスタイム制は、清算期間内に総労働時間を満たす必要があり、法定労働時間の総枠を超過した場合は割増賃金が支給されます。
このように形態が異なる制度であるため、併用は不可能です。ただし、1人の従業員に対して、同一の期間中に裁量労働制とフレックスタイム制を併用することは制度上できませんが、企業内で職種や部署ごとに異なる労働時間制度を導入することは可能です。
関連記事:裁量労働制とフレックスタイム制の違いとは?併用できる?詳しく解説
5-2. 裁量労働制からフレックスタイム制に移行するには?
裁量労働制からフレックスタイム制に移行をする場合には、フレックスタイム制の導入に必要となる手続きをおこなわなければなりません。
フレックスタイム制の導入に必要となる事項を検討し、労使間による協議をおこなったうえで、労使協定を締結し、就業規則を更新することで移行することが可能です。
5-3. 裁量労働制やフレックスタイム制の勤怠管理を効率化するには?
裁量労働制やフレックスタイム制を導入すると、労働時間がバラバラになり勤怠管理が複雑化します。人事・労務担当者の負担が増えるケースも多いため、勤怠管理システムを導入するとよいでしょう。
勤怠管理システムを活用すれば、労働者ごとに異なる出退勤時刻を自動的に集計してくれます。給与計算システムと連携すれば、毎月の給与の算出まで自動化することが可能です。
また、クラウド型の勤怠管理システムであれば、スマートフォンやタブレットからでも打刻できるため、リモートワークを採用している企業にも最適でしょう。
6. 裁量労働制とフレックスタイム制の違いを理解して最適な制度を導入しよう
 今回は、裁量労働制とフレックスタイム制の特徴とあわせて、2つの制度の違いについて詳しく紹介しました。
今回は、裁量労働制とフレックスタイム制の特徴とあわせて、2つの制度の違いについて詳しく紹介しました。
どちらも生活スタイルに合わせた柔軟な働き方に対応していますが、時間や給料の扱い方は大きく異なります。裁量労働制とフレックスタイム制は、根本的に全く別の制度であることを理解しておきましょう。
両者ともメリットとデメリットがあるので、自社に合った制度の導入を検討してみてください。また、裁量労働制やフレックスタイム制を取り入れると、労働時間の管理が複雑になるため、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。昨今ではあらゆる機能が搭載されたシステムが多く提供されているので、自社に合ったサービスを選択しましょう。