 裁量労働制とは、あらかじめ決められたみなし労働時間分を働いたとみなす制度です。個人の裁量で仕事の時間を決めたり業務配分ができたりするため、仕事の成果が出て高い評価につながりやすくなります。
裁量労働制とは、あらかじめ決められたみなし労働時間分を働いたとみなす制度です。個人の裁量で仕事の時間を決めたり業務配分ができたりするため、仕事の成果が出て高い評価につながりやすくなります。
しかし、裁量労働制は適用される職種が限られており、全ての企業が導入できるわけではありません。
この記事では、裁量労働制が適用される職種や導入方法について解説します。専門業務型と企画業務型との関係についても述べていますので、ぜひ最後までご覧ください。
裁量労働制制は適用できる職種が法律で定められていたり、導入する際にも種類によって労使協定の締結などが必要になったりします。
また、「フレックスタイム制など類似制度との違いがわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは「柔軟な働き方を実現するための制度解説BOOK」を用意しました。
「裁量労働制の制度概要や導入手順を知りたい」「自社にはどのような制度があっているのか知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 裁量労働制とは
まずは、裁量労働制について簡単におさらいしましょう。
1-1. 裁量労働制とはみなし労働時間制の1つ
裁量労働制は、生産性を高めることを目的に制定され、時間にとらわれない働き方を認める制度です。実際の労働時間に関係なく、あらかじめ企業と従業員で規定した時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払います。
通常、労働時間は「1日8時間、週40時間」におさめるように労働基準法で定められています。しかし、中には勤務時間を制限することでかえって効率が悪くなるケースがあるため、職種を限定して、就業時間や就業場所を従業員の裁量に任せる裁量労働制の導入が認められています。
また、裁量労働制は労働基準法における「みなし労働時間制」の1つで、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。いずれも職種は限定されますが、多様な働き方に対応する手段の1つとして導入を検討する企業が増えています。
1-2. 裁量労働制のメリット・デメリット
裁量労働制のメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
- 労務管理の負担を軽減できる
- 多様な働き方が認められ、優秀な人材を確保しやすくなる
- 自分のペースで効率よく働くことができる
- 労働時間を短縮できる可能性がある
裁量労働制では時間外労働が発生しにくいため、労務管理の負担を軽減できることは企業にとって大きなメリットです。
従業員は自分のペースで働けるためストレスを感じにくく、裁量次第では労働時間を減らして給与の満額を得ることができます。
しかし、以下のようなデメリットもあります。
- 導入できる企業が限定される
- 長時間労働を助長する恐れがある
- 導入手続きの負担が大きい
- 自己管理が難しい従業員には不向き
裁量労働制のデメリットは、導入手続きの負担が大きい点です。特に企画型裁量労働制は複雑な手続きを踏む必要があるため、企業とって大きな負担となるでしょう。
また、労働時間の制限がないため、法令に違反するような長時間労働につながる可能性もあります。自己管理が難しい従業員にとっては不向きな働き方と言えるため、導入には十分な検討が必要です。
1-3. 裁量労働制と他の制度との違い
裁量労働制意外にも多様な働き方を可能とする制度があります。裁量労働制を検討する際は、他の制度とも比較しましょう。
| 制度 | 制度の概要、裁量労働制との違い |
| 変形労働時間制 |
|
| フレックスタイム制 |
|
| 事業場外みなし労働時間制 |
|
| 高度プロフェッショナル制度 |
|
2. 裁量労働制が認められる職種と業種
 裁量労働制は大きく分けると「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分類できます。
裁量労働制は大きく分けると「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分類できます。
2-1. 専門業務型裁量労働制の業種と職種
専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、仕事の進め方や労働時間の配分を労働者に任せる必要があると定められている業務において利用できます。
該当する職種は全部で19種類のみです。以下は、専門業務型の対象となる具体的な業務です。
- 新商品や新技術の研究や開発に関する業務
- 情報処理システムの分析や設計業務
- 新聞・出版事業における取材や編集業務、放送番組作成のための取材や編集業務
- 衣服・室内装飾・工業製品・広告などのデザイン考案業務
- 放送番組・映画などの制作におけるプロデューサーやディレクター業務
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの創作業務
- 証券アナリスト
- 金融商品の開発業務
- 大学での教授研究の業務
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
これらの職種にあてはまっていたとしても、実際の業務内容によっては適用外だと判断されることもあります。
2-2. 企画業務型裁量労働制の業種と職種
労働者の創造的な能力を発揮し、自由度の高い働き方を実現するために、企画業務型裁量労働制が制定されました。
企画業務型は専門業務型のように対象業務が具体的に決められているものではありませんが、制度を利用するためには対象事業場と対象業務に該当してる必要があります。
以下は、企画業務型として認められている対象業務の条件です。これら全てに該当していなければ、企画業務型裁量労働制の導入は認められません。
- 事業の運営に関する業務
- 企画・立案・調査・分析の業務
- 個人の裁量に任せる必要があると判断される業務
- 使用者が具体的な指示をしない業務
なお、上記全ての業務にあてはまる上で、以下のいずれかの事業場であることも条件です。
- 本社・本店
- 事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場
- 本社や本店から指示を受けず、事業の運営に影響を及ぼす決定が行われている支社・支店など
制度を導入するにあたり、対象労働者には個別で同意を取る必要があります。
関連記事:裁量労働制はデメリットしかない!?|残業代や適用職種についても詳しく解説!
3. 裁量労働制の導入方法
 裁量労働制を導入するためには、労使協定を締結したり、労働基準監督署へ届け出たりしなければなりません。制度を利用する場合は、労働者の不利益にならないように適切に運用する必要があるでしょう。
裁量労働制を導入するためには、労使協定を締結したり、労働基準監督署へ届け出たりしなければなりません。制度を利用する場合は、労働者の不利益にならないように適切に運用する必要があるでしょう。
専門業務型と企画業務型で手続き方法が異なりますので、それぞれの方法を紹介します。
3-1. 専門業務型を導入するための手続き
専門業務型を導入するためには、労使協定で決議を行い、以下の事項を定める必要があります。
- 制度の対象業務
- 業務の遂行方法や時間配分を労働者に指示しないこと
- みなし労働時間
- 労働者の健康を確保するための具体的な措置の内容
- 労働者からの苦情の処理のために実施する具体的な措置の内容
- 協定の有効期間
- 4と5で講じた措置の記録を有効期限及び期間満了後3年間保存すること
これらを書面で定めて、労働基準監督署へ届け出ます。届け出たら、労働者に周知して就業規則も改正しましょう。
3-2. 企画業務型を導入するための手続き
企画業務型は、専門業務型のように具体的な業務が定められていないため、より厳しい手続き内容となっています。
企画業務型を導入する際は、労使協定ではなく、労使委員会を設置して決議を行わなければなりません。
労使委員会で決議する事項は以下の通りです。
- 制度の対象業務の具体的な範囲
- 対象労働者の範囲
- みなし労働時間
- 労働者の健康を確保するための具体的な措置の内容
- 労働者からの苦情の処理のために実施する具体的な措置の内容
- 労働者本人の同意を得らなければならないこと、不同意の労働者を不利益扱いしないこと
- 決議の有効期限
- 企画業務型の実施にかかわる記録を有効期限及び期間満了後3年間保存すること
これらの事項は、労使委員会の4/5以上の多数による議決で決議する必要があります。後は、専門業務型と同じように、労働基準監督署に届け出ましょう。
制度導入において、労働者から得る個別の同意は、就業規則等で周知するだけでは不十分です。制度に関する十分な説明を行い、書面を用いて同意を得ることが望ましいでしょう。
専門業務型も企画業務型も、手続きで不備がある場合や、運用が正しくおこなわれていない場合などは、導入後であっても無効になるので注意してください。裁量労働制を導入する際には概要をしっかりと確認しておくことで手続きの不備などを防ぐことができます。当サイトでは、裁量労働制の概要や導入方法をわかりやすく解説した資料を無料でお配りしています。裁量労働制の導入を検討している方はこちらからダウンロードしてご活用ください。
4. 裁量労働制における残業時間の考え方
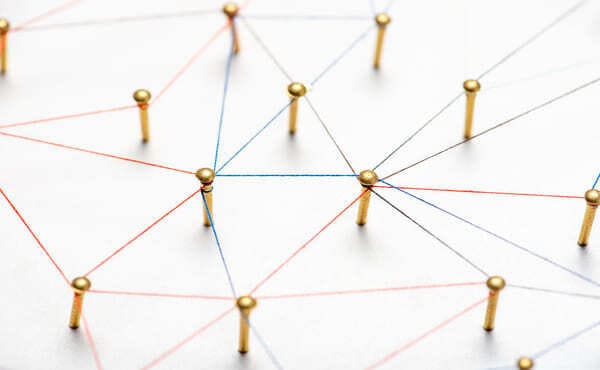
冒頭にも解説の通り、裁量労働制は実働時間ではなく、みなし労働時間で給与が決まります。そのため、残業代は発生しないと考えられがちですが、それは誤りです。
裁量労働制においても残業手当や休日手当、深夜手当が発生するケースがあります。ここからは、裁量労働制の労働時間の考え方を紹介します。
4-1. みなし労働時間における残業時間の考え方
裁量労働制はみなし労働時間制の1種です。そのため実際に働いた時間ではなく、事前に取り決めていた「みなし労働時間」が労働時間となります。
例えば、みなし労働時間を1日8時間と定めた場合は、実際の労働時間が4時間であっても8時間労働したとみなします、一方、10時間働いた場合でも8時間労働となるため、残業手当は発生しません。つまり、実際の労働時間が4時間でも8時間でも、1日8時間の賃金を支払うことになります。
4-2. 裁量労働制でも残業手当が発生する3つのケース
裁量労働制の場合、原則残業手当は発生しません。しかし、これから紹介する3つのケースに該当する場合は残業手当の支払いが必要となるので注意してください。
4-2-1. みなし労働時間が法定労働時間を超えるケース
労働基準法は、1日8時間・週40時間までを法定労働時間と定めています。そのため、みなし労働時間を8時間以上で定めた場合は、法定労働時間を超えた時間分の残業手当を支払うことになります。
4-2-2. 深夜労働に該当するケース
労働基準法では、22時~翌5時を深夜労働と定めているため、この時間に働いた場合は裁量労働制であっても賃金を割増する必要があります。なお、割増率は25%以上です。
4-2-3. 休日出勤に該当するケース
週1日または4週ごとに4日の法定休日に働くと労働基準法の休日労働にあたるため、割増賃金の対象となります。
4-3. 裁量労働制も36協定の適用対象
法定労働時間を超えて勤務する場合、36協定を締結する必要があります。これは、裁量労働制においても同様です。
36協定を締結すれば法定時間を超える労働が可能となりますが、月45時間・年360時間を超えると労働基準法違反となるため注意しましょう。
5. 【2024年4月】裁量労働制の職種が拡大し制度が改訂される

2024年4月1日より、裁量労働制が見直されました。これに伴い導入の手順が変更になるなど、企業への影響も少なくありません。
ここからは、裁量労働制の変更点を紹介します。また、企業が取るべき対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
5-1. 裁量労働制見直しの背景
裁量労働制が適用される対象業務の拡大は検討されており、本来は2018年に改正される予定でしたが、根拠となるデータに不備があったことから、見送られることとなりました。
働き方の多様化が推進される現代において、自由度が高い裁量労働制を導入したいと考えている企業は多いかもしれません。しかし、実際導入するためには厳しい条件があるため、なかなか利用できないという企業も少なくないでしょう。
2021年に厚生労働省がおこなった「就労条件総合調査」によると、専門業務型裁量労働制を採用している企業は2.0%、企画業務型裁量労働制は0.4%と、非常に低い利用率であることが分かります。[注1]
裁量労働制は正しく運用されないと、長時間労働を助長するという声がある一方、柔軟な働き方が実現できるという意見もあります。そのため、データの不備による見送りがあった後も適用範囲拡大の検討が続けられてきました。その結果、2024年4月からの改正が実現されたという経緯があります。
5-2. 専門業務型裁量労働制の変更点
専門業務型裁量労働制の変更点は以下の2点です。
- 労使協定に定める事項の追加
- 対象業務の追加
まずは、労使協定についてです。これまでは、7項目についての締結が必要でしたが、以下の4項目が追加されました。
- 労働者本人の同意を得る
- 労働者が同意しなかった場合の不利益な取り扱いの禁止
- 同意の撤回の手続き
- 労働者ごとの同意および同意の撤回に関する記録を保存すること
特に注意すべきは、4つ目の「労働者の同意と同意の撤回」に関する事項が追加された点です。この事項は、これまで「企画業務型裁量労働制」にのみ定められていました。
今回の変更では、記録の保存期間は労使協定期間中および期間満了後3年となっています。
次に、対象業務の追加です。これまで、専門業務型裁量労働制の対象業務は19業務でした。
今回の見直しで、新たに「銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」が追加されています。
5-3. 企画業務型裁量労働制の変更点
企画業務型裁量労働制の変更点は以下の3点です。
- 労使委員会の決議に定める事項の追加
- 労使委員会の運営規定に定める事項の追加
- 定期報告の頻度変更
まずは、労使委員会の決議に定める事項についてです。労使委員会の決議に定める事項として、次の2項目が追加されました。
- 同意の撤回の手続きに関すること
- 同意撤回に関する記録を保存すること
今回の改正では、専門業務型と同じく、「同意の撤回」に関する記録の保存も必要になります。なお、保存期間は労使協定期間中および期間満了後3年です。
また、対象の従業員への評価制度や、賃金に関するルールを変更する際は、変更内容を企業が労使委員会に説明しなければならないため注意が必要です。
次に、「労使委員会の運営規定に定める事項の追加」についてです。今回の改正では、労使委員会の運営方法も見直され、運営規定に以下の2点が追加されました。
- 制度の趣旨に沿った運営確保に関する事項を定める
- 労使委員会を6ヶ月以内ごとに1回開催する
今回の変更により、労使にとってより建設的な制度になることが期待されています。
3つ目は、「定期報告の頻度変更」です。従来の企画業務型裁量労働制では、労使委員会で決議のおこなわれた日から6ヶ月以内ごとに1回の頻度で、所轄の労働基準監督署への定期報告が義務づけられていました。
しかし、2024年4月からはその頻度が変更され、決議の有効期間の始期から起算して、初回は6ヶ月以内ごとに1回、2回目以降は1年以内ごとに1回となったため注意が必要です。
5-4. 裁量労働制の変更に伴って企業が取るべき対策とは
2024年4月からの裁量労働制変更に伴い、企業が取るべき対策は3つあります。
5-4-1. 継続導入の場合は協定の再締結が必要
裁量労働制の見直しで特に注意すべきは、継続して導入するケースです。先述の通り、専門業務型裁量労働制も企画業務型裁量も、労使で決議しなければならない事項が追加されました。
裁量労働制を継続して導入する場合は、新たに追加された事項を決議して新様式で届出をおこなわなくてはなりません。なお、この場合は、2024年3月末までに届出を提出しなければならない点も注意が必要です。
5-4-2. 対象者本人の「同意」を得る
2024年4月1日以降は、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制ともに対象従業員の「同意」を得る必要があります。
同意を得る方法は、書面や電子データなどが挙げられます。また、この記録は労使協定又は決議の有効期間中から満了後3年間保存しなければならないことも忘れてはいけません。
なお、同意を得るためには、以下の内容を説明し、本人が理解・納得した上で同意を得ることが大切です。
- 対象業務の内容を始めとする協定又は決議の内容など裁量労働制の制度の概要
- 同意した場合に適用される評価制度とこれに対応する賃金制度の内容
- 同意しなかった場合の配置・処遇
5-4-3. 勤怠管理の方法を見直す
裁量労働制では、労働時間の管理が課題です。従業員に始業・終業時間や業務ペースなどを任せるため、過重労働につながる可能性もあります。
裁量労働制を導入する前に、労働時間を正確に把握できる管理体制を整えることが大切です。法定を超える労働をしていないか、深夜労働や休日労働などが発生していないかなどを確認できる勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。また、給与の計算方法を見直すことで、人事業務の負担がより軽減され、正しい給与計算が可能となります。
今後、ますます働き方が多様化すると考えられるため、ITツールを使用した勤怠管理は必要不可欠と言えるでしょう。
6. 勤怠管理システムを活用して裁量労働制を適切に運用しよう
 裁量労働制には、専門業務型と企画業務型があり、職種も限定されています。いずれも専門性が高く、業務遂行のための方法や、時間配分に関して使用者が指示しづらいような業務が対象です。
裁量労働制には、専門業務型と企画業務型があり、職種も限定されています。いずれも専門性が高く、業務遂行のための方法や、時間配分に関して使用者が指示しづらいような業務が対象です。
どちらも導入するためには、厳しい条件での手続きが必要なので、現状で裁量労働制を導入している企業はそれほど多くありません。しかし、裁量労働制には業務効率の向上などのメリットがあるため、手続きの煩雑さを理由に諦めるのは得策ではありません。自社にとって裁量労働制が必要か否かを十分に検討しましょう。
なお、2024年4月から制度の内容が一部見直されました。すでに裁量労働制を導入している企業は新たな手続きが必要となるため注意が必要です。
裁量労働制を導入している、これから導入する場合でも、勤怠管理方法を見直すことで制度を正しく運用でき、給与計算などの業務負担も軽減されます。裁量労働制を導入する際は、併せて勤怠管理システムの活用も検討しましょう。








