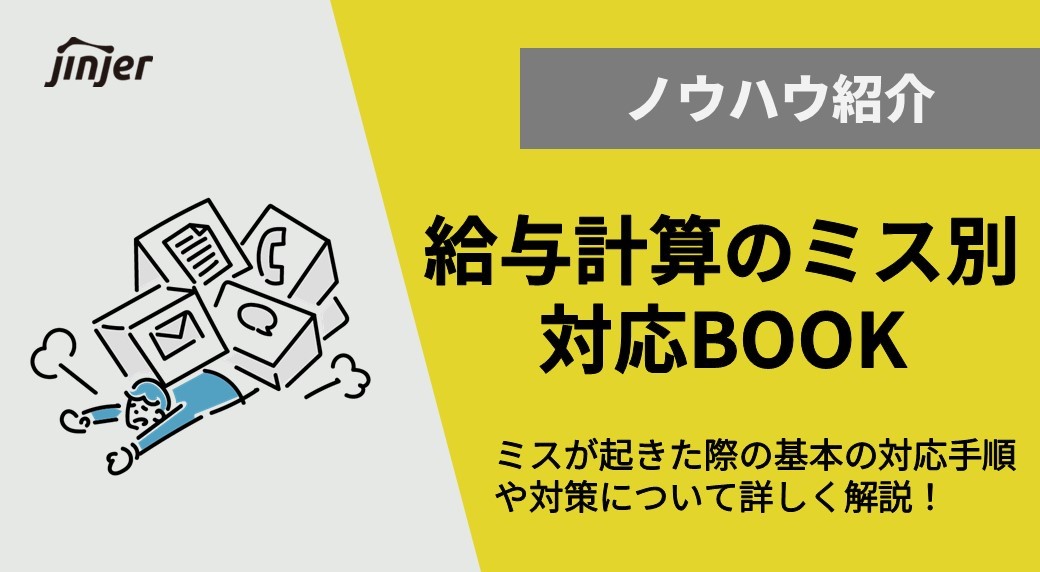従業員に支払う給与の計算にはミスは許されません。
従業員に支払う給与の計算にはミスは許されません。
また、一定期間ごとにかならずおこなう必要がある業務ですので、効率化のための工夫をすることも大切です。
給与計算における基本的な流れや計算方法、さらにミスが発覚した際の対応などについて詳しく解説します。
関連記事:給与計算とは|概要から手取りの計算方法まで基礎知識を総まとめ
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
- 給与計算でミスが頻発していてお困りの方
- 給与計算業務のチェックリストがほしい方
- 給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
このお悩みに当てはまるご担当者様は、こちらから「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、ぜひお役立てください。
1. 給与計算の流れと具体的な方法
 給与計算は単純に給料や手当の足し算をすればいいというものではなく、非常に複雑です。
給与計算は単純に給料や手当の足し算をすればいいというものではなく、非常に複雑です。
漏れや抜けのないように、基本の計算の流れや具体的な方法を確認しましょう。
関連記事:給与計算の流れを5ステップで解説!マスターするためのポイントをチェック
1-1. 総支給額を計算する
まずは総支給額を算出します。
時給や月給、特別手当などは従業員ごとで違うので、それぞれ抜けのないように正しく算出してください。
総支給額は、基本給に交通費など各種手当をプラスし、欠勤、遅刻、早退した分を差し引いたものです。
手当には役職手当や資格手当などの毎月変動しないものと、時間外労働に置ける残業手当や休日労働手当、交通費など、毎月変動するものがあります。
それぞれ別の項目を作成して計算するとスムーズです。
1-2. 控除額を計算する
保険料や税金などの控除額を計算します。
保険料や社会保険や雇用保険などがあり、それぞれに保険料率、税率が違います。間違いのないように計算をおこなってください。
税金には住民税や所得税があります。
課税対象額は総支給額から手当を差し引いた金額に各税率をかけた金額です。
社会保険料の計算は保険料ごとに保険料と税率が異なるなど計算が複雑になることからミスが多発しやすいものです。ミスを防ぐためにも、社会保険料の計算方法をしっかりと理解しておきましょう。当サイトでは、わかりやすい社会保険料の計算について解説した資料を無料でお配りしています。こちらからダウンロードして給与計算ミスの発生防止にお役立てください。
1-3. 最終的な支給額を計算する
総支給額と控除額を算出したら、最終的な支給額を決定します。
総支給額から控除額を差し引いたものが最終的な支給額です。いわゆる「手取り」と言われる金額がこれです。
給与明細には手取りの金額だけでなく総支給額や控除額、手当などすべてを記載する必要がありますので、計算したデータはすべて確認できるようにしておきましょう。
1-4. 各従業員への振り込みをおこなう
各従業員へ給与を振り込みます。
従業員によって振り込む金融機関は違いますので、振り込み先や振り込み方法、手数料を間違えないよう注意してください。
また、計算が正しくても振込金額を間違えてしまうと意味がありません。
振り込みの際は一人の担当者だけがおこなうのではなく、ダブルチェックをする必要もあります。
1-5. 保険料や税金を納付する
控除した保険料や税金を毎月10日までに納付しなければなりません。
保険料や税金を納付していないことが発覚し、それが何度も続いたり発覚してから長期間対応が見られない場合は企業がペナルティを受ける可能性もあるので注意してください。
関連記事:給与計算によって決まる所得税について計算方法や源泉徴収を詳しく紹介
2. ミス発生時の対応
 給与計算にミスは許されませんが、人が計算をおこなっている以上絶対にミスが発生しないとは言い切れません。
給与計算にミスは許されませんが、人が計算をおこなっている以上絶対にミスが発生しないとは言い切れません。
給与計算のミスを引き起こしてしまった場合の対応についても事前に確認しておきましょう。
2-1. ミスの内容を説明し謝罪する
ミスが発覚した時点ですぐに従業員にミスの内容を説明し、謝罪しましょう。
給与計算は従業員にとって大切なだけでなく、保険料や税金なども扱う非常に重要な業務です。
ミスを隠ぺいしたりごまかしたり、謝罪がなかったりすると、従業員からの信頼を失うだけでなく社会的な信頼も失うことになります。
関連記事:給与計算に間違いがあった際のお詫びや対応方法を紹介
2-2. 正しい金額を振り込む
ミスが発覚したらすぐに従業員へ謝罪し、正しい計算をおこないましょう。
確定した金額を振り込み、さらにその後従業員に正しい明細書を渡します。
次の賃金の支払いで相殺することは場合によっては認められますが、金額が大きいと従業員の生活に関わってしまいます。
できるだけすぐ対応するようにしてください。
2-3. 再発防止策を考える
なぜミスが起きたのかをよく考え、再発防止策を考えましょう。
給与計算の担当者が複数人いる場合はミスの原因や再発防止策を共有する必要があります。
何度もミスが起きる場合は計算方法や業務フローの根本に問題があるかもしれません。
今一度基礎の計算方法や利用しているツールを確認してください。
3. リスクと対処法
 給与計算で確認しておかなければならないリスクと対処法を紹介します。
給与計算で確認しておかなければならないリスクと対処法を紹介します。
実際にミスが発覚してから行動するのではなく、事前に対処法を意識することが大切です。
3-1. 最低賃金や法改正の確認をする
地域によって最低賃金は変動しますが、この金額は毎年改訂されています。
最低賃金ギリギリの賃金で従業員を雇用している場合は毎年この金額をよく確認し、給与計算に反映させてください。
また、税金や保険料なども法律の改定に伴い変動します。こちらも気づかない内に違法になっていたということがないよう注意しましょう。
3-2. 割増賃金の計算を正しくおこなう
労働時間や労働日数は、労働基準法によって厳しく定められています。
法律の上限の労働時間や労働日数を超過した場合は時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当として割増賃金を支払わなければなりません。
これらの割増賃金の計算も正しくおこなってください。
時間外労働などに関する割増賃金は1時間ごと、30分未満は切り捨て、30以上は切り上げて計算をおこないます。
3-3. 勤怠管理を正しくおこなう
従業員の勤怠管理を正しくおこなっていなければ正確な給与計算はできません。
欠勤したらその分の金額を差し引かなければなりませんし、遅刻や早退もどれくらい遅れたのか、何時に早退したのかを把握しておく必要があります。
リモートワークやフレックスタイム制など、従来とは違う働き方も増えてきています。
勤怠管理はより複雑になっていますので、管理しやすいツールなどを利用することもおすすめです。
4. ミスなく効率よく行う方法
 ミスなく効率的に給与計算をおこなう方法を3つ紹介します。
ミスなく効率的に給与計算をおこなう方法を3つ紹介します。
今後の給与計算の参考にしてください。
4-1. 表計算ソフトを使う
エクセルなど、パソコンにあらかじめ入っている表計算ソフトを利用することで計算をスピーディーに、正確におこなえるようになります。
給与計算用のシートを一から作るためには専門的な知識が必要ですが、無料で配布しているサイトもあります。
エクセルなどを使えばコストを大幅に抑えた上で簡単に計算ができるというメリットがあります。
関連記事:エクセルで行う給与計算について方法や関数をわかりやすく紹介
4-2. 給与計算ツールを利用する
有料ではありますが、給与計算ツールを導入する方法もあります。
給与計算ツールは勤怠管理も同時にできるものが多く、わざわざ勤怠を確認しながら計算をおこなう手間が省けます。
税金などに関する法律の改定に合わせて自動的にアップデートしてくれるので、情報を把握していなかったり数値を間違ったりした結果計算ミスが発生する事態も防げます。
エクセルよりも見やすい画面で感覚的に給与計算をおこなえるため、より給与計算担当者の負担を軽減できます。
5. 給与計算の基礎を確認してミスを防ごう
 給与計算について、その手順や方法の基本を解説しました。
給与計算について、その手順や方法の基本を解説しました。
給与計算を間違えると従業員に迷惑がかかるだけでなく違法行為になってしまう可能性もあります。
ミスが発覚してから対応するのではなく、ミスを未然に防ぐ方法、リスク管理を把握しておきましょう。
手書きでの計算は担当者の負担になるだけでなくミスを引き起こしやすいです。エクセルなどの表計算ツールや、給与計算の専門のツールも導入し、給与計算をよりスムーズなものにしましょう。
給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。
当サイトでは、給与計算で生じるミスの対処方法を場合別に紹介した「給与計算のミス別対応BOOK」を無料で配布しております。
- 給与計算でミスが頻発していてお困りの方
- 給与計算業務のチェックリストがほしい方
- 給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
このお悩みに当てはまるご担当者様は、こちらから「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、ぜひお役立てください。