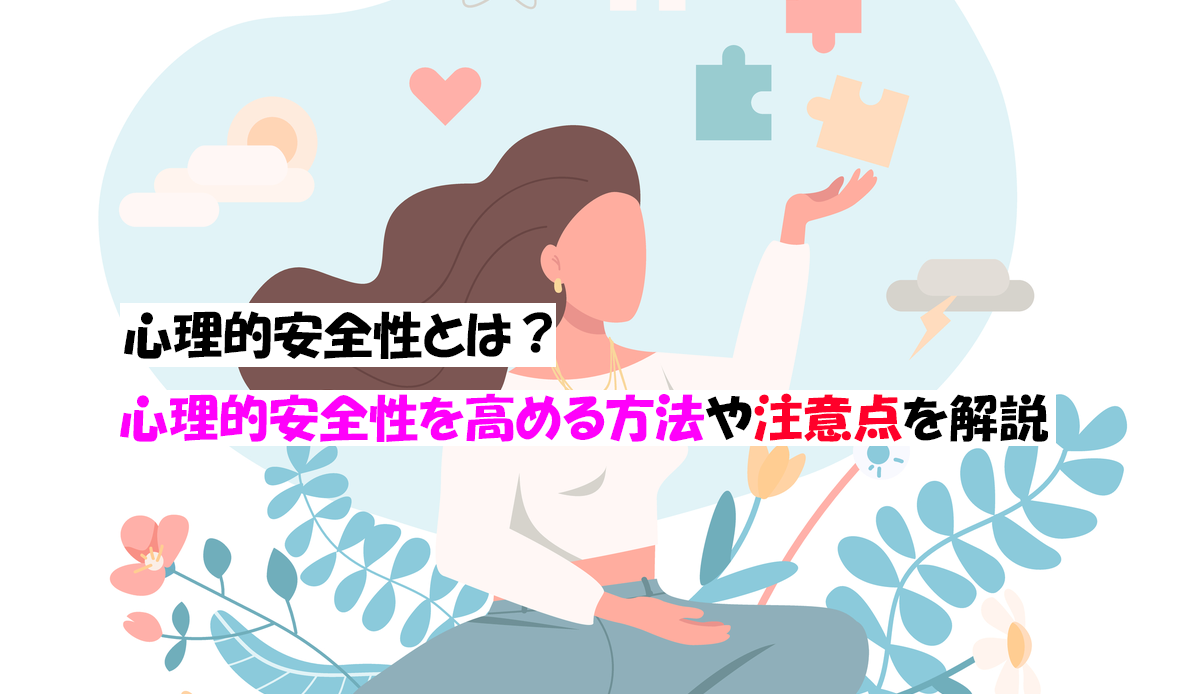
心理的安全性を高めることで、従業員と組織の生産性を向上させることができます。この記事では、心理的安全性とは何か、ぬるま湯組織との違いを踏まえてわかりやすく解説します。また、心理的安全性を高めることによるメリットや、心理的安全性が低い職場の問題点、心理的安全性の作り方のコツについても紹介します。
目次
1. 心理的安全性とは?

心理的安全性は、英語で「psychological safety」と表現され、1999年に組織行動学を研究する米・ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した心理学用語です。心理的安全性とは、会社や企業などの組織の中で自分の思っている考えや価値観を安心して表現できる状態を指します。ここでは、心理的安全性が注目される理由や背景、心理的安全性とぬるま湯組織の違い、心理的安全性の具体例について紹介します。
1-1. 心理的安全性が注目される理由や背景
心理的安全性が注目される大きなきっかけとなったのは、Google社の「プロジェクトアリストテレス」が、心理的安全性と生産性の関係に着目し、「心理的安全性が高いチームほど生産性が高い」という調査結果を示したことです。このような理由・背景により、企業を成長させるため、心理的安全性を重視する企業が増えています。
1-2. 心理的安全性とぬるま湯組織の違い
心理的安全性が高い組織とぬるま湯組織は、組織の特徴において違いがみられます。ぬるま湯組織とは、相手との衝突を避けるために自分の考えがあっても言わなかったり、相手の意見に簡単に同調したりする状態が慢性化している組織のことです。一方の心理的安全性が高い組織とは、異なる意見であっても恐れることなく発言でき、活発なコミュニケーションがおこなわれている組織を指します。
心理的安全性の高い組織とぬるま湯組織を混同し、同じ意味合いで捉えてしまうと、間違ってぬるま湯組織を作り出し、成長性の期待できない会社・企業となってしまう可能性があります。心理的安全性の高い組織とぬるま湯組織の違いを正しく理解して、心理的安全性の高い職場を目指せるような施策をおこなうことが大切です。
1-3. 心理的安全性の高い職場と低い職場の具体例
ここでは、心理的安全性の理解を深めるため、上司からの提案に対して部下が疑問を抱いた場合を例に、心理的安全性の高い職場と低い職場の違いを紹介します。
部下は自分の意見が歓迎されている組織だと感じているため、恐れることなく上司に疑問点を伝えました。結果として、上司と部下の話し合いを通じて、お互いが納得する提案につなられました。
部下は自分の意見を言うと、上司に嫌われ評価が下がると考え、上司に疑問点を伝えることなく、提案をそのまま受け入れることにしました。結果として、上司から伝えられた提案に問題点があったため、タスクを終えるまでに時間がかかることになりました。
このように、心理的安全性の高い職場と低い職場では、自分の意見の発言しやすさが異なります。心理的安全性の高い職場を作り出せれば、コミュニケーションが活性化し、強固な組織作りにつなげることが可能です。
2. 心理的安全性が低い職場が抱える問題

心理的安全性が低い職場では、どのような問題が起こりえるのでしょうか。心理的安全性が低い職場で働く従業員は、さまざまな不安を抱く恐れがあります。ここでは、心理的安全性が低い組織のメンバーが抱える可能性のある不安について詳しく紹介します。
2-1. 自分が無能であるという不安
心理的安全性が不足しているチームでは、他のメンバーに質問や相談をする必要がある場合に、「こんなこともわからないのか」と思われてしまうかもしれないと、メンバーが不安を抱えるようになります。「自分が無能であると思われることへの不安」は、自分のミスを素直に認めない、あるいは失敗をしても他のメンバーへ報告しないといった行動につながり、後々になってトラブルが発生する恐れもあります。
2-2. 他のメンバーの邪魔になっているのではないかという不安
心理的安全性が低いと、「チームのメンバーに嫌われているのではないか」「自分の発言のせいで議論が進まないと思われてしまうのではないだろうか」といった不安を抱えるようになります。不安を感じているメンバーは発言を控えるようになり、新たな意見を共有することが難しくなります。結果として、チームにとって本来プラスになるはずのアイデアが得られない可能性が起こりえます。
2-3. 自分がネガティブな人間だと思われているのではないかという不安
チームで活動するうえでは、他のメンバーに指摘が必要な場合も少なからずあります。心理的安全性が不足したチームに在籍することで、自分がメンバーの迷惑になっているのではないかと不安を抱き、指摘することをためらうようになります。これにより、チームが重要な課題に気づくのが遅くなったり、最悪の場合、気づかずにそのまま物事が進んでしまったりする恐れがあります。
2-4. 自分が無知であるという不安
心理的安全性が低いチームでは、知らないということに恥ずかしさや申し訳なさを感じ、他のメンバーや上司に質問することを避けるようになってしまいます。組織力を高めるためには、不明点を解消して、知識力や対応力を高めることが欠かせません。心理的安全性が低いとメンバーが無知なままになってしまい、組織全体の成長につながっていかない恐れがあります。
3. 心理的安全性が高いことで「個人」が得られるメリット

心理的安全性の高い職場で働くことで、従業員はさまざまなメリットが得られます。ここでは、心理的安全性が高い職場を作り出すことで「個人」が得られるメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 仕事のパフォーマンス向上
心理的安全性が高い職場では、自分の意見を発言しやすい環境を構築することができます。従業員が働きやすい職場だと感じられることで、仕事へのモチベーションが高まります。また、不安が少なくなり、精神的に安定した状態で仕事を進められるので、集中力が高まり、パフォーマンスの向上も期待できます。
3-2. やりがいや責任感を感じやすくなる
心理的安全性の低い職場では、仕事に対するモチベーションが下がってしまいます。一方、心理的安全性の高い職場では、帰属意識が高まり、やりがいや責任感を感じやすくなります。これにより、従業員は主体的に働くことができるようになります。
3-3. 人間関係のストレスを軽減できる
心理的安全性の低い職場だと、周囲に常に気を遣わなければならず、ストレスが蓄積されていきます。場合によっては、メンタル面に不調が出る恐れもあります。心理的安全性の高い環境を構築できれば、不要な気遣いがなくなり、人間関係のストレスを軽減することが可能です。
4. 心理的安全性が高いことで「組織」が得られるメリット

心理的安全性の高い職場は、従業員個人だけでなく、組織全体としてもメリットが得られます。ここでは、心理的安全性が高い職場を作り出すことで「組織」が得られるメリットについて詳しく紹介します。
4-1. エンプロイーエクスペリエンスを向上できる
エンプロイーエクスペリエンス(Employee Experience)とは、従業員が組織の中で体験する経験価値を指します。心理的安全性の高い職場では、従業員体験の質も高めることができます。エンプロイーエクスペリエンスが高まれば、従業員エンゲージメントも向上します。
関連記事:従業員エンゲージメントとは?調査方法や高める施策、高い企業の事例も紹介
4-2. 生産性が高まる
心理的安全性の高い職場では、従業員のパフォーマンスが向上します。また、従業員同士のコミュニケーションが活性化し、情報共有がしやすくなります。組織の意思が統一されることで、組織全体としての生産性も向上させることが可能です。
4-3. イノベーションを推進できる
心理的安全性の高い職場で、精神的に安定した状態を維持しながら仕事に取り組むことによって、従業員は新しいことや困難なものに挑戦しやすくなくなります。また、自分の意見を発言しやすい環境は、コミュニケーションを活発化させ、イノベーションを生まれやすくすることが可能です。
4-4. 採用力を強化できる
心理的安全性を高めることで、意見を交わしやすい職場を作り出すことができます。風通しのよい企業だと社会に認知されれば、多様な価値観を持った人が集まりやすくなり、求人応募者数の増加が期待できます。結果として、優秀な人材を獲得できる可能性が高まります。
4-5. 人材の定着率が向上する
心理的安全性が高いことで、従業員は職場に対して、「居心地が良い」「仕事がしやすい」と感じるようになり、帰属意識が高まります。そのため、離職・転職しようとする従業員が減り、離職率の低下につなげることが可能です。結果として、優秀な人材の流出を防止し、人材の定着率を高めることができます。
関連記事:「心理的安全性の高いチームはどう作るのか?」これからのマネジメントに求められるスキルを学ぶ
5. 心理的安全性を高める4つの因子

心理的安全性を高めるためには、「話しやすさ」「挑戦」「助け合い」「新奇歓迎」の4つの因子に注目することが大切です。ここでは、心理的安全性を高める4つの因子それぞれについて詳しく紹介します。
5-1. 話しやすさ
話しやすさは、心理的安全性の高い組織に共通する要素の一つです。自分の考えを素直に発信できない、意見を言っても否定されるような気がするなど、話しにくい組織の場合、新しいアイデアが生まれにくいだけではなく、コミュニケーション不足からミスが発生する可能性も高まります。自分の意見を受け入れてもらえるという雰囲気があれば、気軽に意見交換したり、ミスを指摘し合ったりできる組織へと成長できます。
5-2. 挑戦
心理的安全性が高い組織では、失敗を恐れずに新しい企画や事業にチャレンジすることができます。仮に失敗したとしても、単に責めるだけで終わらず、一緒に原因を探ったり、改善策を考えたりするなど、建設的な行動へとつながります。挑戦を避けるような雰囲気になっている場合、心理的安全性が低くなっている可能性もあります。ミスを受け入れる姿勢を示すなど、誰もが安心して新しいことに挑戦できるような環境を整えることが重要です。
5-3. 助け合い
心理的安全性の高い組織を目指すなら、助け合いという因子に注目することも大切です。トラブルが発生したときに全員で協力して対応策を考えたり、それぞれのスキルをかけ合わせて新しいことに挑戦したりしている場合、心理的安全性は高まっているといえます。逆に、チームメンバーが孤立しているような場合は、自然と助け合いが起こるような組織運営を心がけることが大切です。
5-4. 新奇歓迎
奇抜な考え方や従来にない価値観を受け入れることは、心理的安全性を高めるために重要な要素の一つです。組織を運営するうえで協調性はもちろん大切ですが、個性的な人を避けたり、他人を主観で判断したりすることは避けるべきです。さまざまなタイプの人を受け入れる雰囲気を作り出すことで、組織の心理的安全性は高まっていきます。
6. 心理的安全性を測定する7つの質問

心理的安全性が低い職場は、従業員の不安につながり、生産性を下げる原因になります。心理的安全性を高めることで、従業員と組織ともにあらゆるメリットが得られます。しかし、自社の心理的安全性をどのように測定すればよいかわからない人も少なくないでしょう。ここでは、組織の心理的安全性を測るための7つの質問を紹介します。
- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある
- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
- チームのほかのメンバーに助けを求めることは難しい。
- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、生かされていると感じる。
この7つの質問は、組織行動学者エイミー・エドモンドソン氏が提唱したもので、ポジティブな回答が多ければ「心理的安全性の高いチーム」、反対にネガティブな回答が多ければ「心理的安全性の低いチーム」であると判断することができます。
6-1. 心理的安全性を測定するための3つのサイン
エイミー・エドモンドソン氏は、次の3つのサインがあることも心理的安全性が高い職場の特徴であると述べています。
- 前向きな発言が多い
- 失敗や課題について話し合う機会が多い
- 笑いとユーモアがある
成功や成果についてだけではなく、失敗や解決すべき課題についても気軽に話し合える職場は、心理的安全性が高いといえます。心理的安全性の高い組織を構築するため、失敗に対して叱責や非難をするばかりではなく、前向きな解決策を提案できるような職場環境を構築していくことが大切です。
7. 心理的安全性の高い組織の作り方(上司・マネージャー向け)

自社の心理的安全性を測定できたら、必要に応じて心理的安全性を高める行動や施策をおこなうことが大切です。ここでは、上司やマネージャー向けに、今すぐからできる心理的安全性の高い組織の作り方について詳しく紹介します。
7-1. 相手への感謝・受け入れる姿勢を示す
従業員が「組織に貢献できている」「組織から必要とされている」という実感を持てれば、エンゲージメントは高まり、心理的安全性の高い職場へとつながります。そのため、上司やマネージャーは部下に対して、日常的に感謝の気持ちや受け入れる姿勢を示すことが大切です。
7-2. 話しやすい雰囲気を作る
経験の豊富な上司やマネージャーに対しては、部下も委縮してしまい、思っていることを話せないケースがよくあります。ランチに誘ったり、雑談を活用したりして、話しやすい雰囲気を醸成することで、部下は心を開き、自分の意見をいいやすくなります。また、どのような提案に対してもまずは耳を傾け、ポジティブに反応することで、話しやすい環境を作り出すことが可能です。
7-3. 発言できる機会を均等にもてるようにする
上司やマネージャーが一方的に話していると、部下は話を切り出せず、思っていることを打ち明けられない可能性があります。心理的安全性を高めるためには、誰もが自由に発言できる環境を作り出すことが大切です。上司・マネージャーは発言回数や発言時間が特定の人に偏らないよう、まんべんなく意見を言えるように会議を進めるようにしましょう。
7-4. 完璧を求めない
完璧主義を求める環境では、ミスを恐れるようになり、心理的安全性を低下させる原因にもなります。仕事には失敗がつきものです。失敗した後に、どのように改善につなげるかが成長のためにも重要なポイントです。そのため、上司やマネージャーは部下に対して完璧を求めないことが大切です。また、自分から弱みや失敗した経験などを打ち明けることで、部下は上司・マネージャーに対して親近感を持ち、信頼関係の向上につながります。
7-5. 否定ではなく問題解決に努める
部下がチャレンジした結果に対して評価する際、ネガティブになってしまうこともあるかもしれません。挑戦したことを否定してしまうと、今後は委縮して新しいことに取り組まなくなる可能性があります。「どのようにしたら上手くいったのか」など、問題解決に努めることが大切です。建設的な話し合いをおこなうことで、部下は次の行動につなげやすくなります。
8. 心理的安全性の高い職場の作り方(人事担当者向け)

ここでは、人事担当者向けに、心理的安全性の高い組織の作り方について詳しく紹介します。自社でも導入できると感じたら、ぜひ取り組んでみてください。
8-1. 1on1ミーティングを実施する
1on1ミーティングは、人事評価面談と異なり、部下の成長のため、上司と部下が1対1で定期的に対話をおこなうマネジメント手法のことです。1on1ミーティングを実施することで、上司が部下の考えていることを正しく把握し、相互理解を促進することができます。ただし、適切に1on1ミーティングを導入しなければ、時間の無駄となったり、関係性を悪化させたりする可能性があります。心理的安全性の高い職場を構築するために、正しい方法で1on1ミーティングを導入しましょう。
関連記事:1on1ミーティングとは?運用時のポイントや企業事例をご紹介
8-2. 評価制度を変更する
評価制度に不公平さがあると、従業員の不満につながります。また、挑戦に対してマイナス評価をするような人事評価制度は、従業員がチャレンジに対してネガティブになる原因になります。まずはすべての従業員が納得感を持てるような評価制度に改善することが大切です。また、成果だけでなく、取り組む姿勢も評価に入れることで、心理的安全性を高めることができるかもしれません。
8-3. OKRを導入する
OKR(Objectives and Key Results)とは、組織の大きな目標である「達成目標」(Objectives)を定義したうえで、その達成度を測定すためのる「成果指標」(Key Results)を設定する目標管理手法を指します。OKRを活用することで、従業員個人の成果が組織目標に対してどのぐらい貢献できているかを可視化できるので、やりがいが感じられるようになります。結果として、仕事へのモチベーションも向上し、心理的安全性を高めることが可能です。
関連記事:OKRとは?意味や目標・評価の設定、導入企業の具体例を紹介
8-4. ピアボーナスを設ける
ピアボーナスとは、従業員同士で報酬などを送りあえる制度のことです。感謝の気持ちがあっても届いていなければ、相手はそれを実感することができません。ピアボーナスにより、感謝の気持ちを可視化することで、「自分の行動が人の役に立った」などと職場に明るい雰囲気をもたらし、心理的安全性を高めることができます。
関連記事:ピアボーナスとは?制度の意味やメリット・デメリットを紹介
8-5. チーム編成を見直す
いろいろな施策をおこなっても組織の心理的安全性が高まらない場合、メンバー間に問題がある可能性も考えられます。従業員それぞれ性格が違い、相性もあります。そのため、組織の編成を変えることで、メンバー間のコミュニケーションを改善できる可能性もあります。
9. 心理的安全性を高めるときの注意点

心理的安全性を高めることは、「馴れ合いの関係・楽ができる場所」を作り出すことではありません。ぬるま湯組織のようになると、意図したこととは反対にそれが悪影響となり、組織の生産性が低下してしまう恐れがあります。ここでは、心理的安全性を高めるときの注意点について詳しく紹介します。
9-1. 適度な緊張感を保つ
心理的安全性とは、あくまで対人関係が良好で心理的に開かれている状態であり、単に仲がよく居心地がよいだけの状態ではありません。馴れ合いの関係になっているぬるま湯のような職場では、チームが高い生産性を発揮するのは難しくなります。心理的安全性を尊重するあまり、職場やチームに緊張感が失われてしまわないよう注意が必要です。
9-2. 従業員の同意を得る
1on1ミーティングやピアボーナス、OKRなど、心理的安全性を高める施策はさまざまあります。しかし、従業員の同意を得ず、人事担当者のみで施策を進めてしまうと、従業員の会社に対する不満につながる恐れがあります。心理的安全性を高めるための施策をおこなう際は、その施策の目的やメリットを周知し、従業員からの同意を得たうえで進めることが大切です。
9-3. 全員が意見を発信できているか観察する
チーム内の議論や発言が活発化しているケースをよく観察すると、積極的に発言しているのが一部のメンバーのみということもあります。せっかくさまざまな個性をもつメンバーが集まっているのに、意見を積極的に発信できない状態が続いてしまうのは大きな問題です。メンバーが居心地の悪さを感じていることをきっかけに、チームの分断が起きてしまう可能性も考えられます。心理的安全性を維持するためにも、チーム内のあらゆるメンバーが意見の発信をおこなっているか定期的に確認しましょう。
10. 職場の心理的安全性を高めて組織力を強化しよう!

心理的安全性を高めることは組織を活性化させ、生産性を向上させるのに重要な役割を果たします。心理的安全性を高めるには、その組織や従業員にあった方法を採用することが大切です。心理的安全性を向上させて、強固な組織を作り出しましょう。







