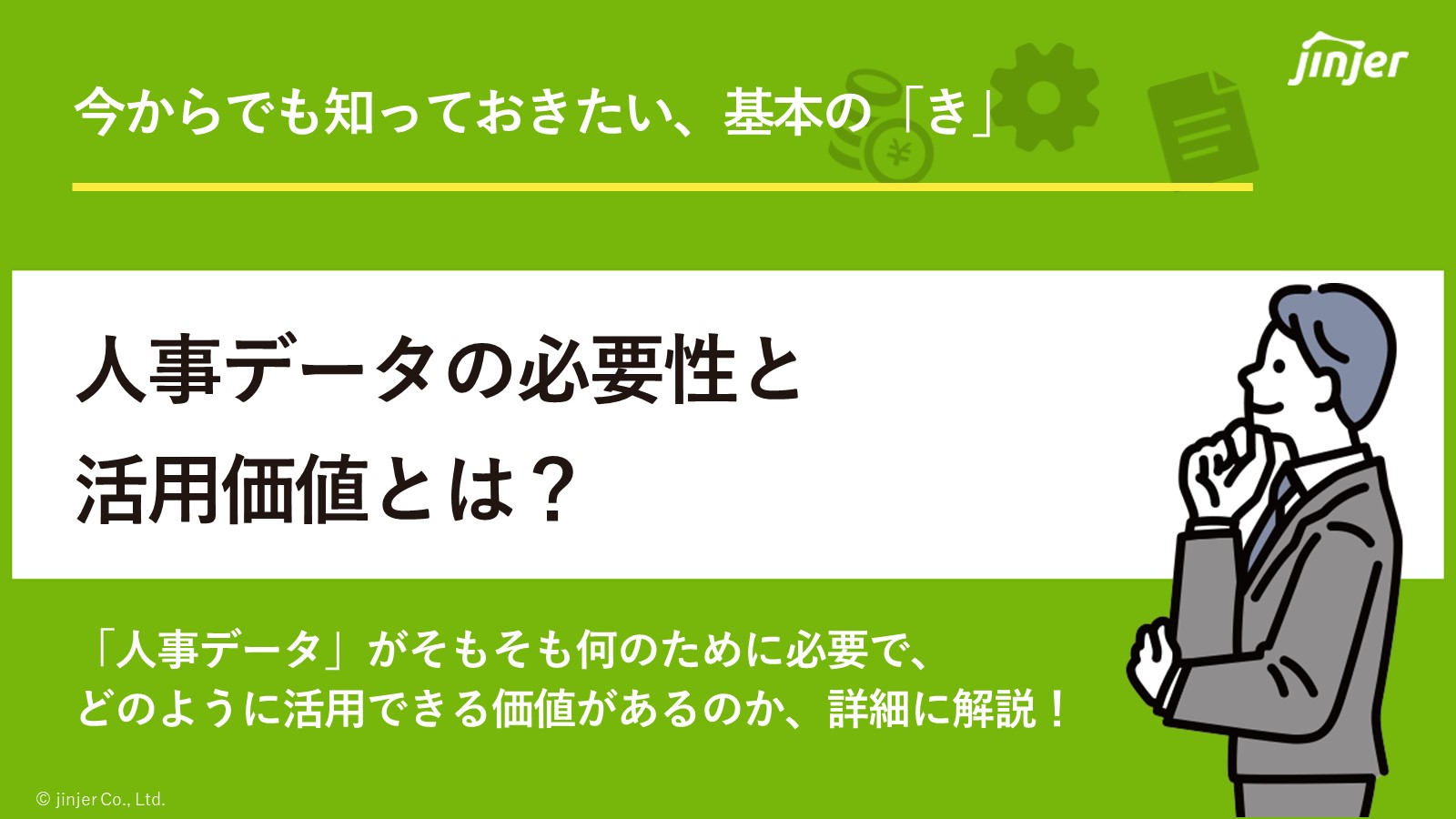コンピテンシーアセスメントとは、能力・技能を意味する「コンピテンシー」と評価・査定を意味する「アセスメント」を組み合わせた用語です。高い業績を出している従業員の能力を分析することで、タレントマネジメントに役立てることができます。本記事では、コンピテンシーアセスメントとは何か、メリット・デメリットや導入方法、注意点への対策をわかりやすく解説します。
目次
企業として人事データを適切に管理することはとても重要ですが、
そもそもなぜ人事情報の管理が必要であり、その先に大きな活用価値があることについても、正しく理解できていますか?人事情報は、適切な人材配置、従業員のモチベーションの管理、公平な評価制度など、企業として健全な経営をおこなう上で欠かせない情報です。
当サイトでは、人事データの必要性や活用価値をわかりやすく解説した資料を無料配布しています。
「人事情報を取り扱う上での基本や管理方法が知りたい」「人事データを用いた今後の活用例が知りたい」という人事担当者の方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。
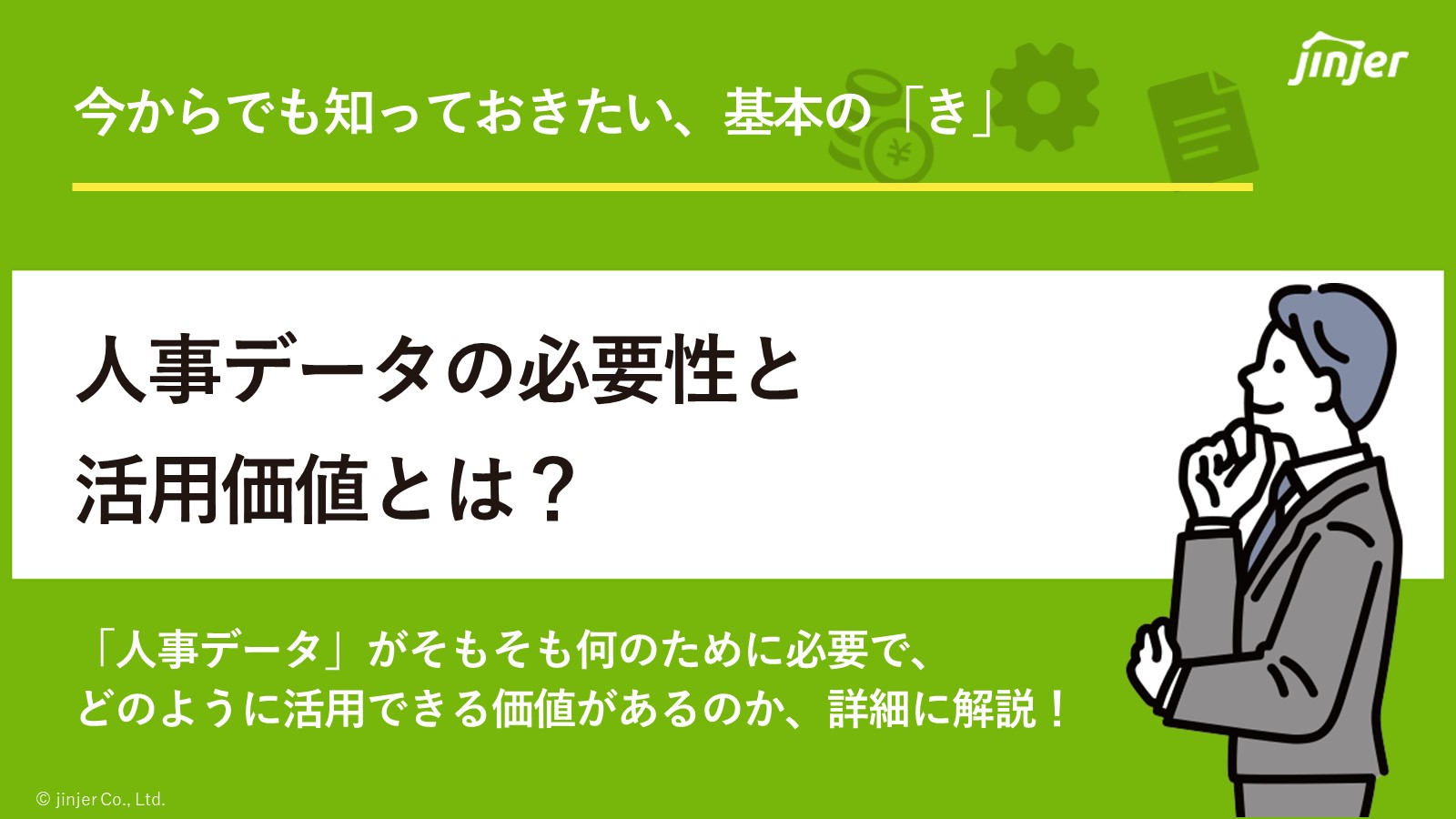
1. コンピテンシーアセスメントとは?

コンピテンシーアセスメントとは、職務で優れた成果を出す社員の行動特性や能力を表す「コンピテンシー」と、評価・査定を表す「アセスメント」を合わせた言葉です。つまり、コンピテンシーアセスメントとは、高いパフォーマンスを発揮している従業員の行動やスキルを分析し、他の従業員と比較するなどして、人事管理に役立てることを意味します。ここでは、コンピテンシーアセスメントが注目される背景・理由や、タレントマネジメントとの関係性について詳しく紹介します。
1-1. コンピテンシーアセスメントが注目される背景や理由
近年では働き方改革の影響もあり、終身雇用や年功序列から成果主義へと移行しつつあります。高いパフォーマンスを出している従業員を正しく評価するため、コンピテンシーアセスメントが注目されています。また、少子高齢化による労働人口の減少により、人材確保に悩みを抱えている企業が増えています。限りある人材で高い業績を出すには、従業員の能力・スキルを客観的に把握し、人材育成や人材配置に役立てることが重要とされています。このような背景・理由もあり、コンピテンシーアセスメントが注目されています。
1-2. コンピテンシーアセスメントとタレントマネジメントの関係性
タレントマネジメントとは、従業員それぞれが最大限に能力を発揮するため、年齢や性別などの基本情報だけでなく、経験やスキルといったタレント情報も管理するマネジメント手法のことです。効率よく人材育成や人材配置などのタレントマネジメントの目的を果たすためには、コンピテンシーアセスメントが役立ちます。高い成果を出している従業員の行動や能力を分析して、育成カリキュラムを作成したり、人事異動をおこなったりすることで、効果的なタレントマネジメントを実現することが可能です。
関連記事:タレントマネジメントの導入を成功させるコツとは?選び方のポイントも紹介
2. 役割ごとに異なるコンピテンシーアセスメントの基準

コンピテンシーアセスメントは、従業員の役割や立場に応じて基準が異なります。それぞれの要点を押さえて運用することが大切です。ここでは、「一般社員」「管理職」「経営者」に区分したうえで、それぞれに求められるコンピテンシーについて詳しく紹介します。
2-1. 一般社員
新入社員を含む一般社員に求められるコンピテンシーの一つは「成長意欲」です。まずは主体性をもって学び、行動する能力が、将来成果を出す人材になるために必要とされます。また、チーム内のコミュニケーションを円滑にするためにも、信頼関係を築くための努力や、誠実さといった側面も要求されます。
2-2. 管理職
管理職は、チームを目標達成に導くためのコンピテンシーが求められます。目標達成意識はもちろん、問題に直面した際の解決能力も必要です。分析思考と対人能力を持ち合わせ、組織から信頼を獲得するために行動し続けられているかどうかが重要とされます。
2-3. 経営者
経営者に求められるコンピテンシーは、大胆な決断力や推進力といった、経営課題を解決し続ける意識です。会社の経営課題をクリアにし、目標を達成し続けるためには、迅速な判断能力が欠かせません。また、経営者としての感度を高め続ける成長意欲も、大切な要素の一つです。
3. コンピテンシーアセスメントを導入するメリット

コンピテンシーアセスメントを導入することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、コンピテンシーアセスメントを導入するメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 社員の本来の能力を発見できる
現状では本来の能力を発揮できていない従業員もいるかもしれません。しかし、評価するための指標がなければ、正しく従業員の特性を評価することができません。コンピテンシーアセスメントにより、コンピテンシーモデルと評価対象の従業員の行動や能力を比較することで、潜在的なスキルを見つけ出すことができます。
たとえば、現在は事務部門に配属されている社員の場合、管理能力は平均以下であるものの、ビジネス理解力やコミュニケーション能力がほかの社員より高いなら、営業部門のほうが適している可能性があるなどと、判断することが可能です。このように、コンピテンシーアセスメントは従業員の潜在的な能力を発見するために役立ちます。
3-2. 人事異動の精度が向上する
管理職と一般社員では求められる行動特性や能力は異なります。仕事ができる社員を昇格させたからといって、管理職になっても能力を発揮できるとは限りません。コンピテンシーアセスメントを活用すれば、若手社員や管理職など、立場により求められる行動特性を備えているかどうかを事前に把握することができます。
また、コンピテンシーアセスメントでは、従業員の能力・スキルを客観的に評価できるため、根拠のある結果に基づいて人材配置をおこなうことが可能です。従業員が持つコンピテンシーを活用できるようなポジションへの配置は、生産性向上や業績アップに寄与します。各従業員の強みを最大限に活かすことで、組織全体のパフォーマンスも向上します。
関連記事:人員配置とは?意味や最適化のポイントをわかりやすく紹介
3-3. 効果的な人材育成につながる
コンピテンシーアセスメントでは、コンピテンシーモデルと社員を比較し、足りない行動特性・能力を補うようにサポートすることもできます。たとえば、コンピテンシーアセスメントにより、不足している知識・スキルを洗い出し、研修などの学習機会を用意することで、従業員と企業双方の成長へとつなげることが可能です。このように、コンピテンシーアセスメントは、効果的な人材育成にも役立ちます。
関連記事:人材育成で大切なこととは?考え方や課題、目標や具体例などを詳しく紹介!
3-4. 従業員の評価への満足度を高められる
成果が高い従業員と低い従業員が同様の評価をされている場合、ハイパフォーマーの従業員の会社に対する不満へとつながる可能性があります。コンピテンシーアセスメントにより、成果に基づき、公平な評価制度を構築することで、従業員の評価への満足度を高めることが可能です。また、コンピテンシーアセスメントにより、評価基準が明確になることで、目標設定や行動・改善がしやすくなります。
関連記事:従業員エンゲージメントとは?調査方法や高める施策、高い企業の事例も紹介
3-5. 採用活動に活用できる
コンピテンシーアセスメントを、採用基準の一つとして取り入れることで、採用活動の生産性を向上させることができます。コンピテンシーアセスメントにより、求められるスキルや行動パターンに基づいて求職者を評価し、組織のニーズに適した人材を採用することができるようになります。これにより、ミスマッチを減らし、採用成功率を高めることが可能です。
4. コンピテンシーアセスメントを導入するデメリット
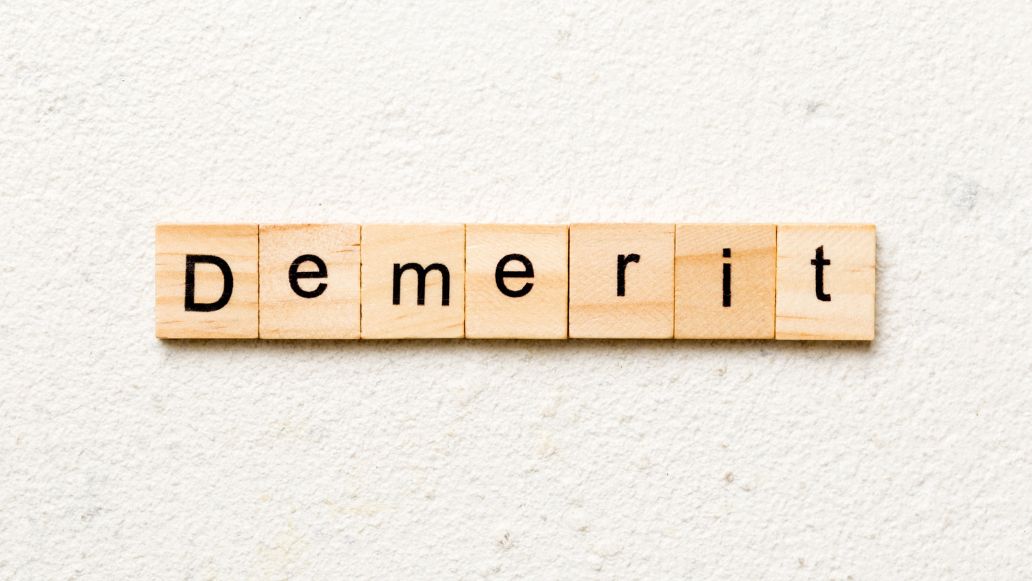
コンピテンシーアセスメントを導入する場合、メリットだけでなく、デメリットが生じることもあります。デメリットへの対策をおこなったうえで導入することで、効果的なコンピテンシーアセスメントを実現することが可能です。ここでは、コンピテンシーアセスメントを導入するデメリットについて詳しく紹介します。
4-1. 導入に時間や手間がかかる
コンピテンシーアセスメントを導入するには、ハイパフォーマーの選出・分析を実施したうえで、適切に人材配置・人材育成をおこなう必要があります。多くの過程を踏まなければならないので、時間や手間がかかります。また、時代の変化とともに見直しも必要になるため、担当者の負担が大きくなる恐れもあります。コンピテンシーアセスメントを導入する場合、スムーズに導入・運用できるよう、組織全体が協力して施策を進めることが大切です。
4-2. コンピテンシーモデルの作成が難しい
コンピテンシーアセスメントの導入において最も困難とされるのが「コンピテンシーモデルの作成」です。数値化して評価しづらい部署の場合、何をもってコンピテンシーが高いと評価するのか基準を定めるのが難しいです。また、ハイパフォーマーを選定できたとしても、その人がなぜ成果を出せているのか言語化できず、上手に基準を作成できない可能性もあります。
コンピテンシーモデルの作成がぞんざいになってしまうと、コンピテンシーアセスメントを効果的に運用することができません。このように、コンピテンシーアセスメントはタレントマネジメントに大きく役立ちますが、コンピテンシーモデル作成のハードルが高いことを押さえておきましょう。
4-3. 従業員の不満につながる恐れがある
コンピテンシーアセスメントにより、人事評価基準を作成する場合、公平な評価制度にしなければ、かえって従業員の不満につながる可能性があります。また、評価基準が明確でなければ、従業員は目標が立てにくく、モチベーション低下につながる恐れもあります。このように、コンピテンシーアセスメントを導入する場合、納得感のある人事評価制度を構築できるよう慎重に施策を進めることが大切です。また、成果が出ていない従業員へのフォローも忘れないようにしましょう。
5. コンピテンシーアセスメントを導入するときの注意点

コンピテンシーアセスメントはさまざまな場面で活用できるものの、導入目的が明確でないと、コンピテンシーモデルの作成自体に失敗する恐れもあります。ここでは、コンピテンシーアセスメントを導入するときの注意点について詳しく紹介します。
5-1. 導入目的を明確にする
コンピテンシーアセスメントは人材育成だけでなく、採用活動や人事評価、人事異動など、さまざまな場面で活用することができます。しかし、導入目的が明確でないと、その条件を達成するコンピテンシーモデルの作成ができません。たとえば、新規採用後の人材の定着率を上げたい場合と、中堅社員の業務効率を上げたい場合では、対象となるハイパフォーマーが異なります。まずはコンピテンシーアセスメントを導入する目的を明確にし、コンピテンシーモデルをスムーズに作成できるようにしましょう。
5-2. 定期的に見直す必要がある
コンピテンシーアセスメントは、導入後の運用の仕方が重要です。社会情勢や企業の置かれた状況、そして従業員の意識などは、その時々で変化します。どのような人材が結果を出していて、どのような人材を組織が求めているのか、PDCAサイクルを繰り返し、定期的な見直しをおこなうことが大切です。
5-3. 他の評価方法とも比較して導入を検討する
必ずしもコンピテンシーアセスメントを導入しなければならないわけではありません。コンピテンシーアセスメントにはメリット・デメリットがあり、向いている企業と向いていない企業があります。たとえば、成果でなく、プロセスに基づき評価したい場合、コンピテンシーアセスメントは向いていないかもしれません。そのため、MBOや360度評価など、他の評価手法とも比較して導入を検討しましょう。
関連記事:360度評価とは?メリット・デメリットや評価方法を紹介
6. コンピテンシーアセスメントの導入を成功させるためのコツ

コンピテンシーアセスメントの導入を成功させるためにはいくつかのポイントがあります。ここでは、コンピテンシーアセスメントの導入を成功させるためのコツについて詳しく紹介します。
6-1. スモールスタートで取り組む
コンピテンシーアセスメントをいきなり導入すると、評価制度が大きく変わり、現場の従業員の混乱を招く可能性があります。また、従来の評価手法に満足している従業員にとっては不満につながる恐れもあります。コンピテンシーアセスメントを導入する際は、「人事・総務部門のみ」「新入社員のみ」などのように、スモールスタートで段階的に導入するのがおすすめです。また、コンピテンシーアセスメントを導入する前に、目的やメリットを周知し、従業員からの理解を得ることで、スムーズに施策を進めることができます。
6-2. ツールの導入を検討する
コンピテンシーアセスメントを導入する場合、ハイパフォーマーの分析やコンピテンシーモデルの作成に時間や手間がかかり、スムーズに運用できない可能性があります。また、担当者の業務負担が大きくなる恐れもあります。そのため、業務を効率化するため、コンピテンシーアセスメントツールの導入を検討してみるのも一つの手です。ただし、導入・運用コストがかかるので、複数のサービスを比較して、自社のニーズにあったツールを導入することが大切です。
6-3. 成果に着目してみる
コンピテンシーアセスメントにおいて、コンピテンシーモデル(理想像)の作成に工数をかけすぎると、運用するまでに大きな時間がかかります。また、コンピテンシーモデルを目標として基準を設定しても、成果につながらず、意味のないものとなってしまう恐れもあります。コンピテンシーモデルは、成果に直結するかどうかの観点から作成してみるのがおすすめです。また、時間をかけすぎず、運用と改善を繰り返して理想に近づけていくことで、コンピテンシーアセスメントの導入を成功させることができます。
7. コンピテンシーアセスメントの導入方法

コンピテンシーアセスメントをスムーズに導入するためにも、導入方法を理解しておくことが大切です。ここでは、コンピテンシーアセスメントの導入方法について詳しく紹介します。
7-1. 部門ごとの行動特性を把握する
まず、各部門で優れた業績を上げている社員「ハイパフォーマー」を複数人集め、聞き取り調査を実施します。ハイパフォーマーが業務をおこなうにあたり、何を考え、どのように行動しているか詳細に調査しましょう。
7-2. コンピテンシーモデルの作成
ハイパフォーマーから聴取した行動特性を具現化したコンピテンシーモデルを作成します。作成時は行動特性を「コミュニケーション能力」や「自己管理能力」などの3~5の大カテゴリと、複数の小カテゴリに分類し数値化します。コンピテンシーモデルは次の3タイプから作成するのが一般的です。
- 実在型モデル:社内のハイパフォーマーをモデルにする
- 理想型モデル:企業が求める理想の社員を作成しモデルにする
- ハイブリッド型モデル:実在型モデルと理想型モデルを組み合わせる
なお、コンピテンシーモデルの作成は専門性が高く難しいため、専門家に依頼してもよいでしょう。
7-3. 社員自身で行動目標を設定する
コンピテンシーモデルの作成が終わったら、社員自身の業務上の行動目標を設定させましょう。なお、この段階ではコンピテンシーそのものの数値を取り入れたり、上司が目標を設定したりするのではなく、あくまでも社員自身で設定する点がポイントです。目標を押し付けるのではなく、自身で設定することで、達成意欲の向上も期待できます。
7-4. 評価方法と評価のタイミングを決定する
コンピテンシーアセスメントでは、コンピテンシーモデルと比較して、評価を実施します。評価のタイミングは長すぎず短すぎない範囲で、適宜おこないましょう。また、社員自身がコンピテンシーモデルと比較するだけでなく、多角的な評価視点を取り入れることも大切です。目標が未達成だった場合は、その目標を達成するために必要な行動を明確にし、今後の課題を設定しましょう。
とはいえ、そもそも適切な人事評価制度を現状構築できておらず、これから検討しようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。人事評価制度を構築すると言っても何から手をつければ良いか分からない方へ向けて、本サイトでは「人事評価の手引き」を無料で配布しています。自社にとって適切な人事評価制度を検討するために、まずは人事評価制度について網羅的に理解したいという方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
8. コンピテンシーアセスメントの活用例

コンピテンシーアセスメントは、評価基準または、行動基準として活用するのが一般的です。ここでは、コンピテンシーアセスメントの具体的な活用例を紹介します。
8-1. 人事や採用の評価基準に活用する
人事評価や採用基準など、評価基準としてコンピテンシーアセスメントを活用する場合は、コンピテンシーモデルとどの程度同じ行動を取れているかを確認しましょう。とくに、人事評価ではコミュニケーション能力のように全社員共通して必要なものと、社員一人ひとりに必要なものに分けて設定するのがポイントです。
8-2. 人材育成の行動基準に活用する
人材育成にコンピテンシーアセスメントを用いる場合は、コンピテンシーモデルを行動基準として設定してみましょう。たとえば、コンピテンシーの基準には「グループ内のコミュニケーションに積極的に参加する」のように、具体的な行動を設けます。従業員がコンピテンシーの行動を真似ることで、生産性の向上や組織の成長が期待できます。
9. コンピテンシーアセスメントで効果的なタレントマネジメントを実現しよう

コンピテンシーアセスメントでは、コンピテンシーモデルとの比較により、社員本来の能力を把握することができます。また、不足している行動特性を身に付けられるようサポートし、人材育成に役立てることもできます。コンピテンシーアセスメントを上手く活用して、効果的なタレントマネジメントを実現しましょう。
企業として人事データを適切に管理することはとても重要ですが、
そもそもなぜ人事情報の管理が必要であり、その先に大きな活用価値があることについても、正しく理解できていますか?人事情報は、適切な人材配置、従業員のモチベーションの管理、公平な評価制度など、企業として健全な経営をおこなう上で欠かせない情報です。
当サイトでは、人事データの必要性や活用価値をわかりやすく解説した資料を無料配布しています。
「人事情報を取り扱う上での基本や管理方法が知りたい」「人事データを用いた今後の活用例が知りたい」という人事担当者の方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。