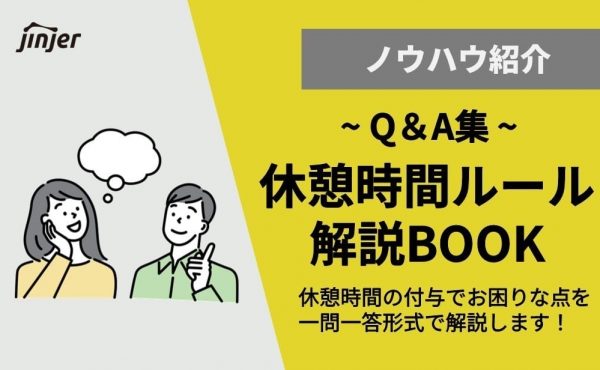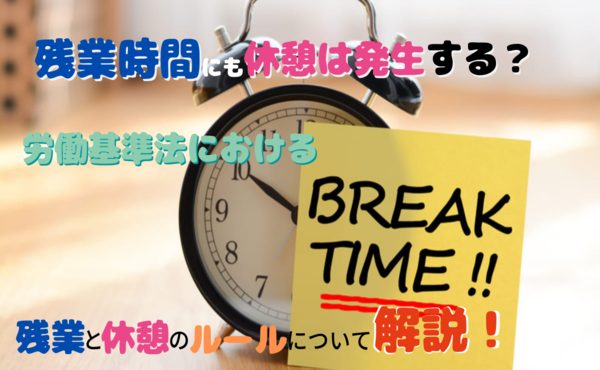
休憩時間とは、従業員が一定の時間を超えて労働をおこなった場合に付与されます。では、従業員が残業した場合でも、休憩時間は付与されるのでしょうか。
本記事では、労働基準法で定められた残業や休憩時間に関する規則について解説します。
関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!
休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 労働基準法で定められた休憩時間のルールとは?

ここでは、労働基準法によって定められた休憩時間の付与ルールについて解説します。
休憩時間に関する基準は3種類あります。以下の項目では、労働時間に応じて、どれくらいの休憩時間が発生するのかを解説しているので、ぜひ確認しておきましょう。
関連記事:労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説!
1-1. 労働時間が6時間以下の場合
労働時間が「6時間以下」の場合、法律上、休憩時間を付与する必要はありません。そのため、労働時間が6時間ちょうどだった場合でも、休憩時間は発生しないことになります。もちろん、会社独自のルールを設定して、休憩を付与することも可能です。
関連記事:6時間勤務の休憩時間を労働基準法に基づき解説!8時間や15時間の場合も紹介!
1-2. 労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合
労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合、少なくとも45分の休憩時間を付与する必要があります。6時間から1分でも超えると、休憩の付与義務が発生するため注意が必要です。休憩時間については、労働基準法第34条に明記されています。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
「少なくとも45分」なので、従業員に45分を超えて1時間の休憩時間を付与していても違法ではありません。
1-3. 労働時間が8時間を超える場合
労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を付与する必要があります。「少なくとも1時間」であるため、従業員に1時間を超えて2時間の休憩時間を付与していても違法ではありません。
また、労働基準法に明記されている休憩時間の付与ルールは「労働時間が8時間を超える場合」までです。そのため、1日12時間働いた場合であっても、休憩時間を1時間与えていれば法律違反とはなりません。ただ、長時間労働は従業員の心身に悪影響を及ぼす恐れがあるので、厳正に管理することが必要です。
関連記事:労働時間短縮に効果的な取り組みとは?メリット・デメリットや助成金制度を紹介
2. 休憩時間を付与する際の3原則

前項では、休憩時間の付与義務が発生する基準や、付与しなければならない休憩時間の長さについて解説しました。ここでは、従業員に休憩時間を付与する際の3原則について解説します。
休憩時間の長さと同様、労働基準法によって定められたルールであるため、しっかりと理解しておきましょう。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
2-1. 途中付与の原則
最初に紹介するのは「途中付与の原則」です。これは「休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならない」という原則です。終業時間の1時間前に1時間の休憩を与えることは労働基準法違反となります。
2-2. 一斉付与の原則
次に紹介するのは「一斉付与の原則」です。これは「休憩時間は従業員に一斉に付与しなくてはならない」という原則です。本来、休憩時間を交代制で付与するのは認められていません。ただし、以下の業種・業界では適用されません。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
また、上記以外の業界であっても、労使協定であらかじめ休憩の取り方について決めている場合、「休憩一斉付与の原則」は適用除外となります。
2-3. 自由利用の原則
最後に紹介するのは「自由利用の原則」です。これは「休憩時間中は労働から完全に自由でなくてはならない」という原則です。休憩時間中にもかかわらず、従業員が電話対応をおこなったり、商品の陳列を手伝ったりするのは労働基準法違反となります。
ここまで、休憩時間を付与する際の3原則について解説しました。休憩時間には発生する基準や付与するための規則など、決まりごとが多いので注意が必要です。
3. 残業で労働時間8時間を超えた場合、別途休憩時間を付与すべき?

残業時間は労働時間に含まれるため、残業時間が加わることによって休憩時間が変動するケースもあります。以下、2つのパターンに分けて解説します。
3-1. 残業時に別途休憩時間を付与しなくてよいケース
すでに従業員に1時間の休憩時間を与えていた場合、残業によって労働時間が8時間を超えたとしても別途休憩時間を付与する必要はありません。
ただし、休憩なしで働き続けると生産性が低下したり、ミスが起こりやすくなったりします。従業員の健康を守るためにも、休憩時間を追加で付与するようなルールを検討することが重要です。
3-2. 残業時に別途休憩時間を付与すべきケース
従業員に45分間の休憩時間を与えているという状況で、残業により労働時間が8時間を超えた場合、1時間の休憩時間が必要になるため、別途、少なくとも15分間の休憩時間を与えなければなりません。具体例は以下の通りです。
例)勤務時間が9時半~17時半の従業員が1時間の残業をおこなった場合
元々、勤務時間が9時半〜17時半なので、所定労働時間は7時間15分で休憩は45分必要です。1時間の残業がおこなわれた場合、合計の所定労働時間が8時間15分となり、休憩時間は少なくとも1時間付与する必要が出てきます。すでに45分付与しているので、別途で15分の休憩を付与する必要があります。
関連記事:休憩時間が取れなかった場合に生じる問題とは?必要な対応をわかりやすく紹介
3-3. 深夜残業における休憩時間は?
労働基準法には、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、労働時間の途中で与える必要があることが明記されています。
しかし、日中と深夜、または通常の労働時間と残業を区別した休憩時間は定められていません。そのため、残業によって労働時間が8時間を超える場合、1時間の休憩を付与すれば法的には問題ありません。
ただし、長時間の残業は好ましいものではないので、体調やパフォーマンスを考慮して、適宜休憩を付与したほうがよいでしょう。長時間の残業が発生しないような労働環境を整備していくことも重要です。
4. 残業に対して適切な休憩時間を付与しないときのリスク

残業に対して適切な休憩時間を与えない場合、法律違反として罰則を受ける可能性があります。ここでは、休憩時間を付与しない場合のリスクについて解説します。
4-1. 法律違反となり罰則を受ける
労働時間に応じた休憩時間を付与することは、労働基準法によって定められた義務です。この義務を無視して休憩時間を適切に付与しないと、同法に従って30万円以下の罰金、または6ヵ月以下の懲役が科せられる可能性もあるため注意しましょう。
また、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、社会的なイメージが悪化したりするケースもあるため、しっかりと対応することが重要です。
4-2. 従業員の心身の健康を維持できなくなる
残業に対して適切な休憩時間を付与しないと、従業員の心身の健康状態が悪化する可能性もあります。長時間労働が常態化することでモチベーションが低下したり、病気になって休職したりするケースもあるかもしれません。
仮に従業員が休職や離職をしてしまうと、残った従業員の負担が増えてしまいます。その結果、健康状態が悪化する従業員が連鎖的に増えてしまう可能性もあるでしょう。事業を継続的に展開していくためにも、適度な休憩を付与することで従業員の健康を守り、働きやすい環境を構築することが重要です。
5. 休憩時間を適切に付与するための対応

ここからは、休憩時間を適切に付与するための対応について解説します。
5-1. 雇用形態にかかわらず休憩は付与する
休憩時間の発生や付与に関する規則は、労働基準法によって定められたものです。労働基準法は雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されます。そのため、パートやアルバイト、契約社員に対しても休憩時間を付与しなければなりません。
従業員に休憩時間を付与することは企業の義務です。仮に「早く帰りたいので休憩はいらない」という従業員がいたとしても、法律違反になってしまうので、正しく休憩時間を取得させる必要があります。
5-2. 就業形態にかかわらず休憩は付与する
就業形態が時短勤務や裁量労働制であっても、労働基準法に基づいて休憩時間を付与する必要があります。
6時間を超えない時短勤務の場合、休憩時間は必須ではありません。しかし、1分でも残業が発生すると労働基準法違反となってしまうため、休憩時間を付与するケースが大半です。
みなし労働時間が6時間を超える裁量労働制においても、同様に休憩時間を付与しましょう。労働基準法に則り、休憩時間を付与することが重要です。
5-3. 休憩時間には仕事をさせないようにする
前述の通り、休憩時間中は労働から完全に離れ、自由な状態でなければなりません。たとえば、ランチを食べながら自席で電話番をさせる、来客に備えて待機させる、といった場合、休憩時間ではなく労働時間としてカウントされます。
簡単な作業であっても労働であるとみなされるため、休憩時間には仕事をさせないようにしましょう。
5-4. 休憩を取れなかったときは時間をずらして付与する
急な対応などで規定の時間に休憩時間を付与できなかった際は、時間をずらして付与しましょう。
たとえば、12時から13時までが休憩時間の従業員が、12時30分まで休憩を取れなかった場合、休憩時間の終了は13時ではなく13時30分とし、柔軟に対応することが大切です。
5-5. 休憩時間は分割して付与してもよい
業種や業界によっては、まとまった休憩時間を取れないケースもあります。そのような場合は、休憩時間を分割して付与することが可能です。たとえば、労働時間が8時間を超えており、1時間の休憩を取る場合、1時間の休憩を「30分×2」として、分割して付与することが可能です。
ここまで、休憩時間を付与するときのポイントについて紹介しました。このように、休憩時間の付与方法やルールは細かく定義されています。ルールをしっかりと守らないと違法になる可能性もあるため、自社の設けている休憩時間が適切なのかしっかりと確認しましょう。当サイトでは、休憩時間の付与に関してよくある疑問について解説した資料を無料で配布しております。休憩時間を正しく取得させられているか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。
6. 残業と休憩時間に関する規則を理解し、従業員が健康的に働ける職場づくりを!

本記事では、休憩時間に関する基準や原則、残業時間と休憩の関係について解説しました。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を付与しなければなりません。また、休憩時間に電話番などの仕事を命じることは避け、自由に利用させることが大切です。
残業時間や休憩時間について理解を深めることは、知らず知らずのうちに労働基準法違反となるリスクをなくすだけでなく、従業員が健康的に働ける職場を作ることにもつながります。正しく休憩時間を付与し、労働基準法を遵守した職場づくりに努めましょう。
休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。
「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。