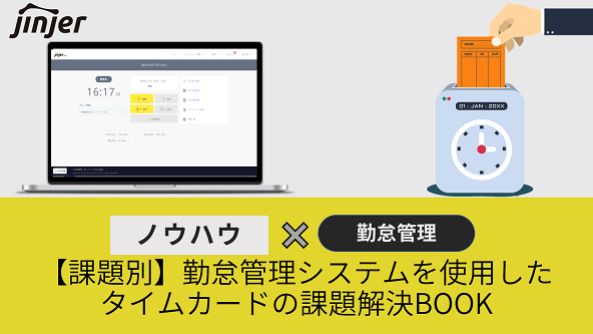勤怠管理を効率よく進めるためには、タイムカードやICカードを活用することが大切です。ただし、一見タイムカードとICカードは同じようなものだと思えますが、実はまったく違う特徴があります。
勤怠管理を効率よく進めるためには、タイムカードやICカードを活用することが大切です。ただし、一見タイムカードとICカードは同じようなものだと思えますが、実はまったく違う特徴があります。
この記事では、勤怠管理におけるタイムカードとICカードの違いや、ICカードによる勤怠管理のメリット・デメリットを紹介していきます。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードとICカードの勤怠管理の違いとは?

まずはタイムカードとICカードの大きな違いを確認しておきましょう。
1-1. タイムカードによる勤怠管理
タイムカードでの勤怠管理とは、タイムレコーダーに紙を差し込んで打刻し、従業員の出勤・退勤時間などを管理する方法です。締め日に従業員のタイムカードを回収して、各従業員の月ごとの勤務時間を担当者が集計し、給与計算をおこないます。
手軽に利用できますが、従業員数が多くなると回収や集計の手間がかかり、担当者の負担が増えるでしょう。
1-2. ICカードによる勤怠管理
ICカードでの勤怠管理とは、ICカード内に内蔵されている従業員の個人情報をもとにして、専用のスキャナーで読み込み、従業員の出勤・退勤時間を管理する方法です。
給与計算の際には、機械に集約されているデータを勤怠の締め日に出力して給与計算をおこないます。
タイムカードとICカードは従業員がそれぞれ備え付けの機械に対して打刻をおこなうため、混同されがちですが、実は全く機能が異なります。
関連記事:タイムカードとは?仕組みや使い方、メリット・デメリットを徹底解説
2. ICカードの勤怠管理に適している企業
 前章では、タイムカードとICカードによる勤怠管理の違いについて解説しました。
前章では、タイムカードとICカードによる勤怠管理の違いについて解説しました。
ここからは、ICカードを使った勤怠管理に適している企業について紹介していきます。
2-1. 勤怠管理を簡略化したい企業
勤怠管理を簡略化したい企業は、ICカードで従業員の勤怠情報を管理することをおすすめします。なぜならICカードでは、専用のスキャナーにカードをかざすだけで打刻できるうえに、タイムカードよりも打刻のミスが起こりにくいといった特徴があるからです。
タイムカードは機械にカードを入れ込んで刻印する仕組みのため、カードの差し込み位置がずれたり、印字がかすんだりして、正確な打刻日時がわからず、従業員に確認する手間が発生する可能性があります。確認作業が生じると作業が滞るため、給与計算作業に必要以上に時間がかかってしまいます。
スムーズに就業時間を把握したい場合は、ICカードが適しているといえるでしょう。
2-2. コスト削減を図りたい企業
勤怠管理にかかるコストを削減したい企業にも、ICカードを利用した勤怠管理は適しています。
なぜなら、ICカードを利用した勤怠管理の方法であれば、低単価のICカードの専用スキャナーを購入し、ICカード自体も比較的低単価のものが多いためです。
タイムカードの場合は、毎月従業員の人数分のカードが毎月必要になります。長期的に見ると固定費がかさむ可能性があります。
2-3. 会社全体で1つのデバイスを共有している
従業員が一定数いて、1つのデバイスを共有して利用している企業もICカードの勤怠管理に向いています。
ICカードをかざすだけで打刻ができるので、もし従業員の出勤が重なる時間帯でも、「デバイスの周りが混んでいて打刻を後回しにし、そのまま打刻しそびれてしまう」といったリスクも少なくなります。
2-4. 交通系ICカードの利用率が高い企業
交通系ICカードの利用率が高い企業は、ICカードによる勤怠管理をおこなうのがおすすめです。従業員が普段利用しているICカードを、そのまま勤怠管理に活用できます。新たに専用のカードを準備する必要がないため、導入コストを抑えられるでしょう。
また、普段持ち歩いているICカードであれば忘れることも少なく、打刻漏れを防止することも可能です。
3. ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法
 ここからは実際に、ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法について解説していきます。
ここからは実際に、ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法について解説していきます。
3-1. 各ICカード専用のスキャナーを使用する
ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法1つ目は、「専用スキャナーを使用する」です。専用スキャナーを出入り口に設置しておくことで、従業員の打刻漏れを防ぐことができます。
3-2. 従業員共有のタブレットなどをICカードスキャンに適用する
ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法2つ目は、「従業員共有のタブレットなどをICカードに適応する」です。
ICカードをタブレットにかざすと打刻が完了するので、タイムカードのように出退勤時刻を読み込む時間をなくすことができます。
3-3. ICカードの種類
ICカードは、FeliCa規格とMIFARE規格の2つに大きく分類できます。FeliCa規格は、日本で広く利用されている非接触型のICカードの規格です。PASMOやSuicaなど、一般的な交通系ICカードはFeliCa規格に分類されます。
MIFARE規格は、国際的に利用されている規格です。国内ではtaspoなどが採用しています。価格が安いため導入しやすく、社員証や学生証として広く活用されています。
どちらの規格でも勤怠管理をおこなうことは可能ですが、カードに対応したカードリーダーを導入しなければなりません。事前にどの規格のICカードを利用するかを決定し、対応したカードリーダーを選びましょう。
4. ICカードによる勤怠管理のメリット
 前章では、ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法について解説しました。
前章では、ICカードで従業員の勤怠情報を読み取る方法について解説しました。
ここからは、 ICカードによる勤怠管理のメリットについて紹介していきます。
4-1. 勤怠情報の管理が簡単
ICカードによる打刻では、従業員の労働時間がリアルタイムで計算され、月末に発生する集計業務の手間を省くことができます。従業員の労働時間を正確に把握することができ、過重労働を事前に避けることも可能です。
知らないうちに労働時間の上限を超過することを防止でき、法律を遵守しながら働いてもらうことができます。
関連記事:効率的なタイムカードの集計方法とは|人事・経理から個人管理まで
4-2. 不正打刻を防止できる
タイムカードは共有スペースに置かれているため、誰でも持ち去ることが可能ですが、ICカードは基本的に本人が所持し管理しています。
そのため、ICカードによる勤怠管理では、第三者が代わりに打刻するといった行為を防止することができます。
関連記事:タイムカードの改ざんは違法!不正打刻や改ざんを防ぐ方法をご紹介
4-3. 費用を抑えることができる
従業員がすでに持っているICカードを会社の勤怠管理に活用することで、導入コストを抑えることができます。
また、ICカードをかざす際の専用スキャナーやデバイスは買い切りのことが多いため、システム導入した際にかかる運用コストなどが発生しません。
4-4. 打刻のハードルが低い
ICカードによる打刻は、カードをかざすだけで打刻できるといった点が多くの人に浸透しており、導入するにあたっても従業員から受け入れられやすいでしょう。
また、従業員がすでにICカードを持っている場合、ICカードに従業員の識別番号を登録し、専用のスキャナーを購入するだけなので、システムよりも比較的簡単に導入することができます。
4-5. かざすだけなので教育コストがかからない
ICカードによる打刻は、電車に乗るときに改札でICカードをかざす対応と同じです。
ほとんどの従業員が経験済みの対応であるため、ICカードによる打刻の教育コストをかけなくて済みます。
ここまでICカードでの打刻のメリットをお伝えしましたが、「打刻が便利になるのはわかるけど、そのあとの集計まではどのように行われるの?」とICカード打刻による勤怠管理のイメージがつかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、ICカードで打刻ができる勤怠管理システムではどのように労働時間の集計まで行われるのかを、わかりやすく解説した資料を無料で配布しております。
「ICカード打刻が便利なのはわかったので、実際にどのような勤怠管理になるか知りたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
5. ICカードによる勤怠管理のデメリット
 ここからは反対に、ICカードによる勤怠管理のデメリットについて紹介していきます。
ここからは反対に、ICカードによる勤怠管理のデメリットについて紹介していきます。
5-1. 従業員がICカードを紛失する可能性がある
ICカードは個人で管理することになるため、タイムカードとは異なり、紛失してしまうリスクがあります。紛失が発生すると打刻できなくなるため、他の方法で出退勤時刻を記録しつつ、早急に再発行しなければなりません。
ただ、ICカードの再発行には時間がかかってしまうため、従業員が紛失することのないように対策を考えておきましょう。
5-2. 従業員による打刻忘れのリスクがある
ICカードによる勤怠管理は、タイムカードと同様、打刻忘れが発生する可能性があります。
そのため、従業員間で打刻の確認をおこなう、ポスターで打刻の重要性を周知するなど、打刻忘れを防ぐための対策を取るようにしましょう。
関連記事:タイムカードの打刻ミスがあった場合の対処法|打刻漏れを防ぐ方法についても紹介!
5-3. ICカードをかざすスキャナーの導入コストがかかる
ICカードによる勤怠管理では、どうしても最初にICカードをかざすためのスキャナーが必要になるため、初期コストがかかってしまいます。
とはいえ、勤怠管理で発生するコストは必要不可欠なものなので、費用対効果を踏まえて適切なツールを導入することは重要です。
関連記事:タイムカード打刻のメリットより時代はペーパーレスの勤怠管理システム
5-4. リモートワークに対応しにくい
リモートワークに対応しにくいことも、ICカードによる勤怠管理のデメリットです。会社に設置してあるスキャナーでICカードを読み取る必要があるため、在宅勤務の従業員や直行直帰する従業員は、打刻することができません。
多様な働き方に対応したい場合は、どこにいても打刻できる勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。
5-5. セキュリティ強化が必要になる
ICカードによる勤怠管理を導入するなら、セキュリティ強化が必要です。ICカードのなかには、さまざまな個人情報や機密情報が入っています。
情報漏洩が発生すると、従業員に迷惑がかかるだけではなく、企業の社会的なイメージ悪化にもつながります。重要な情報が漏洩しないよう、セキュリティ対策を徹底しておきましょう。
6. ICカードを使った打刻システムを選ぶ際のポイント
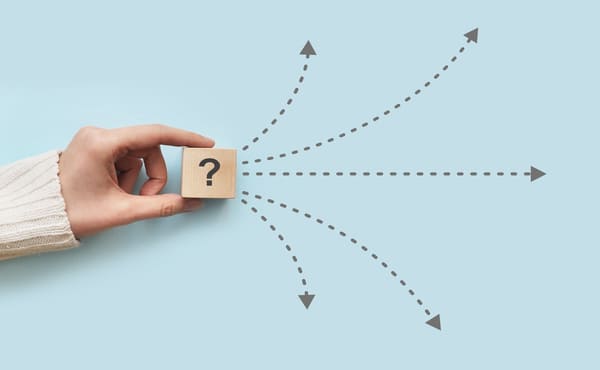
ICカードでの打刻のメリットを最大化するためにも、自社の運用に合った打刻機を選定することが大切です。打刻システムを選ぶ際には以下のポイントを比較すると良いでしょう。
6-1. セキュリティ対策が充実しているか
万が一ICカードを紛失した際、個人情報が流出するリスクがあります。また、ICカードの打刻システムには、交通系ICカ―ドやクレジット機能付きカードを使用できるものもあります。紛失した際に情報が漏洩しないものを選びましょう。
また、従業員の勤怠データは5年間保有していなければなりません。データが破壊されてしまうとこの保管義務を果たすことができなくなってしまうため、セキュリティ対策が万全なシステムであるか導入前に確認しましょう。パスワードなどでデータを管理するシステムや、プライバシーマークやISO27001取得しているシステムを選ぶと安心です。
6-2. 費用対効果が適切か
ICカードでの打刻機は、1台あたり10万円から20万円程度のものが一般的です。多くの従業員が在籍していたり、勤務場所が分かれていたりする場合には打刻機が複数必要になります。
ICカードの打刻システムには、パソコンと接続することでパソコンを打刻機代わりに利用できるものもあり、このタイプのカードリーダーは5,000円程度であることが一般的です。
自社の労働環境とシステムの費用対効果が適切か検討し、打刻デバイスを選択すると良いでしょう。
6-3. 法改正に対応できるか
法改正に対応できるかどうかも重要なチェックポイントです。勤怠管理に関する法律は随時改正されているため、企業はしっかりと対応しなければなりません。
ICカードを利用した打刻システムのなかには、法改正に合わせて自動でアップデートされるものもあります。社内で設定を変更する手間を省けるため、うまく活用するとよいでしょう。
6-4. 他のシステムと連携できるか
他のシステムと連携できるかどうかも確認しておきましょう。たとえば、給与管理システムと連携できれば、勤怠情報を自動で共有し、従業員ごとの給与を算出することが可能です。
手作業で勤怠データを移行する手間を省きつつ、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止できるため、連携性については事前に確認しておく必要があります。
6-5. 自社で使いたいICカードに対応しているか
システム指定のICカードではなく、個人が所有している交通系ICカードや電子マネーのICカード、自社の社員証など、さまざまなカードでの打刻に対応しているシステムがあります。
もし、自社の社員証を打刻にも使用したいと考えている場合には、FeliCa規格、MIFARE規格など、対応カードと使用したいカードの規格が一致しているか確認しましょう。
6-6. 導入のサポート体制があるか
導入後、打刻の操作や打刻データの出力などに不具合が発生した場合にすぐに確認できるサポート体制があるかも検討する際の比較ポイントです。
先述の通り、打刻の記録は適切に保管しなければなりません。もし機械の不具合で打刻データが取得できない事態が発生すると、罰則を受ける可能性があります。
速やかに問題を解消できる体制が整っているシステムを選定すると安心です。
7. 勤怠管理をタイムカードからICカードに切り替えて業務効率を上げていこう
 本記事では、タイムカードとICカードによる勤怠管理の違いや、ICカードによる勤怠管理のメリット・デメリットなどについて詳しく紹介しました。ICカードによる勤怠管理を導入すれば、勤怠データを効率よく管理でき、不正打刻を防止できます。
本記事では、タイムカードとICカードによる勤怠管理の違いや、ICカードによる勤怠管理のメリット・デメリットなどについて詳しく紹介しました。ICカードによる勤怠管理を導入すれば、勤怠データを効率よく管理でき、不正打刻を防止できます。
ICカードを使った打刻システムを選ぶ際は、「サポート体制が整っているか」や「安全性が整っているか」に注意するとよいでしょう。また、ICカードを活用した勤怠管理は、タイムカードよりも従業員の労働時間の集計が簡単です。不正打刻を防ぎたい、業務効率を上げたい企業には、ICカードでの打刻がおすすめです。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正を行えるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。