
会社側が退職手続きをスムーズに進めるためには、退職の申し出を受けてから退職するまでの業務フローや必要になる書類を頭に入れておく必要があります。本記事では、会社側がすべき退職手続きの流れをわかりやすく解説します。また、従業員から返却してもらうものや退職時に退職者に渡すものなどのチェックリストも紹介します。
目次
1. 会社側がすべき退職手続きの流れ
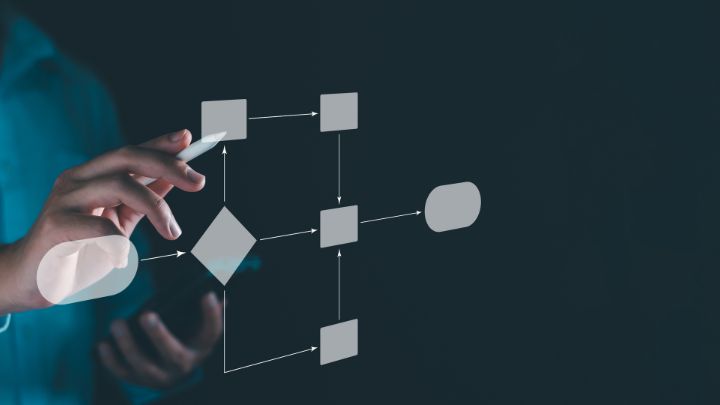
ここでは、退職の申し出を受けてから従業員が退職した後までで、どのような業務が必要になるのか、時系列で具体的な業務の流れを紹介します。
1-1. 退職の意思表示を受ける(1〜3ヶ月前)
退職手続きは、原則として、労働者から退職の意思表示を受けてから開始します。民法第627条に則り、無期雇用労働者の場合、退職の申し出から2週間を経過することで、労働契約は終了します。一方、有期雇用労働者の場合、やむを得ない事情がない限り、契約期間の途中で退職することができません。しかし、労働基準法第137条に則り、契約初日から1年を経過した日以降、使用者に申し出て即日に退職することも可能です。
このように、法律で定められている退職のルールは複雑です。会社側としては後任者の調整や業務の引き継ぎなどがあるため、急に退職されては業務に支障が出てしまいます。1~3カ月前までに退職の意思表示を申し出るようにするなど、事前に就業規則や個別の雇用契約書に退職に関するルールを明記し、従業員に周知しておくことで、トラブルを防止することができます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(省略)
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
1-2. 退職届の提出・業務の引継ぎ(1ヶ月~2週間前)
具体的な退職日が決まったら、労使間のトラブルを回避するという意味でも、退職届を提出してもらいましょう。この際に退職理由が、自己都合あるいは会社都合なのかを確認しておきます。退職理由は、基本手当(失業手当)の支給日数や退職金の支払いなどに関係するため、忘れずに必ずチェックしましょう。また、退職手続きに必要な書類、貸与品の返却など退職に必要な手続きについての説明もおこないます。
退職者が受け持っていた業務の後任者が決まっている場合は、事前に退職の業務の引き継ぎをおこなってもらいましょう。後任者が見つからない場合には、業務の引き継ぎ資料を作成してもらい、後任者が決まってからスムーズに引き継ぎがおこなえるよう準備しておきます。また、営業職など取引先に挨拶が必要な場合は、具体的にいつまでに挨拶回りを済ませておくか指示を出しておきましょう。
1-3. 社内挨拶・必要書類を渡す・備品返却等(退職日当日)
退職当日は、社内への挨拶回りや貸与品の返却をしてもらいます。従業員から年金手帳(基礎年金番号通知書)や雇用保険被保険者証を預かり会社で保管している場合は、退職日に返却します。このような書類は、転職先での手続きや、国民年金保険の手続きなどに必要なため、忘れずに返却することが大切です。
1-4. 社会保険と税金の手続きをする(退職後)
従業員が退職した後、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届を提出する必要があります。また、給与や退職金を確定させて、源泉徴収票を送付する必要もあります。社会保険や税金の手続きは、期限が決まっているので速やかに対応しなければなりません。
2. 従業員からの返却物チェックリスト

退職手続きでは、会社が支給しているものを返却してもらう必要もあります。また、退職する際に従業員から会社に提出してもらう書類もあります。従業員からの返却・提出物のチェックリストは、次の通りです。
- 健康保険証(資格確認書)
- 貸与品(社員証や制服・作業着、名刺、パソコン・スマートフォン、鍵など)
- 業務上作成した書類やデータ
- 退職所得の受給に関する申告書
ここでは、従業員から返却・提出してもらう書類についてそれぞれ紹介します。
2-1. 健康保険証(資格確認書)
健康保険は、退職の翌日に資格喪失します。そのため、退職日に健康保険証(資格確認書)を返却してもらうのが一般的です。扶養家族がいる場合、扶養家族分の健康保険証(資格確認書)も忘れずに回収する必要があります。
たとえ退職者が健康保険を任意継続する場合であっても、手続き後に新しい健康保険証(資格確認書)が交付されるので、退職前に交付されている健康保険証(資格確認書)を回収しなくてはいけません。また、高齢受給者証や健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額認定証などが交付されている場合もあわせて回収しましょう。
2-2. 貸与品
貸与品には、身分証明書(社員証やカードキー、社章など)や名刺、制服・作業着、携帯電話、パソコン、スマートフォン、鍵など、会社によって異なります。通勤定期券がある場合は、退職日までに精算を済ませてから返却してもらいましょう。このように、会社が所有者である貸与物は、退職前に返却してもらうことが大切です。
2-3. 業務上作成した書類やデータ
企画書や報告書類など、従業員が業務上作成した資料やデータ類は機密情報に該当する場合もあります。外部に漏洩しないよう全て回収することが大切です。テレワークなどで働いているため、回収が困難な場合は、退職と同時に破棄してもらうよう伝えましょう。
2-4. 退職所得の受給に関する申告書
退職金制度がある場合、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を交付し、退職金の支払いがおこなわれる前に提出してもらいましょう。退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、退職金に対して一律の税率で源泉徴収がおこなわれるため、退職所得控除を適用できず、税金の納め過ぎになる可能性が高いです。
適切に源泉徴収を実施するため、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらうことが大切です。なお、退職所得の受給に関する申告書の提出忘れがあった場合、納め過ぎた税金の還付を受けるには、自分で確定申告をしてもらわなければならないので、手続きの仕方を伝えてあげましょう。
関連記事:退職金にかかる税金(所得税・住民税)の仕組みや計算方法をわかりやすく解説!
3. 退職時に渡すもののチェックリスト

従業員が退職する際に渡す必要がある書類もあります。退職時に渡すもののチェックリストは、次の通りです。
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 給与所得者異動届出書(退職者が間を空けず転職する場合)
ここでは、退職時に従業員に渡す書類についてそれぞれ紹介します。
3-1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)
年金手帳とは、公的年金制度の加入者一人ひとりに交付されているものであり、基礎年金番号や年金に関する情報が記載されています。転職先でも同じものを使用するため、企業で預かっている場合は必ず返却する必要があります。従業員から原本を回収している場合は、きちんと返却しましょう。
なお、2022年4月から年金手帳は廃止され、それから初めて公的年金に加入する場合、基礎年金番号通知書が発行されます。そのため、年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書の返却が必要なケースもあるので気を付けましょう。
3-2. 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明するために、ハローワーク(公共職業安定所)から発行される書類を指します。雇用保険被保険者証は、転職先で雇用保険に加入したり、失業手当を受給したりするために必要です。従業員本人でなく、会社側が管理していた場合には、必ず退職時に従業員へ返却しましょう。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?発行方法や再発行のやり方、退職日・転職の際の手続きを紹介!
3-3. 退職証明書
退職証明書は、労働基準法第22条に則り、退職者から要求された場合に発行する義務がある書類です。記載内容としては、「雇用期間」「業務内容」「事業における地位」「賃金」「退職理由」などが挙げられます。なお、従業員が希望しない項目は記載してはならないので注意が必要です。
国民健康保険や国民年金保険に加入する場合、健康保険資格喪失証明書や離職票などで手続きできますが、届くまでに時間を要するのであれば、退職証明書でも手続きができることもあります。また、転職先で前職を確かに辞めたことを証明するために必要になることもあります。そのため、退職証明書は、退職者から要求されたら、速やかに交付するようにしましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)
3-4. 給与所得者異動届出書
給与所得者異動届出書は、住民税の手続きに必要な書類です。退職後、すぐに転職が決まっている場合、退職先だけでなく、転職先でも「特別徴収」を継続することができます。ただし、給与所得者異動届出書の必要事項を記載したうえで、転職先に渡し、手続きしてもらう必要があります。そのため、退職する際に退職者に給与所得者異動届出書を交付し、転職先に渡してもらうように伝えましょう。
4. 公的手続きのチェックリスト

従業員が退職した後、会社側は社会保険の資格喪失手続きや、税金の確定手続きをおこなう必要があります。公的手続きのチェックリストは、次の通りです。
- 雇用保険
- 社会保険
- 所得税
- 住民税
ここでは、従業員の退職後に必要になる公的手続きについてそれぞれ紹介します。
4-1. 雇用保険の手続き
退職者が雇用保険に加入していた場合、雇用保険の資格喪失手続きをおこなう必要があります。資格喪失日(退職日の翌日)の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
退職者がすぐに再就職しない場合は、基本手当(失業手当)の手続きをするために離職票が必要となります。そのため、被保険者資格喪失届に、雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添付して提出しましょう。その際、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿、退職願など、退職理由や退職の事実を確認できる書類の提出も必要になります。
なお、雇用保険法施行規則第7条に則り、退職者が離職票の交付を希望しない場合、離職証明書を添付せず手続きしても問題ありません。しかし、退職日に59歳以上である被保険者については、希望に関係なく、必ず離職票を交付しなければならないので注意しましょう。
3 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?入手方法や提出方法を解説!
4-2. 社会保険の手続き
退職した従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していた場合、社会保険の資格喪失手続きも必要です。資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構(年金事務所)に提出しなければなりません。
協会けんぽに加入している事業者は、健康保険と厚生年金保険の手続きを同時におこなうことができます。ただし、健康保険証(資格確認書)の添付が必要なので、忘れずに回収しましょう。一方、組合健保に加入している事業者は、厚生年金保険の資格喪失手続きは、先ほど解説したようにおこなえば問題ありません。なお、添付書類は原則不要です。しかし、健康保険の資格喪失手続きは、自社の加入している健康保険組合によってやり方が異なる可能性もあるので、事前にチェックしておきましょう。
関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の書き方や提出先を解説
4-3. 所得税の手続き
年末まで勤務している人が年末調整の対象になるため、年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象になりません。しかし、次にあてはまる人は、年末調整の対象になります。
- 海外支店に転勤したことなどの理由によって非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職して給与を受け取る可能性のある人を除く)
- 12月に支給されるべき給与を受け取り退職した人
- パートやアルバイトで働く人のうち、その年に受け取る給与の総額が103万円以下である人
このように、年の途中で退職する人でも年末調整の対象になるケースがあります。また、年末調整の対象外になる人には、後日会社から送付する源泉徴収票を基に確定申告が必要になる可能性もあるので、退職する際に通知をしてあげると丁寧な対応といえます。
関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや対象者、やり方や注意点などを徹底解説!
4-4. 住民税の手続き
従業員が退職したら、すぐに再就職する場合を除き、会社が住民税を徴収して納める「特別徴収」から従業員自身で納める「普通徴収」に切り替えをおこなう必要があります。そのため、給与所得者異動届出書を退職した月の翌月10日までに退職者の住所地の市区町村へ提出しなければなりません。
なお、例外的に普通徴収となっている従業員については、会社側の手続きが不要です。また、退職する時期によって、次のように住民税の納付手続きのやり方が変わります。
- 6月1日~12月31日に退職:普通徴収もしくは一括徴収
- 1月1日~4月30日に退職:一括徴収(例外あり)
- 5月1日から5月31日に退職:通常通り納付
1月1日~4月30日に退職する場合、残税額を一括徴収することが原則ですが、最終月の給与などの合計額を超える残税額がある場合、普通徴収への切り替えも認められています。このように、住民税の手続きは複雑なため、手続きのやり方がわからない場合は、最寄りの自治体に相談してみましょう。
5. 退職後に送付するもののチェックリスト

従業員が退職する際に渡す書類だけでなく、退職した後に手続きをしてから送付する書類もあります。退職後に送付するもののチェックリストは、次の通りです。
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書(特定のきまりはなく必要事項が記載されたものを会社で発行)
- 離職票
- 源泉徴収票
ここでは、従業員の退職後に送付する書類についてそれぞれ紹介します。
5-1. 健康保険被保険者資格喪失確認通知書
健康保険被保険者資格喪失確認通知書とは、「健康保険被保険者資格喪失届」を提出すると発行される通知書のことです。退職後に退職者が保険を切り替える際に必要となるため、会社に通知書が到着次第、退職者に速やかに送付するようにしましょう。
5-2. 離職票
退職者が失業手当の給付を受けるには、受給条件を確認するため、離職票をハローワークに提出しなければなりません。離職票は、会社側が雇用保険の資格喪失手続きをおこなった後に発行されます。また、離職票は、退職者にでなく、退職した会社に送付されます。そのため、会社に離職票が届いたら、速やかに退職者に送付しましょう。
5-3. 源泉徴収票
所得税法第226条に則り、従業員が退職した後、給与の支払いを確定させ、給与所得の源泉徴収票を退職後1カ月以内に送付する必要があります。また、退職金を支給する場合、退職所得の源泉徴収票も退職後1カ月に送付しなければならないので注意しましょう。
給与所得の源泉徴収票は、同一年内に退職し、転職する場合に転職先で年末調整を受ける際に必要になります。一方、退職所得の源泉徴収票は年末調整を受ける際に不要です。ただし、確定申告の際に必要になることもあるので、正しく管理するよう退職者に伝えましょう。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6. 特定の従業員が退職する際に必要な手続き・対応について

ここでは、特定の従業員が退職する際に必要な手続き・対応について詳しく紹介します。
6-1. アルバイト・パートの場合の対応
パート・アルバイトなどの非正規の雇用形態の従業員に対しても、基本的な退職手続きのフローは変わりません。ただし、社会保険に未加入、住民税や所得税は非課税といったケースもあるため、従業員の状況を確認して対応しましょう。
6-2. 派遣社員の場合の対応
派遣社員は、雇用契約を派遣元の企業と結んでいます。そのため、派遣社員が退職を願い出た場合、派遣元の企業が退職届を受理し、手続きをおこないます。派遣先の会社側は、直接手続きをおこないませんが、業務の引き継ぎなどの調整が必要です。
6-3. 65歳・70歳以上の高齢者の場合の対応
高齢の従業員に対しても、基本的な退職手続きのフローは変わりません。ただし、再就職をしない場合や、健康保険適用事業所ではない再就職先につく場合、次の選択肢から選び手続きが必要です。
- 国民健康保険への加入
- 任意継続被保険者になり、全国健康保険協会・健康保険組合へ加入する
- 健康保険に加入している身内の被扶養者になる
なお、厚生年金保険においては、退職者が70歳以上である場合、退職翌日から5日以内に企業を管轄している年金事務所へ「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出する必要があります。また、退職者が65歳以上であり、再就職を希望しているほか一定の要件を満たしている場合、「高年齢求職者給付金」を受け取れる可能性があります。「複数の受給要件を満たしているか」「住居地を管轄しているハローワークにて求職を申し込むこと」を退職者に確認し、説明するとよいでしょう。
6-4. 退職者が社内融資を活用していた場合の対応
社内にて融資制度を設けている場合、融資を受けていた退職者には、退職のタイミングで一括返済をしてもらうよう取り決めることが一般的です。まずは本人に返済額や返済期間の確認をおこない、手続きを進めましょう。
6-5. 退職者が財形貯蓄をしていた場合の対応
財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄制度)とは、従業員が毎月の給与から定額で天引きしてお金を積立できる制度のことです。退職者が財形貯蓄をしていた場合、まず転職先にて継続するか否かの意思を確認する必要があります。
もし退職から2年以内に、財形制度のある企業へ再就職した場合、そのまま積立を継続することが可能です。積立を継続しない場合は、解約することになります。また、積立期間中に退職した場合、「退職等不適格事由」に該当するため、一定期間以上経過すると課税対象になってしまいます。そのため、会社側から退職から半年以内に「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」を取扱金融機関へ提出する必要があります。
6-6. 外国人従業員が退職する場合の対応
外国人の従業員に関しても、基本的に退職手続きのフローに変更はありません。ただし、雇用保険に加入していない外国人労働者が退職する場合、翌月の末日までに「外国人雇用状況届出」をハローワークに提出する必要があります。
7. 退職手続きに関してよくある質問

ここでは、退職手続きに関してよくある質問への回答を紹介します。
7-1. 退職手続きが遅れるとどうなるか?
退職手続きに遅れが生じた場合、失業給付の手続きができなかったり、転職先で社会保険に加入できなかったりするなど、退職者に不都合が生じます。また、法律違反によって、罰則が課せられる恐れもあります。退職手続きを期限内に完結できるよう、事前に退職手続きマニュアルやチェックリストを作成しておくことが推奨されます。
7-2. 退職代行・弁護士から連絡を受けた場合の対応は?
退職代行とは、退職者から依頼を受けた業者・弁護士が、本人の代理で退職の申し出やその後の必要な対応を全般的に請け負うサービスです。退職代行から退職の連絡を受けた場合、企業側は原則拒否することができません。
法律の要件をチェックし、どうしても納得ができない場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。また、退職代行から電話を受けた際には、退職手続きを進めなくてはならないので速やかに対応することが大切です。
8. 退職手続きを滞りなく進めるには業務フローの把握が大切!
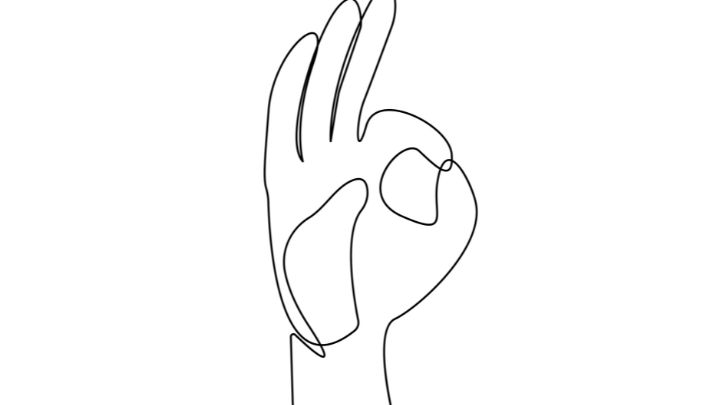
会社側は退職の申し出を受けた時から、退職日や業務の引き継ぎなどを調整し、退職届の提出を求めたり、退職手続きの案内をしたりしなくてはいけません。また、退職後は社会保険や税金の手続きも期限までにおこなう必要があります。余裕を持って退職手続きできるよう、事前に必要な手続きや書類をマニュアルやチェックリストにまとめておくようにしましょう。







