
試用期間とは、従業員を本採用する前に試験的に雇用契約を結ぶ期間のことです。試用期間を設定することで、労働者の仕事に対する適性や能力をチェックすることができます。この記事では、試用期間とは何か、メリット・デメリットや試用期間中の給料・社会保険・退職・解雇に関するルールを踏まえて体系的にわかりやすく解説します。
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 試用期間とは?

試用期間とは、新たに雇用する労働者の適性や能力を見極めるための期間です。実際に業務にあたってもらう中で、採用選考だけでは判断できないポイントについて見極めることを目的としています。ここでは、試用期間と研修期間の違いや、試用期間の最適な長さについて詳しく紹介します。
1-1. 試用期間と研修期間の違い
試用期間と混同しやすい用語に、研修期間があります。研修期間とは、新卒入社や中途入社した労働者に対して、業務遂行のために必要な知識・スキルを教えるための期間のことです。そのため、試用期間と研修期間には、目的の違いがあります。
しかし、試用期間と研修期間を兼ねていたり、試用期間と研修期間を同義として取り扱っていたりするケースもあります。名称だけで判断せず、内容をきちんと確認することが大切です。
1-2. 試用期間の最適な長さは?
試用期間の長さは、法律で明確に定められていないため、会社側の裁量で自由に設定することができます。試用期間の長さは、1カ月~6カ月程度で設定されることが多いようです。
しかし、あくまでも試用期間は、仕事に対する能力や適性を判断するための期間です。1年を超えるような試用期間を設定する場合、民法第90条「公序良俗」に違反し、試用期間が無効になる可能性もあります。試用期間を設ける目的にあわせて、最適な長さに設定しましょう。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。引用:民法第90条|e-Gov
関連記事:試用期間を6カ月設けても問題なし?メリットとデメリットを解説
2. 試用期間を設けるメリット

試用期間を設けることで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、試用期間を設定するメリットについて詳しく紹介します。
2-1. 採用リスクを軽減できる
近年では少子高齢化により人材不足が加速しており、業務量が多く、すぐにでも働いてほしいと考えている企業も少なくないでしょう。しかし、履歴書と面接だけでは、その人の人となりが正しく把握できず、ミスマッチを引き起こすリスクがあります。
試用期間を設ければ、一時的に給料を低く設定したり、解雇予告を不要にできたりするなど、採用リスクを減らして採用することが可能です。これにより、人材の確保がしやすくなります。
2-2. 仕事に対する能力や適性を確認できる
労働者の能力や適性を見極めず、いきなり本採用をすると、適切な人材配置をおこなえず、従業員のモチベーション低下や組織全体の生産性低下を招く恐れがあります。
試用期間を設けることで、じっくり仕事に対する能力や適性をチェックすることが可能です。試用期間後に本採用をし、部署・部門配属をすることで、その人にあった人材配置をおこなうことができます。
2-3. 本採用後よりも解雇がしやすい
試用期間中は、解約権を留保していると考えられ、「三菱樹脂事件」の裁判事例にも記載されているように、本採用後に比べると解雇が認めらやすい傾向にあります。しかし、正当な理由なく解雇するのは違法です。労働条件通知書や雇用契約書に、試用期間における解雇の基準をきちんと明示したうえで、試用期間中であっても慎重に解雇の手続きを取ることが大切です。
右の留保解約権に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、前者については、後者の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきものといわなければならない
引用:昭和43(オ)932 労働契約関係存在確認請求 昭和48年12月12日 最高裁判所大法廷(三菱樹脂事件)|裁判例検索
3. 試用期間を設けるデメリット
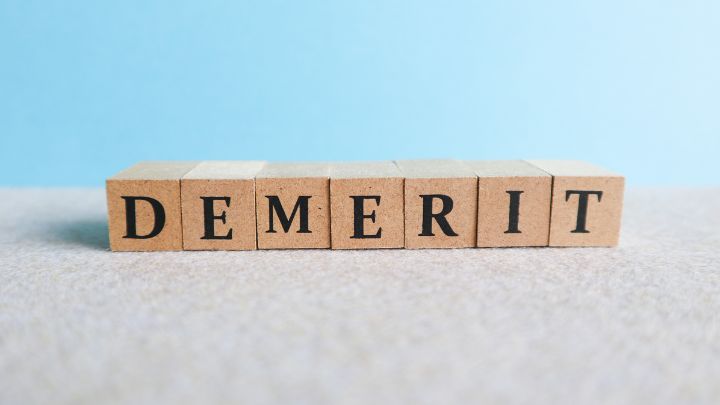
試用期間を設ける場合、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、試用期間を設定するデメリットについて詳しく紹介します。
3-1. 試用期間中と本採用後の労働条件を明示する必要がある
試用期間を設定する場合、試用期間中の労働条件を明確にし、労働者に周知しなければなりません。試用期間中と本採用後の労働条件が異なる場合、雇用条件を明示する負担が大きくなる恐れがあります。試用期間を設ける目的を明確にし、正しく試用期間中の労働条件も明示するようにしましょう。
3-2. 労働者の不満につながる
試用期間中は本採用後よりも、賃金を低く設定することができます。しかし、見た目上は業務適性を判断するとしているが、実質はコスト削減が試用期間の目的となっている場合、試用期間が長いことに対して労働者が不満に思う恐れがあります。
また、試用期間があまりに短く、求められる基準が高い場合、労働者はプレッシャーに感じ、持っている能力を十分に発揮できない可能性もあります。このような事態を招かないよう、試用期間を設ける目的を明確にし、労働者に配慮した試用期間の長さを設定するようにしましょう。
4. 試用期間中の労働条件に関する注意点

ここでは、試用期間中の労働条件に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 労働条件通知書や雇用契約書の交付が必要
本採用後に労働条件を明示すればよいと考えている人もいるかもしれません。しかし、試用期間中も労働者に変わりないため、労働条件通知書や雇用契約書の交付が必要です。労働基準法第15条により、試用期間が始まる前に労働条件通知書を交付しない場合、違法になる可能性もあります。
また、雇用契約書を交わさない場合、労使双方が試用期間中の労働条件に合意したことを記録に残せないため、後に「言った、言わない」などの雇用条件に関するトラブルが発生しやすくなります。そのため、試用期間前に労働条件通知書と雇用契約書の両方を交付するようにしましょう。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)
関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説
4-2. 契約社員やパート・アルバイトにも試用期間を設けられる
試用期間は正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトに対しても設けることができます。長期的に働いてもらうのであれば、試用期間を設けて能力や適性を見極めることは有効的です。ただし、契約社員(有期雇用労働者)やパート・アルバイト(短時間労働者)には、パートタイム労働法に基づき、次の労働条件も事前に明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
このように、試用期間中であっても、雇用形態によって労働条件の明示内容が変わる可能性があるので気を付けましょう。
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
関連記事:アルバイトへの試用期間とは?メリットや注意点・解雇ルールも解説!
5. 試用期間中の給料に関するポイント

試用期間中の給料は一時的に減額することができます。ここでは、試用期間中の給料に関するポイントについて詳しく紹介します。
5-1. 試用期間中の給料は最低賃金を下回ることができる
試用期間中の給料は、最低賃金法第7条により、最大で最低賃金額の20%を減額することができます。ただし、最低賃金の減額の特例を受ける場合、事前に都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。また、この場合の試用期間の長さは、6カ月以内に設定しなければなりません。
試用期間中の給料を低く設定することで、採用リスクを減らすことができます。しかし、労働者の不満につながる可能性もあるので、就業規則や雇用契約書に試用期間中の給料についてきちんと明示し、従業員の同意を得ることが大切です。
(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
(省略)
二 試の使用期間中の者
(省略)
「業種・職種等の実情に照らし必要と認められる期間」ですから、必要最小限度の期間としてください。この期間は、最長でも6箇月としてください。
5-2. 残業代や割増賃金の支給が必要
試用期間中であっても労働者であるので、当該従業員には労働基準法が適用されます。そのため、労働基準法に基づき、残業代や割増賃金も支給しなければなりません。
「試用期間中は残業をしても残業代を支給しない」と個別の雇用契約書に定めても、それは無効になります。また、試用期間中の労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合であっても、事前に36協定の締結・届出をしなければならないので注意が必要です。
5-3. 賞与やボーナスを支給なしにできる
賞与やボーナスは法律で支給が定められたものではありません。そのため、就業規則に定めることで、会社の裁量で自由に支給するか決めることができます。就業規則に「試用期間中の労働者には賞与を支給しない」と定めれば、通常の従業員には賞与を支給し、試用期間中の従業員には賞与を支給しないとすることが可能です。
この考え方は、住宅手当や家族手当などの任意で支給する手当についても、同じように適用することができます。なお、労働契約法第12条により、雇用契約書に「試用期間中は賞与や手当を支給しない」と個別に定めても、就業規則に「すべての従業員に賞与や手当を支給する」と定めている場合、雇用契約書のその部分の労働条件は無効になり、就業規則の定めが優先して適用されるので注意が必要です。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
関連記事:試用期間中の給料設定のルールを徹底解説!最低賃金以下の設定も可能なの?
6. 試用期間中の退職・解雇に関するポイント

試用期間中は退職や解雇のルールが異なるケースもあります。ここでは、試用期間中の退職・解雇に関するポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 試用期間中でも法律に基づく退職ルールがある
「試用期間中に労働者が退職を希望し、そのまま出社しなくなってしまった」など、試用期間中に従業員が会社とのミスマッチを感じ、退職を希望するケースもあるかもしれません。とはいえ、試用期間であっても労働者は会社の一員であるため、突然の退職は認められません。
試用期間中であっても、退職を希望する場合には就業規則や雇用契約書に則った申し出が必要です。期間の定めがある場合や期間の定めがない場合、やむを得ない事情がある場合など、法律における退職のルールは細かく定められています。試用期間中のトラブルを防ぐため、法律に則り、退職手続きについて就業規則や雇用契約書に明記しておくことが大切です。
関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介
6-2. 試用期間中でも解雇予告が必要
試用期間中に解雇する場合も、労働基準法第24条に基づき、30日以上前に解雇予告をおこなう必要があります。30日以上前に解雇予告ができない場合、その不足する日数に応じて解雇予告手当を支給しなければ違法になるので気を付けましょう。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(省略)
②前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。(省略)
6-3. 14日以内の場合は解雇予告手当が不要
労働基準法第21条により、試用期間中で働き始めてから14日以内に解雇する場合、解雇の予告や解雇予告手当の支払いは不要です。ただし、2週間を超えて雇用されることになった場合、通常の労働者と同様で、解雇予告および解雇予告手当の支給が必要になるので注意しましょう。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(省略)第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
(省略)
四 試の使用期間中の者
引用:労働基準法第21条一部抜粋|e-Gov
6-4. 試用期間中の人材において確認しておきたい項目
試用期間中は本採用後よりも解雇がしやすいとはいえ、労働契約法第16条により、解雇をするには相当の理由が必要です。試用期間中の労働者であっても、正当な理由なく解雇をおこなった場合、解雇権の濫用とみなされ、当該解雇が無効になる可能性もあります。
そのため、どのような場合に解雇が可能なのか、あらかじめ整理しておくことが大切です。本採用拒否の判断に相応する特徴として、次のようなものが挙げられます。
- 勤怠不良がないか
- 健康状態に問題がないか
- 職場の規律を順守しているか
- 経歴・スキルを詐称していなかったか
このような特徴に該当していても、会社の教育によって改善される見込みがあれば、解雇は無効になる可能性が高いです。解雇は最終手段として、まずは当該労働者に改善してもらうよう指導をきちんとおこないましょう。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
関連記事:試用期間でも解雇できる?認められる理由・認められない理由を紹介
7. 試用期間中の社会保険に関するポイント

試用期間中の労働者も社会保険の加入が必要です。ここでは、試用期間中の社会保険に関するポイントについて詳しく紹介します。
7-1. 労働条件を確認して社会保険に加入させる
試用期間中であっても、社会保険の加入条件を満たす場合、社会保険に加入させる必要があります。なお、社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の総称をいいます。狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)と雇用保険、労災保険で加入要件は変わってくるので注意が必要です。
社会保険に加入させるかどうかは、労働条件をチェックして決めましょう。試用期間中の給料を低く設定している場合、本採用後に社会保険の加入条件を満たすことになる可能性もあります。加入要件を満たしているのにもかかわらず、社会保険未加入のまま働かせていると、違法になる恐れもあるため注意しましょう。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
7-2. 扶養の要件をチェックする
試用期間中であっても、年収130万円以上になる見込みがある場合、自分で社会保険に加入しなければならず、扶養から外れる必要があります。また、社会保険の加入条件を満たした場合も、会社の社会保険に加入する必要があるので扶養から外れます。
一方、これらに該当しなければ、試用期間中であっても家族の扶養に入れる可能性があります。扶養に入りながら働きたい労働者の希望をヒアリングしたうえで、試用期間中と本採用後の労働条件を決めることが大切です。
関連記事:試用期間中でも社会保険は必須!対象外のケース・未加入のリスクも解説
8. 試用期間に関するよくある質問

ここでは、試用期間に関するよくある質問への回答を紹介します。
8-1. 試用期間の延長は可能?
試用期間中に労働者の能力や適性を十分に見極められなかった、かつ、解雇するには相当の理由がない場合、試用期間の延長を選びたいと考える人もいるかもしれません。試用期間の延長は、就業規則や雇用契約書にその旨や条件を明記し、労働者に周知していた場合であれば可能です。ただし、合理的な理由もなく、試用期間を延長することは違法になる可能性もあるので、試用期間の延長は慎重に判断しましょう。
8-2. 試用期間中の能力不足により本採用拒否できる?
試用期間中の能力不足を根拠に本採用拒否をしたいと考える人もいるかもしれません。試用期間中の能力不足による解雇が認められるには、改善する見込みがなく、本採用後の雇用関係が維持できないほど重大な能力が欠如している場合です。
試用期間中の能力不足による解雇を踏み切る前に、まずは当該労働者にきちんと指導や教育をおこないましょう。また、会社側から退職してもらいたい旨を労働者に伝えて退職を促す「退職勧奨」を検討するのも一つの手です。
9. 試用期間を設ける場合は社内環境の整備に努めよう!

試用期間は単なるお試し期間でなく、本採用を前提として働いてもらう期間です。勤務にあたって大きな問題があるという場合を除き、簡単には解雇できません。試用期間中に不当な解雇をした場合、解雇が無効とされることもあります。トラブルを避けるためにも、試用期間を設ける際には適切に運用できる仕組みを整備することが大切です。
労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。
当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









