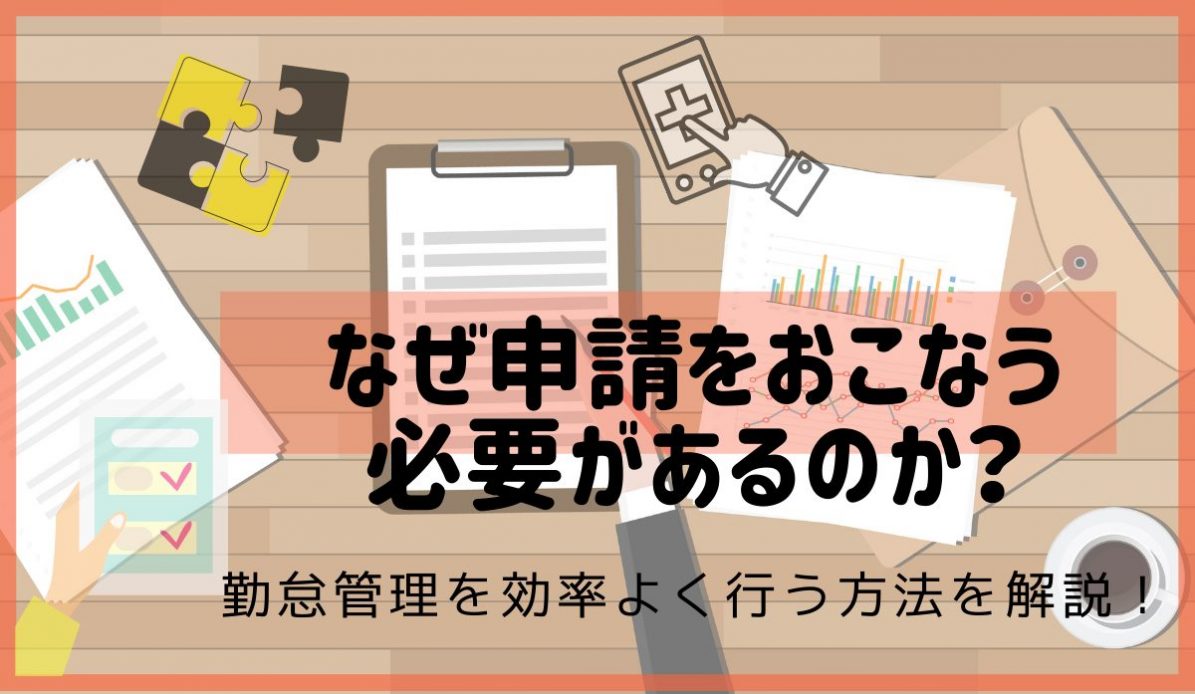
近年、新型コロナウイルス感染防止対策や働き方改革関連法によってテレワークの需要が高まっていますが、その一方で、従業員の勤怠管理に難しさを感じる企業が増えているのではないでしょうか。
従来のように会社に出社するのが当たり前ではなくなり、働く場所や時間も選択できるようになって勤怠管理も複雑になっています。また、2025年の育児・介護休業法の改正でもテレワークの環境整備が入っており、今後ますます適正な勤怠管理が求められるでしょう。
従業員の勤怠を効率よく管理するためにはどうすれば良いのか、今回は、組織管理・労務管理の中でも勤怠申請の効率化について解説していきます。
関連記事:勤怠とは?勤怠管理の目的や具体的な方法、注意点について解説
働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。
しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
目次
1.そもそも勤怠の申請とは
 従業員が勤怠を申請する際の種類(項目)は、主に以下のようなものがあります。
従業員が勤怠を申請する際の種類(項目)は、主に以下のようなものがあります。
- 打刻時間の修正
- 時間外労働
- 遅刻・早退申請
- 深夜労働
- 休暇申請 (有給休暇・慶弔休暇・夏季休暇等)
- 残業・休日出勤申請
- 代休申請
- 振休申請
労働基準法第108条では、従業員が労働した時間のみ賃金台帳に記入するのではなく、時間外労働、深夜労働、休日労働時間など、賃金計算を項目ごとに分けて賃金台帳へ記入しなくてはならないとされています。
従業員に勤怠申請を正しく行ってもらうことで、労働日の始業・終業の時間をただ記録するだけでなく、時間外労働、深夜労働、休日出勤などの全体的な労働時間の把握をすることができるようになります。
参考:労働基準法第108条、厚生労働省労働基準法第36条について
関連記事:勤怠管理でチェックすべき項目4つや管理方法ごとの特徴を紹介
2.勤怠申請を正しくしてもらう必要性

そもそも勤怠管理とは、勤怠管理者(人事担当者)が社員一人一人の労働時間を適正に把握し管理することで、正しい給与計算をするためにおこないます。企業は、勤怠情報から労働基準法に抵触するような労働がないか、従業員が過度の業務で健康状態を悪くしていないか等、把握する必要があります。
特に、2019年の法改正により残業時間の上限規制が設けられたほか、年に10日以上の有給休暇が与えられている労働者は、5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されています。これらを守らなかった場合、会社に罰則が与えられるため、労働基準法の遵守を徹底する必要があります。
そのため、時間外労働や休日出勤、有給休暇の取得日数などの項目について、従業員に申請してもらう勤怠申請は、従業員の労働時間を正確に把握するという点で企業にとって重要な意味を持ちます。
2-1. 働き方改革関連法で義務化もされている!
2019年に、働き方改革関連法の一環として労働安全衛生法が改正となりました。
この改正により、企業による従業員の労働時間の把握が義務化され、方法として「タイムカードによる記憶」「パソコン上の記録」などが必要となりました。
また、勤怠の記録は5年間の保存が義務付けられており、それは仮に退職した従業員であっても適用されます。
当サイトでは、本章で解説した法改正の内容や勤怠管理において、よく起こりうる課題やその解決方法についてまとめた資料を無料で配布しております。
自社の勤怠管理の方法に関して不安な点があるご担当者様は、「働き方改革に対応した勤怠管理対策BOOK」をダウンロードしてご確認ください。
3.勤怠管理に要する勤怠申請書のフォーマットの種類
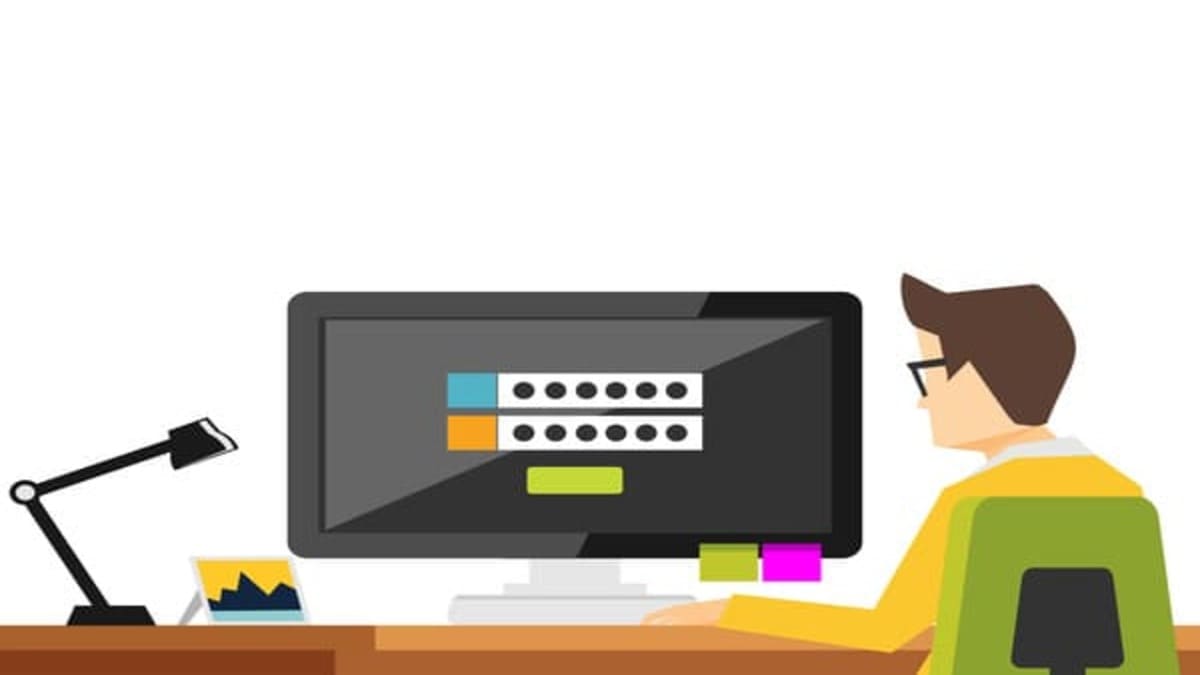 昨今では新型コロナウイルスの感染対策が追い風となり、場所や時間に制限されない働き方が増えてきています。そのため、時代の変化に合わせて、就業規則や勤怠管理の申請書を柔軟に更新する必要があります。
昨今では新型コロナウイルスの感染対策が追い風となり、場所や時間に制限されない働き方が増えてきています。そのため、時代の変化に合わせて、就業規則や勤怠管理の申請書を柔軟に更新する必要があります。
ここでは、勤怠管理を正しく行えるような申請書の種類を解説します。
3-1.勤務時間や出勤日数の申請書
勤務日報や勤務届、勤務変更届等が該当します。
例えば、仕事が多く残業をする際や勤務時間や出勤日数の変更をする際に、勤務時間や出勤日数の申請書を提出する必要があります。
なお、働く日時に柔軟性を持たせている会社においては、フレックス勤務申請書等の会社独自の申請書を設ける等の取り組みも、勤怠管理をする上で重要となります。
3-2.休暇に関する申請書
休暇の種類ごとに申請書のフォーマットを用意する必要があります。
休暇には有給休暇や特別休暇、ボランティア休暇申請書など様々な種類があります。
そのため、普段使用する機会のないような申請書も就業規則に合わせて用意することが重要です。
3-3.特殊な場面で用いられる申請書
育児や介護等で自宅で仕事をした方が時間を有効活用できる従業員もいるでしょう。
そのような従業員は自宅作業許可申請書を使用することで自宅での業務が可能となります。
ただし、労働時間が変化しやすい側面があるため、法定労働時間を超えないように厳密に時間を把握しておくことが大切です。
4.従業員が勤怠の申請をおこなう上で課題となること

このように、従業員の勤怠を正しく把握する上で、従業員側から実際の労働時間についての申請をおこなってもらうことは、非常に重要です。
特に、テレワークによる働き方の変化により、従業員による勤怠の申請はこれまで以上に増えているのではないでしょうか。
しかし、実際に勤怠を申請してもらう上で、従業員側が負担に感じてしまうようであれば、なかなか運用にはうまく乗らないことでしょう。
また、労働時間の把握や保存について法律で定められていることで、勤怠申請を正しく行われないために、人事担当者への負担が大きくなってしまうケースも多くあります。
従業員に勤怠の申請を行ってもらう上で課題となることは、次のようなものがあります。
4-1. 勤怠申請の項目が多く、書類管理の負担が大きい
上で記載したように、従業員が勤怠を申請する際の種類(項目)は、とても多くあります。また、職種によって残業時間なども変わってきます。
そのため、それらを全て紙管理で計算しようとすると、人的作業が増え、ミスが発生してしまいます。
また、紙での管理は、本人も担当者もリアルタイムに正確な残業時間について把握が難しいため、申請を行う以前に残業時間の上限を超えてしまう場合もあります。
このように、各従業員の情報をバラバラな紙で管理することは、人事担当者側としての負担がとても大きくなってしまうことに繋がります。
- 勤務変更届
- 残業申請
- 直行・直帰申請
- 早退・遅刻連絡
といった勤務に関する連絡・申請や、
- 有給休暇取得申請
- 代休取得申請
- 特別休暇申請
- 欠勤申請など
といった休暇に関する申請など、これまで紙での申請を扱っていた企業は、これらの管理における負担を軽減するために、管理方法を検討する必要があるでしょう。
関連記事:勤怠報告とは?5つの方法や連絡する際の注意点について
4-2. 「打刻漏れ・打刻ミス」「不正打刻・改ざん」の発生が起こらないような仕組みづくり
社員数が多くなると同時に、勤怠における「打刻漏れ・打刻ミス」は多くなってしまいます。
また、遅刻しそうな場合に、同僚に頼んで打刻してもらうといった、意図的な「不正打刻・改ざん」がおこなわれてしまうケースは、簡単に想定できるのではないでしょうか。
営業職が多い企業では、直帰する従業員がタイムカードに打刻ができないことで、担当者が連絡を受けたのに処理を忘れてしまうというケースがあるかもしれません。
従業員に勤怠申請を行ってもらう中で、こうした事象が起こらないような管理方法を整えることが非常に大事です。
これまで、オフィスなどに出社する場合における勤怠管理では、「出勤時に出勤簿に捺印をする」「時間外の労働は手書き記入する」「タイムカードで時間管理する」など、アナログな形で管理している企業も多かったかもしれません。
しかし、新型コロナウイルスによりテレワークを導入したことで、勤怠管理システムを導入するなどの対応を進めた企業も多いかと思います。
各企業ごとに、従業員に申請をしてもらう上で抜け漏れないフローを組むようにすることが大事です。
関連記事:勤怠の改ざんはどんな罪になるのか?従業員への対処についても解説
4-3. 残業や休暇の申請がしやすい職場環境をつくる
勤怠の申請において最も課題となるケースが多いのは、従業員が「残業」や「休暇」についての申請がしにくいと感じ、なかなか申請をしてくれないことです。
たとえば、企業として残業時間の減少に取り組んでいるものの、現場では効率よく業務ができないことで残業が多くなってしまい、上司に「残業が多い」と指摘されてしまうといったケースはよく聞かれます。
これにより、実際の時間よりも少なめに残業申請をおこなう従業員が増え、いわゆる「サービス残業」が定着してしまっているような企業も多いのではないでしょうか。
従業員の労働時間が長くなる原因は、職種や役職の違いだけでなく従業員のパフォーマンスの違いによる部分も大きいため、組織として仕事の要領が悪い場合は、社員教育や適切な業務量などを見直す必要があります。
また、真面目に効率的に業務を終えていく社員と、ダラダラとやっている人の給料が同じといったケースも大きく、各個人の能力やスキルがの違いがあることによる待遇の差が無いことに不満を思っている社員も少なくないかもしれません。
4-4. 自己申告が少ない場合には黙認は良くない
残業が多いと上司に注意を受けるのをさけるため、、打刻後に勤務を続ける人もいます。
そのような社員に対して、上司は対応の難しさから申請せずに残業することを黙認してしまっている場合もあります。
正確な勤怠管理をするためにも、申請せずに残業や休日出勤が行われていないのかアンケートを取ったり、定期的に従業員に声をかけて確認したりする等の対策が重要です。
また、日頃からのコミュニケーションも大切です。
もし、申請なしの残業や休日出勤があった場合、コミュニケーションを取りやすい環境を作り相談事を気軽に話せるような状態にしておくことが重要でしょう。
5.勤怠の申請を正しく行わなかったらどうなる?

勤怠の申請を適切に行わなかった場合に、どのような事態が発生するのでしょうか。
5-1. 給与の未払いが発生する
まず従業員は、正しい給与を受け取ることができません。申請すれば受け取れたはずの給与が受け取れないことは、会社に対する従業員の不満にもつながります。
実際に残業代の未払いの違反は多くなっており、平成27年の定期監督では約76%の事業場で違反がありましたが、この中で最も多かったのは労働基準法第32条(労働時間)に違反するもの、次いで労働基準法第37条(割増賃金)に違反するものでした。
このようなケースが起こった場合、金銭的な賠償以外にも、社名を公表されて社会的な信用を失うといったことも考えられます。
5-2. 実態把握が難しく、勤怠の改ざんがおこる
勤怠申請を正しくしなければ、労働者がどのくらい働いているのか実態把握が困難です。
例えば、従業員が遅刻しそうな際に同僚に頼んで打刻してもらったとすると、勤怠担当者は正しい勤務状況を把握することが困難です。
また、会社側から残業しないように言われている場合であっても仕事が納期までに終わらないとなれば、退社の処理をした後(打刻後)にこっそり残業をするという勤怠の改ざんがおこなわれる可能性があります。
6.勤怠申請を適切に行う方法
 勤怠申請・管理の業務効率は企業の取り組み次第で改善することが可能です。
勤怠申請・管理の業務効率は企業の取り組み次第で改善することが可能です。
ここでは、勤怠関係の業務効率を向上させるための方法を3つ解説します。
6-1. 厚生労働省のガイドラインを確認・参考にする
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、原則として企業がとるべき勤怠管理の方法が示されています。
使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
基本的にはこの方法を順守し、勤怠管理を実施します。
ただし、従業員による自己申告制での勤怠管理については、そうせざるをえない状況下で必要な措置を講じた際にのみ認められます。
6-2. 勤怠管理システムの利用
紙での勤怠管理を行っている場合、間違えた際に申請書を最初から書き直すことになり、提出の工数が増えてしまいます。また、承認者も大量の申請に対応しなくてはならないため、本来の仕事に時間を割けなくなります。
しかし、勤怠管理システムを利用すれば、スピード感をもって円滑に勤怠申請・承認ができるのは魅力的でしょう。
6-3. 残業の事前承認制度・許可制度の導入
残業の事前承認制度や許可制度を取り入れることによって、残業を承認・許可する際に従業員の残業時間を把握することが可能です。休日出勤に関しても承認・許可制にすることで勤怠管理の業務効率を向上させられます。
また、従業員は事前に勤怠申請することで自身の勤務状況を正しく把握できます。
7.勤怠の申請が簡単な勤怠管理システムをご紹介
 勤怠管理システムは、パソコンやスマホから申請・承認できたり、残業時間・有給取得日数が自動集計される等、従業員にとっても勤怠管理者にとってもメリットが多い管理方法となっています。また、勤怠情報をリアルタイムで確認して残業時間も把握できることは魅力です。
勤怠管理システムは、パソコンやスマホから申請・承認できたり、残業時間・有給取得日数が自動集計される等、従業員にとっても勤怠管理者にとってもメリットが多い管理方法となっています。また、勤怠情報をリアルタイムで確認して残業時間も把握できることは魅力です。
本記事では、最後に従業員が勤怠の申請を簡単におこなうことができ、担当者の負担を軽減することのできる勤怠管理システムをご紹介させていただきます。
4-1. ジンジャー勤怠
jinjer(ジンジャー)では、様々な端末で打刻ができるという点が大きな特徴です。
また、データに基づく管理や承認のフロー設定を細かく設定できるなど、勤怠管理も徹底的に行える点も大きな魅力です。
外国語にも対応しているため、多言語を必要とする企業も安心して使うことができるサービスです。こうした様々な機能を持ち併せていること自体がjinjer(ジンジャー)の特徴と言えるでしょう。
勤怠管理をする側も勤怠打刻をする側も使い勝手の良いサービスです。契約継続率99.4%、導入者数13000社突破という数字からも、人気を集めている勤怠管理システムと認識できます。
jinjer株式会社 (jinjer Co., Ltd.)
東京本社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿
4-2. 勤次郎

勤次郎はパソコン打刻以外にも、タイムレコーダー打刻(IC/磁気カード)、スマートフォン/タブレット、ICカードリーダー(パソリ)、指情報リーダー、リコー製複合機打刻など、用途に合わせてさまざまな打刻方法があります。
また打刻データの自動収集・集計により、リアルタイムに勤務状況を把握できます。打刻漏れなどのエラーデータや遅刻早退などのアラームデータ、修正箇所に対して色別表示されるため実績データの確認などがスムーズに行えます。そして過重労働の防止には月途中の勤務状況の把握、過重労働に対する気づきを伝えてくれる環境構築が必要です。「勤次郎Smart」ならあらかじめ設定した基準時間に対して、超過している従業員は赤色、超過しそうな従業員は黄色と色分けされるので、残業の多い従業員が一目で分かります。
勤次郎株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田4丁目14番1号秋葉原UDXビル北8階
4-3. KING OF TIME (キングオブタイム)

「KING OF TIME(キングオブタイム)」には、次のような機能が搭載されています。
- 出勤管理
(指紋認証打刻、ICカード打刻、パスワード認証打刻、WEBブラウザ打刻、GPS打刻、Windowsログオン・ログオフ打刻、チャット打刻など) - 残業基準の設定
- スケジュール・シフト管理
- 管理者権限機能
- 申請承認機能
- 休暇管理機能
- アラート機能
- 帳票出力
- 働き方改革関連設定
- データ分析
従業員の残業申請と承認はブラウザ上で完結するため、日々の業務を圧迫しません。そのほか、各拠点のシフトと人件費を同一ページで確認できるため、人件費が予算内に収まっているかどうか一目でわかります。
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT 新宿ビル4F
8.まとめ
 ここまで、勤怠管理をおこなう上で従業員に勤怠申請を正しくおこなってもらう具体的な方法についてご紹介してきました。
ここまで、勤怠管理をおこなう上で従業員に勤怠申請を正しくおこなってもらう具体的な方法についてご紹介してきました。
勤怠管理システムを導入していない企業の方は、ぜひシステムで管理することの重要性を感じていただくとともに、自社にとっておすすめの勤怠管理方法を確立していっていただければと思います。










