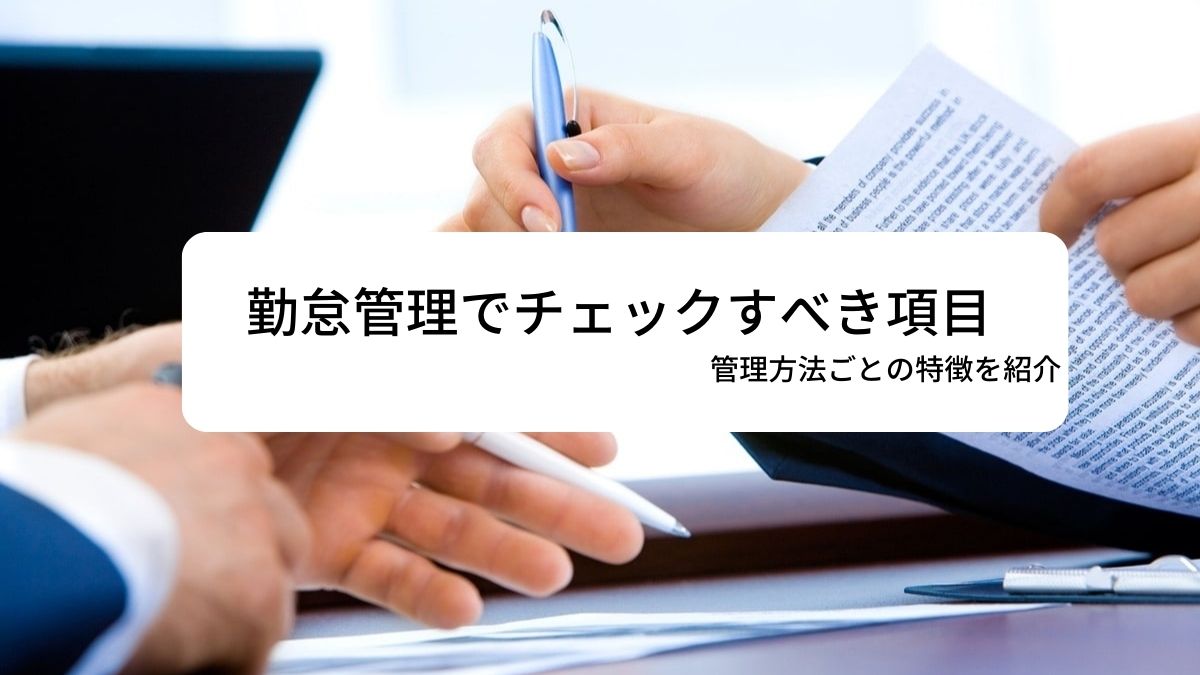
近年の法律改正や働き方の多様化にともない、どうやって勤怠管理を行っていくべきかお悩みの管理者は多いのではないでしょうか。
適切に勤怠管理を行うためには、正しい知識を身につけることが大切です。そこで今回は、勤怠管理チェックの必要性のほか、チェック項目や管理方法の種類とその特徴、特に注意すべきポイントなどについて詳しく解説します。
関連記事:勤怠とは?勤怠管理の目的や具体的な方法、注意点について解説
勤怠管理の原則や守らなければならない法律を知りたいという方に向け、当サイトでは勤怠管理の原則的な方法や働き方改革による労働基準法改正の内容を解説した資料を無料で配布しております。
どのように勤怠管理をすべきか具体的に解説しているため、「法律に則った勤怠管理の方法を確認したい」という方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。
1. 勤怠管理のチェックがなぜ大切なのか

そもそも、なぜ勤怠管理をチェックする必要があるのでしょうか。
ここでは、勤怠管理のチェックが大切である主な理由4つについて解説します。
1-1. 企業にとっての義務である
まず、労働基準法第32条により、企業は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間が適正に守られているか、それに応じて正しい賃金を従業員に支払えているか、という点について常に把握しておく義務があります。
また、政府が推進する「働き方改革の実現」にともなって2019年4月1日より労働安全衛生法が改正され、「客観的な方法による労働時間の把握」が義務化されました。
このような背景から、企業は従業員の勤怠状況について、機器などを活用して客観的に記録し、一定期間のあいだ保存する必要があるのです。
関連記事:勤怠管理の法律上のルールとは?違反した場合や管理方法について
1-2. 正しい給与計算につながる
勤怠管理のチェックは、正しい給与計算に役立ちます。適切に勤怠管理を行うことで、従業員の労働時間を正しく把握できるためです。
たとえば残業代は、保険料や税金の計算にも関わってきます。そのため、残業代を正確に把握できていない場合、保険料や税金の計算が異なってしまう恐れがあります。
賃金請求権は5年(当分の間3年)であり、さかのぼって支払うこともできますが、従業員との信頼関係を維持するためにも、日頃から適切な勤怠管理とミスのない給与計算を意識することが大切です。
1-3. 従業員の過重労働の防止につながる
従業員の残業時間や休日の取得状況などを管理者がチェックすることで、従業員の過重労働の防止につながります。
たとえば残業時間や休日出勤が多いといった気になる働き方が発覚した場合は、早い段階で対策に着手することが可能です。長時間労働による健康被害や訴訟などのトラブルも回避しやすくなるでしょう。
過重労働を減らすことは、従業員の心身の健康を維持や、生産性の向上にもつながります。
1-4. 健全な経営につながる
適正な勤怠管理は、企業が法令を守り、健全な経営を行っているという姿勢を示すことにもつながります。勤怠管理のチェックには、コンプライアンスを遵守した健全な労務をアピールできるというメリットにも期待できるのです。
2. 勤怠管理でチェックすべき項目4つ

勤務管理においては、具体的にどのような項目をチェックするべきなのでしょうか。
管理者として把握しておくべき必須項目を4つに分けて紹介します。
2-1. 始業・終業時刻、労働時間、休憩時間
従業員が何時から何時まで働いたのか、労働時間を正確に把握するために必要な項目です。始業・終業時刻については1分単位で管理し、適切に給与計算しましょう。把握した情報は、遅刻や早退が多い従業員に対して適正な業務指導や配置換えを検討するといった対処にも活用することができます。
関連記事:勤怠管理をする上での休憩時間の決まりとは?トラブル例や注意点を解説
2-2. 時間外労働・深夜残業・休日労働時間
従業員が法定労働時間を超えて働いた時間についても、正確に把握することが重要です。企業は、時間外労働や深夜残業、休日出勤について、通常よりも割増しした賃金を支払う必要があります。それぞれで割増率も異なるため、賃金の割増対象となる労働時間を正確に把握する必要があります。
2-3. 出勤日・欠勤日・休日出勤日
勤務時間だけでなく、日数単位・月単位で勤務状況を把握することも大切です。休日を取得できているか、休日出勤があった際には振替休日や代休をきちんと取得できているかといった情報の把握は、従業員の健康管理や生産性の向上に役立ちます。もちろん給与計算にも影響するため、適切に管理しておく必要があります。
関連記事:勤怠控除を正しく理解|計算方法、運用の注意点を解説!
2-4. 有給休暇の日数・残日数
2019年4月施行の働き方改革関連法案により、企業は10日以上の有給休暇が付与される従業員については、付与されてから1年以内に5日は時季指定をして取得させることが義務化されました。それぞれの従業員が適切に有休を取得できているか把握するためにも、しっかりと勤怠管理をチェックすることが大切です。
有給休暇の取得推進には、従業員のモチベーションアップや採用にあたっての企業のイメージアップに期待できるというメリットもあります。
このように企業には、従業員の勤務時間や有休の取得状況などを管理する義務があります。
しかし、時間や日数の規定が細かかったり、管理方法が分かないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは勤怠管理のノウハウを分かりやすくまとめた無料ガイドブックをご用意しました。
法律に則った勤怠管理の方法や法改正への対応方法を解説しているため、こちらから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」をダウンロードして、法令規則に則った管理にお役立てください。
3. 勤怠管理の5つの方法とその特徴

勤怠管理にあたっては、次の3つの手法が認められています。[注1]
- 使用者が自らが確認し、適正に記録する
- 電子機器などを用いて客観的に確認・記録する
- 自己申告制
[注1]厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
上記の条件を満たす勤怠管理の方法には、いくつかの種類があります。ここでは、主な勤怠管理方法5つとその特徴について、メリット・デメリットをふまえて紹介します。
3-1. 手書きの出勤簿
紙媒体の出勤簿によって勤怠を管理する方法です。カレンダー仕様のフォーマットを活用し、従業員の勤怠に関する情報を手書きで書きこみます。
1枚の書類に必要情報をまとめて管理できることがメリットです。デメリットには、不正申告やサービス残業につながりやすいほか、手書きの手間がかかることなどが挙げられます。
3-2. タイムカード
タイムレコーダーに専用のタイムカードを差し込み、出退勤時間を打刻する方法です。
低コストで導入できることに加え、簡単な操作で運用できるというメリットがあります。一方、休日取得や残業時間の管理には不向きであるほか、テレワークや直行直帰で業務にあたる従業員についてはリアルタイムで記録できないというデメリットがあります。
3-3. ICカードや指紋認証
ICカードや指紋認証を活用して勤怠管理を行う方法です。
本人以外が代わりに記録するといった不正が発生しづらい一方で、専用の打刻機を導入する必要があり、設置場所も限定されます。また、本人がその場で打刻する必要があることから、テレワークや直行直帰の際は後から処理するという手間が発生します。
3-4. Excel
必要情報をExcelに入力して管理する方法です。
あらかじめ数式を設定しておくことで、出退勤時刻の入力のみで自動で労働時間を計算できます。特別な導入コストもかかりません。その一方で、入力ミスや不正申告が起こりやすく、適正な管理が難しいというデメリットもあります。
3-5. 勤怠管理クラウドシステム
タイムレコーダーやパソコン、スマートフォンなどの機器と連携し、打刻から集計、分析までをまとめてシステムで管理する方法です。
社外からの打刻も可能であるほか、打刻漏れに対するアラート発信やGPS打刻など、申請ミスや不正防止に役立つ機能を備えたシステムもあります。デメリットとしては、導入コストがかかることや、操作方法の周知が必要となる点が挙げられます。
4. 勤怠管理を行う際の注意点

実際に勤務管理を行ううえで、特に注意しておきたいポイントについて解説します。
4-1. テレワーク
近年普及が進んでいるテレワークにおいては、タイムカードやICカードによるリアルタイムでの出退勤管理が難しくなります。そのため、勤怠管理にあたっては、オンライン上で打刻を行う従業員による自己申告制を取り入れることが一般的です。
ただし、その場合上司が直接従業員の勤務状況を把握できないことが課題となります。
下記のような方法で、対策を講じる必要があるでしょう。
- 社内ルールを徹底させる
- 実態調査を行う
- GPS打刻機能を活用する
4-2. 扶養控除
配偶者の扶養に入っている従業員は、年収や週の労働時間が定められた規定範囲を超えると、配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。
ひとくくりに「扶養」といっても、以下のようにさまざまなケースが存在します。
- 所得税
- 従業員自らの社会保険加入義務が発生する諸条件
- 配偶者の社会保険
そのため、対象の従業員がどの「扶養控除内」を希望しているかを事前に確認したうえで、勤務日数や時間を正確に管理・調整する必要があります。従業員自らの判断で管理・調整させるのではなく、管理監督者も勤怠状況を把握しておくことが望ましいでしょう。
4-3. シフト制
パートやアルバイト従業員などシフト制で勤務している場合は、勤務時間が日によって変わることは珍しくありません。また、従業員ごとに時給が異なるケースもあります。そのため、勤務日・勤務時間・時給などを特に注意して管理する必要があるといえるでしょう。
4-4. 自社の状況に適した管理方法の選択
せっかく勤怠管理の体制を整えても、自社の状況に合わない方法を選んでしまった場合、思うような管理が叶わない可能性もあります。
- 従業員の働き方にマッチした管理方法か
- 管理者または本人が管理機能を使いこなせるか
上記のようなポイントを考慮しながら、自社の状況に適した管理方法を選ぶ必要があります。
5. 勤怠管理をしっかりチェックしよう

勤怠管理のチェックは企業にとっての義務であり、正しい給与計算や従業員の過重労働の防止につながるといったメリットもあります。
手書きから勤怠管理クラウドシステムの活用までさまざまな勤怠管理の方法があるため、各手段のメリット・デメリットを押さえたうえで、自社の状況に合う管理方法を選ぶことが大切です。
また、テレワークや扶養控除、シフト制など、通常とは異なる働き方の従業員に関する勤怠管理においては、特に注意を払う必要があります。
管理者は勤怠管理に関する正しい知識を備え、適切なチェックを心がけましょう。









