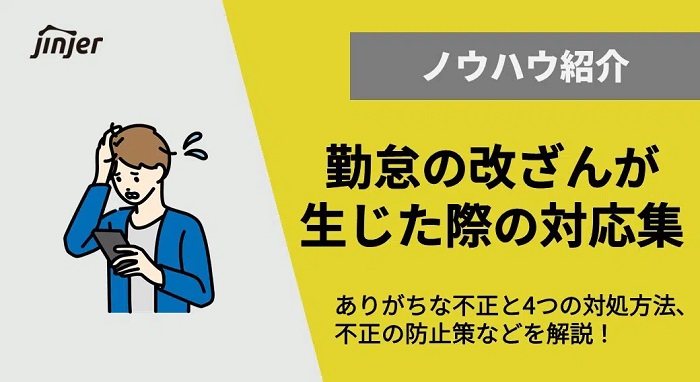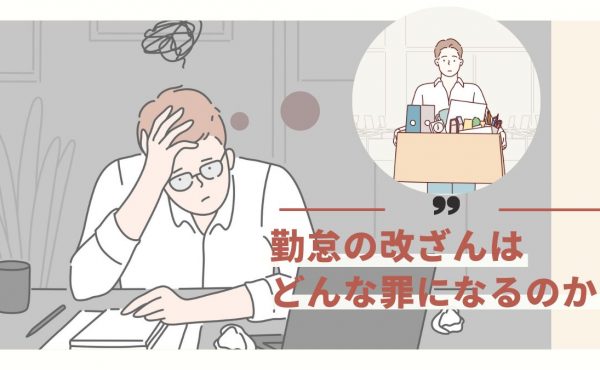
紙のタイムカードやExcel・スプレッドシートなどで勤怠管理をしている場合、代理打刻や不正書き換えなどの違法な勤怠の改ざんが発生するケースもあります。勤怠が改ざんされた場合、刑法や労働基準法などの法律に則り、懲役・罰金などの罰則が課される恐れがあります。本記事では、勤怠の改ざんのリスクやその予防策についてわかりやすく解説します。
勤怠の改ざんがあった際、直ちに従業員を解雇とすることは、法律的にも「不当解雇」とみなされる可能性があるため、処罰には順を追う必要があります。
当サイトでは、従業員による勤怠の改ざんが起こった際、どのように対応していけばよいか、わかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「何が不正にあたるか確認したい」「従業員の不正に適切に対処したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 勤怠の改ざんとは?
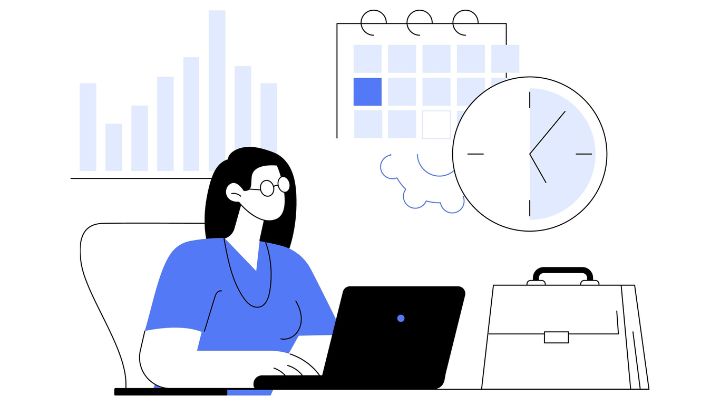
従業員により勤怠が改ざんされることで、企業は正しい勤怠管理ができず、労働災害が発生したり、罰則が課せられたりするリスクもあります。ここでは、勤怠とは何か説明したうえで、なぜ勤怠は改ざんされるのかその理由について詳しく紹介します。
1-1. 勤怠とは?
勤怠とは、辞書によると「仕事に励むことと怠けること」を意味します。ビジネスでは、労働者の出勤・退勤時間や残業時間、休憩時間、休暇など、勤務状況を指して用いられることが多いです。たとえば、「勤怠管理」という用語は、従業員の労働実態を管理することを意味します。
関連記事:勤怠とは?意味や勤怠管理の目的・具体的な方法について解説
1-2. なぜ勤怠は改ざんされる?
勤怠の改ざんは、さまざまな理由によりおこなわれます。次のようなケースが、主な理由として挙げられます。
- 給与に不満があり、水増ししたい
- 労働基準法に抵触しないようにごまかしたい
労働基準法により、労働時間や残業時間の上限が定められています。そのため、労働基準法で決められた時間以上、労働者を働かせることはできません。しかし、業務に支障をきたすので、従業員が勤怠を改ざんして出勤する可能性があります。また、労働基準法違反が発覚すると、企業側に罰則が課せられるため、使用者が勤怠を改ざんするケースもみられます。まずは勤怠の改ざんを防ぐため、その理由をきちんと確認することから始めましょう。
関連記事:タイムカードの改ざんは違法!不正打刻や改ざん防止の方法を紹介
2. 勤怠の改ざんによるリスク

勤怠が改ざんされることで、企業側にどのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、勤怠の改ざんによるリスクについて詳しく紹介します。
2-1. 人件費の高騰化
勤怠が改ざんされることで、必要以上に賃金を支払なければならない可能性があります。これにより、人件費が高騰化し、コストの負担が大きくなります。企業の存続に影響を及ぼす恐れもあるため、勤怠が改ざんされない仕組みを構築することが大切です。
2-2. 職場の秩序が乱れる
勤怠が改ざんされても、とくに大きな問題がないからといって見過ごし、それを許してしまうと、改ざんの頻度が多くなる恐れがあります。また、これまで以上に遅刻・早退が増えたり、申請・承認作業が雑になったりするなど、他にも弊害が生じる恐れがあります。このように、勤怠の改ざんに気づかなかったり、それを一度許してしまったりすると、職場の秩序が崩壊してしまうリスクがあります。勤怠の改ざんがあったら、毅然とした態度で対処することが重要です。
2-3. 優秀な社員の離職
勤怠が改ざんされ、職場の秩序が乱れると、一生懸命仕事に取り組んでいる従業員のモチベーションが下がってしまいます。内部統制がしっかり取れている企業へ転職を考える人も出てくるかもしれません。優秀な従業員が離職してしまうことで、会社全体の生産性が低下するリスクもあります。勤怠の改ざんは社内全体に影響を及ぼすことを押さえたうえで、対策を検討しましょう。
3. 勤怠の改ざんの具体的な手口
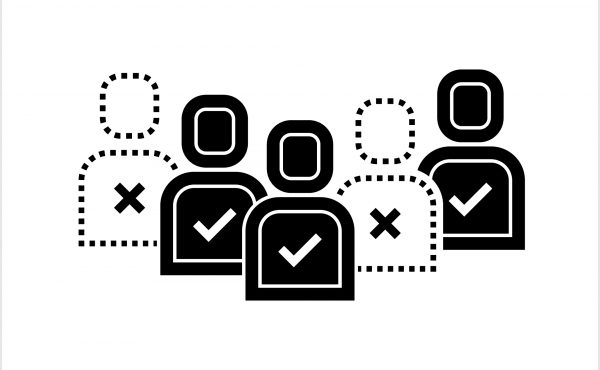
勤怠の改ざんは、さまざまな方法でおこなわれます。ここでは、勤怠の改ざんの具体的な手口について紹介します。
3-1. 代理打刻
タイムカードをタイムレコーダーに通して勤怠管理をしている場合、本人以外でも出勤・退勤を打刻できるため、他の従業員に代理で打刻をしてもらうことができてしまいます。たとえば、遅刻してしまった際に他の社員に頼んで出勤の打刻をしてもらったり、本人が打刻せずに退勤して、残業している他の社員に打刻を依頼したりするといったケースが考えられます。このように、実際には労働していないにもかかわらずタイムカードを代理打刻し、勤怠は改ざんされる可能性があります。
3-2. 本人による書き換え
紙のタイムカードやExcel・スプレッドシートを使用して勤怠管理をしている場合、本人による書き換えで勤怠が改ざんされる可能性があります。たとえば、18時に退勤して打刻したにもかかわらず、後から二重線を引いて19時、20時などと書き換えるケースがあります。また、Excel・スプレッドシートで勤怠管理をしている場合も、セキュリティ体制をきちんと整備していないと、本人によって後から書き換えられる恐れもあります。このように、代理打刻だけでなく、本人による書き換えによって勤怠が改ざんされる可能性もあります。
3-3. 残業代の水増し
残業をする場合、申請制としている企業も少なくありません。しかし、上司と部下が共同して、残業がないにもかかわらず、残業したとみなし、残業代を水増しするケースがあります。また、申請制のやり方によっては、本来の残業時間よりも多くの時間を申告して、不正に残業代を受け取るケースもあります。このように、残業を申請制としている場合、仕組みをきちんと整備していないと、勤怠を改ざんされるリスクがあります。
4. 勤怠を改ざんした場合の罰則

勤怠の改ざんは違法であり、実際の給与よりも多い金額を得ることで会社に損害を与えます。ここでは、勤怠を改ざんした場合、どのような罰則が適用されるのかについて詳しく説明します。
4-1. 詐欺罪
代理打刻や不正打刻により勤怠を改ざんし、労働していない時間の賃金を会社からだまし取ったとなれば詐欺罪が成立する可能性があります。刑法第246条により、10年以下の懲役の罰則が課せられる恐れもあります。また、未遂であったとしても、詐欺罪は適用される可能性があります。従業員に対して、あらかじめ詐欺罪について周知しておくことで、勤怠の改ざんを未然に防止することができるかもしれません。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
4-2. 悪意の受益者の返還義務等
民法第704条により、勤怠を改ざんしたことにより賃金を不正受給した場合、その賃金に利息を加えて返還しなければならない義務が生じます。また、会社側に損害が発生した場合、その賠償責任を負うことにもなります。民法に基づき、勤怠の改ざんが発覚したら、会社側が不利益を被らないよう、賃金の返還や損害の賠償を求めましょう。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
4-3. 電磁的記録不正作出罪
Web上のタイムカードやExcel・スプレッドシートなどの勤怠データの改ざんは、刑法第161条の2に基づき電磁的記録不正作出罪が成立する可能性があります。なお、未遂の場合も電磁的記録不正作出罪は成立します。罪が認められれば、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金のペナルティが課せられます。なお、公務所や公務員によって作成される勤怠データの改ざんに該当すれば、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。
(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
4-4. 【ポイント】従業員だけでなく使用者が罰される可能性もある
法定労働時間(1日8時間、週40時間)や36協定の時間外労働の上限を超えるからといって、従業員が勤怠の改ざんをおこなうと、労働基準法に基づき、従業員だけでなく、使用者も罰される可能性があります。タイムカードなどの勤怠データに関係なく、労働者の実労働時間が労働基準法に違反していることと認められれば、使用者に懲役や罰金といった罰則が課せられる恐れもあります。このように、勤怠の改ざんにより会社側に罰則が与えられるリスクもあることを押さえておきましょう。
関連記事:これだけは知っておきたい労働基準法|法律の内容や罰則をわかりやすく解説
5. 勤怠の改ざんをした従業員への対処

従業員による勤怠の改ざんが発覚した場合、会社側はどのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、勤怠の改ざんをした従業員への対処方法について詳しく紹介します。
5-1. 事実確認
勤怠の改ざんが発覚したら、まずは事実を客観的に立証するために証拠を集めましょう。オフィスの入退室記録や防犯カメラの映像などの証拠を元に、従業員に勤怠の改ざんを認めさせます。このときに、後から「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも第三者に立ち会ってもらったり、ボイスレコーダーにやり取りを録音したりすることが推奨されます。
5-2. 給与の返還請求
勤怠の改ざんによって従業員がこれまで不正に受け取っていた給与に関しては返還請求をおこないましょう。また、あらかじめ就業規則で勤怠の改ざんに関する定めがある場合は、返還請求だけでなく、規則に従って減給や降格などの処分も下しましょう。
5-3. 懲戒解雇
勤怠の改ざんが悪質な場合は、従業員の懲戒解雇が認められたケースもあります。ただし、勤怠の改ざんが原因で解雇した従業員から裁判を起こされ「不当解雇」と判断された事例もあるため、事前に弁護士に相談するなど慎重に手続きを進めることが大切です。具体的には、次のような場合であれば従業員の懲戒解雇が認められる可能性が高いです。
【従業員側の条件】
- 明確な悪意を持って勤怠を改ざんしている
- 長期にわたって不正打刻を続けている
【会社側の条件】
- 勤怠の改ざんについて明確な証拠がある
- 適切に勤怠管理をしていた
つまり、従業員の動機や勤怠の改ざんをしていた期間、証拠の有無が懲戒解雇のポイントになります。打刻を忘れてしまったなどの単なるミスではなく「残業代を水増ししてやろう」という明確な悪意があったうえで、その動機に基づいて長期間勤怠の改ざんをしていたという証拠があり、会社の勤怠管理に非がないことが明確であれば、就業規則に基づく懲戒解雇を検討しましょう。
関連記事:勤怠不良の社員を解雇する際のポイントや未然に防ぐ方法についても解説
5-4. 懲戒解雇が難しい場合はどうする?
従業員が勤怠の改ざんをしていても、次のように会社側が適切に勤怠管理をおこなっていなかった場合、懲戒解雇が不当解雇と判断される可能性があります。
- 勤怠の改ざんを知りながら、見て見ぬふりをしていた
- 不正打刻をした従業員に対して適切な指導をしていない
このような場合、会社側が勤怠管理を怠っていたと判断され、懲戒解雇が認められない可能性があります。他にも、従業員の悪意が明確とまでは言い切れない場合や、不正が短期間の場合にも、懲戒解雇は認められにくいです。懲戒解雇が難しい場合は、適切な手順を踏んだうえで、退職勧奨を検討しましょう。
懲戒解雇は最も重い処分であるため、従業員の懲戒解雇を検討している場合は、事前に弁護士や社労士に相談して慎重に進める必要があります。「解雇といかずとも、まずは注意してうちうちに済ませたい」という方に向け、当サイトでは勤怠の改ざんが起きた際に対応すべきことをまとめた資料を無料で配布しております。解雇の前に対応すべきことを確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
6. 勤怠の改ざんをした従業員を退職に促す方法

勤怠の改ざんをした従業員に対して「証拠が揃わず懲戒解雇はできないが、反省の様子も見られない」「他の社員に悪影響がある」などの理由から「会社を辞めてもらいたい」と思うこともあるかもしれません。ここでは、懲戒解雇をするのが難しい場合に、違法とならない退職の促し方について詳しく紹介します。
6-1. 退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社側が従業員に対して自主的に退職を勧めることです。退職勧奨の場合、会社は退職を促すことはできても、解雇のような法的効力はなく、辞めるか否かの最終的な判断は従業員がします。このように、退職推奨はあくまでも「会社からのお願い」であり、強制してはいけません。必要以上に強く退職推奨すると違法になる恐れがあるため、進め方については労務の問題に詳しい弁護士などに相談しましょう。
6-2. 退職勧奨の注意点
退職推奨はあくまでも「会社からのお願い」であり、最終的には従業員の意思によって決まることを留意しておきましょう。退職勧奨をする際は、次のような注意点に気を付けましょう。
- 相手の名誉を傷つけないような言葉遣いで退職を勧める
- プライバシーが守られる個室で業務時間内に短時間で実施する
- 従業員が退職を拒否した場合は、その意思を尊重する
- 退職以外の選択肢もあることを伝える
- 繰り返し退職推奨をしない
- 大人数で説得するなど不適切な圧をかけない
行き過ぎた退職勧奨は「会社に脅されて強引に退職させられた」として、慰謝料請求をされる、社会的な信用を落とすなどの恐れがあります。実際に不当な心理的圧力を加えた場合や、名誉感情を害する言動を用いた場合には、退職勧奨が違法だと認められた判例もあるため注意が必要です。
7. 勤怠の改ざんを予防する方法

勤怠の改ざんを予防するには、改ざんをさせない仕組み作りがポイントです。ここでは、勤怠の改ざんを予防する方法について詳しく紹介します。
7-1. 勤怠管理システムを導入する
紙のタイムカードやExcel・スプレッドシートなどを使用した勤怠管理では、不正打刻や書き換えができてしまうため、どうしても勤怠の改ざんが発生する恐れがあります。勤怠管理システムを導入すれば、ICカードやPCログなどを用いて自動的に打刻管理ができるので、勤怠の改ざんを防止することが可能です。また、生体認証を採用している勤怠管理システムを利用することで、代理打刻や不正打刻を防ぐことができます。このように、勤怠の改ざんをなくすために、勤怠管理システムの導入を検討してみるのも一つの手です。
7-2. 就業規則を明確に定める
勤怠の改ざんを予防するには、勤怠の改ざんを禁止するためのルールを就業規則に明確に定めることが大切です。勤怠の改ざんをした場合に減給や降格といった罰則を課すことで、抑止力が働くようになります。このような罰則についても、きちんと就業規則に記載することが重要です。また、就業規則を定めるだけでなく、研修・セミナーなどの場を設けて内容をきちんと周知しましょう。
7-3. 従業員の自制を促す
勤怠管理システムを導入しても、不正の可能性を完全に排除することはできません。従業員の自制を促すため、会社側が証拠として使用できるものの存在を従業員に意識させることも大切です。たとえば、タイムレコーダーの近くに監視カメラを設置することが挙げられます。ただし、行き過ぎた監視はプライバシーの侵害になる恐れもあるので、慎重に対策を検討しましょう。
7-4. 人事評価や労働環境を見直す
従業員が勤怠の改ざんをする理由から、予防策を考えてみるのも一つの手です。労働に見合った賃金が支払わておらず、従業員が給与に不満を感じている場合、人事評価の見直しを検討しましょう。また、残業や休日出勤が多く、労働基準法違反になるような労働をさせているのであれば、業務量を減らすなど、労働環境を改善することが大切です。このように、従業員が働きやすい環境を整備することは、勤怠の改ざんの防止にもつながります。
7-5. 【注意】従業員だけでなく会社側の改ざんのリスクも確認しておく
勤怠の改ざんは労働者だけでなく、使用者によっておこなわれることもあります。刑法第159条により、使用者が労働者の勤怠情報を改ざんした場合、私文書偽造罪として1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。また、労働基準法違反に該当し、懲役や罰金のペナルティを受けるリスクもあります。このように、従業員だけでなく、会社側の改ざんのリスクも把握しておきましょう。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
8. 勤怠の改ざんができないようにあらかじめ対策しておこう

勤怠の改ざんは違法行為であり、悪質な場合は詐欺罪が成立する可能性もあります。まずは勤怠の改ざんをした従業員に給与の返還請求をしましょう。場合によっては、懲戒解雇や退職推奨も検討しましょう。また、勤怠の改ざんを予防するため、紙のタイムカードを廃止し、勤怠管理システムを導入してみるのもおすすめです。
勤怠の改ざんがあった際、直ちに従業員を解雇とすることは、法律的にも「不当解雇」とみなされる可能性があるため、処罰には順を追う必要があります。
当サイトでは、従業員による勤怠の改ざんが起こった際、どのように対応していけばよいか、わかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「何が不正にあたるか確認したい」「従業員の不正に適切に対処したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。