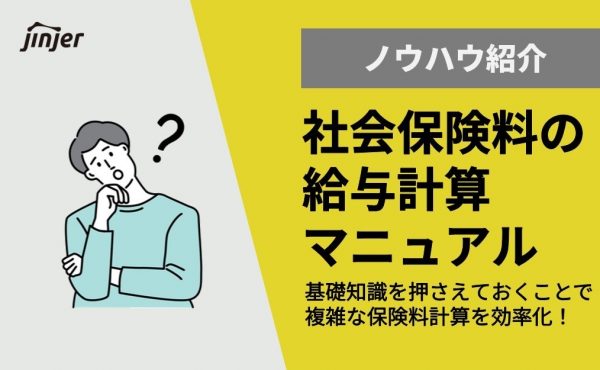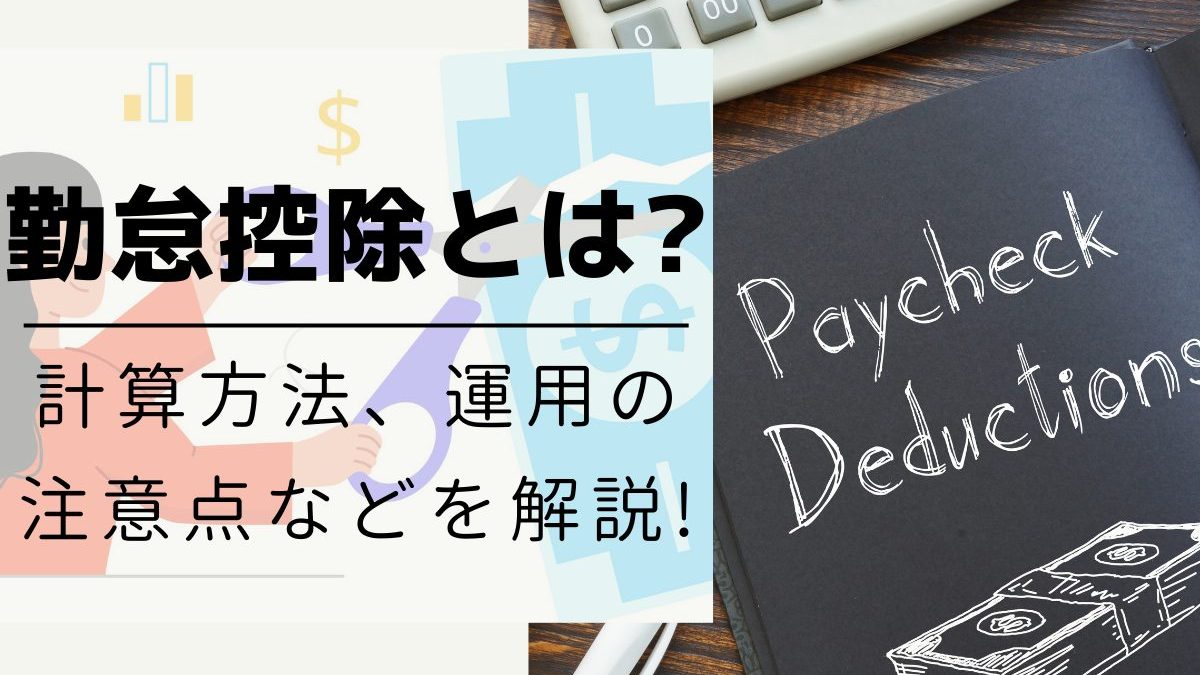
従業員が遅刻や早退、欠勤などによって働けないことで発生する「勤怠控除」。
「勤務形態によって計算方法が変わる」「手当によっては控除しないものもある」など、実際の計算方法は複雑です。
今回は、勤怠控除が発生するシーンや計算方法に関して紹介しますので、理解を深めておきましょう。
関連記事:勤怠とは?勤怠管理の目的や具体的な方法、注意点について解説
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
1. 勤怠控除とは

勤怠控除とは、遅刻や早退、欠勤をした際に、労働がなかった時間分の賃金を給与から差し引くことを指し、 1カ月に定められた勤務時間を満たさなかった場合は、月給制であっても給与が差し引かれる仕組みになります。
労働者の勤務体系や勤怠控除の方法によっては、給与の金額が変わることも多くあるため、人事担当者としては注意が必要です。
1-1. 勤怠控除の根拠となるノーワークノーペイの原則
企業が勤怠控除をおこなう根拠となっているのが、商慣習上、広く認められた「ノーワークノーペイの原則」です。ノーワークノーペイの原則は、従業員が労務を提供しなかった場合、企業は報酬を支払わなくてもよいという考え方です。
ノーワークノーペイの原則に関連した内容は、労働契約法第6条と民法第624条に記載されています。いずれの法令も従業員の労務提供があった場合のみ、企業が給与を支払う義務を負うとしています。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない
1-2. 法定控除と協定控除
給与から差し引かれるものとして、「法定控除」「協定控除」の2種類が存在します。以下、それぞれの意味を紹介します。
法定控除とは
法廷控除とは、社員の賃金から会社が法律上当然に控除できる項目を表しています。
以表に、法定控除に該当する6項目をまとめました。
|
法定控除項目 |
控除額の計算方法 (本人負担分) |
|
健康保険料 |
標準報酬月額×保険料率(都道府県ごとに決められた率で、約5%) |
|
介護保険料 |
標準報酬月額×保険料率(全国一律 1.58%)(40歳以上のみ) |
|
厚生年金保険料 |
標準報酬月額×保険料率(全国一律 8.914%) |
|
雇用保険料 |
額面×0.5% (建設業などは別料率) |
|
所得税 |
「月額表」「日額表」という国税庁が出している表に当てはめる |
|
住民税 |
市区町村から通知された額(前年の所得による) |
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料と、法律で給与から控除(天引き)することが定められている所得税や住民税といった税金が該当しています。
協定控除とは
協定控除は、上記の法定控除以外の控除額のことです。
企業ごとに異なる額や計算方法で設定されており、たとえば、社宅の使用料、財形貯蓄、生命保険料、従業員旅行の積立などが該当します。
企業と従業員の間で労使協定によって取り決めることになるため、人事担当者としては該当する項目を事前に決めておく必要があります。
2. 勤怠控除が発生する3つのケース
勤怠控除が発生するのは、以下のようなケースです。
- 体調不良により欠勤・遅刻・早退をした場合
- インフルエンザや新型コロナウイルス感染症により従業員が自主的に休みを申し出た場合
- 裁判員制度で裁判員に選ばれたことにより欠勤した場合
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
2-1. 体調不良により欠勤・遅刻・早退をした場合
体調不良を理由とした欠勤や遅刻、早退には、勤怠控除が適用されます。丸一日欠勤したときや、遅刻や早退により勤務時間の一部を働かなかったときは、その時間分の給与を支払う必要はありません。
子どもの送り迎えのための遅刻や早退なども同様です。
2-2. インフルエンザや新型コロナウイルス感染症により従業員が自主的に休みを申し出た場合
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に罹患したことを理由に、従業員が自主的に休みを申し出た場合は、勤怠控除が適用されます。
ただし、会社側から出勤を控えるように指示した場合は、基本的に勤怠控除は適用されません。会社都合の場合は、休業手当を支給すべきケースもあるため注意しましょう。
2-3. 裁判員制度で裁判員に選ばれたことにより欠勤した場合
裁判員制度により裁判員に選ばれ会社を欠勤した場合も、勤怠控除の適用対象です。有給休暇を使わずに会社を休んで裁判に参加した場合は、勤怠控除が適用されるため給与を支払う必要はありません。
ただし、裁判員に選ばれると日当が支払われるため、従業員が経済的負担を感じることは少ないでしょう。
3. 勤怠控除に関する計算方法

ここからは、勤怠控除に関する具体的な計算方法について解説していきます。
3-1. 欠勤控除を正しく計算する方法
従業員の欠勤控除を正しく給与に反映するためには、まず1日あたりの賃金(日給)を算出する必要があります。
この日給について2通りの計算方法があるため、具体的にどのように計算すべきか紹介します。
(1)日給を「年平均の月所定労働日数」から算出する
1つ目の方法は、年平均の所定労働日数から日給を計算し、欠勤控除額を出す方法です。具体的な計算式は、以下の通りとされています。
月給与額 ÷ 月平均の月所定労働日数 × 欠勤日数 = 欠勤控除額
この計算方法は、1年を通して欠勤控除の金額が同じになるため、欠勤日数をかけ合わせることで算出される値です。
たとえば、年平均の所定労働日数が20日で、欠勤した月の所定労働日数が21日であった場合、20日間欠勤すると、1日労働しているにもかかわらず、給与が0円になってしまいます。
ただし、年間を通してみると、欠勤日数に対する控除額の総額に過不足がなく、違法とはなりません。
この計算方法の場合、欠勤1日あたりの控除額は年間を通じて一定で、月による変動がありませんので、計算をおこなう際には注意しましょう。
(2)日給を「該当月の所定労働日数」から算出する
2つ目は、欠勤をした月の所定労働日数を使って日給を算出し、欠勤控除額を求める方法です。具体的な算出方法は以下の通りです。
欠勤した月ごとの所定労働日数を利用して日給を算出すると、月によって所定労働日数が異なるため、1日あたりの欠勤控除金額も月によって変動します。
計算をおこなう際には、欠勤した日数を踏まえたうえで、労働時間を正確に算出するように心がけましょう。
3-2. 遅刻・早退控除を正しく計算する方法
月給制において、残業無し、定時に退社する働き方を例として紹介します。計算式は以下の通りです。
月給与額 ÷ 月の平均所定労働時間 × 遅刻や早退の時間 = 「遅刻・早退控除額」
たとえば、月給30万円で、月の平均所定労働時間が160時間の従業員が、1カ月で合計4時間の遅刻・早退した場合、遅刻早退控除額は、30万円÷160時間×4時間=7,500円となります。
ただし、計算式が自社の就業規則と異なる場合には、自社の就業規則を優先しましょう。
また、本章で解説した控除の計算方法を間違えてしまうと、正しい所得額を算出できなくなってしまい、所得税や保険料の計算にミスが出てしまうリスクがあるので注意が必要です。
当サイトでは、毎年改定のある社会保険料の計算方法や担当者が気を付けるポイントなどを解説した資料を無料で配布しております。
所得額のみすによる保険料の計算ミスに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
4. 勤怠控除に関する注意すべきポイント

最後に、勤怠控除に関して注意すべきポイントを紹介します。
4-1. 勤怠控除に関する内容は全て就業規則に明記する
自己都合・会社都合の場合でどう変わるか、欠勤や遅刻・早退によって控除される適応要件、勤怠控除の計算式など、勤怠控除に関する内容は就業規則に詳細に記すことが重要です。
会社都合の場合は欠勤控除を満額支給しなければならないかと思いますが、会社によっては、社員が子どもの行事に出席するなど自己都合の休暇を認めて、欠勤控除の対象にしているケースも見受けられます。
欠勤控除や年次有給休暇として扱うか否かは、会社側の判断に委ねられているのです。
また、定年退職する従業員を再雇用しない場合、60歳に到達日を退職日として設定できるため、それ以降に働くことがあれば、賃金を1日ごとに満額支給する必要があります。
4-2. 手当が控除されるパターンもある
有給休暇を使って通常の出勤日に休んだ場合は、欠勤控除の対象になりません。就業規則などに基づいた形で、所定の金額を賃金として支払う必要があります。
また、会社都合により、もともと出勤日だった日を休業として扱う場合も多くありますが、この場合は会社側が平均賃金の60%以上の金額を「休業手当」として支払う必要があります。
創立記念日などで休業になった場合は手当が控除されるため、事前に確認しておきましょう。
4-3. 休職中や退職後の控除はできない
従業員の休職中は、厚生年金や健康保険などの社会保険料の負担額は本人負担、会社負担ともに変更はありません。これは、休職に関する定めが法的なものではなく、あくまで各会社の就業規則による形になっているためです。
通常、給与から社会保険料が天引きとなるケースが多いですが、無給の場合においては、従業員が社会保険料を支払い続けるのは難しいかもしれません。
このような場合に備えて、会社側は休職期間中の社会保険料の支払いについても、就業規則に事前に明記しておきましょう。
4-4. ボーナスからも勤怠控除できる
就業規則の内容にもよりますが、基本的にはボーナスにも勤怠控除を適用できます。ボーナスは一般的な給与と同様、労働への対価と解釈されるからです。
一般的な就業規則には、「ボーナスの支給額は企業の業績などを考慮して決定する」などと記載されています。このような記載がある場合、企業側がボーナスの有無や支給額を決定でき、遅刻や欠勤などに応じてボーナスを減額することも可能です。
4-5. 勤怠控除額は勤務形態・給与形態によって変わる
勤務形態によって1日あたりの所定労働時間の考え方が変わります。そのため、勤務形態ごとに勤怠控除の算出方法が異なります。
また、フレックスタイム制を採用している企業の場合、働く時間は従業員自身が決めることができるため、遅刻や早退が発生しません。勤務形態によっては、そもそも勤怠控除を適用できないケースもあります。
| – | 1日あたりの所定労働時間 | 勤怠控除額の算出方法 |
| 一般的な勤務形態 (出社時間や退社時間が定められた勤務形態) |
一定 | 欠勤した日数に応じて給与を控除できる |
| 変形労働時間制 シフト制 |
会社が設定 | 会社が設定した所定労働時間に満たない場合に給与を控除できる |
| フレックスタイム制 | 従業員が設定 | 原則として、労働時間は従業員自身が決めるため勤怠控除はできない コアタイムが設定されている場合、遅刻や早退を理由に通勤手当や皆勤手当などを減額することは可能 |
勤務形態と同様、給与形態によっても勤怠控除額の算出方法が変わります。給与形態別の勤怠控除の計算方法は次の通りです。
| – | 給与の支払い方法 | 勤怠控除額の算出方法 |
| 日給月給制 | 働いた日数をベースに月額の給与を支給する | 欠勤した日数に応じて勤怠控除をおこなう |
| 完全月給制 | 働いた日数にかかわらず固定金額の給与を支給する | 原則として、勤怠控除はできない |
| 年棒制 | 年単位で給与総額を決定する | 年間の所定労働日数を計算し、1日あたりの給与を算出する |
| 時間給 | 働いた時間をベースに給与を支給する | 勤怠控除ではなく、働いた時間に応じた給与を支給する運用が一般的 |
| 歩合給 | 基本給に加えて成果に応じた出来高給を支給する | 基本給の部分のみ勤怠控除をおこなうことが可能 |
5. 勤怠控除を正しく理解したうえで計算しよう!
勤怠控除の内容は会社ごとに決めることができます。勤怠控除は義務化されていないため、すべての企業で必ずしもおこなわれているとは限りません。
しかし、適用範囲などを曖昧にしておくと、従業員とのトラブルに発展する可能性があります。
従業員からの信頼を得るためにも、自社において勤怠控除をおこなっているか否か、雇用形態に合わせて設定された計算方法など、事前に就業規則に明記しておきましょう。