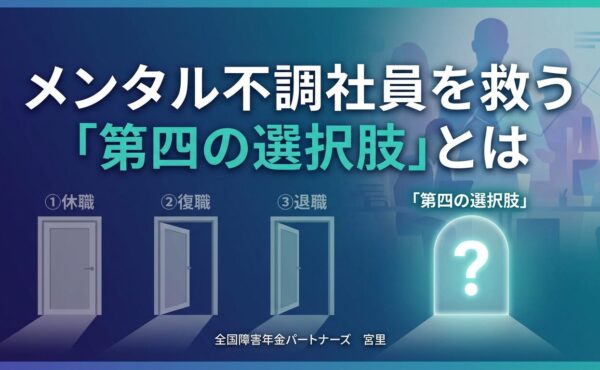柔軟な働き方を可能とする変形労働時間制ですが、メリット・デメリットがあるため、導入前に把握しておくことが重要です。
変形労働時間制のデメリットとしては、残業代の計算や勤怠管理の煩雑化、社員から不満が出やすいことなどが挙げられます。一方で正しく運用すると、残業代を削減できるなど、さまざまなメリットを得ることが可能です。
本記事では、変形労働時間制のメリット・デメリット、うまく運用するためのポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
1. 変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、繁忙期と閑散期がある事業場にて、ある週は長く、別の週は短くなど、一定期間内の労働時間を調整できる制度です。変形労働時間制を導入すると、さまざまなメリット・デメリットが生じますが、その前に制度内容について簡単におさらいしていきましょう。
1-1. 変形労働時間制は1ヵ月・1年・1週間単位で設定できる
変形労働時間制は、週単位や月単位で労働時間を平均して法定労働時間内に収まっていれば、特定の日や週、月の労働時間については法定労働時間を超えて設定できる制度です。
1ヵ月・1年・1週間単位の3種類がありますが、それぞれの単位は労働時間を平均して法定労働時間を超えていないか確認する期間でもあります。
また、変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結し所轄の労働基準監督署長に届出をする、もしくは就業規則にて規定する必要があります。
1-2. 変形労働時間制は従業員に損?不利益変更に当たる?
変形労働時間制を導入すると、労働時間を柔軟に調整できる一方で、ときには長時間労働が発生したり、労働時間が不規則になったりすることも想定できます。しかし、生産性が向上し、総労働時間の減少が見込まれる場合には、従業員にとってもメリットが生じます。そのような場合、不利益変更には該当しないでしょう。
関連記事:変形労働時間制とは?残業の考え方や導入方法、注意点をわかりやすく解説
2. 変形労働時間制のデメリット(企業側)

変形労働時間制は、一定期間の労働時間を柔軟に調整できるものですが、それに伴ってデメリットが生じることもあります。変形労働時間制を導入すると、企業にはどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
2-1. 勤怠管理・残業代計算の業務が煩雑化しやすい
勤怠管理が難しくなることは、変形労働時間制のデメリットの一つです。変形労働時間制を導入すると、それぞれの従業員に合わせた勤怠管理が必要となります。
また、残業が発生した場合の計算も個々の所定労働時間に準じておこなわなければなりません。勤怠管理の担当者に大きな負担がかかってしまうことは、懸念点として捉えておきましょう。
2-2. スケジュール調整が難しい
スケジュール調整が難しくなることも、変形労働時間制を導入するデメリットです。それぞれの従業員の労働時間が固定されていないため、打ち合わせの日程調整が難航したり、コミュニケーションの機会が減ったりすることもあるでしょう。
また、クライアントとのスケジュール調整が難しくなるケースもあるので注意が必要です。
2-3. 社員から不満が出る可能性がある
一般的な勤務体系の場合、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超える労働に対し、1.25倍以上の割増賃金を支給する必要があります。
しかし、変形労働時間制を導入すれば、一時的に所定労働時間を法定労働時間(1日8時間、週40時間)よりも長く設定でき、その所定労働時間内であれば残業代が発生しません。そのため、変形労働時間制の導入によって従業員の残業代がこれまでよりも少なくなってしまう可能性があり、不満を感じる社員が出てくるケースもあります。
関連記事:変形労働時間制の残業時間の上限とは?残業代や割増賃金の計算方法も解説!
2-4. 運用方法を間違えてしまうリスクがある
制度の内容を理解しないまま変形労働時間制を導入すると、不適切な運用がおこなわれる可能性もあるでしょう。
たとえば、変形労働時間制の導入後に、管理者が残業代を支払わないケースが考えられます。しかし、変形労働時間制であっても、時間外労働には所定の残業代の支払いが必須です。
その他に気をつけたいのは、深夜割増の考え方です。繁忙期の業務時間を長く設定した場合、深夜労働(原則22時~5時の労働)に対する割増賃金が発生するケースもあります。
また、所定労働時間を超えない範囲で制度を運用することや、勤務時間や勤務日数の上限を超えないようにすることも重要なポイントです。運用方法を間違えてしまうと従業員から不満が出たり、制度の運用が違法とみなされ、従業員から訴えられたりする可能性もあるので気を付けましょう。
3. 変形労働時間制のメリットとは(企業側)

ここからは、変形労働時間制を導入することで企業が得られるメリットについて解説します。
3-1. 残業代の削減に期待できる
変形労働時間制の大きなメリットは、企業が従業員に支払う残業代を削減できることです。
一般的な勤務体系の場合、1日8時間・週40時間を超える労働に対し、1.25倍以上の割増賃金を支払う必要があります。繁忙期は法定労働時間を超えることが多く、割増賃金が企業の負担になるケースもあるでしょう。
逆に閑散期においては、規定の労働時間で働かせた場合、非効率であり生産性が低い時間に対しても給与を支払わなければなりません。
しかし、変形労働時間制を導入すると労働時間の調整が柔軟になるため、結果的に残業代を削減できます。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
3-2. 業務の効率向上・光熱費等の削減
変形労働時間制においては、繁忙期の労働時間を長くし、閑散期の労働時間を短縮できることから、全体業務の効率が上がりやすいでしょう。
また、一般的な勤務体系では、通常の勤務時間だけではなく、残業時間分の光熱費もかかってしまいます。一方で変形労働時間制を導入すると、閑散期の労働時間を短縮できるため、オフィスの光熱費の負担も減り、コスト削減につながることが考えられます。
3-3. 企業のイメージアップにつながる
企業のイメージアップにつながることも、変形労働時間制の大きなメリットです。柔軟な働き方を取り入れ、業務効率化や無駄な経費の削減に取り組んでいることをうまくアピールすれば、企業のイメージが向上するでしょう。
その結果、認知度がアップしたり、採用活動がスムーズに進んだりすることも期待できます。
4. 変形労働時間制のデメリット(従業員側)

ここまで、変形労働時間制を導入した際に企業に生じうるメリット・デメリットを紹介しました。ここからは、従業員側のデメリットについて紹介します。
4-1. 繁忙期に負荷がかかりやすい
変形労働時間制を導入すると、繁忙期における労働時間が増えてしまいます。
その結果、短い期間に長時間の労働が発生してしまい、心身に負荷がかかりやすいことが考えられるでしょう。1年単位の変形労働時間制の場合は、繁忙期の範囲が長期にわたり、体調を崩しやすくなることも考えられます。
4-2. 給与が削減してしまう可能性がある
変形労働時間制を導入すると、これまでの一般的な勤務形態ではもらえるはずであった時間外労働に対する割増賃金が、付与されなくなるケースもあります。
そのため、給与が減少する従業員が出てくるかもしれません。
4-3. 他部署とコミュニケーションが取りにくい
変形労働時間制を一部の部署や役職にのみ導入すると、他部署との勤務タイミングにズレが生じやすくなります。するとコミュニケーションが不足し、業務にも支障をきたす可能性があります。あらかじめ会議が可能である時間帯や、連携時間などを定めておくことで対策する必要があるでしょう。
5. 変形労働時間制のメリット(従業員側)

ここからは、変形労働時間制を導入することで従業員が得られるメリットについて紹介します。
5-1. 非効率な労働時間を削減でき、メリハリのある働き方ができる
繁忙期には密度高く働き、閑散期は早めに退勤するといった、メリハリのある働き方ができることは、従業員にとってのメリットといえるでしょう。
閑散期の勤務時間が減少することで、一般的な勤務体系では得られなかった身体を休める時間をつくることができます。
5-2. ワークライフバランスが向上する
繁忙期においては変わらず労働時間が長いことが想定されますが、業務量が減る閑散期に関しては、業務時間が短くなるほか、休日として調整するケースが増えるでしょう。
そのため従業員にとっても、プライベートにより多くの時間を割くことができ、ワークライフバランスの向上も見込めます。
6. 変形労働時間制の導入方法

変形労働時間制は、企業側が勝手に導入できる制度ではありません。以下のような手順で進める必要があるため、事前にチェックしておきましょう。
6-1. 現状の勤務状況を把握する
変形労働時間制を導入する前に、社内の現状を把握しておくことが重要です。繁忙期と閑散期における労働時間の差が大きい、柔軟な働き方の導入を求める意見が多い、といった状況の場合は、変形労働時間制の導入を進めてもよいでしょう。
ただし、裁量労働制や時短勤務制度など、変形労働時間制以外の制度を導入すべきケースもあります。まずは社内の課題を把握したうえで、最適な制度を導入しましょう。
6-2. 期間や対象者を決める
変形労働時間制には、1ヵ月単位・1年単位などの種類があるため、繁忙期のタイミングなどに合わせてどの制度を導入するか選びましょう。
また、変形労働時間制を適用する対象者を決める必要もあります。全従業員を対象とすることもできますが、特定の部署や職種に限定することも可能です。業務に支障が出ないよう慎重に決定しましょう。
6-3. 就業規則の変更・労使協定の締結をおこなう
変形労働時間制を導入するときは、就業規則を変更しなければなりません。変形労働時間制の対象期間や対象となる従業員の範囲、労働時間などを明記しておきましょう。
また、一部の例外を除き、労使協定の締結も必要です。導入後のトラブルを防止するためにも、労使間でしっかりと話し合ったうえで協定を結びましょう。
6-4. 労働基準監督署への届出をおこなう
労使協定を締結したら、労働基準監督署へ届出をおこないます。清算期間が1ヵ月以内のフレックスタイム制を導入する場合は届出が不要ですが、基本的には届出が必要であるため忘れないようにしましょう。
関連記事:変形労働時間制とフレックスタイム制の違いについて徹底解説
6-5. 従業員へ周知する
新しい制度が導入されたことや運用ルールなどを、従業員へ周知しておくことも重要です。変形労働時間制は、通常の勤務形態とは異なり仕組みが複雑であるため、必要に応じて説明会を開催したり、マニュアルを作成して配布したりするとよいでしょう。
7. 変形労働時間制のデメリットの解消方法

変形労働時間制では、所定労働時間や残業の考え方を正しく把握する必要があります。また、制度の内容を社内に周知することも重要なポイントです。
ここからは、変形労働時間制の導入で考えられる問題を解消する方法について見ていきましょう。
7-1. 就業規則を明確に定める・都度確認する
所定労働時間があやふやになってしまう原因の一つとして、就業規則がしっかりと作成されていないことが挙げられます。変形労働時間制を導入する場合、就業規則を丁寧に見直し、後で制度があやふやになってしまうことがないよう正しく整備をおこないましょう。
7-2. 従業員にわかりやすく説明する
残業代の減少などで従業員から不満が出るのを防ぐためには、十分な周知や説明が不可欠です。デメリットはあるものの、適切に変形労働時間制を導入できれば、従業員のワークライフバランス向上にもつながります。
従業員に説明する際には、繁忙期に多く働いて、閑散期には早めに業務を終了させたり休日を設定したりとプライベートの充実が実現できる点を強調しましょう。
7-3. 勤怠管理システムを活用する
変形労働時間制の導入にあたっては、勤怠管理の担当者に大きな負担がかかるリスクが考えられます。まずは担当者が制度や勤怠管理の方法を把握できるよう、研修を設けるなどの対策をおこないましょう。
また、勤怠管理システムを導入すると、法律に沿った労働時間の調整や、複雑な時間外労働(残業)の計算にかかる工数を削減することができます。使いやすいシステムを選んで取り入れれば、担当者にかかる負担も減らせるでしょう。
8. 変形労働時間制の注意点

ここからは、変形労働時間制の注意点について解説します。
変形労働時間制には、労働基準法に基づいたさまざまな規定があるため、適切に運用できない場合は法律違反となり罰則が科されてしまう可能性もあります。
適切な運用をおこなうためにも、以下の注意点をおさらいして、正しくルールを理解しましょう。
8-1. 導入には複数の手続きが必要
変形労働時間制は、正式な手続きをおこなわなければ運用が認められません。
変形労働時間制を実施するうえで必要な項目を定めたあと、就業規則の整備、労使協議会の開催、労使協定書の作成、労働基準監督署長への届出など、複数の手続きが必要であるため忘れないようにしましょう。
関連記事:変形労働時間制の届出に必要な書類や書き方は?手続きフローもあわせて解説
8-2. 所定労働時間の繰り上げや繰り下げはおこなえない
変形労働時間制では、所定労働時間を変更することは認められていません。たとえば、残業が発生した日の残業時間分を、他の日の所定労働時間から差し引き、相殺することは禁じられています。
変形労働時間制の残業代は、1日・週・月ごとに算出する必要があるため注意しましょう。
8-3. 期間内の労働日数・連続した労働日数にも上限がある
変形労働時間制においては、期間内の労働日数・連続労働日数に関して上限が設けられています。
労働日数の限度は、原則1年につき280日とされてます。ただし、対象期間が3ヵ月以内である場合、制限は設けられていません。
対象期間が3ヵ月超え~1年未満の場合は、下記の公式にて対象期間の労働上限日数を計算することができます。
連続労働日数の限度は、最長6日とされています。ただし、あらかじめ労使協定にて繁忙期に定める「特定期間」を設けた場合、最長12日まで延長することが可能です。
8-4. 残業代の算出方法が異なる
変形労働時間制の残業時間に関しては、1日・週・月単位で算出する必要があります。また割増率は、一般的な勤務形態と変わらず以下の通りです。
- 法定時間外労働:25%
- 深夜労働(22~5時までの間の労働):25%
- 休日労働(法定休日での労働):35%
残業代の計算を間違えると、未払い賃金が発生するなど、従業員とのトラブルを生むので、正しく勤怠管理・給与計算できる仕組みを整えておきましょう。
8-5. 変形労働時間制とシフト制との違い
変形労働時間制とシフト制は、ともに労働時間を柔軟に調整できる制度ではありますが明確な違いがあります。
変形労働時間制は、繁忙期や閑散期が発生する事業場にて所定労働時間を柔軟に調整できる制度で、週・月・年単位から選択できます。
一方でシフト制は、従業員が時間ごとに交代して勤務する制度です。シフト制には、法定労働時間の範囲内で運用する限り、必ずしも労使協定の作成・提出が必要ない点、勤務時間が不規則になりやすく、人材確保が難しい点なども特徴として挙げられます。
関連記事:変形労働時間制とシフト制の違い!併用は可能?メリットやデメリットも解説
9. 変形労働時間制のデメリットは勤怠管理システムの導入などでカバーしよう

今回は、変形労働時間制のメリット・デメリットやうまく運用するためのポイントなどを解説しました。変形労働時間制は、うまく運用すれば、企業の業務効率を飛躍的に高められる制度です。さらに、従業員のワークライフバランス向上も見込めます。
その一方で、新制度導入直後には運用方法を誤ってしまったり、従業員からの不満が噴出したりするおそれもあるものです。まずは制度導入の担当者が十分に内容を理解し、従業員に周知することが大切です。また、制度導入と同時に新たな勤怠管理システムを導入するなどの工夫を講じ、導入失敗のリスクを防ぎましょう。