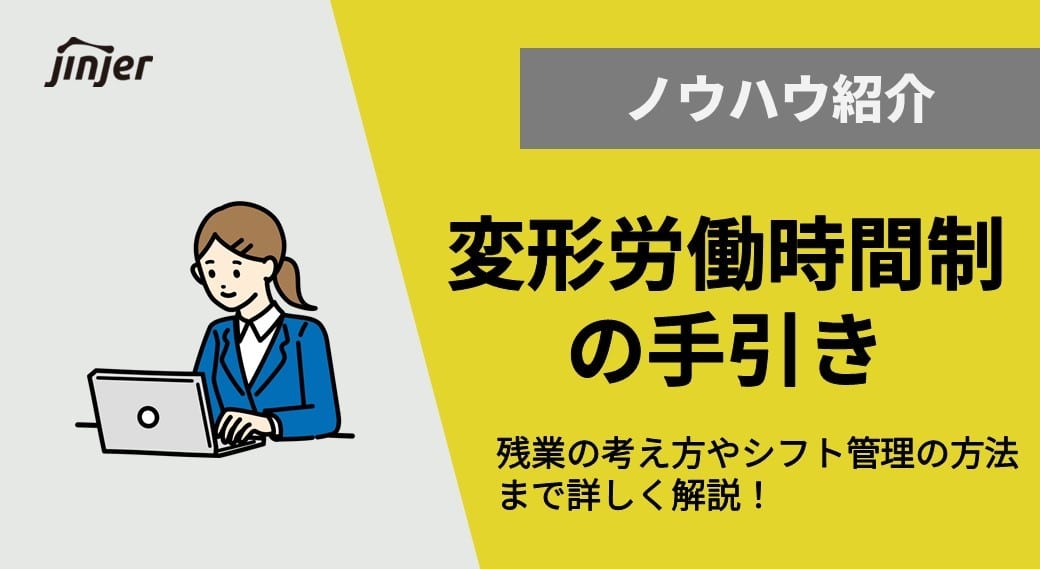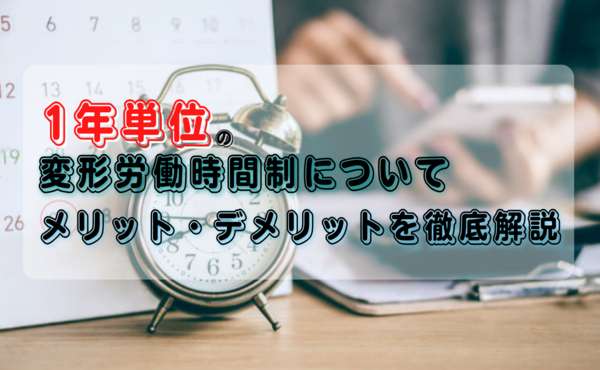
変形労働時間制を導入する際は、1ヵ月や1年などの単位を設定します。1ヵ月単位の変形労働時間制は、月内で繁忙期と閑散期が分かれている場合に効果的です。しかし、大規模な工事などをおこなっているなど、1ヵ月を通じて忙しいというケースもあります。そのような場合は、1ヵ月単位よりも1年単位の変形労働時間制のほうが効果的です。
本記事では1年単位の変形労働時間制について詳しく解説します。これから1年単位の変形労働時間制の導入を考えているという企業は、ぜひ参考にしてみてください。
変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 1年単位の変形労働時間制の定義
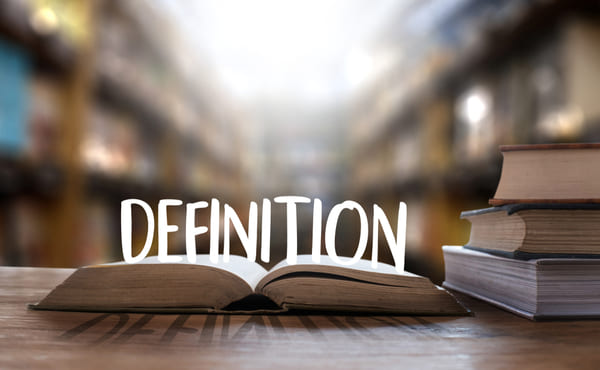
そもそも変形労働時間制とは、特定の日・週の所定労働時間について法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて設定したとしても、対象期間(1ヵ月または1年など)を通じて、平均して週40時間以内に収まっていれば、法定労働時間を超えた分を時間外労働(法定外残業)とはみなさない制度です。
まずは、1年単位の変形労働時間制の定義や導入率について確認しておきましょう。
1-1. 1年単位の変形労働時間制の定義
1年単位の変形労働時間制とは、1年間を通じて労働時間を調整し、週平均で40時間以内に収まる範囲で、一部の期間に1日8時間・週40時間を超えて働かせることができる制度です。1年単位の変形労働時間制の具体的な条件は以下の通りです。
- 対象期間が1ヵ月を超え1年以内(1ヵ月以内を対象にはできない)
- 対象期間の1週間の平均労働時間が40時間以下
- 労働時間が1日10時間・1週52時間以内(これ以上の労働をさせることはできない)
- 1年当たりの労働日数の限度は280日
- 連続して労働させる日は連続6日(特定期間は12日)が上限
- 対象期間の労働日・労働日ごとの労働時間を特定する
1-2. 1年単位の変形労働時間制における法定労働時間の上限
1年単位の変形労働時間制を採用した場合、法定労働時間の上限は以下のようになります。
- 365日の場合:2085.7時間
- 366日(閏年)の場合: 2091.4時間
1年単位の変形労働時間制を導入する際は、所轄の労働基準監督署に届出をする必要がありますが、その際は上記の条件を満たしているかどうかをチェックされます。条件が満たされていないと、1年単位の変形労働時間制を利用できないので注意してください。
このように変形労働時間制では通常の労働形態とは異なり、1日8時間・1週40時間を超過した労働においても時間外労働とならないなど、通常の労働形態とは異なるルールが多数あります。また、単位も1年のほかに、1週、1ヵ月がありますが、自社にどの期間の変形労働時間制が最も適切かわからず悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当サイトでは、変形労働時間制の種類のおさらいや、導入するにあたり注意すべき点などをわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。変形労働時間制の概要を理解し、自社に適切な制度であるか知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1-3. 1年単位の変形労働時間制の導入率
変形労働時間制には、1年単位以外にも1ヵ月単位、フレックスタイム制などの種類があります。厚生労働省が公表した「令和6年 就労条件総合調査」によると、変形労働時間制のなかでも、1年単位の変形労働時間制が最も多く利用されていることがわかります。
それぞれの割合は以下の通りです。
- 1年単位:32.3%
- 1ヵ月単位:25.2%
- 1週間単位:1.4%
- フレックスタイム制:7.2%
1-4. 1ヵ月単位の変形労働時間制との違い
1ヵ月単位の変形労働時間制との大きな違いは、1日や1週の労働時間の上限があるかどうかです。前述の通り、1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間・週52時間以内という範囲内で運用しなければなりません。
一方で1ヵ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、1ヵ月以内の期間を平均して、1日8時間・週40時間以内となるように調整できます。つまり、1日あたりの労働時間については、とくに制限はありません。
関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制とは?残業の考え方や届出の流れをわかりやすく解説!
2. 1年単位の変形労働時間制における残業の考え方・計算方法

1年単位の変形労働時間制における残業の考え方は少し複雑です。しかし、理解してしまえばそれほど難しいものではありません。ここでは、残業時間の考え方や注意点、残業代の計算方法を解説します。
2-1. 残業時間の考え方と計算方法
まず、1年単位の変形労働時間制を就業規則に記載する際に、所定労働時間を定める必要があります。1年単位の変形労働時間制では、就業規則に定めた所定労働時間を超えた分を残業としてカウントします。このとき、月単位で労働時間が変化しても問題ありません。なお、1時間残業した翌日に1時間早く早退をしたとしても、残業をなかったことにはできないため注意してください。
たとえば、1〜3月の業務時間は9時〜20時(1日の所定労働時間10時間)、4〜6月の業務時間は9時〜17時(1日の所定労働時間7時間)のように、規定内であれば所定労働時間を変更して設定することが可能です。
この場合、1月に21時まで仕事をしたとしたら、1時間分の時間外労働(法定外残業)が発生したとみなされます。一方、4月に21時まで仕事をした場合は、法定労働時間を超えた3時間が時間外労働(法定外残業)になります。なお、所定労働時間を超えたけれど、法定労働時間を超えない1時間分の労働については、法定内残業とみなされ、通常の賃金の支払いは必要になるので気を付けましょう。
関連記事:変形労働時間制の残業時間の上限とは?残業代や割増賃金の計算方法も解説!
2-2. 1年単位の変形労働時間制における残業を計算する際の注意点
先ほどの解説で、1年単位の変形労働時間制における、1日あたりの残業の計算方法は理解できたかと思います。さらに、1年単位の変形労働時間制では、1日あたりに加え「1週あたり」「1年間あたり」の残業も集計しなくてはなりません。
1週あたり・1年間あたりの考え方も同様で、それぞれの所定労働時間を超えた分が残業時間となります。通常、1週あたりの時間外労働(法定外残業)となる労働時間は40時間を超えた分からですが、変形労働時間制では、週の所定労働時間を50時間に定めた場合、50時間を超えた分からが時間外労働(法定外残業)となります。また、1年あたりの時間外労働(法定外残業)は、2,085時間(閏年は2,091時間)を超過した分からとなります。
ただし、法定労働時間よりも所定労働時間を短く設定する場合は、1日あたりの残業の考え方と同様で、法定労働時間を超えた分から時間外労働(法定外残業)となるので注意が必要です。また、休日においては、連続して労働できる上限日数は6日で、最低でも85日の年間休日を付与しなくてはなりません。
2-3. 1年単位の変形労働時間制での残業代の計算方法
1年単位の変形労働時間制の場合、時間外労働として割増賃金(法定外残業代)を支払うのは以下のケースです。
|
単位 |
所定労働時間 |
時間外労働(法定外残業)として扱う時間 |
|
1日あたり |
所定労働時間が8時間以内の場合 |
8時間を超えた分から |
|
所定労働時間が8時間を超える場合 |
所定労働時間を超えた分から |
|
|
1週間あたり |
所定労働時間が40時間以内の場合 |
40時間を超えた分から |
|
所定労働時間が40時間を超える場合 |
所定労働時間を超えた分から |
|
|
1年間あたり |
2,085時間を超えた分から (閏年は2,091時間) |
1年単位の変形労働時間制であっても、割増率は通常の残業と変わりません。時間外労働には1.25倍(月60時間超えは1.5倍)、休日労働には1.35倍、深夜残業には1.5倍の賃金を支払います。
残業代は「残業時間 × 1時間あたりの賃金 × 割増率」で求めることが可能です。1年単位の変形労働時間制であっても、所定労働時間や1年あたりの労働時間の上限を超えると残業となります。法令に基づいた賃金を支払うためには、給与の計算はもちろん、対象従業員の労働時間を正しく把握することが大切です。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
3. 1年単位の変形労働時間制のメリット
 1年単位の変形労働時間制には多くのメリットがあります。メリットをしっかりと理解しておくことで、より効果的に1年単位の変形労働時間制を活用できるでしょう。
1年単位の変形労働時間制には多くのメリットがあります。メリットをしっかりと理解しておくことで、より効果的に1年単位の変形労働時間制を活用できるでしょう。
3-1. 残業に関するコストを削減できる
1年単位の変形労働時間制を導入すれば、繁忙期の所定労働時間を延長することが可能です。そのため、残業代の削減を図れるというメリットがあります。。もちろん、他の月の所定労働時間は通常よりも短くなっているのですが、1年単位で考えたときに働いている時間は変わっていないので大きな問題ではないでしょう。
残業代は非常に大きな支出なので、少しでも減らしたいと考えている企業も多いのではないでしょうか。残業代を減らして経営を安定させたいという場合は、ぜひ1年単位の変形労働時間制の活用を検討してみてください。
3-2. 総労働時間を減らせる
先ほど、1年間を通して総労働時間は変わっていないと説明しました。総労働時間が変わらないようにルールを設定することもできますが、閑散期の労働時間を減らすことも可能です。これによって労働者の休息時間が増えます。
たとえば、閑散期であっても所定労働時間が8時間と設定されていれば、その通りに働かなくてはいけません。仕事が少ないにも関わらず、長時間出社しなくてはいけないというのは非常に非効率です。
このような場合、1年単位の変形労働時間制を採用すれば、閑散期の所定労働時間を短縮することができます。閑散期の労働時間を削減することで、ワークライフバランスが整い、労働者にとってはより働きやすい職場になっていくでしょう。
3-3. 企業のイメージアップにつながる
企業のイメージアップを図れることも、1年単位の変形労働時間制を導入するメリットです。前述の通り、繁忙期と閑散期の労働時間をうまく調整すれば、労働者の休息時間を確保し、働きやすい職場環境を構築することができます。
忙しい時期はあるものの、しっかりと休める期間を設けていることで、ホワイトな企業というイメージが浸透していくでしょう。その結果、入社したいという人材が増え、採用活動がうまく進むことも期待できます。
4. 1年単位の変形労働時間制のデメリット
 1年単位の変形労働時間制はメリットばかりのようにも思えますが、デメリットもあります。デメリットをよく理解したうえで、1年単位の変形労働時間制を導入するかどうか検討してください。
1年単位の変形労働時間制はメリットばかりのようにも思えますが、デメリットもあります。デメリットをよく理解したうえで、1年単位の変形労働時間制を導入するかどうか検討してください。
4-1. 就業規則を改定する必要がある
1年単位の変形労働時間制を導入する際は、就業規則を改訂しなくてはいけません。就業規則に則った所定労働時間に基づいて労働時間の算出をおこなう必要があるので、必要があれば所定労働時間から見直さなくてはいけなくなるかもしれません。そのほか、後述するような手続きが必要となるので注意しましょう。
4-2. 労働時間の管理が難しくなる
1年単位の変形労働時間制を導入すると、週や月ごとの所定労働時間が変わるので、労働時間の管理が複雑になります。勤怠管理をおこなう部署の業務量が増える可能性があるため、必要に応じて勤怠管理ツールを導入して厳格に管理しなければいけません。
4-3. 労働者の理解が得られない可能性がある
1年単位の変形労働時間制の場合、閑散期は繁忙期に比べ残業代が少なくなります。そのため、閑散期の収入が減り、従業員の生活に影響を及ぼす可能性もあります。労働時間が多くても収入が増えるなら問題ない、と考える労働者もいるかもしれません。このような従業員に理解を求めなくてはならないのは、デメリットといえるでしょう。
4-4. 社内の連携が難しくなる
会社全体ではなく、一部の部署だけに1年単位の変形労働時間制を採用するという方法もあります。しかし、部署によって就業時間が変わってしまい、部署間の連携に支障が出る可能性があります。業務が円滑に進まないなどのトラブルが発生する恐れもあるため、導入前にしっかりと検討しておきましょう。
関連記事:変形労働時間制を採用するデメリット・メリットをわかりやすく解説
5. 1年単位の変形労働時間制を導入するときの流れ

ここでは、1年単位の変形労働時間制を導入する際の流れとポイントについて解説します。手続きをスムーズに進められるよう、確認しておきましょう。
1年単位の変形労働時間制を導入する流れは、以下の通りです。
- 労使協定を締結する
- 就業規則を改定する
- 36協定を締結する
- 労働基準監督署へ届け出る
- 従業員に周知する
1年単位の変形労働時間制は企業・従業員の双方にメリットがありますが、すべての従業員が快く受け入れてくれるとは限りません。1年単位の変形労働時間をスムーズに導入するには、就業規則の改定と労使協定の締結が重要なポイントです。
5-1. 労使協定を締結する
1年単位の変形労働時間を導入するためには、労使間で話し合いをおこなったうえで、労使協定を締結しなければなりません。
労使協定に定める主な項目と概要は、下表の通りです。自社の事業や従業員の労働時間などを考慮して定めましょう。
|
項目 |
概要や注意点 |
|
対象となる従業員の範囲 |
|
|
対象期間 |
|
|
対象期間の起算日 |
|
|
対象期間における労働日・労働日における労働時間 |
|
|
特定期間 |
|
|
労使協定の有効期間 |
|
労使協定においてとくに重要なのは「対象期間における労働日・労働日における労働時間」です。法的な制限、業務量や従業員の負担なども考慮しながら決定しましょう。
なお、労使協定で締結した労働日・労働時間は任意に変更できません。しかし、数ヵ月先の勤務スケジュールを決めるのは困難な企業もあるため、対象期間を1ヵ月以上の期間に区分する場合は、以下のような特例が認められています。
- 最初の期間における労働日・労働日ごとの労働時間を決める
- その後の各期間における具体的な労働日・所定労働時間を定めなくても労使協定を締結することが可能
ただし、労働日や労働時間が直前まで知らされないことは、従業員にとって不利益となる場合があります。そのため、対象期間が始まる30日前までには従業員に勤務スケジュールを通知しましょう。
5-2. 就業規則を改定する
労使協定をもとに就業規則を改定します。就業規則には、始業・終業時刻、休憩時間および休日を記載しなくてはなりません。
1年単位の変形労働時間制の場合の就業規則の具体例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
第○条 労使協定により、1年変形労働時間制を採用する。所定労働時間は、対象期間を平均して1週あたり40時間以内とする。ただし、1年変形労働時間制が適用されない場合については1週40時間とする。
2 1日の所定労働時間は9時間とし、始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。
一、始業…9時
二、終業…19時
三、休憩時間…12時から13時までの60分間
3 第1項の対象期間は1年間とし、起算日は毎年4月1日とする。
第○条 休日は次のとおりとする。
一、日曜日
二、国民の祝日および国民の休日
5-3. 36協定を締結する
1年単位の変形労働時間制でも、設定した所定労働時間や法定労働時間を超える労働が発生する可能性がある場合は36協定を締結します。
そもそも、36協定は「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。変形労働時間制を採用する企業であっても、時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結が必要となります。なお、36協定は労使協定で締結したあと、労働基準監督署に届け出ることで効力を持つため、手続きを滞りなく済ませましょう。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
5-4. 労働基準監督署へ届け出る
就業規則を変更したり、労使協定を締結したりした場合は、労働基準監督署へ届出をしなければなりません。前述の通り、36協定についても同様です。
また、労使協定には有効期限があり、期限がきたタイミングで再度届け出る必要があるため忘れないようにしましょう。
5-5. 従業員へ周知する
変形労働時間制を導入するときは、従業員へ丁寧に説明することが重要です。通常の勤務形態とは異なり、労働時間や残業の考え方が複雑であるため、わかりやすく説明しましょう。必要に応じて、朝礼や全体会議などで説明することも重要です。
6. 1年単位の変形労働時間制を導入する際のポイント

1年単位の変形労働時間制を導入するときは、以下のような点に注意しましょう。
6-1. 1年単位の変形労働時間制に適しているか確認する
変形労働時間制を導入するときは、事業形態について確認しておくことが重要です。先ほども説明しましたが、1年単位の変形労働時間制が適しているかどうかは、事業内容や職場環境などによって大きく異なります。
たとえば、1年を通して繁忙期と閑散期にそれほど差がないという業種の場合は、高い効果を期待できないかもしれません。導入には手間もかかるため、まずは自社に適しているかを確認しておきましょう。
6-2. 従業員の負担にならないように配慮する
1年単位の変形労働時間制が労働者の負担とならないように配慮しましょう。制度を導入すると繁忙期の労働時間が長くなるため、労働者にとってはかなりの負担になってしまう可能性もあります。繁忙期の労働時間を増やしすぎない、収入が大幅に減らないように調整するなどの工夫も必要です。
6-3. 試験的に導入してみる
変形労働時間制を効果的に運用するのはなかなか困難です。試しに1部門だけで導入してみるというのも効果的かもしれません。さまざまな方法を検討して、自社にとって1年単位の変形労働時間制が本当に必要な制度かどうかを判断してください。
7. 1年単位の変形労働時間制のメリット・デメリットを理解して導入しよう
 1年単位の変形労働時間制は、会社側にもプライベートを優先したい社員側にもメリットがある制度です。しかし、一部の社員からすればあまり嬉しくない制度かもしれません。そのため、導入する前に一度社員にアンケートなどをとり、本当に導入しても問題ないかを確認してください。
1年単位の変形労働時間制は、会社側にもプライベートを優先したい社員側にもメリットがある制度です。しかし、一部の社員からすればあまり嬉しくない制度かもしれません。そのため、導入する前に一度社員にアンケートなどをとり、本当に導入しても問題ないかを確認してください。
1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、さまざまな規定を守って労働日や労働時間を設定しましょう。また、法定労働時間を超える労働は時間外労働(法定外残業)となるので、割増賃金の支払いが必要です。
変形労働時間制は労働時間の管理が複雑になるため、労働時間の把握や給与計算にミスが生じやすくなります。1年単位の変形労働時間制を導入する際は、勤怠管理の方法や給与システムの見直しなどもおこないましょう。
変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。