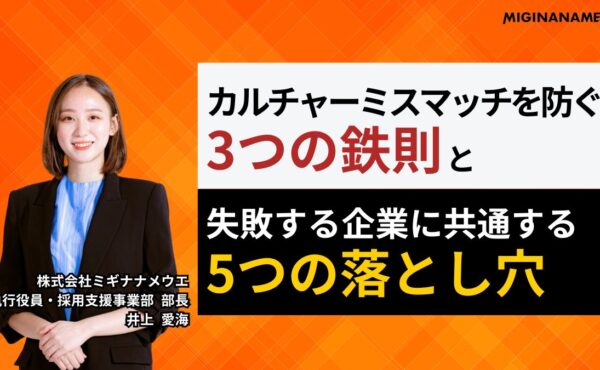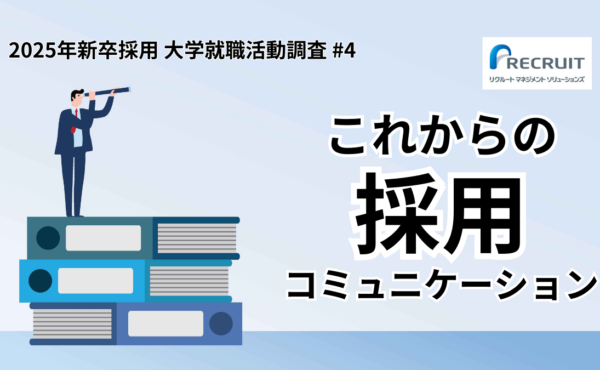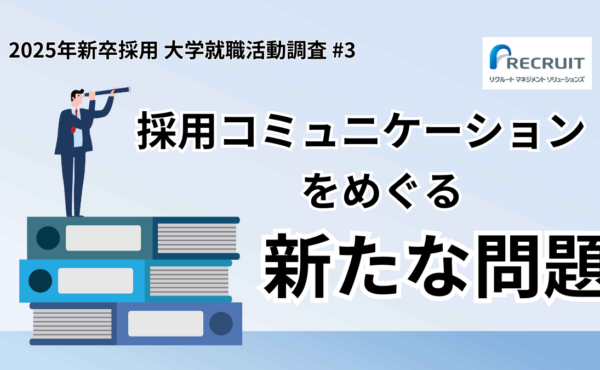採用広報とは、自社の魅力や価値観を伝え、優秀な人材を引き寄せるためにおこなう広報活動のことです。人材確保が困難な現代において、採用広報は重要な役割を担います。この記事では、採用広報とは何か、メリットや活用事例を踏まえてわかりやすく解説します。また、採用広報の戦略設計のコツやポイントについても紹介します。
1. 採用広報とは?

採用広報とは、自社に興味・関心を持ってもらい、採用につなげるために求職者に対しておこなわれる広報活動のことです。ここでは、採用広報が注目される背景や理由と、採用広報を担当する部署・部門について紹介します。
1-1. 採用広報が注目される背景や理由
採用広報が注目されている理由の一つとして、採用が売り手市場になっていることが挙げられます。少子高齢化による労働人口の減少や、働き方改革による人材の流動化の影響により、人材確保に課題を抱えている企業は多く、優秀な人材を獲得するための競争が激化しています。
また、テクノロジーの発展により、採用広報ツールの多様化が進んでいることも、採用広報が注目されている理由の一つです。従来の人材紹介や求人サイトだけでなく、デジタル技術を活用したソーシャルメディアや、ダイレクトリクルーティングサービスなど、採用活動に用いられるツールは多角化しています。
このような背景もあり、今までのように「求人サイトに求人広告を掲載する」「学校へ求人票を送付する」「自社採用HPで募集をかける」「採用パンフレットを用意する」といった「待つ」施策だけでは母集団形成が難しい時代になりつつあります。いかに自社を知ってもらうか、他社と差別化できるかが大きなポイントであり、採用広報の重要性が高まっています。
関連記事:新卒採用の母集団形成の方法とは?メリットや注意点も解説!
1-2. 採用広報を担当する部署・部門はどこ?
採用広報を採用活動のプロセスの一つとして、人事部署・採用部門が担うことが多いです。また、採用と広報を切り離し、人事部門と広報部門が連携しながら採用広報に取り組んでいる企業もあるようです。しかし、人事・広報部門だけで、採用広報を進めてしまうと、発信する内容が現場と乖離していまい、ミスマッチを引き起こす原因にもなりえます。そのため、採用広報を主に担当する部署・部門を定めたとしても、必要に応じて連携しながら、組織全体で採用広報を作り上げる体制を構築することが大切です。
関連記事:そもそも「人事」とは何なのか?企業経営に必須の人事担当者の仕事内容を徹底解説!
2. 採用広報のメリット

採用広報に取り組むことで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、採用広報のメリットについて詳しく紹介します。
2-1. 自社の認知度を高められる
採用広報に取り組み、積極的に自社の仕事内容や魅力などの情報を発信することで、既に転職する業界や業種を定めて活動している「顕在層」だけでなく、良い条件の会社があれば転職したいと考えているだけで行動はしていない「潜在層」にもアプローチすることができます。自社の存在を幅広い人に知ってもらえるので、認知度アップが期待できます。
2-2. 採用にかかるコストを下げられる
採用広報に力を入れることで、自社がどのような企業で、どのような人材を募集しているかを詳細に伝え、自社とマッチする候補者の入社意欲を高めることが可能です。これにより、求人サイトや人材紹介などの既存の採用手法での成果が上がる可能性があります。また、採用広報をおこなっているメディアや、自社ホームページからの応募が増えることで、採用コストを減らすこともできるかもしれません。
2-3. ミスマッチを防止できる
採用パンフレットとイベント説明会などの採用手法の場合、時間やリソースに限りがあり、伝えられる内容を絞らなければならないケースも少なくありません。待遇や評価に興味をもって入社してみたけれど、自社の文化や仕事の進め方にあわず、モチベーションが下がり、離職してしまう従業員もいます。
採用広報を充実させることで、自社の魅力に加えて、現場の雰囲気や仕事の具体的な取り組み方など、多くのリアルな情報を届けることが可能です。採用広報の内容に共感を覚えた候補者が入社すれば、入社前と入社後のギャップを減らし、ミスマッチを防止して定着率を高めることができます。
3. 採用広報の戦略設計のコツやポイント

採用広報の重要性を理解できても、適切な方法で進めなければ効果は出ません。ここでは、採用広報の戦略設計のコツやポイントについて詳しく紹介します。
3-1. ターゲット層を言語化して明確にする
採用広報の目的を明確にし、どのような人に情報を届ける必要があるのか、ターゲット層を言語化して明確にすることが大切です。ただ闇雲に自社情報を発信するのではなく、ターゲット層のニーズにあわせて的確に情報を発信することが重要といえます。
3-2. 採用広報の方法や媒体を適切に選定する
ターゲット層を言語化して明確にできたら、目的やそのターゲット層にあわせて採用広報に用いる方法や媒体を選びます。たとえば、ピンポイントで優秀な人材にアプローチしたいのであれば「ダイレクトリクルーティングサービス」がおすすめです。一方、新卒入社者の離職率を抑えたいのであれば「SNS」「オウンドメディア」などを利用して、入社前後でのギャップをなくすためのリアルな情報を届けることが重要です。このように、目的やターゲット層にあわせて最適な方法を活用することで、採用広報の効果を高めることができます。
3-3. 発信するコンテンツの内容を決める
ターゲット層や使用する媒体が明確になったら、発信するコンテンツを決めましょう。発信情報に一貫性がないと、候補者は混乱してしまう恐れがあります。発信する内容が本当に正しい情報なのかもきちんとチェックすることが大切です。
また、情報が多すぎると、候補者は理解しにくい可能性があります。一方、情報が少ないと、候補者は物足りないと感じてしまいます。そのため、情報量にも気を配って発信することが重要です。場合によっては、候補者からどのような情報が欲しいかを聞いてみるのもおすすめです。
3-4. 組織全体で取り組む
採用広報の運用環境が整備できたら、実際に情報を発信してみましょう。人事・広報担当者だけでは、十分に現場の声を届けることができない可能性もあります。そのため、現場にヒアリングしたり、アンケートを取ったりすることが必要になるケースもあります。このように、採用広報は組織全体で取り組むことが成功のコツです。採用広報に取り組むにあたり、あらかじめ現場の協力を得られるような体制を構築しておきましょう。
3-5. 評価と改善を実施する
採用広報に取り組んでみた結果に対して評価をおこなうことで、正しく成果を確認することができます。最初に立てた目的に対してどのような効果が得られたかをチェックしましょう。効果が出ていない場合は、原因を分析して、改善を繰り返すことで、採用広報の質を高めることができます。
関連記事:KPIとは?メリット・デメリットや設定のポイントをわかりやすく解説!
4. 採用広報の主な手法

採用広報によく用いられる手法に「トリプルメディア戦略」があります。トリプルメディア戦略とは「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」の3つにメディアを区分して、それぞれの特徴を活かした戦略を実施することです。ここでは、3つのメディアの意味や定義と、それぞれのメディアに属する媒体について詳しく紹介します。
4-1. オウンドメディア
オウンドメディアとは、自社で保有しているメディアの総称を指します。代表的なオウンドメディア媒体として、下記が挙げられます。
- コーポレートサイト
- 自社の採用ホームページ
- 自社のブログ
オウンドメディアは自社で開発・運用しているため、カスタマイズ性の高さが特徴です。開設してすぐに効果が出ることはあまりありません。しかし、継続的に改善し、ノウハウを蓄積させることで、コストを抑えながら自社の魅力を効果的に伝えることができます。
関連記事:オウンドメディアリクルーティング|効果的な活用方法を紹介
4-2. ペイドメディア
ペイドメディアとは、企業が費用を支払ったうえで広告を掲載してもらう従来型のメディアを指します。代表的なペイドメディア媒体として、下記が挙げられます。
- テレビ
- ラジオ
- 新聞
- 雑誌
- Web広告
- 求人サイト
- 採用イベント
- トレインチャンネル
ペイドメディアは技術の発展に伴い、幅広い形態が登場しています。ペイドメディアは影響力が大きいため、短期間で多くの人にアプローチすることが可能です。ただし、費用を支払って利用するので、コストに見合った効果が得られない恐れがあります。そのため、オウンドメディアやアーンドメディアと組み合わせて利用することが推奨されます。
4-3. アーンドメディア
アーンドメディアとは、有料広告ではなく、消費者や利用者、メディア関係者などの自社と直接関わりのない第三者が発信するメディアを指します。代表的なアーンドメディア媒体として、下記が挙げられます。
- 個人ブログ
- 口コミ・レビューサイト
- SNS(X、Instagram、TikTok、YouTube、Facebookなど)
アーンドメディアはコストが不要ですが、情報発信をおこなうのは第三者であるため、自社でコントロールすることが難しいです。また、拡散力が高く、リスクが大きいことも押さえておきましょう。アーンドメディアを活用する場合、媒体の選択やコンテンツの決定を慎重におこなうことが大切です。また、アーンドメディアから得られたリアルな情報を基に、自社の体制を見直すことも重要といえます。
関連記事:SNSでの採用活動とは | アメリカ企業の94%が検討しているワケ
5. 採用広報の活用事例

ここでは、採用広報を活用したい事例について紹介します。事例を参考にして、ぜひ自社でも採用広報に取り組んでみてください。
5-1. 採用コストを抑えたい
採用予定人数が少なく、コストを抑えたい場合、採用広報に「ダイレクトリクルーティングサービス」を活用してみるのがおすすめです。ダイレクトリクルーティングは採用担当自らが動いて求職者に自社の魅力を伝えていくことが求められるため、営業力や広報力がより必要になってきます。たとえば、スカウトメールによりアプローチする、ミートアップのイベントを開催するなど、求職者に興味を持ってもらう機会をつくり、自社の魅力や募集職種などを的確に伝えましょう。
関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?メリット・デメリットや新卒・中途向けサービスを解説!
5-2. 応募が集まらない
募集職種によっては「未経験歓迎」「やる気があれば歓迎します」と幅広く募集をかけても集まらない職種もあります。その場合、動画機能がついた求人サイトや、YouTubeなどの動画サイトを利用し、候補者に強く訴えかけてみるのも一つの手です。募集職種がどのような仕事なのか、仕事をしている現場を撮影して提供することで、一生ものの技術を身につけたいと思って仕事を探している人や、技術職に興味を持っている人の心に訴えることができます。
関連記事:採用動画サービス7選|企業の魅力を伝える採用動画のメリットとは
5-3. 入社後のミスマッチが多い
入社後のミスマッチが多い原因として、入社前に伝える情報が実際と乖離していたり、そもそも情報が不足していたりする可能性が考えられます。そのため、発信内容を見直すことが大切です。
たとえば、自動車製造に使用する部品設計者を募集する際に「本社での設計」と記載すると、本社で設計をする内勤のイメージを持つ可能性が高くなります。しかし、実際は自動車メーカーに出向いてクライアントと話し合いながら設計をして、製造部門と調整までする仕事であれば、設計だけでなく営業的要素も入ってきます。このような場合、ミスマッチを起こす可能性があります。仕事のやりがいだけでなく、仕事における困難な部分、課題などのマイナスイメージも記載し、そのうえで「この仕事をやりたい」という人に応募してもらうようにしましょう。
求人サイトや採用ホームページで募集職種の紹介に枠を多めに取る、SNSで1日の行動スケジュールを紹介するなど、候補者が働くイメージを持てるようにすることが重要です。応募要件に「求める人材」の要素を詳しく記載して、求職者が自分に当てはまるかチェックできるようにするのも効果的です。
5-4. 企業の知名度が低い
企業の知名度が低い場合、「採用広報」だけでなく、「企業広報」にも力を入れることが大切です。たとえば、大田区を盛り上げたいという想いから生まれたプロジェクト「下町ボブスレー」のようなユニークな取り組みを大々的にアピールすることで、求職者が企業に関心を持ち、さらなる情報を求めてホームページなどにアクセスする可能性が高まります。また、自社の知名度を高めるため、「世界に誇る技術」「日本で唯一手作り」など、自社の強みを積極的に外部に発信することで、自社の認知度が上がり、効果的な採用広報にもつながっていきます。
6. 採用広報を活用して効率よく採用活動を進めよう

採用広報で最も大切なことは、自社の「求める人材」を明確化かつ言語化することです。「求める人材」が曖昧になってしまうと、いくら予算と時間をかけても良い人材を採用することができません。また、採用広報のやり方やそれに関するツールは変化の動きが早いため、現在はどのようなツールがあるのかを常にリサーチするように心がけることも大切です。採用広報に力を入れて、効率よく採用活動を進めましょう。