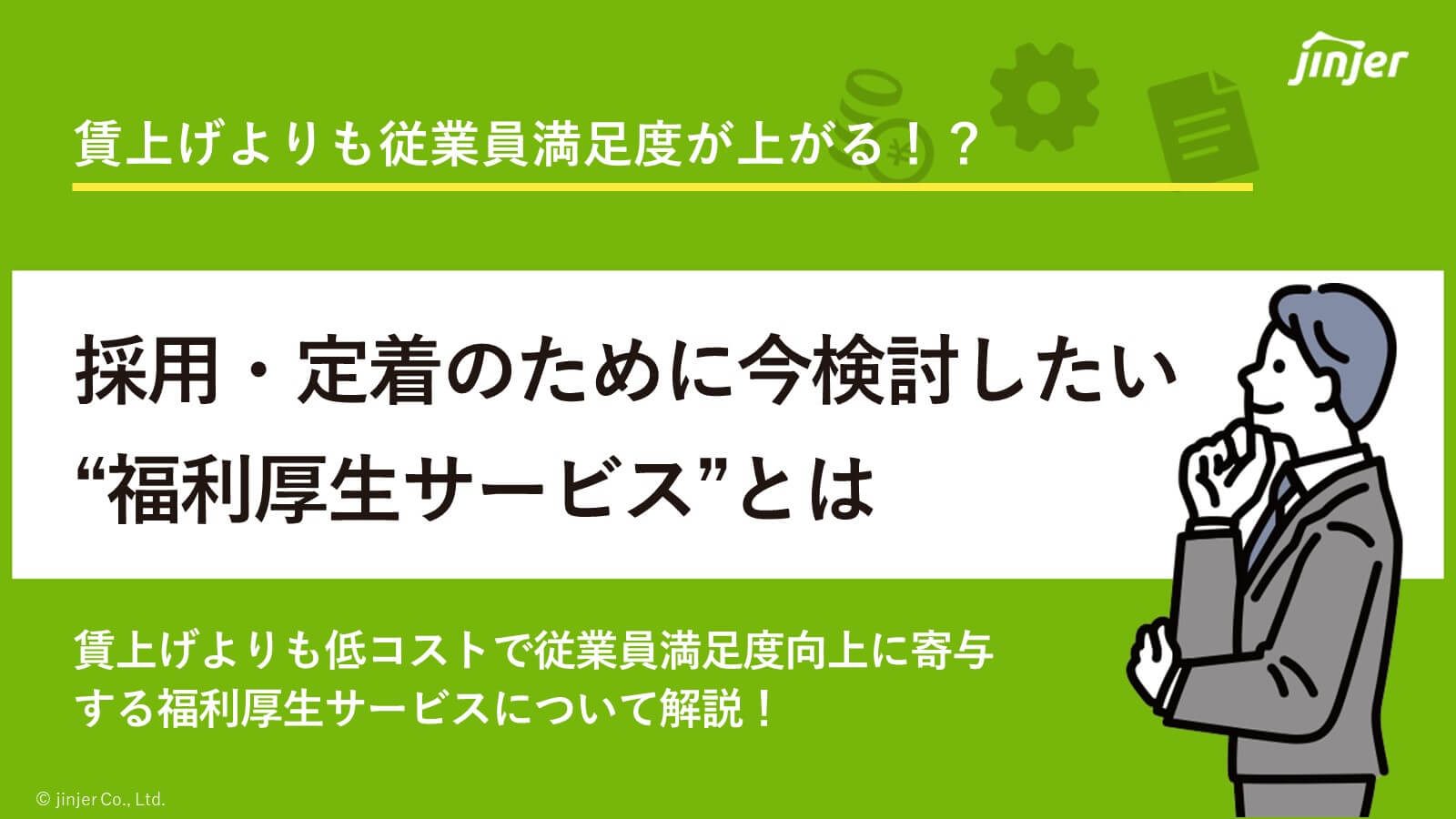「福利厚生が非課税になる要件は?」
「福利厚生が非課税になる事例は?」
「福利厚生が非課税の場合の経理処理が知りたい!」
人事労務担当として従事するうえで、上記のような疑問を感じる場面もあるでしょう。
法定福利厚生は原則として非課税である一方、法定外福利厚生は一定の要件を満たさなければ課税対象となります。法定外福利厚生を非課税として経理処理するためには、要件について深く理解しなければなりません。
本記事では福利厚生の非課税に関する要件・事例・経理処理について詳しく解説します。福利厚生を活用した企画を検討する場合や経費の申請をおこなう場合は、ぜひ参考にしてください。
▼そもそも福利厚生とは何かを知りたい方はこちら
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 法定福利厚生は原則として非課税

法定福利厚生は法律で設置が義務化されている福利厚生であり、原則として非課税とされています。法定福利厚生に含まれる項目は以下の6つです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
- 子ども子育て拠出金
上記に該当しない「通勤手当」や「食事手当」などは、法定外福利厚生に分類されます。法定外福利厚生とは、法律で設置が義務化されていない福利厚生のことです。
法定外福利厚生は条件によって課税されるケース・非課税になるケースに分けられるため、要件を正しく理解しなければなりません。
▼法定福利厚生の社会保険について詳しく知りたい方はこちら
福利厚生と社会保険の関係性とは?2024年10月より適用される社会保険の概要を解説
2. 法定外福利厚生が非課税になる4つの要件
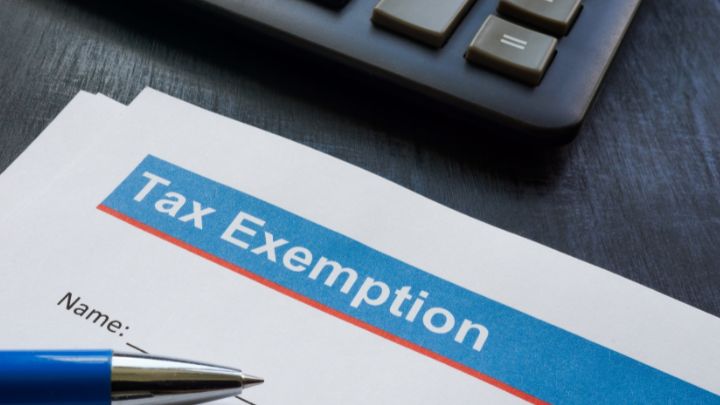
法定外福利厚生を非課税にするには、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 全従業員が利用できる
- 費用が一般的な金額である
- 非課税となる上限金額を超えていない
- 現金による支給ではない
それぞれの要件について詳しく確認しておきましょう。
2-1. 全従業員が利用できる
全従業員が利用できる法定外福利厚生は、非課税の対象とされます。一部の従業員・役員しか利用できない法定外福利厚生は課税されるため、福利厚生費として処理できません。
ただし、全従業員が対象となっており、従業員本人の意思で利用していない場合は、福利厚生費として処理することが可能です。
2-2. 費用が一般的な金額である
福利厚生にかかる費用が一般的な金額であれば、非課税の対象となります。ただし、社会的に高額であると判断された場合は、福利厚生費として認定されません。
たとえば、新入社員の歓迎会を開催するために、1人10万円もの費用を支給する場合、一般的な金額を超えていると見なされ課税されるでしょう。
2-3. 非課税となる上限金額を超えていない
法定外福利厚生の種類によっては、上限金額が設けられている場合もあります。それぞれの上限金額を超えてしまうと、課税されるため注意しましょう。
2-4. 現金による支給ではない
現金による支給の場合、給与と見なされ課税されます。また、商品券やギフト券などのように換金性の高いものも同様です。福利厚生を目的として支給したとしても、課税対象となるため注意しましょう。
関連記事:福利厚生と給与の違いは?どちらか判断する基準を紹介!
3. 法定外福利厚生が非課税対象になる事例7選

法定外福利厚生が非課税対象になる事例について、以下7つを紹介します。
- 通勤手当
- 葬祭料・香典・見舞金
- 食事の支給
- レクリエーション
- 社内イベント費用
- 育児・介護費用
- スキルアップ費用
それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。
3-1. 通勤手当
従業員や役員の通勤手当は、一定の金額を超えなければ非課税の対象です。国税庁では、課税されない通勤手当の金額を明記しています。それによると、通勤手当は1カ月あたり15万円を超えなければ課税されません。もし1カ月15万円を超える場合は、給与として課税されるため注意してください。
参照:No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
3-2. 葬祭料・香典・見舞金
従業員本人や従業員の親族が亡くなった場合に支払われる慶弔見舞金は、社会通念上相当とされる金品であれば非課税の対象です。また被災した従業員に対する災害見舞金も福利厚生費として扱われ、非課税の対象とされます。
加えて退職した従業員や内定者に対する見舞金も、被災した従業員と同じ基準で支給する場合は福利厚生費として対応可能です。
関連記事:慶弔見舞金とは?種類・相場がいくらかや支給方法を解説
3-3. 食事の支給
企業が従業員に対して社員食堂や弁当などを提供する場合、一定の金額を超えなければ非課税の対象となります。ただし非課税の対象になるには、以下2つの要件をすべて満たさなければなりません。
- 従業員が負担する費用が半額以上である
- 企業の負担額が3,500円(税抜)以下/月である
なお深夜時間に勤務する従業員に対しては、1食につき300円(税抜)以下であれば課税されません。
参照:食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)|国税庁
関連記事:福利厚生における食事補助とは?メリットや導入方法を解説
3-4. レクリエーション旅行
レクリエーション旅行の場合は、以下の条件を満たすことで非課税の扱いを受けられます。
- 旅行の期間が4泊5日以内である
- 旅行の参加者が全従業員の50%以上の人数である
なお以下の場合はレクリエーション旅行に該当しないため、非課税としての処理が認められていません。
- 役員限定の旅行
- 取引先に対する接待・慰安などの旅行
- 私的と認められる旅行
- 参加する代わりに金銭の支給を受けられる旅行
レクリエーション旅行や研修旅行に関する課税の具体例は、以下の国税庁HPを確認してください。
参照:No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁
関連記事:社員旅行は福利厚生費に計上できる?条件やケース別の対応を解説
3-5. 社内イベント費用
一定の条件を満たせば、社内イベントの費用は非課税となります。新入社員の歓迎会や忘年会、新年会などの費用は非課税となる可能性があるため覚えておきましょう。
ただし、非課税として処理するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 全従業員が参加できる
- 全事業所・全部署に開催の権利がある
- 相当数の従業員が参加している
役員のみの懇親会や、特定のチームのみで開催する忘年会などは、非課税対象ではありません。
3-6. 育児・介護費用
育児・介護を補助するための費用も非課税対象となります。たとえば、育児に関する施設を利用したときの費用や、介護用具を購入するための費用の一部などを支給した場合、非課税対象として処理することが可能です。
ただし、支給金額が妥当でなければ課税されるため注意しましょう。
3-7. スキルアップ費用
従業員がスキルアップするための費用も、福利厚生費として計上できます。たとえば、資格試験を受けるための費用や研修会への参加費などは、福利厚生費として認められるでしょう。
4. 法定外福利厚生が課税対象になる事例4選

法定外福利厚生が課税対象になる事例として、以下3つを紹介します。
- 福利厚生を利用できる従業員が限定されている場合
- 法律で定められた上限金額を超えた場合
- 従業員に現金支給をおこなった場合
- 換金性が高い物品の支給をおこなった場合
それぞれの事例について順番に見ていきましょう。
4-1. 福利厚生を利用できる従業員が限定されている場合
「正社員のみ」「パート・アルバイトを除く」など、福利厚生を利用する範囲が限定されていると課税対象となります。「全従業員が利用できる」ことが、非課税の要件であるからです。
また雇用形態で利用を限定するだけでなく、性別・年齢・役職などで利用を限定している場合も課税対象となります。課税対象とならないためにも、全従業員が利用できる福利厚生を検討しましょう。
関連記事:パート・アルバイトも福利厚生は利用できる!適用条件や種類を詳しく解説
4-2. 法律で定められた上限金額を超えた場合
通勤手当や食事補助など、法律で定められた上限金額を超えた場合も課税対象となります。課税対象となると、給与として課税されるため注意しなければなりません。
また、福利厚生にかかる費用が社会通念上相当の金額以上である場合、課税対象となる場合があります。過去には高額な福利厚生費は給与所得に該当する判決が下されているため、福利厚生にかける費用は十分な検討が必要です。
参照:(平22.12.17裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
関連記事:食事補助を福利厚生に取り入れる上限額は?非課税にならないケースや注意点を解説
4-3. 従業員に現金支給をおこなった場合
福利厚生の目的であっても、従業員に現金を支給した場合は課税対象です。たとえば、健康診断や食事の費用などを従業員に立て替えてもらい、後日現金を支給した場合が課税対象に当てはまります。
また従業員に対し、健康診断や食事の費用として現金を前払いした場合も課税対象です。企業側が病院側に支払わないと、非課税の扱いとならないため注意してください。
関連記事:健康診断は福利厚生費に計上できる!条件や注意点を解説
4-4. 換金性が高い物品の支給をおこなった場合
商品券や旅行券など、換金性が高いものを支給すると給与と見なされ、課税対象になります。また、スーツの現物支給も課税対象です。制服とは異なり、特定の企業の従業員であることが判別できないものは、課税対象となってしまいます。
5. 福利厚生が非課税になる場合の経理処理

非課税の福利厚生を経理処理する際は、法定福利厚生と法定外福利厚生で使用する勘定科目が異なります。使用する勘定科目は以下の通りです。
|
福利厚生の種類 |
勘定科目 |
|
法定福利厚生 |
企業負担分:法定福利費 従業員負担分:法定福利費もしくは預り金 |
|
法定外福利厚生 |
福利厚生費 |
法定福利厚生に含まれる社会保険は企業と従業員で費用を負担するため、確認しやすいように勘定科目が異なる場合があります。
また、会計処理の方法によって計上するタイミングが異なるため、企業で採用されている会計処理のルールを確認しましょう。
経費を計上するタイミングについて以下の記事にまとめているため、併せて確認してみてください。
関連記事:経費を計上するタイミングとは?|企業会計で知っておきたい発生主義・現金主義を解説
6. 福利厚生が課税になる場合の経理処理

法定外福利厚生が課税対象になった際、「福利厚生費」ではなく「給与」として経理処理する場合があります。
たとえば企業でレクリエーションをおこなった場合、非課税になる要件を満たせば「福利厚生費」として経理処理が可能です。
しかし、不参加の従業員に対しレクリエーション費用に相当する金額を支給する場合は、「給与」として処理しなければなりません。
上記のように「福利厚生」ではなく「給与」として計上するケースは、レクリエーション以外にもあります。詳しい概要は、以下の国税庁HPを参考にしてください。
7. 福利厚生が非課税となる基準を理解しておこう!
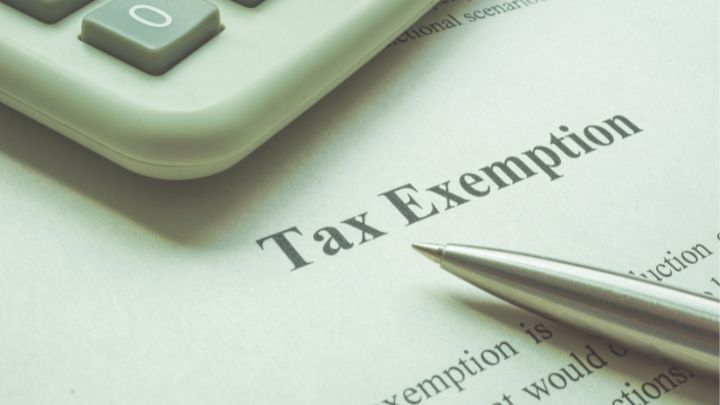
今回は、福利厚生が非課税となる基準について解説しました。福利厚生のために発生した費用は、基本的に非課税ですが、一定の条件を満たしていない場合は課税対象となるケースもあります。間違った会計処理をすると、税金を正しく納付することができなくなるため、基準をしっかりと理解しておきましょう。
また、福利厚生を導入する際は、非課税対象となるようなルール設定をすることも重要です。支給金額や支給対象者を考慮することで、非課税対象となるケースも多いため、福利厚生をうまく活用して節税していきましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。