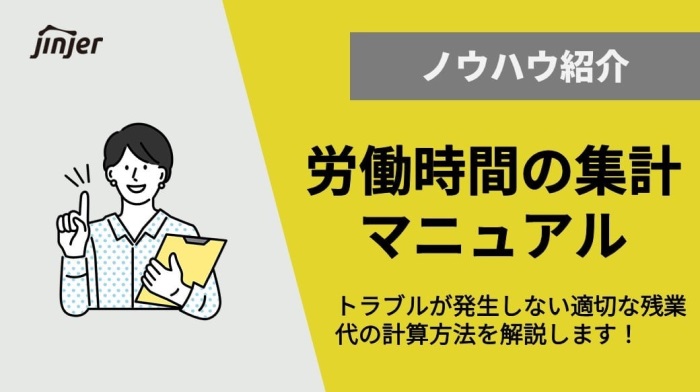時間外労働・休日労働・深夜労働(割増労働)が発生した場合、使用者は従業員に対して割増賃金を支払う必要があります。割増賃金を計算する際は、「割増賃金の基礎となる賃金」について理解しておかなければなりません。
今回は、割増賃金の基礎となる賃金の計算方法や、算定時に除外される手当などについて解説します。
関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説
労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。
当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。
「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」
「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 割増賃金の基礎となる賃金(割増賃金算定基礎)とは?

割増賃金の基礎となる賃金(割増賃金算定基礎)とは、所定の労働時間におこなった労働に対して支払われる「1時間あたりの基礎賃金」を指します。1時間あたりの基礎賃金は、割増賃金を正しく算出するために必要です。
従業員に残業や夜勤、休日出勤といった負荷のかかる労働をおこなわせた際は、1時間あたりの基礎賃金をもとに割増賃金を計算して支給しなければなりません。1時間あたりの基礎賃金の計算が正確にされていないと、割増賃金の計算に誤りが生じ、支払いトラブルにもつながりかねないため注意が必要です。
時給制の場合はそのまま時給が1時間あたりの基礎賃金となりますが、月給制の場合などは少々複雑な計算が必要になります。
1-1. 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増率
時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増率は下表の通りです。割増労働の種類によって割増率が異なるため注意しましょう。
| 割増労働の種類 | 割増率 |
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
状況によっては、割増率が加算されるケースもあります。たとえば、深夜帯に時間外労働が発生した場合は、割増率が加算され50%となるため覚えておきましょう。
2. 割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金の計算方法
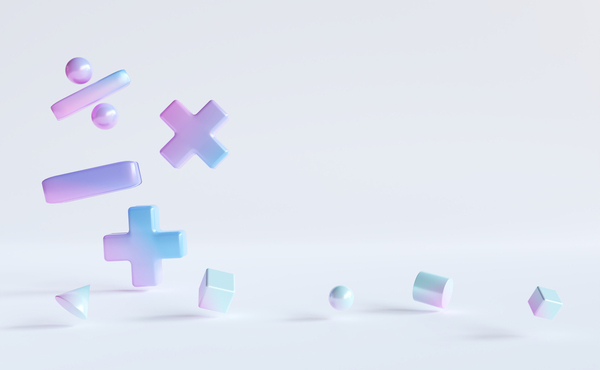
ここでは、割増賃金の基礎となる「1時間あたりの基礎賃金」の計算方法と、計算時に除外される各種手当について紹介します。
2-1. 1時間あたりの基礎賃金の計算方法(月給制の場合)
月給制の場合、従業員の1時間あたりの基礎賃金は、以下の計算式で算出できます。
1ヵ月平均の所定労働時間は、1年間で考えた場合の月平均の所定労働時間のことです。以下の計算式で求められます。
たとえば、月給30万円で所定労働時間を1日7.5時間とし、年間休日125日の従業員の場合、1ヵ月平均の所定労働時間および1時間あたりの基礎賃金は以下の通りです。
1ヵ月平均の所定労働時間 =(365日 − 125日)× 7.5時間 ÷ 12ヵ月 = 150時間
また、1時間あたりの基礎賃金は以下の通りです
1時間あたりの基礎賃金 = 30万円 ÷ 150時間 = 2,000円
よって、1時間あたりの基礎賃金は2,000円と算出できました。
2-2. 割増賃金の基礎となる賃金から除外される手当
1時間あたりの基礎賃金を計算するとき、従業員個人の事情により支給されている手当については、労働基準法第37条第5項、および労働基準法施⾏規則第21条により、基礎賃金算出の対象外となります。
◇基礎賃金の対象外となる手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居⼿当
- ⼦⼥教育⼿当
- 住宅⼿当
- 臨時で⽀払われた賃⾦
- 1ヵ月を超えた期間ごとに⽀払われる賃金
原則、これら7つの手当に該当するものは、基礎賃金を計算する際に対象外となります。たとえば、年末年始手当やオンコール手当などは「6. 臨時で支払われた賃金」に該当するため、割増賃金の基礎となる賃金の計算から除外することが可能です。
ただし、家族手当・通勤手当・住宅手当について、以下のような場合は計算に含めなければなりません。
- 家族手当:扶養家族の有無や家族の人数に関係なく、一律に支払っているもの
- 通勤手当:通勤に要する費用や距離に関係なく、一律に支払っているもの
- 住宅手当:住宅の形態によって、一律で支払っているもの
このように、従業員の個人事情を加味せず、一律で支給する手当は、割増賃金の基礎となる賃金の計算に含めなければならないので気を付けましょう。
2-3. 割増賃金の基礎となる賃金に含める手当
支給されている手当のうち、割増賃金の基礎となる賃金を算出する際に除外しない手当もあります。具体的には、以下のような手当が挙げられます。
- 資格手当
- 皆勤手当
- 役職手当
- 営業手当
ただし、各手当の名称と内容に明確な定義はなく、企業によって呼び方は異なるでしょう。役職手当という名前で固定残業代を定めているケースなどもあるため、安易に手当の名称で判断せず、何に対しての手当であるのか、その内容に注意して計算に含めるか判断することが大切です。
関連記事:割増賃金の計算から除外可能な手当とは?固定残業代の取り扱いも解説!
3. 時間外労働・休日労働・深夜労働が発生した場合に支給する割増賃金

割増労働が発生した場合には、割増賃金の支払いが必要です。ここでは、時間外労働・休日労働・深夜労働が発生した際に支給する割増賃金の計算方法についてそれぞれ紹介します。
3-1. 時間外労働発生時の割増賃金
通常、時間外労働による割増賃金を算定する場合、以下の計算式を用います。
労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定めています。この時間を超えて従業員に労働をさせた場合には、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外労働が月60時間を超えた場合には、割増率50%以上として割増賃金を支払う必要があります。時間外労働が月60時間を超えた場合の計算式は以下の通りです。
3-2. 休日労働発生時の割増賃金
従業員に休日労働をさせた場合には、従業員の1時間あたりの基礎賃金を基にして35%以上の割増賃金を支払う必要があります。この場合の計算式は、以下の通りです。
この割増賃金が適用されるのは、あくまでも法定休日に出勤した場合なので注意しましょう。法定休日にあたらない会社独自の所定休日(法定外休日)で、時間外労働・深夜労働にも該当しない場合、割増率を適用した計算はおこなわれず、以下の計算式で賃金の計算をします。
3-3. 深夜労働発生時の割増賃金
従業員に22時~翌5時までの時間に労働をおこなわせた場合には、従業員の1時間あたりの基礎賃金を基にして25%以上の割増賃金を支払います。この場合の計算式は、以下の通りです。
3-4. 割増条件が重複した場合
ここまでの3つの割増条件が重複して発生している場合には、各割増率を加算して計算をおこないます。ここでは、「時間外労働と深夜労働が重なった場合」「休日労働と深夜労働が重なった場合」の2パターンの割増率の計算を紹介します。
3-4-1. 時間外労働と深夜労働が重なった場合
時間外労働を命じられたために夜勤をすることになったなど、時間外労働と深夜労働が重なった場合には、時間外労働と深夜労働それぞれの割増率を合算し、それに割増賃金の基礎となる賃金を掛け合わせて割増賃金を計算します。
つまり、最低でも50%以上の割増率を適用して、割増賃金を計算しなければなりません。時間外労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金の計算式は、次の通りです。
3-4-2. 休日労働と深夜労働が重なった場合
法定休日に夜勤をおこなったなど、休日労働と深夜労働が重なった場合には、休日労働と深夜労働それぞれの割増率を合算し、それに割増賃金の基礎となる賃金を掛け合わせて割増賃金を計算します。
つまり、最低でも60%以上の割増率を適用して、割増賃金を計算しなければなりません。休日労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金の計算式は、次の通りです。
なお、法定休日に出勤する場合に、1日8時間・週40時間を超えて働くことになったとしても、時間外労働の割増率は適用されません。
時間外労働は労働義務のある日において発生するものであり、休日労働は法定休日とよばれるもともと労働義務がない日において発生するものだからです。そのため、時間外労働と休日労働が重なるケースはないので正しく理解しておきましょう。
関連記事:割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介!
4. 割増賃金の計算の際に必要な労働基準法の知識

時間外労働や休日出勤などの割増賃金における計算では、関連する規定が定められた労働基準法第37条に関する知識が必要です。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(省略)
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
同法では、従業員の法定労働時間を超える時間外労働や休日労働、深夜労働について割増賃金を支払うことを定めています。違反すると罰則の対象となるため、しっかりと理解しておきましょう。
5. 割増賃金の基礎となる賃金を間違えるとどうなる?

ここでは、割増賃金の基礎となる賃金の計算を間違えることによるリスクを紹介します。
5-1. 未払いの賃金を請求される
割増賃金の基礎となる賃金の計算を間違えると、従業員に対して正しい割増賃金を支給できません。後で計算が間違っていたことが判明した場合、再計算して正確な賃金を支給する必要があります。
また、従業員側から未払いの賃金を請求されることもあります。賃金請求権の時効は5年(当面の間は3年)です。過去の計算間違いだからといって、賃金の支払いを避けることはできないため注意しましょう。
参照:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省
5-2. 企業のイメージが悪化する
計算間違いが頻発していると、企業のイメージ悪化にもつながります。とくに従業員との裁判となったり、労働基準監督署から指導を受けたりすると、企業の社会的な印象が悪くなるでしょう。
その結果、取引先との関係が悪化する、採用活動がうまく進まなくなるといった影響が出る可能性もあります。割増賃金の基礎となる賃金は、ルールに従って正確に計算することが重要です。
6. 割増賃金の基礎となる賃金を正しく算出しよう!

今回は、割増賃金の基礎となる賃金の計算方法や、計算上の注意点について解説しました。時間外労働・休日労働・深夜労働が発生したときは、従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金の基礎となる賃金をもとに正確に計算する必要があるため、対象となる手当・対象外の手当など、ルールをしっかりと把握しておきましょう。
また、正確な割増賃金の計算をおこない、労働対価を支払うことは、従業員の健康を守り、労使トラブルを防ぐことにもつながります。従業員のおこなった時間外労働・休日労働・深夜労働に対すする割増賃金を計算する際には、労働基準法の内容を正しく理解しておきましょう。
労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。
当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。
「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」
「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。