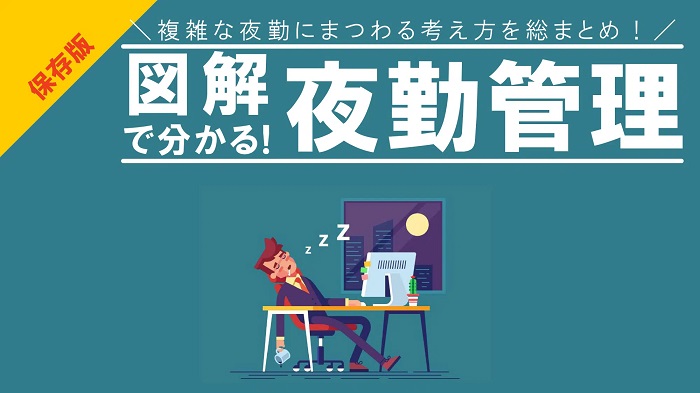近年、労働基準法に関する取り締まりが強化されています。使用者は、労働基準法などの法令を遵守して従業員を労働させる義務を負いますが、「深夜労働」も注意して管理しなくてはならないポイントの一つです。
今回は、未成年者の深夜労働(夜勤)に関する規則に焦点を当て解説していきます。
関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説
日勤とは異なる勤務形態である夜勤は、労働基準法で別にルールが設けられているため、「何が正しい夜勤の勤怠管理か理解できていない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤時の休憩や休日の取らせ方、割増賃金の計算方法まで、労働基準法に則った夜勤の扱い方について解説した資料を無料で配布しております。
「法律に沿って正しい夜勤管理をしたい」という方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 深夜労働(夜勤)は何歳から可能?

深夜労働(夜勤)は一体何歳から可能なのでしょうか?
ここでは、深夜労働の基本を紹介します。
1-1. 深夜労働とは
深夜労働とは、22時から翌5時までの時間帯に勤務することで、夜勤などとも呼ばれます。
この時間帯に勤務することができる年齢には制限があり、労働基準法第61条において下記の通り規定されています。[注1]
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
引用:労働基準法第61条
1-2. 深夜労働は18歳以上ならできる
労働基準法で深夜労働が制限されているのは、満18歳未満の未成年者です。
よって満18歳以上の従業員であれば、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させても問題ありません。
1-3. 【例外】18歳未満でも深夜労働が認められるケース
一部例外的に、18歳未満であっても深夜労働が認められるケースがあります。
1-3-1. 交代制によって勤務する16歳以上の男性
労働基準法では、但し書きとして、「交替制によって使用する満16歳以上の男性」については深夜労働を認めています。
なお、この「交替制」とは、同じ労働者が一定期日ごとに、昼間勤務と夜間勤務とに交代制で就業することです。昼間勤務を挟むことで、深夜労働による疲労が一定程度回復されると予想されることが、例外として認められる理由となっています。
1-3-2. 交代制の事業で行政官庁から許可を受けている場合(22時30分まで勤務可能)
交替制で労働させる事業においては、22時30分までであれば未成年者を使用することが可能です。これは、労働基準法61条3項に明記されており、労働基準監督署の許可を得ることが条件です。
なお、この交替制で労働させる事業とは、事業そのものが二交替・三交替制をとっているものを指し、個別の労働者に交替制を適用するという意味ではありません。
1-3-3. 農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換といった業務の従事者
農林、畜産・養蚕・水産業、病院・保健衛生業及び電話通信業務については、業務の性質から、年少者の深夜労働禁止規定が適用されません。
ただし、この場合も深夜労働は法定時間外労働となるため、使用者は25%以上の割増賃金を支払うことになります。
1-3-4. 非常災害時で行政官庁からの認可を受けている場合
労働基準法33条1項では、災害などの事由により行政官庁の許可を得ている場合に限り、労働者に労働時間の延長や休日労働をさせることを認めています。また、緊急性がある労働については、深夜労働の制限も適用されません。
わかりやすく言うと、災害などによって事業場を復旧しなければならないような事態となった場合は、行政官庁の許可を得て、年少者を深夜労働に従事させることが可能となります。
1-4. 18歳以上の高校生に深夜労働させるときは要注意
18歳以上とはいえ、高校生に深夜労働をさせる際はいくつかのリスクが伴います。一番の懸念は、学業への影響です。深夜労働によって疲れが生じ、学業が疎かになることで、学生の人生を左右してしまうかもしれません。
また、深夜は犯罪や事故に遭う可能性も高まります。職場から家まではどのように行き来するのか、事前に確認をおこなったほうが無難でしょう。
その他、校則違反でないかどうかも、トラブルを防ぐためにも確認する必要があります。
2. 労働基準法における未成年の深夜労働に関するルール
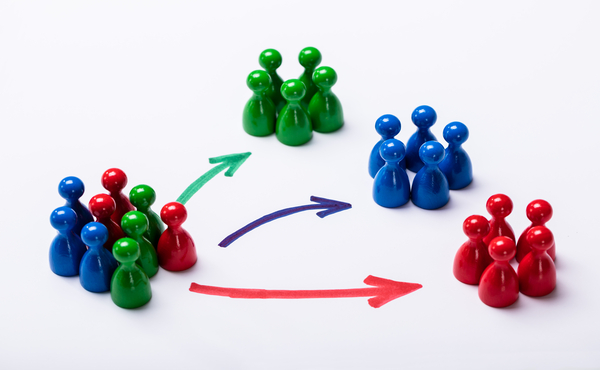
労働基準法では、「未成年者」のなかに更に細かい区分が存在しています。各区分ごとに保護規則が定められているため、雇い入れる際には雇用者の年齢に合わせて条件を確認しなければなりません。
また、2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、労働基準法の一部規則にも変化が生じているため、しっかりと確認しておきましょう。
2-1. 未成年者の年齢区分
成人年齢の引き下げの前・後で、未成年者の区分は下記の通り変化しています。
【成人年齢引き下げ前】
|
区分 |
保護規定 |
|
|
成人 |
満20歳以上 |
なし |
|
未成年者 |
満20歳未満 |
|
|
年少者 |
満18歳未満 |
|
|
児童 |
満15歳に達する年の年の年度まで |
原則使用禁止 |
【成人年齢引き上げ後(2022年4月1日以降)】
|
区分 |
保護規定 |
|
|
成人 |
満18歳以上 |
なし |
|
年少者 (=未成年者) |
満18歳未満 |
|
|
児童 |
満15歳に達する年の年の年度まで |
原則使用禁止 |
上記から、年少者としての保護規則が外れる年齢と成人年齢が一致したことになります。
また、この改正に伴い、今まで未成年として保護対象であった18歳以上20歳未満については、労働基準法の定める保護対象からは除外されます。
参考:年少者使用の際の留意点 ∼ 児童労働は原則禁止 ! ! ∼|厚生労働省
参考:高校生や中学生などを雇用するときの注意点|厚生労働省 山梨労働局
2-2. 年少者の雇用に関する制限
「年少者(満18歳以下)」の雇用時には、以下のような保護規則が存在します。違反すると罰則の対象となるため、しっかりと確認しておきましょう。
①原則として深夜労働が禁止
先述の通り、22時から翌5時までの時間に年少者を働かせることはできません。
②時間外労働の禁止
18歳以上であれば、36協定を締結した場合、残業を命じることが可能です。
しかし、18歳未満については、たとえ合意があっても、残業や休日出勤をおこなわせると労働基準法第60条に違反することになります。[注2]
また、1日8時間以上週40時間以上労働させることはできないため、夏休みなどの長期休暇中の労働時間には特に注意しましょう。
③変形労働時間制の禁止
年少者をフレックスタイム制や変形労働時間制で勤務させることはできません。
しかし、満15歳に達した日以後の最初の3月31日から満18歳未満の従業員に関しては、下記の条件に限り変形時間労働制を導入することが可能です。[注2]
- 1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、1週40時間以内で他の日に10時間まで労働させる
- 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1カ月または1年単位の変形労働時間制を適用する
④一部業務への従事制限
年少者は、肉体的、精神的に未熟であるために、安全、衛生、福祉的な観点から労働基準法第62、63条では従事を禁止する業務が明記されています。[注3]
具体的な禁止業務は下記の通りです。
〈禁止業務の一例〉
- 重量物の取り扱い業務
- ボイラーの取り扱い業務
- クレーンや大型トラックなどの取り扱いや運転業務
- 高さが5メートル以上の場所で墜落の危険のある業務
- 深さが5メートル以下の場所で土砂などの崩落の危険のある業務
- 危険物や有害物質を取り扱う業務
- 著しく暑熱または寒冷な場所及び気圧変化の大きい場所での業務
- 刑事施設や精神科病院等での勤務
- 焼却や清掃、と殺などの業務
- バー、クラブなどでの業務
- 坑内での業務
3. 18歳未満の年少者に深夜労働させた場合の罰則

労働基準法第61条によって、18歳未満の年少者の深夜労働は禁止されています。
これに違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。[注1]
法令に違反すると単に刑罰が科せられるだけでなく、企業イメージの低下にもつながるため注意しなければなりません。事業者は年齢制限をしっかりと確認したうえで、従業員を雇い入れましょう。
4. 18歳以上の従業員に深夜労働させるときの注意点

18歳以上の従業員であれば深夜労働をさせることができますが、その際には以下のポイントに注意しましょう。
4-1. 割増賃金を支払う
従業員を深夜に労働させる際には、従業員の年齢や雇用形態にかかわらず、労働基準法第37条の規定に従って割増賃金を支払う義務が生じます。従業員に深夜労働を命じる場合は必ず深夜手当を支給しましょう。
同法第38条で、深夜労働の賃金の割増率は25%以上と規定されています。
計算方法は下記の通りです。
「割増賃金=1時間あたりの賃金×労働時間×1.25」
(例)
- 1時間あたりの賃金:1,000円
- 勤務時間:18時~23時の5時間
上記の条件で従業員が勤務した場合、18〜22時までの4時間分は通常勤務、22時〜23時までの1時間が深夜労働に該当します。
1,000円×4時間=4,000円
1,000円×1時間×1.25=1,250円
よって、深夜労働分の割増賃金は1,250円となります。
したがって、この場合の支払うべき総賃金は4,000円+1,250円=5,250円です。
また、給与形態が時給制でなく月給制の場合でも、必ず1時間あたりの賃金を算出しなければなりません。
月給制の場合、1時間あたりの賃金は下記の計算式で算出可能です。
「1時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間数*」
(*年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12カ月)
月によって所定労働日数が異なっているのに対し、月給は基本的に金額が固定されています。
安易に月給を勤務月の労働時間数で割り、1時間あたりの賃金を算出してしまうと、月ごとの1時間あたりの賃金にばらつきが生じてしまいます。そのため、月給制の場合の割増賃金の計算は、必ず月平均労働時間を算出してからおこないましょう。
参照:しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-|厚生労働省
このように深夜労働がおこなわれた際には、従業員に必ず割増賃金を支給しなければなりません。加えて残業や休日労働が重なった場合は、それぞれ25%の割増が加算されることとなります。
当サイトでは、正しい割増手当の求め方をわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。 労働基準法に準じた休憩時間の取り方、深夜0時をまたぐ際の暦日の考え方などもあわせて解説しておりますので、深夜労働の適切な管理方法を確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください
関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説
4-2. 校則で深夜労働が禁止されていないか確認する
校則で深夜労働を禁止する学校も少なくありません。そのため、親や学校の承諾がないまま深夜労働をさせてしまうと、後になってトラブルに発展する可能性があります。
学生本人が問題ないと話していても、確認を怠らないようにしましょう。対策としては、生徒手帳を見せてもらったり、学校へ問い合わせをおこなったりして、夜勤が可能な条件を満たしていることを確認してください。
5. 深夜労働は18歳以上なら可能だが注意点もある!

深夜労働は一部例外的な状況を除き、満18歳以上の従業員にしか認められません。法定規則に違反した場合、刑罰が科せられるだけでなく、企業イメージを損なう可能性もあります。
誤って深夜労働をさせてしまったといった状況が発生しないよう、事業者は雇用する従業員の年齢を確認し、雇用形態・事業内容の年齢制限にも十分注意するように心がけましょう。
[注1]労働基準法第61条|e-Gov
[注2]労働基準法第60条|e-Gov
[注3]労働基準法第62条、63条|e-Gov