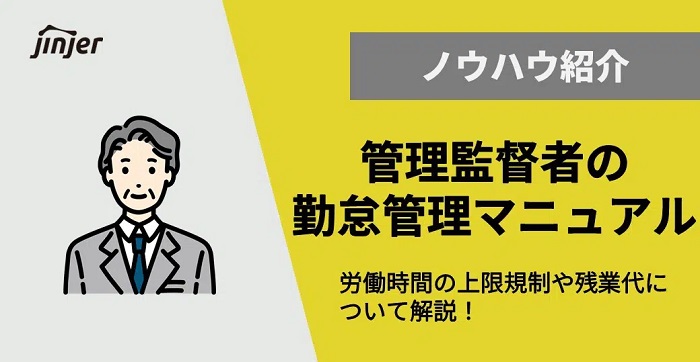企業において重要な地位であり、経営者と密接な関係である労働者のことを管理監督者と呼びます。管理監督者は、部下へ指示を出したり経営方針を決定したりするうえで非常に重要な役割を担っています。
しかし、この管理監督者について、実は明確な定義はありません。そのため、労働状況を踏まえ、管理監督者かどうかを個別的に判断をする必要があるのです。この判断を間違えてしまうと法律違反となり、さまざまな労働トラブルを引き起こす可能性があるので注意してください。
本記事では、管理監督者の定義や労働時間について解説します。一般的な社員とは異なる点がたくさんあるので、しっかりと理解しましょう。
関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則って行いたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 管理監督者の労働時間に上限はない

労働基準法では、管理監督者のことを監督や管理の地位にあるものと定義しています。また、管理監督者の労働時間についての規定は、一般の従業員と異なっています。
ここでは、管理監督者と一般の従業員において、労働時間に関する規定がどのように異なるのか、また、除外されずに適用される規定ついて詳しく解説します。
関連記事:月の労働時間上限とは?月平均所定労働時間や残代計算について解説!
1-1. 時間外労働・休日の規定は適用除外
管理監督者は重要な業務を担っており、時を選ばず経営上の判断や対応が必要になる場面も多いでしょう。そのため、時間外労働の上限や休日に関する労働基準法の規定の対象からは除外されます。つまり、労働基準法の「1日8時間、1週間40時間」という労働時間の上限や、36協定の「時間外労働が1カ月最大45時間、年間320時間」という上限規制も対象外です。
一般の従業員に時間外労働・休日労働をさせた場合には、それぞれ基礎賃金を25%、35%割増した割増賃金を支払う必要がありますが、管理監督者に対してはこれらを支払う必要はありません。
また、通常は週に1日、1カ月に4日の法定休日を取得させる義務がありますが、管理監督者には休日を付与しなかったり、振替休日を設けなかったりしても、労働基準法の違反にはなりません。
ただし、時間外労働が月に80時間を超過した際の産業医による面接指導の規定や、労働契約法第5条の従業員に対する安全配慮義務は管理監督者であっても適用されるため、健康への配慮はおこなう必要があります。
関連記事:労働時間の上限とは?2024年建設業、運送業への法改正についても解説!
1-2. 深夜労働の規定は適用
時間外労働・休日労働に関する規定からは除外されますが、深夜労働の規定は管理監督者にも適用されます。
22時~翌5時の深夜時間での勤務は、健康を害するリスクが高まります。そのため、管理監督者であっても、深夜労働は可能な限り避けなければなりません。深夜労働をおこなわせた際は、基礎賃金の25%以上の割増賃金を支払いましょう。
また、月に4回以上深夜労働をさせた従業員に対して発生する「特定業務健康診断」も受診対象です。月4回以上の深夜労働が発生した場合には、半年に1回、年2回の健康診断受診を促しましょう。
1-3. 有給休暇の規定は適用
管理監督者であっても、有給休暇の規定は適用されます。勤続年数に応じて、正しく付与することが重要です。
また、年5日の有給休暇取得が義務付けられているので、有給が消化できていないという従業員には取得をするように働きかけましょう。
1-4. 管理監督者であっても月100時間の時間外労働は安全配慮義務に違反する
管理監督者は労働基準法の一部や36協定の適用外となるため、労働時間や残業時間の制限がありません。ただし、月100時間の時間外労働は安全配慮義務違反となります。
100時間を超える残業は、過労死ラインとして労災にも認定されています。管理監督者は労働時間の上限がないものの、安全配慮義務の対象となることを忘れないようにしましょう。
2. 管理監督者は変形労働時間制・フレックスタイム制などの対象外
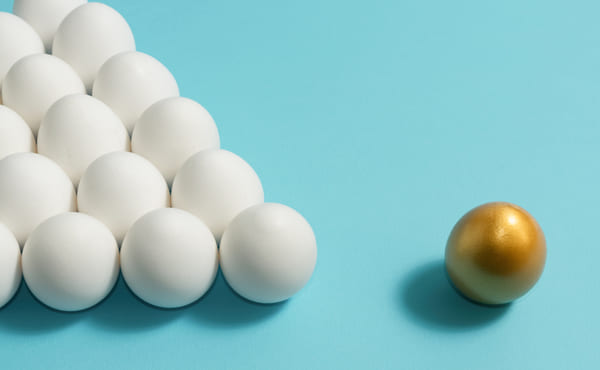 管理監督者は労働時間の制約を受けないので、変形労働時間制・フレックスタイム制に関しても適用対象外となります。変形労働時間制とは、労働時間を1日ではなく月・年・週単位で計算し、忙しい時期や業務に余裕がある時期に合わせて労働時間をうまく調整するという制度のことです。
管理監督者は労働時間の制約を受けないので、変形労働時間制・フレックスタイム制に関しても適用対象外となります。変形労働時間制とは、労働時間を1日ではなく月・年・週単位で計算し、忙しい時期や業務に余裕がある時期に合わせて労働時間をうまく調整するという制度のことです。
フレックスタイム制は変形労働時間制の一種であり、法定労働時間を超えない範囲で労働者が始業時刻や終業時刻を自由に決定できるという制度を指します。
一般的な社員にとって、これらは働きやすさの向上につながる嬉しい制度です。管理監督者にはこれらが適用されません。しかし、管理監督者はそもそも自由に勤務時間を決めたり業務量を調整したりすることができるので、これらの制度が適用されなかったとしてもさほど大きな問題ではないといえるでしょう。
3. 管理監督者の労働時間も把握が義務化

2019年の4月から施行されている働き方改革関連法案にて、一般労働者の残業時間に上限規制が設けられました。これに伴い、労働時間に制限のない管理監督者へしわ寄せがいき、業務が増加する可能性が危惧されていました。
そこで労働安全衛生法が改正され、管理監督者の労働時間も把握することが企業に義務付けられたため、管理監督者の勤怠管理も必要となります。
関連記事:労働時間管理が義務化!厚生労働省のガイドラインに基づく効率的な管理方法を解説
3-1. 労働時間の把握をしなかったときの罰則
労働時間の把握をしなかったことに対する明確な罰則はありません。ただし、把握を怠ったことにより、時間外労働の上限を超えてしまった場合などは罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性もあります。
従業員ごとの労働時間を把握しておかないと、さまざまな違反行為につながる可能性があるため、適切に管理していきましょう。
4. そもそも管理監督者とは?管理職との違い

管理監督者とよく似た言葉に管理職があります。2つの言葉はしばしば混同されていますが、異なるものとして認識しなければいけません。
労働基準法で定められる管理監督者とは、経営者に近い強い権限や責任を担っており、就業時間を自分の裁量で決定し、給与などの面でその地位にふさわしい待遇を受ける従業員のことです。
会社が独自で定める管理職やマネージャー職であっても、上記に当てはまらない要件がある場合は管理監督者として認められないため、管理監督者が免除される時間外労働や休日労働については一般社員と同様の規定で管理する必要があります。
各種規定を回避するため、業務内容は一般社員に近いにも関わらず肩書だけは管理職とし、あたかも管理監督者として従業員を扱う「名ばかり管理職」が問題となっています。
従業員が不当な扱いであることを主張し、未払い賃金を請求する訴訟が複数発生しているため、管理監督者と管理職をしっかりと区別し適切に対応することが重要です。
5. 管理監督者の4つの要件について

管理監督者に関する明確な定義はありませんが、法的には監督や管理の地位にあるものとされています。
管理監督者は、自分の裁量で労働時間や業務量を調整でき、残業時間や割増賃金についても一般の労働者とは違う取り扱いがされます。
もちろん、管理的な立場にある人間がすべて管理監督者になるというわけではありません。具体的な判断基準としては、下記の4つが挙げられます。
- 重要な職務内容を有していること
- 重要な責任と権限を有していること
- 労働時間は自己裁量制であること
- 地位にふさわしい待遇となっていること
これらの詳細について解説していきます。
5-1. 重要な職務内容を有していること
重要な職務内容とは、具体的に説明をすると企業の経営に関わるということです。経営者会議に参加して企業の方針について発言をしたり、部署の予算や部下の労働時間を管理していたり、解雇・採用・人事考課などの人事権を有していたりする場合、企業の経営に関わっていると判断されます。
つまり、経営者から指示を受けて一部の管理業務をおこなっているというだけでは、管理監督者とはみなされません。店舗のマネージャーなどの役職者は管理監督者のように思えますが、企業経営に関与していない場合は管理監督者に該当しないので注意してください。
5-2. 重要な責任と権限を有していること
重要な責任と権限を具体的に説明をすると、採用面接の判断を下す権限や、部下の賃金や人員配置を決定する権限、予算や費用の管理を一任されているなどの権限のことです。部下に業務内容を指示しているという従業員は多いかもしれませんが、決定権限が他部署にあったり上司の決済が必要だったりする場合は、管理監督者に該当しないので注意してください。
また、自分で全てを決定している場合でも、そもそも部下がいないという場合は労務管理や人事について十分な権限があるとはいえないので管理監督者ではありません。
5-3. 労働時間は自己裁量制であること
勤務形態については、会社から拘束されていない必要があります。1日の労働時間や業務量を自らの裁量で決定する必要があります。管理監督者とは、経営上の判断を求められる立場にある存在であるため、労務管理も一般労働者とは区別するべきと考えられているのです。
具体的には出退勤時刻を自由に決定できたり、労働時間を自らの裁量で決めることができたり、業務量をコントロールできたりといった内容となります。そのため、管理監督者は遅刻や早退、欠勤控除も受けません。残業や業務量に上司の許可が必要という場合は、管理監督者とはいえないので注意をしてください。
5-4. 地位にふさわしい待遇となっていること
管理監督者は、経営者と同等の立場の存在です。そのため、それ相応の待遇を受けている必要があり、一般労働者よりも高額な賃金や手当を支給しなくてはいけません。
また、管理監督者には残業代が支給されないため、それによって給与の総額が下がったという場合は管理監督者とは認められない可能性が高いです。長時間労働を強いられた際に、時間単価が一般労働者を下回ってしまう場合でも管理監督者性が否定される可能性があります。
6. 管理監督者に適用される就業規則の範囲
 管理監督者には、就業規則における労働時間や休憩、休日などの規定も適用されません。しかし、就業規則の全てが適用されないというわけではありません。適用除外となるのはこの3つの項目のみであり、その他の規定については一般労働者と同じように適用されます。
管理監督者には、就業規則における労働時間や休憩、休日などの規定も適用されません。しかし、就業規則の全てが適用されないというわけではありません。適用除外となるのはこの3つの項目のみであり、その他の規定については一般労働者と同じように適用されます。
就業規則のどの範囲が管理監督者の適用対象かは非常に複雑です。そのため、管理監督者にはどこまでの範囲が適用されるのか明確になるように、就業規則の文面を整理しておきましょう。
このように管理監督者は、通常の労働者と適用される労働条件が異なるため、労働基準法に違反する勤怠管理をしないよう注意が必要です。 しかし、一部労働時間の規制が適用されないのは把握しているが、細かい内容が把握しきれず、自社の勤怠管理が問題ないか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。 当サイトでは、管理労働者がいる職場にて就業規則に記載すべき内容や、管理監督者の勤怠管理をどのように行えばよいかが具体的にわかる資料を無料で配布しております。 管理監督者における勤怠管理のルールを確認したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
7. 厚生労働省のガイドラインに基づく管理監督者の労働時間の把握方法
 厚生労働省のガイドラインでは、管理監督者の労働時間を把握する方法として以下のいずれかの要件を満たすよう求
厚生労働省のガイドラインでは、管理監督者の労働時間を把握する方法として以下のいずれかの要件を満たすよう求
めています。
- 使用者が自ら現認して記録する
- タイムカード、IC カード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録する
管理監督者は労働時間などの制限がなく、自己裁量によって労働時間を決定します。そのため、労働時間の把握・管理が難しいという問題が生じてしまうのです。
ここからは、管理監督者の労働時間を正しく把握・管理するためのツールを紹介します。
7-1. 自己申告による管理
エクセルや出勤簿を使って自己申告制にする方法もあります。
管理監督者という立場の従業員であれば勤務時間を改ざんするようなことはほとんどありませんが、まったくリスクがないわけではありません。また、エクセルなら計算式を設定すれば勤務時間の集計などが簡易化されますが、入力ミスなどにより誤って勤務時間を管理してしまう可能性があります。
自己申告はすぐに導入できるなどのメリットがありますが、客観的な労働時間の記録として認められていません。違法性はありませんが、より厳格な勤怠管理が必要になるので注意しましょう。
7-2. タイムカードによる管理
中小企業で取り入れられているのがタイムカードによる勤怠管理です。使い方がシンプルで導入も簡単な反面、出勤・退勤時間の記録しかできないというデメリットがあります。また、会社に出勤することを前提とした管理方法なので、リモートワークで働く従業員には対応できず多様性に欠ける管理方法です。
タイムカードは、管理監督者の働き方によっては労働時間を正しく管理できない可能性があるので注意しましょう。
7-3. パソコンの使用記録による管理
パソコンの使用記録は、パソコンの電源を入れた時刻を出勤時間、パソコンの電源を切った時刻を退勤時間とします。正確性や客観性の高い管理方法ですが、休憩時間の把握が難しく、電源を切ったあとに業務をするケースなどには対応できません。
7-4. 勤怠管理システムによる管理
勤怠管理システムは、厚生労働省のガイドラインに則った最適な勤怠管理方法です。社外にいることが多い管理監督者でも、スマートフォンやタブレットなどで簡単かつ正確に労働時間を記録できます。
また、休憩時間・休日労働・時間外労働などを自動的に集計したり、有給休暇を自動付与したりできる便利な機能も備わっています。とくに管理監督者のように労働時間の把握・管理が難しい従業員には、勤怠管理システムがおすすめです。
8. 管理監督者の労働時間を減らす方法

管理監督者の長時間労働が慢性化している場合は、健康を維持するためにも何らかの対策を講じなければなりません。できる限り労働時間を減らせるよう、以下のような方法を検討してみましょう。
8-1. 長時間労働に対する意識を変える
まずは、長時間労働に対する意識を変えることが大切です。「残業をしてでも成果を出すべき」「プライベートより仕事を優先すべき」といった考え方が根付いていると、長時間労働が常態化してしまいます。
ノー残業デーを設定するなど、会社全体で残業を減らす取り組みを進めると意識の変化につながります。残業手当の削減にもつながるため、少しずつ取り組んでいきましょう。
8-2. 業務効率化を図る
管理監督者の労働時間を減らすためには、業務効率化を図ることも重要です。管理監督者は、部署のマネジメントや経営者との会議など、多くの業務を抱えています。
どのような業務を抱えているのかを洗い出し、無駄な作業を削減するようにしましょう。また、便利なシステムを導入して、手間のかかる作業を効率化することも重要です。
8-3. 人員の配置を見直す
人員の配置を見直すことも労働時間の短縮につながります。たとえば部署の人数が多すぎると、管理監督者が把握すべき内容が増え、負担が増えてしまいます。優秀な従業員に中間管理的なポジションを与えるなど、組織構成を見直すと管理監督者の負担を軽減できるでしょう。
9. 管理管理者の労働時間は勤怠管理システムで把握しよう

今回は、管理監督者の労働時間管理について解説しました。企業における管理監督者の割合はそれほど高くありません。だからこそ、労働時間の把握が難しく、安全配慮を怠るなどのリスクがあります。
管理監督者は他の労働者とは違い、適用が免除される上限規制もありますが、他の労働者と同様に遵守しなくてはいけない労働基準法上のルールもあります。管理監督者が遵守すべきルール、適用が除外されるルールをしっかり把握しておきましょう。
また、管理監督者の労働時間の把握が義務化されました。多様な働き方に対応するために、勤怠管理システムによる勤怠の一元管理を検討してみましょう。
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則って行いたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。