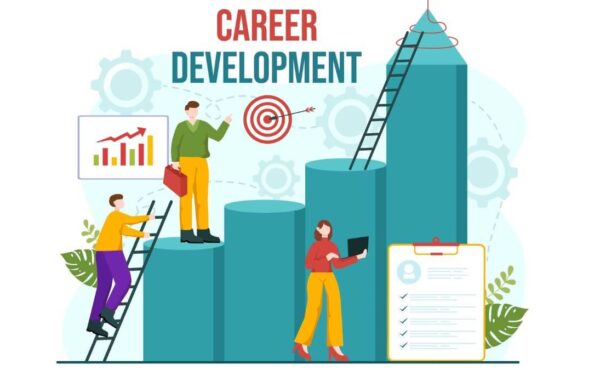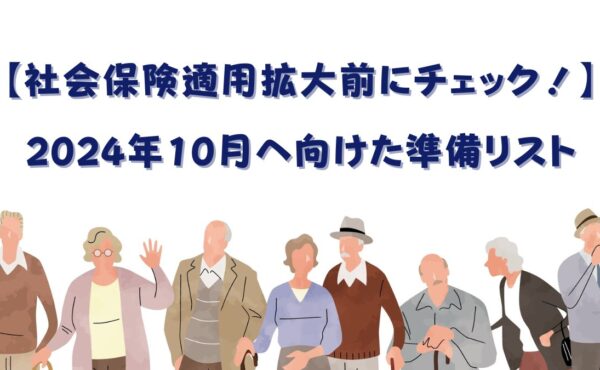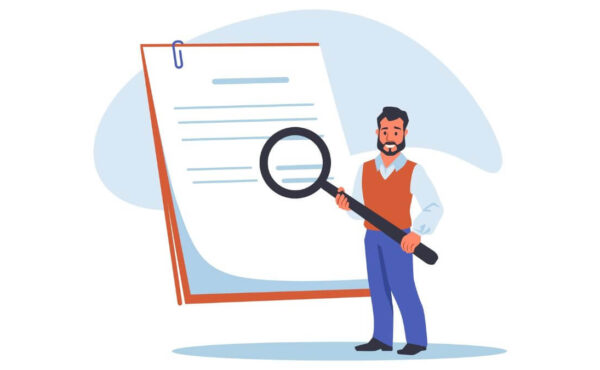企業が従業員を採用する際、未成年者を雇用するケースも珍しくありません。ただし、成人していない者は労働基準法によって保護規定が設けられているため、慎重に雇用する必要があります。
本記事では、使用者として知っておくべき労働基準法による年齢の規定についてまとめています。違反した場合の罰則や年齢規定を遵守するコツも含めて解説しています。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法による年齢規定

まず従業員を雇用をおこなう場合には、労働基準法による年齢規定の基本を押さえておくことが重要です。ここからは、労働基準法にて定められている年齢規定について解説していきます。
1-1. 労働基準法による年齢規定とは
労働基準法では、使用者が雇用できる最低年齢の規定を以下のように定めています。
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
この規定の意味は、ただ単に15歳未満の児童を使用してはならないということに留まりません。たとえ満15歳を超えていても、義務教育である中学校を卒業するまでは労働者として雇用することはできないので注意が必要です。
1-2. 労働基準法における年齢区分(未成年者・年少者・児童について)
先述したとおり、雇用できる最低年齢には制限があります。ただし、この年齢を超えていても未成年である場合、労働基準法による保護の対象となります。
労働基準法における年齢区分は以下のとおりです。
|
未成年 |
労働基準法上、満20歳未満の者 (2022年4月1日以降、民法上の未成年は18歳未満となるので要注意) |
|
年少者 |
労働基準法上、満18歳未満の者 |
|
児童 |
労働基準法上、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者 |
このように、労働基準法では成人に満たない者を未成年・年少者・児童の3つの区分に分けています。
年齢に違いはあるものの、成人ではないことにより労働契約締結において特別な保護を受けます。
未成年者を雇用対象とする企業は、それぞれの保護規定を遵守して採用することが必要です。なお、年齢規定を遵守するポイントについては後ほど解説します。
1-3. 最低年齢の例外について
先ほど、15歳未満の児童は雇用できないと解説しました。ただし例外があり、非工業的業種であり、かつ以下の条件を満たしていれば満13歳以上の児童を使用することが可能です。
- 児童の健康・福祉にとって有害でない
- 児童の労働が軽易である
- 児童の修学時間外の労働である
- 労働基準監督署長に申請をおこない、許可を得ている
非工業的業種とは以下のようなものを意味し、これらの業種であれば児童でも使用することができます。
- 製造業
- 鉱業
- 土木建築業
- 運送業
- 貨物取扱業
- 接客娯楽
- 清掃など
現実的に、児童を使用する非工業的業種の代表的な職業は新聞配達です。
また、映画や演劇などにおいては満13歳未満の児童であっても一定の条件を満たすことで使用が可能です。ただし、これは特別なケースなので、一般的には15歳未満の児童は雇用できないと考えておきましょう。
より詳細の条件を確認したい方は、厚生労働省の以下の資料でご確認いただけます。
参考:年尐者使用の際の留意点 ~ 児童労働は原則禁止|厚生労働省
2. 労働基準法による年齢規定を違反したときの罰則

労働基準法に違反した際は、先述した年齢区分や規定別に罰則が設けられているので注意が必要です。
罰則を受けることがないよう、未成年者の雇用は慎重におこないましょう。
2-1. 「児童」の規定に違反した場合
|
具体例 |
法第56条「最低年齢」に反し、満15歳、かつ最初の3月31日が終了していない児童を就労させた |
|
罰則内容 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
2-2. 「年少者」の規定に違反した場合
年少者においてはさまざまな規定ごとに罰則が設けられています。
|
具体例 |
第57条「年少者の証明書」に反し、年齢を証明する戸籍証明書を保管していない場合 |
|
罰則内容 |
30万円以下の罰金 |
|
具体例 |
第61条「年少者の深夜業」に反し、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に就労させた場合 (ただし、満16歳以上の男子を交代制勤務させた場合を除く) |
|
罰則内容 |
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
|
具体例 |
第62条「年少者の危険有害業務の就業制限」に反し、満18歳に満たない者を、危険な業務や重量物を扱う業務に就かせた場合 |
|
罰則内容 |
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
|
具体例 |
第64条「帰郷旅費」に反し、満10歳に満たない者を解雇し、その日から14日以内に帰郷する場合に使用者が旅費を負担しない場合 |
|
罰則内容 |
30万円以下の罰金 |
3. 労働基準法による児童・年少者の年齢規定を遵守するポイント

児童や年少者は、労働基準法によって保護されています。万が一ルールを遵守せず就労させると罰則の対象となるので慎重な対応が必要です。
ここからは、年齢区分別・項目別に、労働基準法による年齢規定を遵守するためのポイントをご紹介します。
|
規定の対象者 |
規制項目 |
内容 |
|
年少者 |
労働時間と休日 |
(※例外あり 満15歳以上で満18歳に満たない者については以下のいずれかの条件を満たせば変形労働時間制が可能 ・週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、ほかの日の労働時間を10時間まで延長する場合 ・1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合) |
|
児童・年少者 |
深夜業 |
児童は午後8時から午前5時までの就労が禁止 (子役の場合は午後9時から午前6時の就労が禁止) 年少者は原則午後10時から翌日午前5時までの就労が禁止 (満16歳以上の男子に限り、交代制勤務の場合の深夜就労は可能。また、労働基準監督所長の許可があれば、満16歳以上の男子以外でも午後10時30分まで就労可能) |
|
年少者 |
危険有害業務 |
・有害物質や危険物を取り扱う業務 ・クレーン、ボイラー、エレベーターなどの運転など ・焼却、清掃業務など |
|
年少者 |
坑内労働 |
|
|
年少者 |
帰郷旅費の負担 |
(ただし、解雇の理由が労働者にある場合はその必要はない) |
|
年少者 |
年齢証明書 |
|
|
未成年 |
親権者や後見人による労働契約の締結 |
(本人の意思に反して未成年者を労働させることを防ぐ目的などから) |
|
未成年 |
親権者や後見人による賃金の受領の禁止 |
(賃金搾取を防ぐ目的などから) |
4. 労働基準法・年齢規定に関してよくある質問
 ここからは、労働基準法の年齢規定に関してよく生じる疑問について解説します。未成年者・年少者が加入すべき保険、労働基準法の年齢制限の上限について、高所作業の年齢規定についてあわせて回答していきます。
ここからは、労働基準法の年齢規定に関してよく生じる疑問について解説します。未成年者・年少者が加入すべき保険、労働基準法の年齢制限の上限について、高所作業の年齢規定についてあわせて回答していきます。
4-1. 未成年者・年少者が加入すべき保険は?
未成年・年少者においても健康保険・厚生年金保険などの社会保険に関しては、以下の要件を満たしている場合加入させる義務があります。
- 労働契約・就業規則で規定されている所定労働時間および所定労働日数が、一般労働者の所定労働時間および所定労働日数の3/4以上である場合
- 上記の1に該当しない場合でも、以下5つの要件を全て満たす場合
①週の所定労働時間が20時間以上である
②1年以上の雇用期間が見込まれている
③月額8万8000円以上の賃金が支給されている
④学生ではない(もしくは夜間、通信制、定時制の学生である)
⑤従業員を常時101人以上雇用している企業(特定適用事業所)で就労している
未成年者・年少者においても、上記の条件を満たす場合は社会保険へ加入させる義務があるため、ご留意ください。
4-2. 労働基準法に年齢制限の上限はある?
労働基準法において、労働者の募集及び採用においた年齢制限などは存在しません。
また平成19年10月から雇用対策法の改正にともない、労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止が義務化されました。
企業は年齢を問わず均等な機会を与えなければならないため、年齢を理由に応募を断ること、不採用にすることなどは法令違反となるためご注意ください。
また65歳までの「定年制」については、労働基準法による定めはありません。
ただし高年齢者雇用安定法8条によると、60歳未満の定年は禁止とされています。また令和3年4月からは、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされています。
4-3. 労働基準法による高所作業の年齢規定は?
高所作業の年齢規定に関しては、労働基準法では定められておりませんが、労働安全衛生法では18歳以上からと規定されています。一方で年齢上限における規定は存在しません。
とはいえ、高齢になると危険性が高まる傾向にあるため、現場の環境を整えるなどの配慮が求められるでしょう。
5. 労働基準法を確認して年齢の規定を守ろう

未成年者は心身の発達途中であり、労働基準法によって守られるべき存在であります。そのため、労働基準法の年齢規定により年齢区分ごとに雇用条件が設けられており、事業者はこの規定を守って就労させなくてはいけません。万が一、規定に違反すると罰則を課されることもあるので注意が必要です。
これを機に労働基準法における年齢規定を再確認し、法令を遵守した雇用を推進しましょう。
労働基準法総まとめBOOK