
使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休ませた場合、労働基準法第26条の条文に基づき、平均賃金の60%以上を休業手当として支給しなければなりません。この記事では、労働基準法に基づく休業手当の計算方法や、休業補償との違いを解説します。また、パート・アルバイトや派遣社員にも休業手当は支給されるかどうかも紹介します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法第26条による休業手当とは?

労働基準法第26条による休業手当とは、会社側の責任で従業員を休ませた場合に支給しなければならない手当のことです。条文に基づき、事業主は休業させる労働者に、平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければなりません。なお、使用者の責めに帰すべき事由に該当する場合として、次のようなケースが挙げられます。
- 親会社の経営不振
- 資材の調達困難
- 設備や工場の機械不備や欠陥、検査
- 業務量の減少
- 監督官庁の勧告に基づく操業停止
- 自治体の休業要請
- 労働者が所属していない組合のストライキ
休業手当は、労働者の最低限の生活を保障するために支払われるものであるため、使用者の責めに帰すべき事由の範囲は広いことを押さえておきましょう。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
1-1. 休業手当と休業補償の違い
休業補償とは、労働基準法第76条に基づき、労働者が業務を理由に病気やケガをした場合に、使用者がその療養するための期間に支払う補償金のことです。なお、補償金額は、平均賃金の60%以上とされています。休業手当と休業補償は、どちらも労働者が休んだ期間に対して賃金を補償する点で共通しています。
しかし、労働者が休む理由に違いがあります。休業手当は、会社都合による休業が対象になります。一方、休業補償は、業務上の病気やケガを理由として療養する場合が対象です。また、業務上の疾病や療養の範囲は、労働基準法施行規則で細かく定められている点も特徴です。
さらに、休業補償を支払うことが困難なケースなどに備えて、使用者はすべての労働者に労災保険へ加入させる義務があります。そのため、休業補償は、労災保険から賄われることもあります。このように、休業手当と休業補償は異なる手当なので、法律に基づき正しく定義を押さえておきましょう。
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。(省略)
関連記事:労働基準法の第76条「休業補償」とは?支給金額や支給期間をわかりやすく解説
1-2. 休業手当と有給休暇手当の違い
有給休暇手当とは、労働基準法第39条に基づく年次有給休暇を労働者が取得した場合に支払われる手当のことです。なお、有給休暇手当の額は、原則として、所定労働時間の労働をしたときの賃金額です。休業手当と有給休暇手当は、どちらも労働者が休む場合に支給される手当です。しかし、休業手当は平均賃金60%、有給休暇手当は平均賃金100%と、手当の額に違いがあります。
また、休業手当はすべての労働者が対象で、会社都合により休むことになった場合に支給されます。一方、有給休暇手当は労働基準法の要件を満たした労働者が希望して休んだ場合に支給されます。このように、休業手当と有給休暇手当も異なる制度であるため、正しく違いを理解しておきましょう。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(省略)
関連記事:有給休暇の金額はいくら?給料として支払う際と買取の際の計算方法
2. 労働基準法による休業手当の支給条件

労働基準法の休業手当の支給条件として、会社の都合で休業していることに加えて、労働意欲と労働能力がある、休業日が休日ではないことがあります。
2-1. 使用者の責めに帰すべき事由である
休業手当は、使用者の責めに帰すべき事由により、労働者が休むことになった場合に支給すべき手当です。そのため、地震や津波、台風、火山噴火、大雪など自然災害による不可抗力で休業になった場合、会社の責任で休業したと判断されず、休業手当を支給しなくても問題ありません。しかし、会社の過失により火災が発生した場合など、不可抗力だと思われる場合でも、使用者に責任があると認められれば、休業手当を支払わなければならないので注意が必要です。
2-2. 従業員本人に労働意欲と労働能力がある
会社の都合で休業状態にあったとしても、従業員本人に労働意欲と労働能力がない場合は支給の条件にあてはまりません。従業員本人がケガや病気によってすぐに勤務できない状態の場合、労働能力がないと判断され、休業手当は支払われません。
また、労働意欲がある状態でないと休業手当の支給対象とはなりません。そのため、労働者自身がストライキに参加している場合などは、労働意欲がないと認められ、休業手当の支給対象とならないので注意しましょう。
2-3. 休業日が休日ではない
休業手当は、本来勤務する予定であったにもかかわらず、会社の事情で働けなくなった場合に支給されます。そのため、労働の義務が発生する日が支給の対象となり、勤務しない休日は休業手当の対象になりません。
2-4. 時間単位の休業も対象になる
労働基準法に基づく休業とは、労働義務が課されている時間帯に労働者が働けなくなることです。そのため、1日休業する場合だけでなく、時間単位や半日単位で休業する場合も、使用者の責めに帰すべき事由によって休業するのであれば、休業手当を支払わなければならないので注意しましょう。
3. 労働基準法による休業手当の計算方法

休業手当の計算手順は次のとおりです。
- 直前3カ月間の平均賃金を求める
- 平均賃金に60%(以上)と休業日数を掛ける
この手順によって算出された金額が休業手当となります。ここからは、休業手当の具体的な計算方法について紹介します。
3-1. 平均賃金を計算する
労働基準法で支給すべき休業手当の額は、平均賃金の60%以上です。この平均賃金とは、労働基準法第12条で定められており、直近3カ月間に支払われた賃金の総額を総日数で除して求められる賃金のことです。なお、直近3カ月間の起算日は、休業が発生した日が原則です。しかし、賃金の締め切り日がある場合、直前の賃金の締め切り日から起算して計算をおこないます。
平均賃金には、通常の基本給に加えて、通勤手当や残業手当などの手当も含めます。たとえば、次のようなケースであれば、基本給、通勤手当、残業手当を合わせた金額は66万円です。
| 月 | 総日数(暦日数) | 基本給 | 通勤手当 | 残業手当 |
| 9月分 | 30日 | 20万円 | 1万円 | 0円 |
| 8月分 | 31日 | 20万円 | 1万円 | 1万円 |
| 7月分 | 31日 | 20万円 | 1万円 | 2万円 |
| 合計 | 92日 | 60万円 | 3万円 | 3万円 |
66万円を総日数92日で割ると、7,173円91銭が3カ月間の平均賃金と算出されます。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(省略)
3-2. 休業手当を求める
直近3カ月の平均賃金が求まったら、それに60%を掛けて1日あたりの休業手当を計算します。たとえば、直近3カ月の平均賃金が7,173円91銭であれば、平均賃金の60%は4,304円34銭と計算されます。仮に休業により3日出勤できなかったとすると、休業手当は次の通りです。
休業手当では特約がなければ、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げとなるため、12,913円が支払うべき休業手当となります。
3-3. 【注意】平均賃金には例外の計算方法がある
平均賃金を計算する場合、労働基準法第12条によって、さまざまな特例が定められています。たとえば、直近3カ月間に次の期間が含まれる場合、その日数と賃金額は控除して計算します。
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
- 療養のための休業期間
- 産前産後休業期間
- 育児・介護休業期間
- 試用期間
また、雇用されてから3カ月に満たない労働者は、直近3カ月の平均賃金を計算できないため、雇入後の期間で平均賃金を計算します。さらに、日雇労働者も、直近3カ月の平均賃金の計算が困難なので、別の方法で算出されます。その他にも、最低賃金には最低保障額があります。労働基準法の平均賃金の規定を正しく理解し、労働者に応じて正しく休業手当を計算するようにしましょう。
関連記事:労働基準法の平均賃金とは?計算方法や端数処理、最低保障額をわかりやすく解説!
4. 労働基準法による休暇手当に関する注意点

労働基準法に基づく休暇手当には、いくつか気を付けるべき点があります。ここでは、労働基準法による休暇手当に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 会社都合の休業であれば賃金を全額請求できる
民法第536条に基づき、会社都合による休業であった場合、反対給付として、労働者は賃金を全額請求できる権利があります。労働基準法上は、平均賃金の60%を支給すれば問題ありませんが、民法上は、請求があれば休業中に支払うべき賃金をすべて支給しなければならないと考えられるため注意が必要です。なお、使用者に責めに帰すべき事由がなければ、この規定は適用されず、労働者に賃金請求権は発生しないので正しく理解しておきましょう。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 (省略)
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。(省略)
4-2. 休業手当の定めを就業規則に明記しておく
労働基準法第89条に則り、常時従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。休業手当は「賃金」に該当するため、休業手当の決定方法や計算方法、支払い方法をきちんと就業規則に明記しておく必要があります。
たとえば、労働者を保護するため、休業手当の額を平均賃金の70%と、就業規則で法定以上に設定することもできます。また、どのように休業手当を計算するのか、いつ休業手当を支払うのかなども細かく就業規則に記載しておくことで、いざ休業手当を支給しなければならない状況となったときに、労使間のトラブルを防止し、スムーズに手続きを進めることが可能です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(省略)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(省略)
4-3. 休業手当はパート・アルバイトにも支給される
休業手当はすべての労働者が対象になります。そのため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも支給対象に含まれます。一方、個人事業主やフリーランスなど、労働契約を結ばず働く人は、労働者でないので、休業手当の支給対象に含まれません。また、派遣社員は、派遣先でなく、派遣元と雇用契約を締結しているため、派遣元に責めに帰すべき事由があって派遣労働者を休ませる場合、派遣元が休業手当を支給しなければならないので気を付けましょう。
4-4. 所定休日は休業手当の対象から除かれる
事業主は労働者に対して、法定休日(週1日または4週4日)を付与しなければなりません。しかし、法定休日のみだと、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてしまうため、所定休日(法定外休日)を設けている企業も少なくないでしょう。
休業日が休日に該当する場合、休日手当を支払う義務はありません。この休日には、法定休日だけでなく、所定休日も含まれます。これは、所定休日も法定休日と同様で、もともと労働の義務がない日と設定しているためです。
関連記事:法定休日と所定休日の違いは?割増賃金のルールや注意点を解説
4-5. 休業手当は給与所得として課税される
休業手当は、給与所得に該当することになり、通常の給与と同様で所得税の課税対象です。休業手当は、休業がなかった場合の給与とみなされることが理由の一つといえます。一方、休業補償は、所得税法第9条に基づき、業務上の病気やケガに対する療養のための給付金としての性格を有するため非課税とされています。このように、休業手当を支払った場合、課税対象として、源泉徴収や年末調整が必要になるので注意しましょう。
1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(省略)
三 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ (省略)又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
5. 労働基準法による休業手当に関するよくある質問
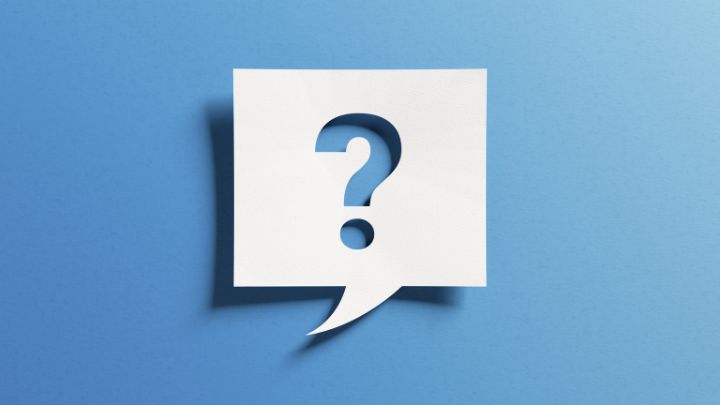
ここでは、労働基準法による休業手当に関するよくある質問への回答を紹介します。
5-1. 健康診断結果に基づき休ませる場合も休業手当の支給が必要?
労働安全衛生法第66条に則り、事業者は労働者に一定の健康診断を受けさせる義務があります。また、労働者は、事業者が法律に基づき実施する健康診断を受ける義務もあります。それでは、健康診断の結果に基づき、労働者を休ませる場合も、休業手当を支払わなければならないのでしょうか。
健康診断の結果を受けて労働者を休業させる場合、不当な取り扱いに該当しなければ、通常の病欠扱いとなり、休業手当を支払わなくても問題ありません。ただし、後でトラブルを生まないよう、給与や手当の支給がないことや、診察料は労働者が負担することなどを事前に周知し、同意を得るようにしましょう。なお、労働災害でない個人的な病気やケガによって休まなければならない場合、傷病手当金を受け取れる可能性もあるので、きちんと周知しておきましょう。
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
(省略)
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。(省略)
5-2. 半日労働をした後に半日休業した場合の休業手当の支給方法は?
会社都合によって時間単位や半日単位で休業をおこなった場合も、休業手当の支給義務が生じます。休業手当は1日あたり平均賃金の60%を支払わなければならないため、半日働いた分の給与がこれに満たない場合、差額分を休業手当として支給する必要があります。
たとえば、1日8時間勤務、1時間あたりの平均賃金1,000円の勤務形態で、半日(4時間)労働し、半日(4時間)休業した場合を考えてみましょう。この日に支給される給与は4,000円(= 1000円 × 4時間)ですが、休業手当としてその日は4,800円(= 1,000円 × 8時間 × 60%)以上の賃金を支払わなければなりません。そのため、給与を4,000円支給し、差額の800円を休業手当として支給すれば法律の要件を満たすことができます。
5-3. 休業期間中に年次有給休暇を申請できる?
休業手当と有給休暇手当では、金額は一般的に有給休暇手当のほうが大きいため、休業期間中に年次有給休暇を取得したいと考える人もいるかもしれません。有給休暇とは、給与が出たうえで、その日の労働義務が免除される休暇のことです。
そのため、有給休暇を申請した時点で、その日に労働義務があるかどうかが重要なポイントとなります。たとえば、休業の命令が出る前に、有給休暇を申請していた場合、申請時点において休業日は労働義務がある日であったため、原則として、有給休暇の申請を認める必要があります。一方、休業の命令が出た後に、有給休暇の申請をおこなう場合、申請時点において休業日は確定していて、労働義務が免除されているので、有給休暇の申請を拒否することが可能です。
6. 休業手当の支給条件と計算手順を把握して正しく支給を!

休業手当は会社都合により休業し、労働者に労働意欲と労働能力がある場合に支給されます。また、休業日が休日に該当しないことも条件の一つです。休業手当はすべての労働者が対象になるので、正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣社員に対しても支給しなければなりません。休業手当の計算方法は、労働者ごとに変わる可能性もあるので、法律に基づき正しく算出し、休業手当を支払うようにしましょう。
労働基準法総まとめBOOK









