
労働基準法第67条には、満1歳未満の子どもを育てている女性労働者が利用できる育児時間に関する定めがあります。就業規則によって、父親(男性)でも育児時間を利用できるケースがあります。本記事では、労働基準法の育児時間の定義や、その使い方についてわかりやすく解説します。また、育児時間中の賃金は有給と無給のどちらかも紹介します。。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法の育児時間とは?

労働基準法の育児時間とは、労働基準法第67条で定められた育児をしながら働く女性を支援するための制度です。ここでは、労働基準法の育児時間の使い方やポイントを詳しく紹介します。
1-1. 育児時間の使い方
労働基準法第37条に則り、満1歳未満の子どもを養育している女性労働者は、原則として、1日2回それぞれ30分以上の育児時間を請求することができます。育児時間の使い方は法律で制限されていません。そのため、授乳のほか、子どもの送り迎えや、病気・ケガのための通院、育児に必要な物品の買い物など、さまざまな使い方が可能です。
育児時間の取得タイミングについては法律に明記されていないため、労使で話し合い決めることが望ましいです。子どもが急に体調を崩したなど、急に育児時間が必要になるケースもあるので、労働者が好きなタイミングで柔軟に利用できるように、制度を整備しておくことが推奨されます。
1-2. 1回にまとめて育児時間を取得することも可能
労働基準法では、育児時間を労働時間の途中に取得するなど、取得方法の決まりを定めていません。そのため、始業してからすぐに30分の育児時間を取得したり、終業の少し前に30分の育児時間を取得したりしても問題ありません。また、2回分の育児時間を1回にまとめて1時間の育児時間を取得できるようにすることも可能です。使用者は女性労働者が柔軟に育児時間を取得できるような制度を整備しましょう。
1-3. 父親(男性)は育児時間を請求できない
労働基準法第67条に規定されているように、育児時間の対象者は、生後満1年未満の子どもを育てる女性です。そのため、男性労働者は、基本的に育児時間を請求することができません。
しかし、仕事と育児を両立する父親をサポートするため、会社独自で男性労働者でも条件を満たせば、育児時間を取得できる可能性があります。男性労働者で育児時間を取得できないか考えている人は、まずは就業規則をチェックし、会社の担当者に相談してみましょう。
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
②使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
2. 労働基準法の育児時間の計算方法

労働基準法の育児時間は具体的にどのように計算されるのでしょうか。ここでは、労働基準法の育児時間の計算方法について詳しく紹介します。
2-1. 育児時間に休憩時間は含まれない
労働基準法第67条に基づき、育児時間には休憩時間は含まれないこととなっています。労働基準法第34条に則り、労働時間が6時間超え8時間未満の場合は45分以上、8時間超えの場合は1時間以上の休憩時間を付与しなければ違法になります。また、休憩時間は労働時間の途中で与えるなど、制限もあるので注意が必要です。
たとえば、9時始業、17時終業(休憩1時間)の勤務形態で、育児時間を1日1回30分取得した場合を考えてみましょう。育児時間は休憩時間を除いて考えるため、この日の労働時間は6時間30分(= 8時間 – 1時間 – 30分)となります。このように、育児時間は業務をおこなっていないので、労働時間に含めないことも押さえておきましょう。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(省略)
関連記事:労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説!
2-2. 育児時間には移動時間も含める
子どもの送り迎えなどには、会社と自宅、自宅と保育所などを行き来する時間が発生します。このような移動時間も育児時間に含めて考えます。たとえば、会社と自宅の往復時間が20分、授乳時間が10分であった場合、育児時間は30分となり違法になりません。
しかし、移動時間により、実際に育児に使えた時間が短くなれば、育児時間の目的が果たされません。そのため、労働者が柔軟に育児時間を利用できるよう、融通が利きやすい制度を整備しましょう。
2-3. 1日4時間以内の勤務であれば1日30分でも問題ない
労働基準法第67条に基づくと、どのような労働者でも、1日2回それぞれ30分以上の育児時間を与えなければならないと解釈できます。しかし、労働基準法の育児時間の規定は、1日8時間勤務の勤務形態を想定し、設計された制度です。そのため、1日の労働時間が4時間以下の場合、1日1回30分以上の育児時間を与えれば問題ないとされています。
育児時間は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、1日2回の附与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の附与で足りる。
参考:基収第8996号・昭和36年1月9日
2-4. 育児時間は時短勤務と併用が可能
育児時間は労働基準法、時短勤務は育児・介護休業法で定められたそれぞれ異なる制度です。育児時間と時短勤務は、対象者の要件を満たしていれば、併用することができます。育児時間と時短勤務の主な違いは、次の表の通りです。
|
育児時間 |
時短勤務(短時間勤務) |
|
|
法律 |
労働基準法第67条 |
育児・介護休業法第23条 |
|
子どもの年齢 |
1歳未満 |
3歳未満 |
|
所定労働時間 |
変更なし |
短くなる |
|
労働者の性別 |
女性のみ |
男性・女性 |
育児時間を利用できるのは、1歳未満の子どもを養育している女性労働者のみです。一方、時短勤務を利用できるのは、3歳未満の子どもを養育している労働者です。そのため、時短勤務は、母親だけでなく、父親も活用できるため、育児時間よりも幅広い労働者が利用できます。しかし、育児休業を取得していないなど、時短勤務を利用するためのその他の要件もあるので注意しましょう。
(所定労働時間の短縮措置等)
第二十三条事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。(省略)
関連記事:時短勤務(短時間勤務)とは?いつまでが適用期間?メリット・デメリットもわかりやすく解説!
3. 労働基準法の育児時間における賃金の計算方法
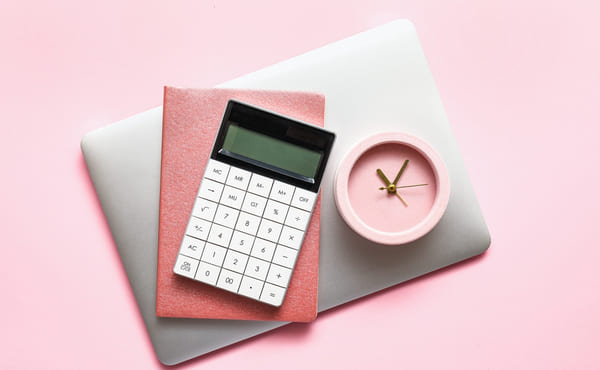
労働基準法の育児時間を利用した場合、その時間も給与が支給されるのか気になる人は少なくないでしょう。ここでは、労働基準法の育児時間における賃金の計算方法について詳しく紹介します。
3-1. 育児時間中の給与は無給
育児時間中の給与は、原則として無給です。労働基準法に育児時間中の賃金に関する記載はありません。そのため、働いていない時間には賃金が発生しないノーワーク・ノーペイの原則に基づき、育児時間には賃金が発生しないことが一般的です。
3-2. 就業規則に記載があれば別途手当などを支給できる
労働基準法に育児時間中の給与支給に関する規定はないため、育児時間中の賃金を有給と無給のどちらかにするかは、事業者の裁量で決めることができます。そのため、育児時間を利用した場合、一定の手当を支給するなどと就業規則に記載すれば、育児時間を取得しても一定の賃金が保障されることとなり、仕事と育児の両立をする女性労働者をサポートすることにつながります。
4. 労働基準法の育児時間に関する注意点
 労働基準法の育児時間に関して、気を付けておきたい点がいくつかあります。ここでは、労働基準法の育児時間に関する注意点について詳しく紹介します。
労働基準法の育児時間に関して、気を付けておきたい点がいくつかあります。ここでは、労働基準法の育児時間に関する注意点について詳しく紹介します。
4-1. 育児時間に関する定めは就業規則に明記しておく
必ずしも育児時間の規定は就業規則に定める必要はありません。しかし、就業規則に育児時間に関する記載がない場合、労使間で育児時間の請求・取得に関するトラブルが発生する可能性があります。
そのため、育児時間の請求方法や賃金・手当の有無などを就業規則に細かく明記しておくことが大切です。また、仕事と育児を両立する労働者を支援するため、事後申請の許可や男性の育児時間の取得などについても、就業規則に盛り込めないか検討してみましょう。
関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項、作成・変更時の注意点を解説!
4-2. 妊産婦に対する労働基準法の規定を確認しておく
妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のことです。産後1年を経過していない妊産婦は、育児時間だけでなく、労働時間の制限など、労働基準法に基づくさまざまな保護を受けられます。
たとえば、労働基準法第66条により、妊産婦が事業主に請求すれば、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、法定休日(週1日もしくは4週4日)の労働、深夜帯(22時から5時まで)の労働を制限することができます。また、妊産婦に対して坑内業務や危険有害業務に就かせることは原則できません。このように、育児時間だけでなく、妊産婦の規定もきちんとチェックし、社内制度を整備しましょう。
第六十六条 (省略)
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
関連記事:労働基準法による妊婦を守る制度についてわかりやすく紹介
4-3. 育児時間の申請を拒否した場合は罰則がある
女性労働者から育児時間の申請があった際にそれを拒否した場合や、育児時間中に業務をおこなわせた場合、労働基準法第67条「育児時間」の規定に違反することとなります。この場合、労働基準法第119条に則り、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。罰則を受けないためにも、正しく労働基準法の育児時間の規定を理解し、定期的に社内制度を見直すことが大切です。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第六十四条の三から第六十七条まで、(省略)の規定に違反した者
4-4. 育児時間の取得を理由にした不利益取り扱いは禁止されている
男女雇用機会均等法第9条、男女雇用機会均等法施行規則第2条の2に基づき、育児時間の請求や取得をしたことによって、不当な給与減額や解雇などの不利益取り扱いをすることは違法となります。女性労働者に育児時間を気持ちよく取得させることは、使用者の義務と考え、適切な社内制度を整備しましょう。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第二条の二 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
(省略)
八 労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。
引用:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(男女雇用機会均等法施行規則)第2条の2一部抜粋|e-Gov
5. 労働基準法の育児時間に関するよくある質問

ここでは、労働基準法の育児時間に関するよくある質問への回答を紹介します。
5-1. 変形労働時間制の場合はどのように育児時間を付与する?
変形労働時間制とは、週や月、年単位で労働時間を設定することで、1日10時間労働、週45時間労働など、一時的に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えても違法にならない働き方制度です。
変形労働時間制を採用する場合、日々労働時間が変わるため、どのように育児時間を付与すべきかわからない人もいるかもしれません。労働基準法の育児時間の規定は最低基準を定めたものであるため、労働時間の制限を受けず変形労働時間制を採用している労働者で、1日の所定労働時間が8時間を超える場合、法定で定められている以上の育児時間を付与することが望ましいとされています。
三 特別の配慮を要する者に対する配慮
(省略)その場合に、法第六七条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであるので、法第六六条第一項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、一日の所定労働時間が八時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮をすることが必要であること。引用:基発第45号・平成11年1月29日
関連記事:変形労働時間制とは?残業の考え方や導入方法、注意点をわかりやすく解説
5-2. パート・アルバイトや派遣社員にも育児時間は必要?
パート・アルバイトや派遣社員なども労働者に該当するため、労働基準法が適用されることになります。そのため、労働基準法の育児時間の対象者の要件を満たす場合、雇用形態に関係なく、育児時間を取得させる必要があります。ただし、1日4時間以内で働く労働者は、1日1回30分の育児時間の付与でも違法とはならないので、正しくルールを押さえておきましょう。
5-3. 育児時間は何歳まで取得できる?
労働基準法の育児時間は満1歳未満の子どもを育てている女性であれば、労働者が何歳であっても取得できます。なお、1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日を指します。そのため、子どもが1歳の誕生日を迎える前々日までであれば、育児時間を取得することが可能です。なお、子どもは、養子であっても育児時間を取得することができます。
6. 労働基準法の育児時間は自社の魅力につながるチャンスでもある!

労働基準法では1歳未満の子どもを育てている女性従業員を対象に、勤務時間に応じた育児時間の取得を認めています。育児時間には賃金が発生しないのが一般的ですが、実際の対応は企業によって異なります。また、男性従業員の育児時間の取得が認められるケースもあります。このように自社の就業規則に判断が委ねられるため、企業側は育児時間についてのルールを明確にしておきましょう。柔軟なルールを設けることで、自社の魅力につながる可能性があります。
労働基準法総まとめBOOK









