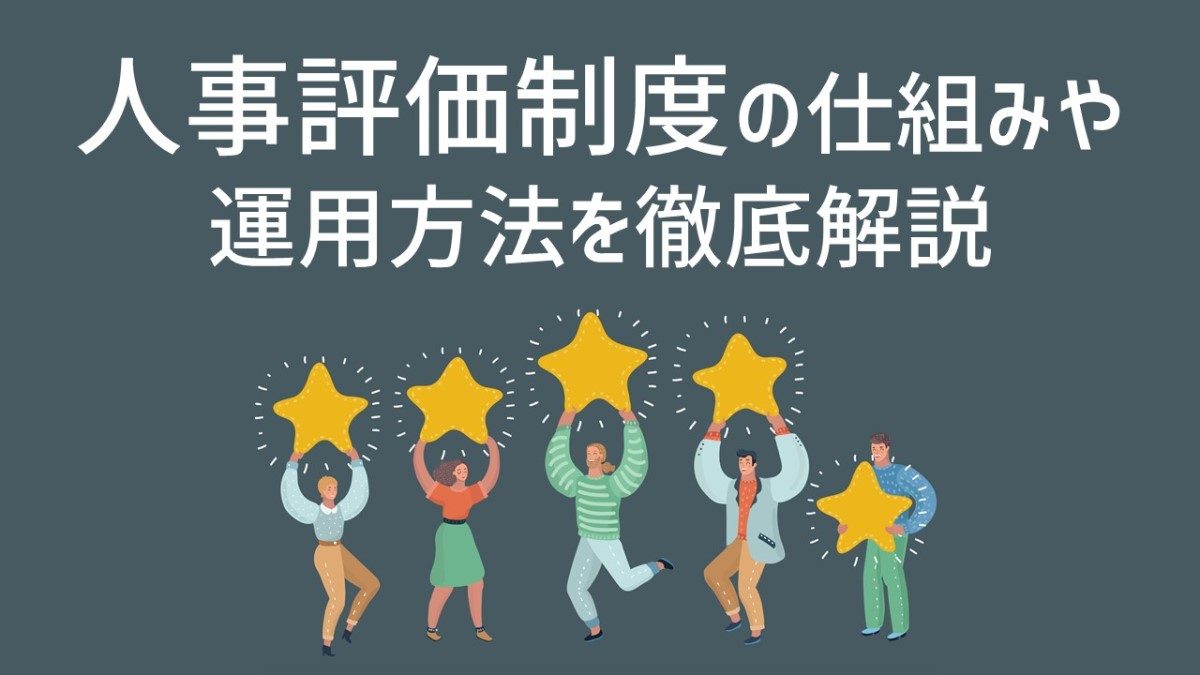
人事評価制度は、MBO(目標管理制度)マネジメントと連動し、社員の貢献度や能力を評価し、昇給や昇格などの処遇へ反映させる制度です。
人事諸制度の根幹といっても過言ではありません。導入においては、人事制度との連携を十分に検討することが重要です。
そこで本記事では、人事評価制度について、目的や評価基準の設定方法、導入までの流れなどを網羅的に紹介します。
「人事評価制度を導入したい」「自社に合った人事評価制度を知りたい」「具体的な導入のポイントを知りたい」といった悩みを持つ人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 人事評価制度とは?目的や役割を詳しく解説

人事評価制度とは、社員のがんばりや能力を評価して、昇給や昇進、昇格、賞与などに反映するための仕組みで、人材戦略の根本となる制度です。
「人事評価」と似たような言葉に「人事考課」がありますが、「人事考課」は昇給や賞与の査定のための評価を意味しており、「人事評価」は社員の業績貢献度だけでなく能力評価なども含みます。
人事考課は短期的な評価で、人事評価は考課を含んだ中長期的な評価といえるでしょう。
1-1. 人事評価と人事制度の関係
人事評価制度は、
- 賃金制度
- 昇進昇格制度
- 教育制度
- 福利厚生制度
といった「人事制度」のうちのひとつです。
社員の貢献度や能力を正しく把握し、賃金制度や昇進昇格制度、教育制度に反映させ、社員の処遇や育成を適正化するための仕組みが人事評価です。人事評価は、人事制度全般に関わる重要なプロセスだといえます。
1-2. 人事評価制度の目的
人事評価制度を導入する目的は3つあります。
【人事評価制度を導入する目的】
- 社員の貢献を業績向上につなげる
- 社員の処遇改善につなげる
- 社員の成長につなげる
社員の貢献を業績向上につなげる
人事評価制度の大きな目的は、社員の貢献を業績向上につなげることです。上司は、貢献目標に対する成果を評価するためのMBO(目標管理制度)とともに人事評価制度を用いて、被評価者の目標達成を促します。明確で公正な評価をされることで被評価者のモチベーションが高まり、その結果、会社業績が向上する仕組みを作ることができます。
社員の処遇改善につなげる
社員の「どのように頑張れば昇給するのか」という疑問に対しても、人事評価制度は機能します。人事評価制度と昇進昇格制度を連動させることで、社員の処遇改善を実現できます。人事評価制度は、処遇につながる制度として就業規則と同じ位置づけで社員に明示しましょう。
社員の成長につなげる
社員を成長させることも人事評価制度の目的のひとつです。評価に関してフィードバックする場面では、結果だけでなくその理由やどの能力を伸ばすとよいかを伝えます。良かった点と改善点を共有することで社員の成長につながり、組織力の強化も図れるでしょう。
2. 人事評価制度を運用するメリット

人事評価制度の運用には、個々の従業員の働きぶりやスキル、問題点などを明らかにするという大きな目的があります。人材の特質を把握したうえで給与や待遇に反映できることが、企業の人事評価制度のメリットです。
また、人事評価制度には人材育成の促進やモチベーションの向上といったメリットもあります。以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
2-1. 人材育成につながる
企業における人事評価制度では、従業員の立場や役職に応じた評価基準を設定します。その従業員にどのような能力や働き方を求めているのか、どのような意識を持ってもらいたいのかを明確にすることが、適正な評価のポイントです。
人事評価において従業員に求める要件が明示されていれば、従業員は今後どのような働き方をすればいいかという方向性を把握できるようになります。また、評価する側である上司にとっても、人事評価は部下をどう育成すべきかという方針を知れるまたとない機会となるはずです。
人事評価を通して現状の課題や問題点を客観的に明らかにすれば、効率のよい人材育成を実現できます。人事評価をおこなったあとには必要に応じて教育や研修、勉強会などを実施し、育成に取り組んでいくことが大切です。
2-2. 従業員のモチベーション向上
人事評価には、従業員のモチベーション向上につながるという大きなメリットもあります。
基準が明確で、公平性や透明性の高い評価制度が運用されていれば、社員はその評価に納得しやすくなります。自身の働きが人事評価という形で認められることで、従業員のやる気はどんどんアップしていくでしょう。
評価の基準を示すことは、企業の理念や目標への理解を深めてもらうことにもつながります。理念に即した指針や評価基準を織り込むことで、どのような人材が評価されるのかが伝わるようになります。人事評価を通して企業と従業員の方向性を一致させておけば、目標に向かって会社全体が一丸となって進むことができるでしょう。
ただし、評価基準があいまいだったり不公平だったりすると、かえって従業員のモチベーションが低下する可能性もあります。人事評価の際には適切な指針を明示し、従業員からの信頼を得ることが大切です。
2-3. 適切な人材配置を実現できる
適切な人材配置を実現できることも、人事評価制度を運用するメリットのひとつです。人事評価制度をうまく運用することで、従業員ごとの特性や得意分野・苦手分野を把握できます。
評価内容を参考にして従業員が成果を出しやすい部署に異動したり、チームを再編成したりすれば、人材配置を最適化できるでしょう。成果を出せることで従業員のモチベーションアップにつながるだけではなく、業務効率化や業績アップも期待できます。
3. 人事評価制度を構成する3つの要素
人事評価制度は、等級制度・評価制度・報酬制度という3つの要素によって構成されます。それぞれの要素の詳細は以下の通りです。
3-1. 等級制度
等級制度とは、従業員に求めるスキルや役割などを分類し、階層化した仕組みのことです。等級ごとに必要なスキルや果たすべき役割を設定し、一覧表のようにまとめている企業も多いでしょう。
明確な等級制度を設定しておくことで、自分は今どのランクにいるのか、何を求められているのか、次のランクに上がるために何をすべきなのか、といったポイントを従業員自身が把握しやすくなります。
3-2. 評価制度
評価制度とは、従業員のスキルや働き方を評価する仕組みのことです。評価の基準や手法については後ほど詳しく解説しますが、業績評価・能力評価・行動評価といった方法があります。また、評価をもとに等級を変更したり、報酬を増減したりするなど、等級制度や報酬制度と連動させるのが一般的です。
3-3. 報酬制度
報酬制度とは、従業員ごとの評価や等級をもとに賃金を決定する仕組みのことです。評価に応じて給与や賞与をアップしたり、等級に合わせて退職金を決定したりする企業も多いでしょう。
賃金以外の報酬を与えるケースもあります。たとえば、等級に応じた学習機会を与える、社内で表彰する、といった方法が挙げられます。賃金アップはもちろん、貢献度に見合った報酬を与えることで従業員のモチベーションアップを図れるため、しっかりと制度を設計しておくことが大切です。
4. 人事評価制度における基準

人事評価制度には、業績評価・能力評価・行動評価など、さまざまな基準があります。
人事評価制度をうまく運用するために、自社に合った基準を選びましょう。
4-1. 業績評価
業績評価においては、従業員がコミットした目標の達成度を評価します。
たとえば、営業に関わる従業員の売上目標に対する達成度や、企画に関わる従業員のKPI目標の達成度などを評価するケースが多いでしょう。業務内容によっては評価が難しい場合もありますが、可能な限り曖昧な表現を避け、わかりやすい数値で評価します。
4-2. 能力評価
能力評価とは、従業員の能力やスキルを評価する手法です。
主に昇格や昇進を判定するために使われます。能力評価のポイントは、”能力を保有しているか”ではなく、”その能力が発揮されているか”を評価することです。
評価期間中に発揮された能力を評価することを「コンピテンシー評価」といいます。
4-3. 行動評価
行動評価は、その名の通り「どのように行動したか」を評価する手法です。
走り幅跳びにたとえると、「何メートル飛べたか」に注目するのが業績評価で、「その結果を出すためにどのような準備や努力をしたか」に注目するのが行動評価といえます。
たとえば、工場の生産ラインでは、チーム長はチームの業績で評価されます。しかし、協働して成果を出すことを求められるメンバーひとりひとりに対して、成果を明確に把握して評価することは難しいでしょう。
工場の生産ラインのように、個人目標を設定しにくい環境においては、行動評価を採用することで適正な評価を実現できます。
4-4. 情意評価
情意評価においては、勤務態度や責任感などを評価します。「新しい仕事に挑戦したか」「責任感を持って仕事をこなせたか」といったポイントで評価するのが一般的です。
「態度評価」とも呼ばれ、新入社員など、業績への貢献度による評価が難しい場合に採用するケースが多いでしょう。
4-5. 360度評価
360度評価とは、上司だけではなく、同僚や部下など、さまざまな視点から評価をおこなう手法です。「多面評価」とも呼ばれ、従業員のいろいろな面を総合的に評価することが期待できます。
しかし、必ずしも評価研修を受けた人が評価するわけではないため、客観性や過去評価との連続性を得ることが難しい方法です。
4-6. MBO(目標管理制度)
MBO(Management by Objectives:目標管理制度)とは、従業員ごとの目標や部署全体の目標を設定し、その達成度を評価する手法です。MBOのメリットとしては、目標が明確であるため努力しやすいこと、客観的に評価できること、評価への納得感を得やすいことなどが挙げられます。一方で、達成するのが不可能な目標を設定すると、従業員のモチベーションが下がってしまうケースもあるため注意しましょう。
4-7. OKR(目標・成果指標)
OKR(Objectives and Key Results:目標・成果指標)とは、先ほどのMBOよりも高い目標を設定し、従業員の育成や企業全体の業績アップを図る手法です。OKRはMBOとは異なり、目標を100%達成する必要はありません。達成するのが難しい目標を設定するため、60〜70%の達成で成功と見なすケースが多いでしょう。
4-8. ノーレイティング
ノーレイティングとは、ランクや等級を付けない評価手法です。ここまで紹介したような評価手法においては、半年や1年といった単位で評価を実施しますが、ノーレイティングでは、基本的にリアルタイムで評価をおこないます。その結果、スピーディな目標達成やモチベーションの維持を期待できます。
変化が激しい業界において有効な手法ではありますが、評価する側の負担が大きくなるというデメリットもあるため注意が必要です。
5. 人事評価制度を導入するまでの手順

人事評価制度は、導入後に現場で運用できるかどうかで効果が変化します。
新たな人事評価制度の導入や、既存の人事評価制度の変更を考えている人事担当者の方は、人事評価制度を導入するまでの手順を振り返っておきましょう。
5-1. 人事評価制度の目的を決める
人事担当者の方はまず、人事評価制度を導入する目的を明確にします。
たとえば、インセンティブの配分を決めることを目的とする場合は、短期的な利益貢献度を把握できる評価制度を検討しましょう。
また、昇進昇格の判断を目的とする場合は、短期ではなく中長期的な評価の仕組みが必要です。
評価制度の目的は制度全体に影響を与えるため、慎重に設定しましょう。
5-2. 従業員社員の業務内容を理解する
次に、従業員の業務内容と働き方を十分に理解し、それらにマッチした人事評価制度を検討します。
「個人目標を掲げている業務」なのか「チームで協働する業務」なのか、しっかりと見極めます。さらに、従業員は”何を評価してもらいたいのか”をアンケートで把握しておくとよいでしょう。
5-3. 評価項目を決定する
評価項目を決める際は、「何に注目して評価するか」に注意しましょう。
たとえば、”勤務態度”と”チームワーク”という項目を設定した場合、「勤務態度が良いからチームワークも良いだろう」といった評価になりがちです。
このように、一つの項目の評価が他の項目の評価に影響しやすい設定は避けるべきです。
5-4. 評価と処遇を連携する方法を決める
評価方法としては、「◎」や「S」などの評価記号を使用する「レイティング評価」や、評価記号を使わない「ノーレイティング評価」があります。
評価を処遇につなげるためには、何らかのアウトプットが必要です。「評価記号を使うのか・使わないのか」「昇給や昇格昇進制度にどのように反映させるか」といった連携方法を考えましょう。
5-5. 規定としてまとめる
人事評価制度の目的や評価項目は、従業員に明示しましょう。
人事評価制度を明確な規定としてまとめることで、従業員は何が評価されるのかを知り、会社の求める業績や行動、人材像を理解することができます。企業理念の浸透やモチベーションアップも期待できるでしょう。
5-6. 評価者研修をおこなう
評価を公正におこなうためには、評価のバラつきを抑えることが重要です。
しかし、評価する側も人間であるため、上司によって評価の厳しさにバラつきが生じるケースもよくあります。そこで、評価者に対して研修をおこない、評価の基準を統一させましょう。
とくに、評価項目や評価記号の意味、心理的なバイアスについて理解してもらうことが重要です。”S評価は全社的な貢献があった場合に相当する”など、認識のすり合わせもおこないましょう。
5-7. 従業員へ説明する
人事評価制度に関する説明は、管理職などの上位層からおこなうとよいでしょう。
可能であれば人事部門が従業員に説明し、「評価が処遇とどのようにつながっているか」といった質問に答えながら進めましょう。
6. 人事評価制度を成功させるためのポイント

人事評価制度は、導入後に現場で運用されなければ効果がありません。人事評価制度の導入を成功させるためには、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 現場の運用が容易である
- 評価の公平性がある
- 処遇の結果に納得性がある
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
6-1. 現場の運用が容易な制度設計にする
人事評価制度を導入するときは、従業員にも評価者にもわかりやすい制度設計にすることが大切です。複雑すぎると、どのように行動すれば評価されるのかがわからなかったり、評価が難しくて評価者の負担が増えたりしてしまいます。人事評価制度は、現場での運用が定着してこそ効果を発揮するものです。丁寧に制度を設計することはもちろん、現場でしっかりと運用されているか、随時チェックするようにしましょう。
6-2. 評価の公平性や客観性を確保する
評価に公平性や客観性がなければ、従業員の納得感を得られず、自身の処遇や会社に対する不満が発生してしまいます。
導入初期は、直属の上司だけでなく、一段上の上長が俯瞰的に評価するなどして評価の公正性を高めるとよいでしょう。評価者が一方的に評価するのではなく、被評価者との評価面談をおこなうことも有効です。
6-3. 評価をもとに適正な処遇につなげる
従業員の評価を実施したあとは、適正な処遇につなげましょう。
評価の低い人が高い人よりも多くの報酬を得たり、評価の割に報酬が少なかったりすると、従業員の納得感を得られません。バランスのよい、適正な処遇を心がけることが重要です。また、評価結果に出勤率を掛け合わせるなど、評価以外の項目を用いる場合は、社員へ説明しておきましょう。
7. 人事評価制度の失敗事例
以下のような場合、人事評価制度の失敗につながるため注意しましょう。
- 公正な評価でない
- 従業員が評価してほしい点とのギャップがある
- 評価者のスキルが不足している
それぞれの失敗事例について詳しく解説します。
7-1. 公正な評価でない
人事評価制度の運用に失敗してしまう大きな原因として、評価者の判断の自由度が高すぎることが挙げられます。
営業成績などの数字だけで評価する場合は、評価者の主観や判断が入る余地は少ないのですが、”優秀”、”秀”といった評価を付ける場合は、評価者によって判断が異なり、公平性が失われる可能性もがあります。
評価者のブレを少なくすることが公正な評価への道です。
評価者研修などを通して、評価制度への理解だけでなく、日常のコーチから評価までのプロセスを覚えてもらいましょう。
7-2. 従業員が評価してほしい点とのギャップがある
従業員が”ここを評価してほしい”と思っていることと、会社の評価の視点がまったく違うと、従業員のモチベーションは下がり、目標達成がされず会社の業績にも影響します。
従業員が何を大事に思って仕事をしているかを把握し、評価に取り入れていきましょう。
7-3. 評価者のスキルが不足している
評価者のスキルが不足していることも、人事評価制度の導入に失敗する理由のひとつです。人事異動で上司が入れ替わったり、外部から新しい人材を採用したりする場合、評価者の評価スキルに差が出てしまうケースもあります。
定期的に評価者研修を実施し、評価者のスキルを常に高めることが必要です。
8. 人事評価制度において重要な評価者のスキルとフィードバック面談

評価者には、評価制度への理解だけでなく、目標設定のスキルや客観的に思考するスキルが求められます。
- 目標設定のスキル
- 観察とコーチングのスキル
- 客観的に思考するスキル
目標設定のスキルとは、組織目標を理解し個人目標に落とし込むスキルです。上位目標を理解し、さらに従業員個人の能力やスキルに合わせて目標を設定します。
また、評価者は被評価者を観察し、コーチングを実施します。評価者の役割は、被評価者の目標を達成させることです。
評価時にだけ「○」「×」を付けるチェックパーソンにならないようにしましょう。そのために日常の観察とコーチングのスキルが必要です。
そして、客観性のある評価を実施するために、ハロー効果やステレオタイプを補うスキルが必要です。評価におけるハロー効果とは、目立った一部分だけで評価をしてしまうことです。
ステレオタイプは、固定的な概念で評価をしてしまうことです。評価者研修などにより、評価者自身の傾向を知ってもらい、客観性のある評価を実施してもらいましょう。
8-1. 人事評価制度におけるフィードバック面談の重要性
評価制度を人材育成につなげるには、本人へのフィードバックが必要です。そのポイントについても知っておきましょう。
フィードバックとは、評価結果を被評価者と共有することです。
評価の理由を具体的な事例を根拠に伝えることで、被評価者の納得度を高めます。しっかりとフィードバックすることで、次の目標への動機付けにつながるでしょう。
【フィードバック面談のステップ】
- 導入:面談の目的を伝えます。
- 本人評価:被評価者の取組や自己評価をヒアリングします。
- 評価を伝える:評価者からの評価を伝えます。
- すり合わせ:評価者と被評価者の評価ギャップをすり合わせます。
- 動機付け:次回への期待や改善点などを伝え動機付けします。
まず、評価の根拠となった具体的な事例を整理し、被評価者からの想定質問への準備をおこないます。
また、フィードバック面談は評価者だけではなく、被評価者にとってもプレッシャーがかかるものです。落ち着いた場所を準備し、事前に被評価者にも日時と場所を伝えておきましょう。
9. 人事評価制度をうまく活用して従業員のモチベーションを高めよう!
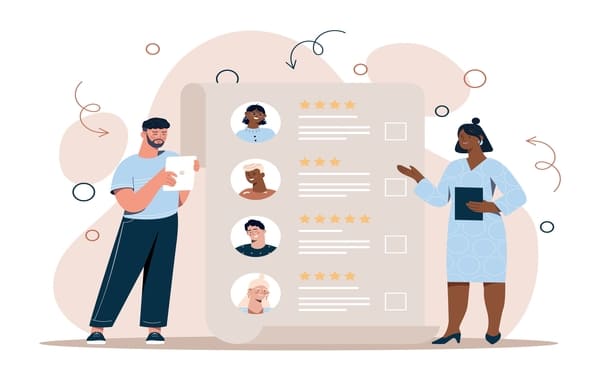
人事評価制度は、処遇決定の参考データとして必要なだけでなく、人材育成にもつながる重要な仕組みです。ポイントは、現場で運用が定着し、評価の公平性が保たれることです。
そのためには、作って終わりではなく、事業に合わせて評価項目を見直し、継続的に評価者研修を実施するなど、メンテナンスをする必要があります。
これから評価制度の導入を検討する場合は、内容はもちろんですが、その後のメンテナンス性も考慮して設計しましょう。







