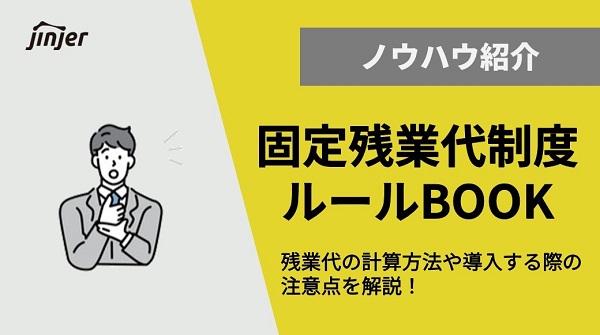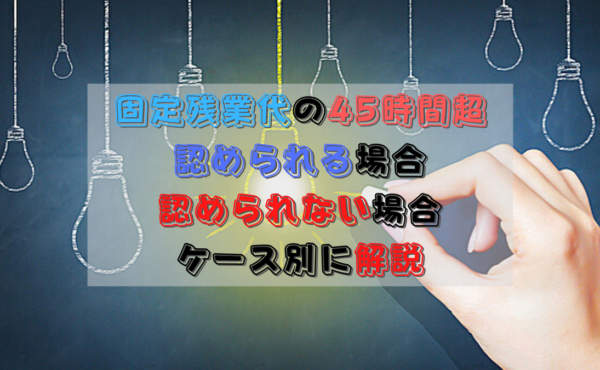
人材の募集要項や求人票に「固定残業代」を含めた賃金表示をするケースも少なくありません。
固定残業代は、企業にとって残業代のばらつきが少なくなるなどのメリットがありますが、固定残業代を設定する際には、注意するべき法律規制があります。
たとえば、残業時間の上限規制です。残業の上限時間を超えて働かせると罰則の対象となるので注意しましょう。今回は、固定残業代の上限や、固定残業代が45時間を超えるリスクについて解説します。
関連記事:固定残業代について周知の義務や上限など基本を優しく解説
「固定残業とみなし残業の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし残業の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 固定残業代の上限は原則45時間

固定残業代とは、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。[注1]
通常、残業代は法定労働時間を超えた分に対して支払いますが、固定残業代を導入した場合、時間外労働の有無に関係なく、一定時間分の残業代を支払うことになります。
事業主にとっては、毎月の残業代のばらつきが少なくなって給与計算業務が楽になり、従業員側にとっては、残業しなかった月でも所定の固定残業代が支払われるため、互いに利のある制度といえます。
ただ、固定残業代を支払えば、その範囲内で制限なく時間外労働をさせられるというわけではありません。
そもそも労働基準法第32条では、使用者は労働者に1日8時間、1週間で40時間(休憩時間を除く)を超えて労働させてはいけないと定めています。[注2]
しかし、同法第36条では、労使間で36協定を締結していれば、法定労働時間を超えた労働をおこなわせても良いとしています。
この36協定を締結した場合に延長することができる残業上限時間が45時間であるため、固定残業代制も45時間を目安に設定しなければいけません。固定残業代制は36協定を前提とした制度なので、導入する際は必ず労使間で36協定を結びましょう。
[注1]固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。|厚生労働省
[注2]労働基準法|e-Gov法令検索
1-1. 固定残業代制の導入に必要な36協定
36協定とは、「時間外・休日労働協定に関する協定届」の通称です。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と締結した後、労働基準監督署長への届け出をおこない、内容を従業員に開示してはじめて有効と認められます。
36協定を締結することで時間外労働をおこなわせることが可能になりますが、無制限に残業をさせられるわけではありません。36協定締結時の残業時間の上限は、「月45時間、年間360時間以内」です。
たとえば、毎月の残業時間が40時間の場合、月の上限である45時間は超過していません。しかし、毎月40時間残業すると年間で480時間となり、年間360時間以内という上限違反となるため、年間を通しても超過しないように注意しましょう。
2. 固定残業代を45時間以上に設定できるケース
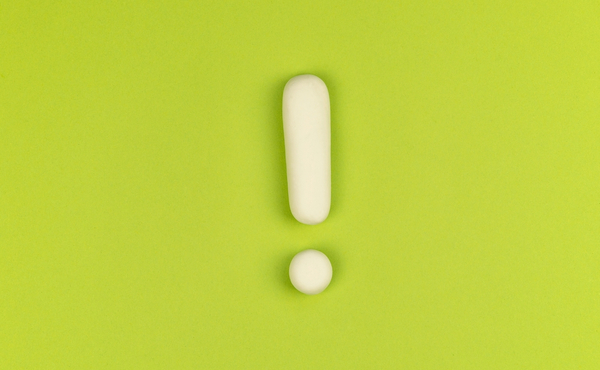
先述の通り、36協定を締結していたとしても、従業員を1カ月に45時間を超えて残業させることは原則として禁じられています。
しかし、一定の要件を満たしていれば、例外として月に45時間を超えて時間外労働させることが認められます。以下では、45時間超えの時間外労働が認められるケースを2つ紹介しますので、確認しておきましょう。
2-1. 臨時の特別な事情で特別条項付き36協定が締結されている場合
臨時的な特別の事情があり、かつ労使が合意する場合は、月45時間、年360時間という上限を超えて時間外労働することが可能です。[注3]
ここでいう「臨時的な特別の事情」とは、労働基準法第36条5の3で定められた「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等」を指します。[注4]
具体的には、納期変更などによる納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、重大な機械のトラブルへの対応などが挙げられます。
これらはすべて「予期しない事象」であることが前提となっているため、同じ状況でもあらかじめ予期することが可能だった場合は「臨時的な特別の事情」とは認められません。
なお、臨時的な特別の事情があったとしても、以下4つの要件は遵守する必要があります。[注3]
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2カ月・3カ月・4カ月・5カ月・6カ月平均がすべて1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間えを超えることができるのは年6カ月が限度
このように、臨時的な特別の事情があっても、上記の上限を超えて時間外労働させることはできないので、あらかじめ注意が必要です。
また、特別条項を結んでいても月45時間を超えて残業をさせることができるのは年6回までなので、45時間を超える固定残業代を設定することは、従業員に違法な労働をおこなわせるリスクを高めてしまいます。
固定残業代を45時間以上で設定しても、実際の労働時間が36協定に違反しなければ違法性はありませんが、不要な人件費をかけてしまうことにもなるので、原則45時間を超える固定残業代の設定はおこなわないほうが良いでしょう。45時間を超える固定残業代を設定していると、「ブラック企業」という印象をもたれてしまう可能性もあります。
[注3]時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省
[注4]労働基準法|e-Gov法令検索
2-2. 特定の事業・業務に適用される猶予期間
時間外労働の上限規制は、大手企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から、それぞれ適用されています。一部の事業・業務については例外として猶予期間が設けられていましたが、2024年4月以降はすべての事業・業務に対して上限規制が適用されるため注意しましょう。[注5]
各事業・業務における猶予期間後(2024年4月1日以降)の取り扱いは以下のようになります。
2-2-1. 建設事業
原則として上限規制のすべてが適用されますが、一部例外として、災害の復旧・復興事業に関しては、時間外労働について「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」という2つの規制は適用されません。[注6]
2-2-2. 自動車運転の業務
特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限は年960時間となります。[注7]
また、時間外労働と休日労働の合計について定めた「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」という2つの規制は適用されません。
さらに、「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで」という規制も適用外となります。
2-2-3. 医師
医師の猶予期間後の取り扱いについては、複数の水準ごとに以下のように区分されます。[注8]
- A水準(診療従事勤務医):年960時間/月100時間未満
- B水準(地域医療確保暫定特例水準)、C水準(集中的技能向上水準):年1,860時間/月100時間未満
なお、C水準については2035年度末を目途に縮減する方向で調整される予定です。
2-2-4. 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
猶予期間後は例外なく、上限規制がすべて適用されます。[注9]
2-3. 45時間超えが認められないケース
先ほど解説した通り、臨時的な特別の事情がある場合や、特定の事業・業務に携わっている場合以外は、原則として月45時間超えの時間外労働は認められていません。
とくに事由を限定せず、「業務で必要だから」「多忙だから」といった理由で月45時間を超えて時間外労働させると、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性もあるので要注意です。
3. 45時間分の固定残業代はいくら支給する?正しい計算の仕方

固定残業時間を45時間とした場合、固定残業代はいくら支給すればよいのでしょうか。計算方法について詳しく見ていきましょう。
3-1. 固定残業代の計算方法
固定残業代は、以下の計算式で算出します。
固定残業代 = 1時間当たりの賃金 × 固定残業時間 × 割増率
1時間当たりの賃金は、「月給(通勤手当などの一定の手当を除く)÷ 月平均所定労働時間」で求めます。 なお、割増率は1.25倍以上でなくてはなりません。
たとえば、月給が24万円、月平均所定労働時間が160時間、割増率1.25倍のケースで考えてみましょう。この場合、1時間あたりの賃金は「20万円 ÷ 160時間 = 1,500円」です。45時間分の固定残業代は「1,500 × 45時間 × 1.25 = 84,375円」となるため、毎月84,375円の固定残業代を支払うことになります。
3-2. 固定残業時間の45時間を超過した分の残業代の計算方法
実際の残業時間が45時間を超えた場合は、その分の残業代を別途支給します。上記の例をもとに、月60時間残業したケースで考えてみましょう。
実際に残業した時間は60時間、固定残業代でない場合に支払うべき残業代は「1,500円 × 60時間 × 1.25 = 112,500円」です。固定残業代は84,375円なので、別途支払うべき残業代は「112,500円 – 84,375円 = 28,125円」となります。
固定残業代は、残業代を削減することを目的とした制度ではありません。残業が45時間を超える場合は、別途残業代を支払う必要があります。固定残業代を正しく運用するためには、従業員の勤怠情報の正確な把握と、超過分の残業代の正しい計算が必要です。
4. 固定残業代45時間はやばい?45時間を超えるリスク

固定残業代制は、原則月45時間が上限です。45時間に設定することは法的に問題ありませんが、長時間残業が常態化する可能性があるため、「やばい」と言われてしまうことがあります。
残業時間が45時間を超えることは、労使それぞれに以下のようなリスクがあることを知っておきましょう。
4-1. 従業員の健康リスク
時間外労働に上限規制が設けられたのは、従業員の過労死リスクを軽減するためです。
月45時間を超えて残業させると、従業員の心身に大きな負担がかかり、病気リスクや過労死リスクが高くなるおそれがあります。労働契約法第5条では、企業に対し、安全配慮義務を下記のように定めています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用:労働契約法第5条|e-Gov法令検索
過度な時間外労働を強いることは、企業の安全配慮義務に反する可能性があるため注意が必要です。また、厚生労働省は、過労死の認定ラインを月80時間と設定し、60時間を超える残業を是正するよう呼びかけています。
4-2. 法令違反のリスク
臨時的な特別の事情なしに、従業員に月45時間を超える残業を強いると、労働基準法違反となります。違反した場合、同法第119条の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。[注10]
2019年の働き方改革関連法案によって残業時間に上限規制が設けられ、1カ月あたりの残業上限時間は45時間と決められています。固定残業代制だからといって残業の実労働時間を計算していないと、この上限時間を超過してしまうリスクがあります。
また、固定残業代の運用において「基本給と固定残業代の内訳を明示していない場合」や、「固定残業代の設定が最低賃金を下回る額で設定されている場合」も違法です。
固定残業代の設定は基本給の1時間あたりの基礎賃金を計算したうえで、残業時間に対する割増率25%を上乗せした額で設定しなければいけません。固定残業代を設定したら「基本給〇〇円(固定残業代▲▲円を含む)」のように内訳を明確に開示しましょう。
加えて、固定残業時間として定めた時間に満たないからといって固定残業代を減額することも違法です。固定残業代の付与に条件を設けることはできないので注意しましょう。
具体的な管理方法について詳しく知りたいという方は、当サイトでお配りしている無料ガイドブック「固定残業代制度ルールBOOK|残業代の計算方法や導入する際の注意点を解説!」をご覧ください。
守るべき法規制や、固定残業代制の運用の注意点なども解説しておりますので、法律に則って固定残業代制度を運用したい方は、こちらから「固定残業代制度ルールBOOK」をダウンロードしてご活用ください。
[注10]労働基準法|e-Gov法令検索
4-3. 就活・採用の妨げとなるリスク
就活をする人は、固定残業代を45時間に設定する会社に対して「ホワイト企業ではないのではないか」など、ネガティブなイメージを抱きやすく、採用の妨げとなる可能性があります。
求人を募集する際、求人情報には「45時間の固定残業代制」のように固定残業代を45時間に設定していることを記載しなくてはなりません。固定残業代制は違法ではありませんが、残業ありきの労働時間を設定していることからホワイト企業ではないのではないかと考える求職者もいるかもしれません。
実際の残業時間が45時間を下回る場合でも、外からは残業の実態を把握することができないため、採用の障壁になる可能性もあります。
今後、どの業界でも人材不足が懸念されています。優秀な人材を確保するためには、固定残業時間を45時間と決め打ちせず、業務効率などを改善して残業時間を削減する取り組みが必要といえるでしょう。また、固定残業代制を45時間に設定する場合も、法令を遵守した運用を徹底することが大切です。
4-4. 従業員のモチベーションが低下するリスク
固定残業代を45時間に設定することで長時間労働が常態化すると、従業員のモチベーションが低下してしまう恐れもあります。長く働けば成果が出るというわけではありません。逆に、疲労が蓄積することで生産性が低下したり、ミスが発生したりするケースも多いでしょう。
モチベーションの低下は、会社への不満にもつながります。もっと働きやすい職場や条件のよい職場を求めて、転職しようとする従業員が増える可能性もあります。過度な残業は優秀な人材の流出にもつながるため、適切な固定残業時間を設定することが重要です。
4-5. 人件費が無駄になるリスク
固定残業代を45時間に設定することで、人件費が無駄になる可能性もあります。前述の通り、実際の残業時間が想定していた固定残業時間より短い場合でも、決められた固定残業代を支払わなければなりません。仮に実際の残業時間が1時間であっても、45時間分の固定残業代が発生してしまうのです。
固定残業代を導入するときは、どの程度の残業が発生しているのかを把握したうえで、適切な固定残業時間を設定するようにしましょう。
5. 残業時間を削減するために取り組みたいポイント

過度な時間外労働の増加は労使ともにリスクがあるので、最小限に抑えるに越したことはありません。ここでは残業時間を削減するために取り組みたいポイントを3つ紹介します。
5-1. 時間外労働の状況を可視化する
時間外労働に従事した時間を正確に管理できないと、知らない間に上限を超えてしまう可能性があります。
また、紙の出勤簿やタイムカードなどを使った勤怠管理は、打刻忘れや入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、時間外労働を正確に把握できなくなるおそれがあります。
打刻データが自動的に入力される勤怠管理システムなどを導入し、時間外労働を可視化すれば、上限を超えて残業するリスクを軽減できるでしょう。
5-2. 業務効率化を図る
人手が足りず、従業員が残業を余儀なくされている場合は、業務の効率化を図りましょう。
たとえば、ペーパーレス化を推進したり、業務フローを見直したりすれば、従来生じていた業務の無駄の削減につながります。業務の一部をアウトソーシングするのも効果的な方法です。
5-3. 残業の申請制度を設ける
従業員が自らの意思で勝手に残業しないよう、上司への事前申請制度を導入するのもひとつの方法です。残業の必要ありと認めた場合のみ申請を許可すれば、無駄な時間外労働を軽減できます。
また、申請の手間があることで、従業員に業務を時間内に終わらせようという意識が芽生え、生産性が向上することも期待できます。
6. 固定残業代は36協定に基づき、月45時間を上限とするのが基本

固定残業代は労使ともにメリットのある制度ですが、1カ月または1年間の時間外労働には上限があるため、際限なく残業させられるわけではありません。
臨時的な特別の事情がある場合は、月45時間を超えて残業させることも可能ですが、従業員の健康を害したり、法令違反に該当したりするリスクがあります。
そのため、固定残業代を導入する際は、はじめから上限の45時間に設定するのではなく、まずは残業の削減に取り組むことが重要です。具体的には、勤怠管理システムの導入や業務の無駄を見直し、残業時間を削減する意識改革を推進しましょう。
「固定残業とみなし残業の違いがよくわからない」「固定残業代の計算方法や、違法にならない制度運用を知りたい」とお考えではありませんか?
当サイトでは、固定残業とみなし残業の違いから固定残業代の計算方法、適切な運用についてまとめた「固定残業代制度ルールBOOK」を無料で配布しております。
自社の固定残業やみなし残業の制度運用に不安がある方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。