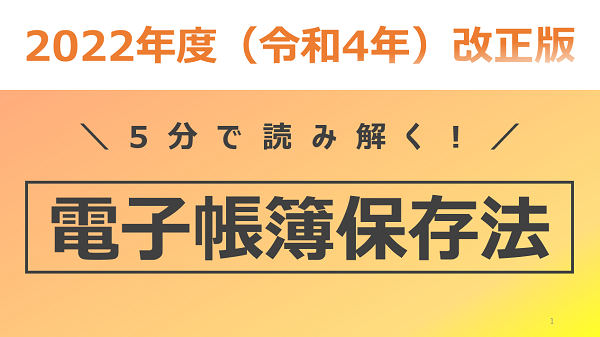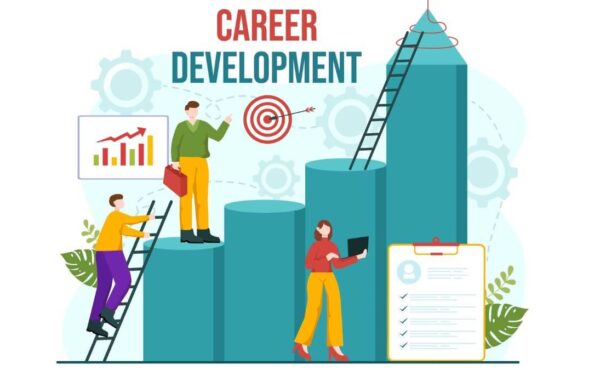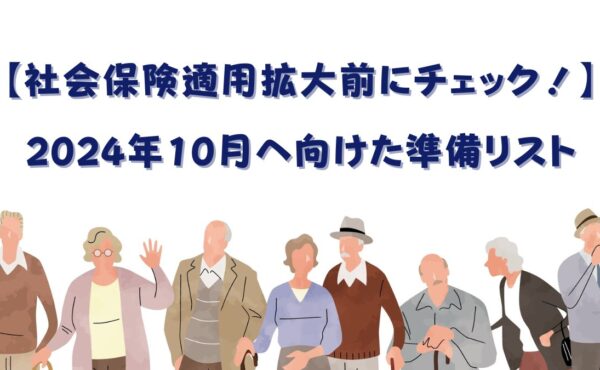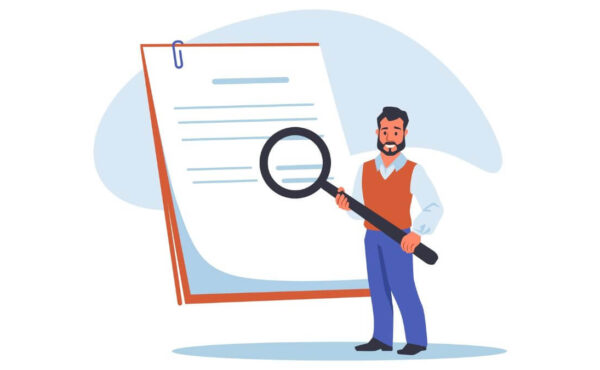電子帳簿保存法で使用できる補助金とは?適用対象事業者や申請の流れを解説
「電子帳簿保存法改正に伴いITツール導入を検討しており、補助金について知りたい」とお考えの企業担当者は多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法改正では、パソコン上で受け取った請求書や領収書の電子データを保存する義務が発生します。これまで取引内容を紙で印刷して保存していた場合、電子データを適切に保存する環境を整えなくてはなりません。
環境を整備するにはコストがかかりますが、補助金を活用することで金銭的な負担を軽減可能です。
そこで本記事では、IT導入補助金の概要や適用対象条件、申請方法について解説します。電子帳簿保存法改正に伴うIT技術導入で補助金を利用したい担当者は、ぜひ参考にしてください。
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが下がりました。 しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律など、電子帳簿保存法そのものの内容や対応する手順など正しく理解しておかなければいけません。 「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正内容と2022年の施行内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。 「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。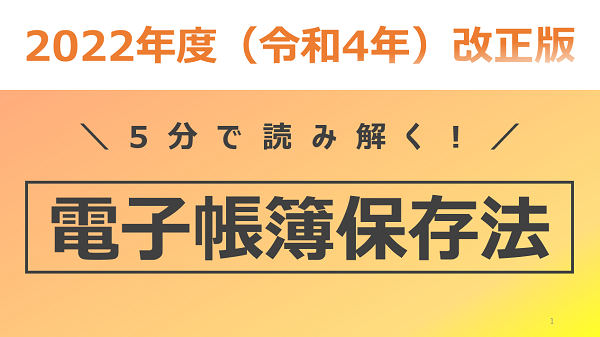

目次
1. 電子帳簿保存法で使用できるIT導入補助金とは? 3つの申請枠も解説

IT導入補助金は、中小企業のITツール導入費用を補填する制度です。導入する企業の目的やITツールの種類によって、最大450万円の補助金が受け取れます。2023年度のIT導入補助金は、電子帳簿保存法改正やインボイス制度に対応するため、以下の3つが用意されました。
- 通常枠
- デジタル化基盤導入類型
- セキュリティ対策推進枠
導入するITツールは「生産性向上IT導入支援事業の事務局」に登録され、認定を受けている必要があります。
参照:IT導入補助金でIT導入・DXによる生産性向上を支援! | 経済産業省
1-1.通常枠(A類型・B類型)
通常枠は、業務効率や生産性の向上を支援する申請枠です。以下のような労働生産性の向上につながるITツールが対象となっています。
- 勤怠管理
- 会計管理
ソフトウェア購入費に加えて、最大2年分のクラウド利用費や導入関連費に対して補助金が支給されます。
1-2.デジタル化基盤導入枠
デジタル化基盤導入枠は、通常枠の目的に加えて電子帳簿保存法改正やインボイス制度対応を見据えた申請枠です。企業間取引などのデジタル化を支援し、以下の機能を持つITツールが対象となっています。
- 会計
- 受発注
- 決済
- EC(電子商取引)機能
通常枠の経費に加えて、ハードウェア関連費にも補助金が支給されます。また、通常枠との併用も可能です。
1-3.セキュリティ対策推進枠
セキュリティ対策推進枠は、サイバー攻撃に対するセキュリティ強化のための申請枠です。「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスが対象となっています。
企業のIT化に伴うサイバー攻撃対策は必須のため、補助金制度があるタイミングでサービス導入を検討すると良いでしょう。
ここまで読んでそもそも電子帳簿保存法がどんな法律なのか、またどのように会社で対応すれば良いかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは5分でわかる電子帳簿保存法という資料を無料配布しております。本資料では電子帳簿保存法に関する概要から、対応方法、また具体的な改正内容などをわかりやすく解説しています。そのため電子帳簿保存法の基礎知識を得られるのはもちろん、会社としてどのような対応をすればよいかも理解することができます。大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
参照:サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト | IPA
2. 電子帳簿保存法で使用できるIT導入補助金の適用対象事業者

IT導入補助金は、基本的に中小企業および小規模事業者などが適用対象です。しかし、大企業以外でも、要件を満たさない場合は補助金の適用対象外となります。
この章で、適用対象となる事業者の条件を知り、自社が当てはまるかしっかり確認をしましょう。
2-1. 適用対象となる事業者
補助金の受け取りには、以下の要件に当てはまる必要があります。
- 交付申請時において日本国内で事業をおこなっている
- 地域別最低賃金以上である(交付申請間近の月の最低賃金)
また、資本金や従業員数は、以下の表の規模を下回っていることが必須です。
|
業種 |
従業員数 |
資本金 |
|
建設業・製造業・運輸業 |
300人 |
3億円 |
|
卸売業 |
100人 |
1億円 |
|
サービス業 |
100人 |
5,000万円 |
|
小売業 |
50人 |
5,000万円 |
|
ゴム製品製造業 |
900人 |
3億円 |
|
ソフトウェア業や情報処理サービス業 |
300人 |
3億円 |
|
旅館業 |
200人 |
5,000万円 |
|
そのほかの業種 |
300人 |
3億円 |
IT導入補助金の適用条件に自社が当てはまるかどうか、申請前に確認をしておきましょう。
2-2. 適用対象されない事業者
中小企業や小規模事業者などであっても、以下の条件に該当する場合、IT導入補助金の適用対象から外れます。
- 1つの大企業が発行済株式の総数および出資総額の半分以上を所有
- 大企業が発行済株式の総数か出資総額の2/3以上を所有
- 役員の半分以上が大企業の役員または職員を兼任
ほかにも法人格のない任意団体など、対象外となる要件があるため、詳細を確認してから申請すると良いでしょう。
3. 電子帳簿保存法で使用できるIT導入補助金の申請までの流れ3STEP

IT導入補助金の交付には、申請までの流れに従い、交付申請の審査に合格する必要があります。交付申請までの流れは、以下のとおりです。
- 会社の目的に合ったITツールの選択
- 交付申請をおこなうために必要な事項を実施
- 交付申請の実施
順番を間違えると補助金が受け取れないため注意してください。この章で、交付申請までの流れを詳しく確認しましょう。
3-1.会社の目的に合ったITツールの選択
最初に、IT導入補助金に対応しており、自社に合ったツールを選択します。同時に、IT導入補助金の目的や方法の理解を深めておきましょう。
公募要領を読み込み、その中から自社の課題を解決するITツールを選ぶことが重要です。
3-2.交付申請をおこなうために必要な事項を実施
ITツールの選択後は、交付申請をおこなう前に以下の3つを実施しましょう。
- 「gBizIDプライム」の取得
- IPAの「SECURITY ACTION」の実施
- みらデジの「経営チェック」
「gBizIDプライム」の取得には約2週間かかるため、早めに申請を済ませましょう。「SECURITY ACTION」は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)実施の情報セキュリティ対策への宣言です。
また、中小企業をデジタル化によってサポートする制度である「みらデジ」の経営チェックも同時におこないましょう。
参照:IT導入補助金の申請要件になりました | SECURITY ACTION
3-3.交付申請の実施
最後に、事業計画を作成し、以下の流れで交付申請をおこないます。
- 事業計画内容の最終確認と申請に対する宣誓
- IT導入支援事業者に必要項目を入力してもらう
- 「申請マイページ」にて基本情報を入力し、事務局へ提出
交付申請で不採択になった場合、申請締め切りに間に合えば再度提出が可能です。しかし、申請内容を見直さないと、再度不採択になる可能性が高いため注意しましょう。
4. 電子帳簿保存法で使用できるIT導入補助金の申請後の流れ4STEP
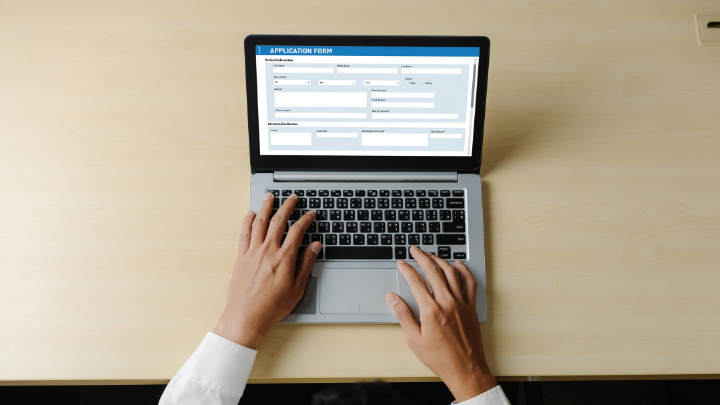
交付決定通知を受け取ったあとも、実績報告や効果報告を忘れずにおこないましょう。交付申請完了後の流れは、以下のとおりです。
- ITツールの契約
- 事業実績報告
- 補助金交付手続き
- 事業実施効果報告
効果報告までのプロセスは複雑ですが、IT導入支援事業者と連携し、相談しながら進められます。この章で、効果報告までの流れを詳しく確認しましょう。
4-1.ITツールの契約
申請後に決定通知が届き次第、ITツールを導入しましょう。補助金の支給決定通知が届く前にITツールを契約すると、補助金の受給資格がなくなる可能性があるため、注意してください。
4-2.事業実績報告
次に、ITツールの契約・支払いを証明する書類を提出します。提出の流れは、以下のとおりです。
- IT導入支援事業者が、事業実績報告を確認したのち必要事項を入力
- 申請マイページから必要情報の入力と証憑の添付をおこない、事業実績報告を作成
IT導入支援事業者に必要情報を入力してもらったら、最終確認をして提出しましょう。
4-3.補助金交付手続き
事業実績報告をおこなうと、ITツールの導入に伴って受け取れる補助金額が確定します。受け取り金額は「申請マイページ」上で確認ができるため、忘れずにおこないましょう。間違いがないことが確認できたら、IT導入補助金が支給されます。
4-4.事業実施効果報告
補助金交付後は、「申請マイページ」において期限内に必要情報を入力し、事業実施効果報告をおこないましょう。事業実施効果報告の内容は、IT導入支援事業者にもしっかり確認してもらう必要があります。
5. 電子帳簿保存法で使用できるIT導入補助金申請の注意点

IT導入補助金は、補助金の交付決定前に契約や支払いをおこなうと、補助金の対象外となるため注意が必要です。また、補助金の交付はITツール導入後となるため、それまでの費用は負担しなければなりません。
しかし、交付後にITツールの購入ができることは、金銭的負担の軽減につながります。また再申請も可能であり、補助金返済も原則不要のため、導入の注意点に気をつけて申請を進めると良いでしょう。
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが下がりました。 しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律など、電子帳簿保存法そのものの内容や対応する手順など正しく理解しておかなければいけません。 「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正内容と2022年の施行内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。 「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。