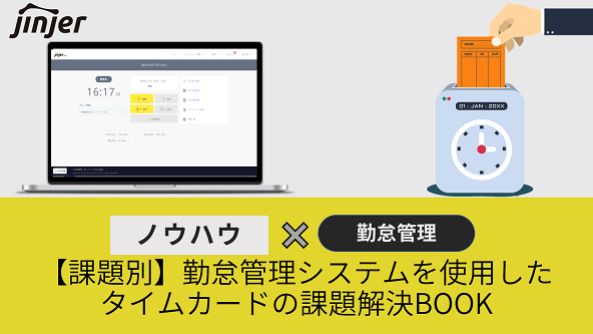近年では、労働基準法など、勤怠管理に関する法改正が実施されたこともあり、従業員の勤務状況をより細かく管理することが求められています。そこで、タイムカードを使用して勤怠管理をおこなうにあたって、書き方のコツや注意点について気になる人は多いのではないでしょうか。当記事では、タイムカードの書き方や注意点について解説します。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正をおこなえるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次
1. タイムカードとは

タイムカードとは、始業や終業時刻などを記載し、従業員の勤怠を管理するための紙のことです。紙のタイムカードの場合、タイムレコーダーに挿入することで打刻をおこなうことができます。なお、タイムカードとタイムレコーダーをあわせて、「タイムカード」とよぶこともあります。
紙とレコーダーを用意すれば、タイムカードでの勤怠管理を実施できるので、コストを低く抑えることが可能です。また、勤怠管理システムなどのようなITツールを使用する場合、使い方が複雑であると、勤怠管理の業務負担が増加する恐れもあります。一方、タイムカードの場合、運用はシンプルであるため、ITツールの操作が苦手な従業員でも簡単に使用可能です。
ただし、手作業で業務をおこなう場合、集計ミスが生じる可能性もあります。また、打刻漏れや不正打刻が発生することもあるので、運用ルールをきちんと定めることが大切です。
2. タイムカード・勤務表への記載事項・書き方とは

ここでは、タイムカードや勤務表に記載すべき項目や書き方について詳しく紹介します。
2-1. 勤怠管理に必要な情報を記載する
タイムカード・勤務表を導入する目的は、適切な勤怠管理をおこなうことです。そのため、従業員の勤務状況を正確に把握するために必要な情報を記載しなければなりません。また、労働基準法に違反しないように、適切な項目を設ける必要があります。
たとえば、タイムカードや勤務表に下記のような項目を設けると、勤怠管理がしやすくなるでしょう。
- 出勤日数
- 出社時刻
- 退社時刻
- 休憩時間
- 出勤日ごとの労働時間
- 時間外労働をおこなった日付および時間数
- 休日労働をおこなった日付および時間数
- 深夜労働をおこなった日付および時間数
- 備考
- 承認印
このように、労働基準法の規定を踏まえたうえで勤怠管理を適切におこなえるように、タイムカードの記載事項や書き方を決めるのがおすすめです。
2-2. タイムカードを押し忘れた際の書き方
タイムカードで勤怠管理をおこなっている場合、従業員がタイムレコーダーに挿入し忘れてしまうことは少なくないでしょう。その場合、タイムカードに手書きで記入することが一般的な対処方法です。タイムカードへ記述した内容が事実であると確認できる場合は、手書きでも実際に労働した時間として認められます。ただし、上司や管理者の許可をとってから手書きで記載する運用方法にすることが重要です。
従業員の意思のみで、タイムカードに手書きで記入できるようにしてしまうと、残業時間の水増しなど、内部不正につながる恐れがあります。上司や管理者の承認フローを導入することで、コンプライアンスを強化し、適切な勤怠管理をおこなうことが可能です。また、タイムカードの押し忘れを防ぐように、タイムレコーダーを配置する場所を工夫するなど、対策をおこなうことが大切といえます。
2-3. 残業時のタイムカードの書き方
残業をおこなった場合には、備考に残業の理由と時間を記載する方法や、タイムカードに残業時間の項目を設けて記載する方法などがあります。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働を原則禁止しています。しかし、36協定を締結すれば、一定の範囲内で法定労働時間を超えて労働(時間外労働)させることが可能です。ただし、時間外労働(法定外残業)に対しては、通常賃金に加えて割増賃金の支給も必要になるので、正しくタイムカードに残業時間を記入させるようにしましょう。
また、残業時間も1分単位で計算する必要があります。時間外労働に関する集計ミスが生じると給与の支払いにも影響を与えるので、従業員と企業の間でトラブルが発生する可能性もあります。
労働基準法を遵守しつつ給与を正確に計算するため、従業員の労働時間を適切に管理して、残業時間をきちんと把握できるよう、タイムカードに記載していきましょう。そして、従業員の適切な勤怠管理をおこなうためにも、残業時間は週末や月末にまとめて記入してもらうのではなく、できる限り時間外労働をおこなった日に記入してもらうことが大切です。
関連記事:なぜ労働時間は1分単位で計算するのか?違法になる根拠や対策方法を解説!
2-4. 有給時のタイムカードの書き方
労働基準法により、6ヵ月以上継続して雇われており、全労働日のうち80%以上出勤している従業員に対しては、有給休暇を付与する義務があります。
有給休暇については、タイムカードに記入せず管理している企業もあるかもしれません。しかし、従業員の勤務状況を効率よく管理するためにも、タイムカードに有給休暇の情報を記入することが推奨されます。タイムカードには、備考や休暇の欄を設けて、「有休」「年休」など、有給休暇とわかるような書き方を採用するのがおすすめです。また、有給休暇の申請やタイムカードの記入方法については、事前にきちんと従業員に周知しておくことが重要といえます。
2-5. タイムカードの書き方を間違えたときの対応
タイムカードの書き方が間違っていると正しい給与を支給できなくなるため、気づいたらすぐに修正するようにしましょう。まずは従業員本人にヒアリングし、正しい内容を確認しましょう。時間が経つと記憶が曖昧になるので、早めに対処することが重要です。
また、従業員に対しても労働時間を正しく報告することで正しい給与計算ができるということを日ごろから伝えておくとよいでしょう。そうすることで従業員の労働時間に対する意識も高くなります。
3. タイムカードの記入例
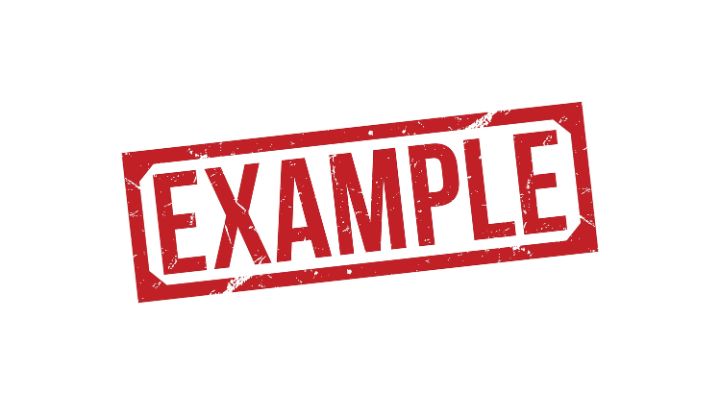
まずは、タイムカードの持ち主がわかるように、氏名や社員番号、部署、連絡先などを記載しましょう。また、就業時間をタイムカードに明示しておくと、残業時間を把握しやすくすることができます。いつのタイムカードか明確にするため、日付もきちんと記載しましょう。
3-1. 時間外労働・深夜労働・休日労働の記入例
出社時間や退社時間はタイムレコーダーで打刻可能です。時間外労働や深夜労働、休日労働についても、正しい書き方の仕組みを整備すればタイムカードで管理できます。しかし、過重労働になっていないか、36協定の上限時間を超えていないかなど、上司や管理者は適宜従業員の労働状況をチェックする必要があります。
そのため、残業や休日出勤といった通常以外の労働が生じる場合、上司や管理者の承認を受けたうえで、備考に理由を添えて記入してもらいましょう。そのため、上司や管理者による承認サインができる項目をあらかじめ用意しておくことが大切です。
関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!
3-2. 遅刻・早退の記入例
備考には、遅刻・早退・有給・欠勤などの情報も記入するような仕組みにすると、適切に勤務状況を管理することが可能です。月末には、出勤日数・有給休暇取得数・法定内労働・時間外労働・深夜労働・休日労働それぞれについて、合計を計算してタイムカードに記入しましょう。
なお、タイムカードの内容を修正する場合には二重線を引き、訂正印を押したうえで修正事項を記入するような仕組みを採用するのがおすすめです。
4. タイムカードの書き方に関する注意点
 タイムカードの書き方について、以下のような点に注意しましょう。
タイムカードの書き方について、以下のような点に注意しましょう。
4-1. 残業時間を忘れずに記載する
前述の通り、従業員の勤怠情報を正確に管理するために、タイムカードには出退勤時刻だけではなく、時間外労働をした時間も記入するようにしましょう。時間外労働(法定外)に対しては、割増賃金を支払う必要があるからです。
また、深夜労働や休日労働に対しても割増賃金が発生するので、それぞれ別に管理する必要があります。
4-2. 紛失しないように管理する
タイムカードは、勤怠管理や給与計算をおこなうために重要な書類となるので、紛失や盗難が発生しないように、セキュリティを考慮したうえで一元化して管理するのがおすすめです。
また、タイムカードの保管期間は5年間と定められています。当面の間は経過措置で3年間でも問題ありませんが、いずれは経過措置が終了するため、5年間保管しておくとよいでしょう。
4-3. 不正が発生しないようにする
タイムカードは改ざんなどの不正が生じることもあるため、しっかりと管理しなければなりません。書き換えや代理打刻などの不正が発覚したときには罰則を適用するなど、毅然とした態度で対応することが大切です。内部不正が発生しないように原因を明確にし、対策をおこなうことも重要といえます。
また、自由に書き換えられる状態では不正が発生しやすいので、タイムカードの内容を修正するときは、あらかじめ上司や管理者に報告させることが重要です。
5. タイムカードの書き方を理解して労働基準法を遵守しよう!

今回は、タイムカードの書き方や記入例、管理するときの注意点などを紹介しました。近年では、労働基準法の改正などにより、より正確な勤怠管理が企業に求められています。そのため、タイムカードで勤怠管理をおこなう場合、残業や有給休暇なども正しく把握できるような書き方を採用することが大切です。
ただし、タイムカードでは人的ミスが生じることもあるので、上司や管理者の承認フローを導入したり、二重チェック体制を採用したりするのがおすすめといえます。また、タイムカードは紛失や盗難が生じたり、内部不正がおこなわれたりする可能性もあるため、一元管理して、適切な運用ルールを設けることが重要です。
タイムカードによる勤怠管理で頭を悩ませるのが、打刻漏れです。毎月締め日に漏れを確認し、従業員に問い合わせるだけでも多くの時間がかかってしまい、人事業務を圧迫していませんか?
勤怠管理システムでは打刻漏れがあった際にアラートが上がる仕組みになっており、すぐに打刻修正をおこなえるため、打刻漏れを減らし確認作業にかかる時間を減らすことができます。
実際、4時間かかっていた打刻漏れの確認作業がシステム導入によりゼロになった事例もあります。
「システムで打刻漏れを減らせるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。