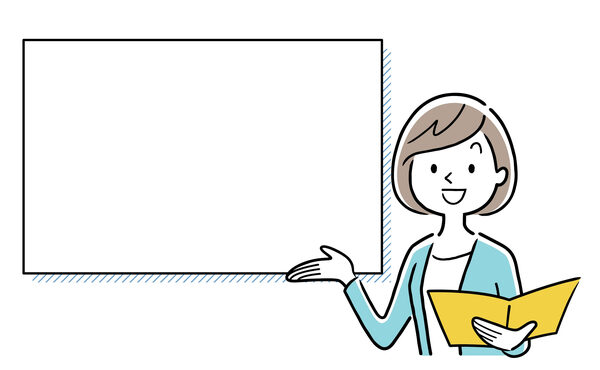
総務担当者は、退職者が出たとき、「退職届を受理する」「社会保険の資格喪失手続きをする」など、さまざまな退職手続きをしなければなりません。スムーズに手続きするため、あらかじめ退職手続きマニュアルやチェックリストを作成しておくことも推奨されます。本記事では、総務担当者がすべき退職手続きの流れについてわかりやすく解説します。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 総務担当者が行うべき退職手続き
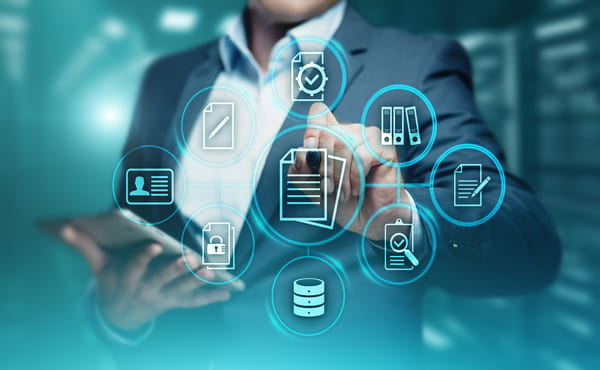
従業員が退職する際に、総務担当者がすべき手続きは多岐にわたります。以下は、退職日までにするべきことや、その後にすべき手続きのおおまかなスケジュールです。
| 日程の目安 | 手続きの内容 |
| 退職の1カ月前~ |
|
| 退職の2週間前~ |
|
| 退職日当日~期限まで |
|
| 退職から5日後まで |
|
| 退職から10日後~1カ月後まで |
|
ここからは、従業員から退職の申し出があった場合の対応や、その後の手続きについて詳しく紹介します。
1-1. 退職日までに行う手続きや対応
退職の申し出があった後は、従業員に「退職届(退職願)」を提出してもらいます。退職届は、従業員に退職の意思があることを証明する書類であり、離職証明書をハローワークへ提出する際にも添付が必要なものです。
会社によっては「退職時の誓約書」を取り交わす場合もあるでしょう。退職時の誓約書は作成義務はありませんが、退職後も業務で知り得た秘密を保持してもらうための守秘義務契約書です。その後は、退職手続きに関することについて説明をします。たとえば、退職時に従業員から提出してもらうものや返却してもらうもの、会社側から渡すものなどを説明しましょう。退職後に渡す書類もあるため、郵送先の住所も確認しておく必要があります。
他にも離職票・退職証明書の準備や、退職金がある場合は「退職所得の受給に関する申告書」を本人に記入してもらう、業務の引き継ぎなど、退職の手続きは多岐にわたります。
1-2. 社会保険の手続き
従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していた場合、社会保険の資格喪失手続きをおこなう必要があります。従業員が退職した日の翌日(資格喪失日)から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を日本年金機構(および健康保険組合)に提出する必要があります。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入していた場合、健康保険と厚生年金保険の両方の手続きを同時におこなうことが可能です。ただし、被保険者資格喪失届を提出する際に、資格確認書や健康保険証などの添付書類が必要になります。
一方、組合管掌健康保険(組合健保)に加入していた場合、健康保険は「組合健保」、厚生年金保険は「日本年金機構」で資格喪失手続きをおこないます。この場合、日本年金機構に被保険者資格喪失届を提出する際の添付書類は不要です。しかし、組合健保に被保険者資格喪失届を提出する際に健康保険証などの添付書類が必要になるので気を付けましょう。
1-3. 雇用保険の手続き
従業員が雇用保険に加入していた場合、同じように資格喪失手続きをおこなわなければなりません。従業員が退職した日の翌々日(資格喪失日の翌日)から10日以内に、所轄のハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
このとき同時に、離職証明書を提出しましょう。離職証明書は、離職票を発行するときに必要な書類です。離職票は、退職者が失業保険の手続きをする際に必要となる重要なものなので、交付が遅れることのないよう注意しなければなりません。離職証明書を提出するときは、賃金支払状況を確認するため、賃金台帳や労働者名簿などの添付が必要になります。また、退職届も必要なのでまとめて準備しておきましょう。
なお、従業員が退職後すぐに転職する場合、離職票が不要なこともあります。従業員から離職票の発行を希望しないことが確認できた場合、離職証明書の提出は不要で、被保険者資格喪失届のみ提出すれば問題ありません。しかし、従業員の退職する際の年齢が59歳以上の場合、本人の希望に関係なく離職票を発行する義務があり、離職証明書の提出も必ず必要になるので注意しましょう。
1-4. 所得税の手続き
従業員が退職したら、所得税法第226条に則り、退職後1カ月以内に給与所得の源泉徴収票の交付が必要です。給与所得の源泉徴収票は、転職先で年末調整を受けたり、確定申告の手続きをしたりするために必要となります。
なお、退職金を支給する場合、退職後1カ月以内に退職所得の源泉徴収票も交付しなければなりません。退職所得の源泉徴収票は、転職先で年末調整を受けるためには不要ですが、確定申告の手続きで必要になる可能性があります。このように、年末調整を受けず、年の途中で退職した従業員に対しては、源泉徴収票を用いた確定申告の手続きについても案内すると丁寧な対応といえます。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1-5. 住民税の手続き
会社勤めの場合は通常、特別徴収と呼ばれる方法で給与から住民税が天引きされます。そのため、退職するときは、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を用いて手続きをし、退職者自身で支払う普通徴収に切り替えることが一般的です。普通徴収に切り替える場合、次のように退職の時期によって対応が異なります。
- 1月1日~4月30日に退職した場合:給与から一括徴収
- 5月1日~5月31日に退職した場合:通常通り給与から特別徴収
- 6月1日~12月31日に退職した場合:普通徴収
住民税の一括徴収は額が大きくなることが多いため、最終給与から支払えない場合、普通徴収への変更も可能です。一方、転職先がすでに決まっている場合、そのまま特別徴収を継続することができます。継続するためには、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して、本人に渡し、転職先の会社へ提出してもらいましょう。
1-6. 退職者へ送付する書類のチェックリスト
従業員が退職した後、送付しなければならない書類は数多くあります。また、退職者が社会保険・雇用保険に加入していたかどうかや間を空けずに転職するかどうかによって送付する書類は変わってきます。退職者に送付する書類のチェックリストは、次の通りです。
-
年金手帳・基礎年金番号通知書
-
雇用保険被保険者証
-
離職票
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書
- 退職証明書
-
給与所得の源泉徴収票
-
退職所得の源泉徴収票
-
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
なお、離職票は、ハローワークから会社に送付されます。そのため、会社に離職票が届いたら、速やかに退職者に送付するようにしましょう。そうすれば退職者は失業給付の手続きをスムーズに行うことができます。また、退職者が退職後、国民健康保険や国民年金に加入するためには、健康保険被保険者資格喪失確認通知書や退職証明書などが必要です。離職票でも代用することができることもあります。
退職証明書は、労働基準法第22条により、退職者から求められたら必ず交付しなければなりません。また、労働者が希望しない事項は記入してはならないなど、注意点もあるので気を付けましょう。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)
2. 退職手続きにおいて従業員に提出してもらう書類のチェックリスト

退職手続きを正しく実施するために、従業員から返却・提出してもらわなければならないものがあります。具体的な返却・提出物のチェックリストは次の通りです。
- 退職届
- 貸与物(社員証や名刺、制服、PC、スマートフォンなど)
- 健康保険証(家族分を含む)
- 書類やデータ
- 退職所得の受給に関する申告書
ここからは、それぞれの返却・提出物について詳しく紹介します。
2-1. 退職届
退職届は、退職の意思を確認するため、従業員から退職前に提出してもらう必要があります。退職日の前日など急に提出されると、退職手続きを余裕を持っておこなえない可能性があります。そのため、就業規則に退職届の提出に関するルールを明記し、従業員に周知しておきましょう。
なお、民法第627条により、期間の定めがない無期契約労働者の場合、退職の意思を表示してから2週間を経過することで労働契約は終了すると定められています。しかし、期間の定めがある有期契約労働者の場合や、やむを得ない事情がある場合、法律の規定が変わります。そのため、雇用形態や退職理由などによって、細かく退職届の提出ルールを定めておくことが大切です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(省略)
関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介
2-2. 貸与物
貸与物には、社員証や名刺、制服、作業着、パソコン、スマートフォン、タブレットなどが挙げられます。これらはすべて退職の際に返却してもらう必要があるものです。とくに、入館証や鍵を貸与していた場合、セキュリティ上の問題があるため必ず返してもらいましょう。返却漏れが起きないよう、事前に返却チェックリストを作成しておくことも推奨されます。
2-3. 健康保険証
健康保険証は、退職日の翌日(資格喪失日)から使えなくなります。また、健康保険の資格喪失手続きをする際に、健康保険証を添付して申請書を提出する必要があります。なお、健康保険証は、退職者だけでなく、退職者に扶養されている者全員分を回収しなければなりません。
そのため、退職日までに健康保険証を回収することを事前に退職予定者に伝えておきましょう。何かしらの理由で回収できない場合、回収不能届を添付する必要があります。
2-4. 書類やデータ
業務で使用していた資料やデータは、機密情報や個人情報が含まれている可能性があるため、返却してもらわなければなりません。返却が難しい場合などは、破棄してもらうよう退職者に伝えましょう。
2-5. 退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書とは、退職金を支払う場合に、適切に源泉徴収を実施するため、退職金を受け取る人に提出してもらう必要のある書類です。もしもこの書類を提出しなかった場合、退職金に対して一律20.42%の税率を掛けて源泉徴収がおこなわれることになります。
税金の納め過ぎとなり、本来はしなくてもよい確定申告や還付申告をしなけれならなくなる可能性があります。そのため、退職金制度を用意している場合、退職する日までに、退職所得の受給に関する申告書を記載し、提出してもらうようにしましょう。
関連記事:退職金にかかる税金(所得税・住民税)の仕組みや計算方法をわかりやすく解説!
3. 総務担当者が退職手続きを行うときの注意点

退職手続きでは多くの書類を準備しなければなりません。トラブルを発生させないためにも、総務担当者は退職手続きをおこなうときに気を付けるべき点を把握しておくことが大切です。ここでは、総務担当者が退職手続きをする際の注意点について詳しく紹介します。
3-1. 退職届は書面で提出してもらう
退職は口頭でも成立しますが、自己都合であることを証明したり、退職の意思を確認して証拠に残したりするため、書面で提出してもらうことが大切です。離職票を発行する際に必要な離職証明書をハローワークに提出する際、退職届を添付しなければならないケースもあるので、フォーマットを整備し、期限までに提出してもらうようにしましょう。
3-2. 手続きの期限を把握しておく
総務担当者がすべき退職手続きは、期限付きのものがあります。
- 社会保険の資格喪失届の提出:退職日の翌日から5日以内
- 雇用保険の資格喪失届の提出:退職日の翌々日から10日以内
- 源泉徴収票の発行:退職日から1カ月以内
- 住民税徴収方法の切り替え:退職日の翌月10日まで
このように、提出期限の起算日は、退職日なのか、資格喪失日なのかなど、書類によって違いがあります。また、数日以内に手続きしなければならないものもあるので、事前に退職手続きのマニュアルを作成し、余裕を持って手続きをおこなうことが大切です。
3-3. 貸与物は早めに回収する
貸与物の中には、会社の入館証やパソコンなど、返してもらわないと会社側が困るものも多くあります。「退職後に返却してもらおうと思っていたら、連絡が取れなくなってしまった」などのトラブルが起きる可能性も考えられるので、返却物はなるべく早く回収したほうが良いでしょう。
3-4. 退職した従業員の個人情報の取り扱いは慎重に
退職した従業員であっても、個人情報は厳正に管理しなくてはなりません。従業員の書類は、個人情報保護の観点や退職後にトラブルが起きた場合の備えとして、退職後も一定期間保管するよう法律で定められています。書類別の保管期間の一例は、以下のとおりです。
| 保管期限 | 書類 |
| 2年 |
|
|
3年(本来5年であるが、暫定的に当面の間は3年)
|
|
| 4年 |
|
| 5年 |
|
| 7年 |
|
退職者の情報を保管する方法にも工夫が必要です。紙による保管の場合は保管スペースを確保しなければならず、書類を探すのに手間もかかります。そのため、システム上で管理できる方法を採用するのも一つの手です。
3-5. 財形貯蓄や社内融資を利用している退職者への対処法
財形貯蓄制度を利用する従業員に対しては、本人の意思を確認します。なぜなら、財形貯蓄は転職先で継続することも可能だからです。財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は、一定期間を経過したのちに課税扱いとなります。そのため、退職後半年以内に財形貯蓄を取り扱う金融機関に「退職等の通知書」を提出しなければなりません。
新しい転職先で積立てを継続する場合は、退職後2年以内に転職継続の手続きをします。その際、同一の財形貯蓄取扱金融機関を利用する場合は「勤務先異動申告書」を、違う財形貯蓄取扱金融機関を利用する場合は「転職等による財形貯蓄継続適用申告書」を用いて転職先で手続きすることになります。
なお、新しい勤務先で財形貯蓄を扱っていない場合や、退職後2年以内に転職しない場合は、原則として財形貯蓄を解約することになります。また、もし社内融資を利用している従業員が退職する場合は、原則として退職と同じタイミングで一括返済する取り決めになっています。返済残高が残っている場合は、返済期間や返済残額を従業員本人と確認のうえ、一括返済の手続きをおこないましょう。
4. 総務担当者が退職手続きを行う際のよくある質問

ここでは、総務担当者が退職手続きをおこなう際のよくある質問への回答を紹介します。
4-1. 退職届の提出はメールでもよい?
退職届は、紙でなく、メールで提出してもらっても法律上問題ありません。しかし、退職届をメールで受け取る場合、誰からいつ提出されたのかをきちんと記録に残せる体制を整備しておくことが大切です。
退職届のデータが紛失してしまうと、退職に関してトラブルが起きたときに証拠を提示できず、会社側が不利になる恐れもあります。そのため、バックアップも保管しておくなど、セキュリティ体制にも注意を払うことが重要です。
4-2. 退職手続きは電子化できる?
退職手続きは、従業員の退職後、速やかにおこなわなければなりません。退職手続きが遅れると、会社側は本来納付が不要な社会保険料などを支払わなければならなくなる可能性があります。また、従業員側は失業手当の手続きができなかったり、新たな就業先で社会保険に加入するのが遅れてしまったりする恐れもあります。
社会保険や雇用保険、源泉徴収票交付などの退職手続きは電子化することが可能です。ただし、従業員の同意が必要なものもあるので注意が必要です。また、特定の法人に該当する場合、退職手続きを電子申請でおこなわなければならない義務がある可能性もあります。退職手続きを法律に則り、スピーディーに実施するためにも、この機会に電子化を検討してみることも推奨されます。
関連記事:社会保険手続きの電子申請が義務化!やり方やメリット・デメリットを解説
5. 総務担当者は退職手続きの流れを理解してスムーズに進めよう!

退職手続きには、社会保険や雇用保険、所得税、住民税、業務の引き継ぎ、貸与物の返却など、さまざまな手続きがあります。総務担当者は退職手続きの重要性を理解し、期限までに余裕を持って手続きをおこなわなければなりません。抜けや漏れが生じないよう、あらかじめ退職手続きマニュアルや返却物チェックリストなどを作成しておくのがおすすめです。また、手続きをスピーディーにおこなうため、退職手続きの電子化も検討してみましょう。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。









