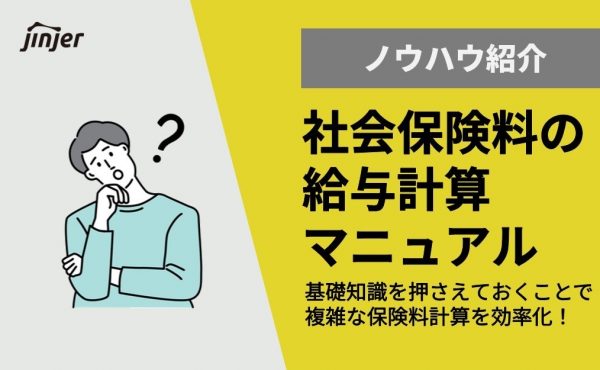傷病手当金は、普通に仕事をしているだけでは支給されることのない手当金です。この傷病手当金は、怪我や病気などで休業した際に受け取ることのできる手当金となっており、働けなくなった従業員を守るために存在しています。
では、傷病手当金に関する社会保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか。本記事では、傷病手当金から社会保険料を天引きするべきか解説します。また、会社が社会保険料を立て替える際の注意点についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:社会保険料とは?|計算方法や注意点、法改正の内容などを徹底解説
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」
という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。
目次
1. 傷病手当金とは?

傷病手当金とは、その名の通り病気や怪我などをした際に受け取ることができる手当金のことです。具体的には、健康保険から支給される手当金となっており、業務外での病気や怪我で会社を休み、十分な報酬が受けられないという条件を満たす場合に支給されます。
あくまでも病気や怪我で働けなくなった際に給料の代わりのような形で支給される手当金であり、病気や怪我が起こるたびに受け取れるわけではないので注意してください。
1-1. 傷病手当金の支給額
傷病手当金の支給額は以下の通りに定められています。
- 1日あたりの支給額 = 支給開始日の以前12カ月間の各月標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3に相当する金額
次に具体的な支給要件について確認していきましょう。
1-2. 傷病手当金の支給要件
傷病手当金の支給を受けるためには、以下4つの要件をすべて満たさなくてはいけません。
業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること
業務上や通勤途中で起こった病気や怪我は、労災保険の給付対象となります。労災保険が支給されているのであれば、傷病手当金は支給されません。
また、病気や怪我の治療に健康保険が適用されなかったとしても、傷病手当金を受け取ることはできます。しかし、美容整形など病気や怪我に含まれない入院の際には、傷病手当金は支給されません。
仕事に就くことができない
当然ですが、働くことができない状況でなければなりません。仕事ができるかどうかは、医師の意見や被保険者の仕事内容なども考慮して判断されます。
例えば、パソコンさえあれば仕事ができるデスクワーク従事者とトラック、タクシードライバーなどでは判断基準が異なるというわけです。
連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を3日間休んだ後に4日目から傷病手当金が支給されます。3日間は連続する必要がありますが、4日目については出社をはさんでも問題ありません。
例えば、3日間休んだ後に出社して、再度療養をするために休んだようなケースでは、再度休んだタイミングから傷病手当金が支給されます。
この待機3日間については、会社そのものが休業していても対象になります。土日祝日であっても3日間待機していたことになるのです。
休業している期間に給与の支払いがないこと
当然ですが、傷病手当金は給料の代わりに支給されているものなので、給料の支払いがあるのなら支給されません。しかし、傷病手当金の満額と支給される給料を比較して、支給される給料の方が少ない場合は、その差額が支給されます。
1-3. 傷病手当金が支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年と6カ月です。令和2年7月1日までは支給開始日より1年6カ月でしたが、令和4年1月1日より通算1年6カ月に変更となりました。
この期間は通算であるため、休職して傷病手当金の支給を受けた後に、回復して業務をおこない、また休職期間に入った場合、業務をおこなっていた期間はカウントされません。
1-4. 傷病手当金の継続給付
一定の条件を満たしている場合は、退職後も継続して傷病手当金を受給できます。具体的には、以下の条件を満たしていれば、継続給付を受けることが可能です。
- 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上ある
- 資格喪失日の前日に傷病手当金が支給されている、または支給要件を満たしている
ただし、一度働ける状態になった場合、その後に再び働けない状態になっても傷病手当金は支給されません。
1-4. 傷病手当金が調整されるケース
傷病手当金は、給与や他手当との重複支給を避けるため、以下5つに当てはまる場合は支給額が調整されます。
- 給与の支払いがあった場合
- 障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
- 老齢退職年金を受けている場合
- 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
- 出産手当金を同時に受けられるとき
それぞれのケースの詳細は以下の通りです。
給与の支払いがあった場合
給与の支払い、または各種手当が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金との差額が支給されます。傷病手当金の受取後に給与や手当の支給が判明した場合は、傷病手当金を返納する必要があるので注意しましょう。
障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
傷病手当金の支給要件を満たしていても、同じ病気や怪我により障害厚生年金の支給を受けるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の支給額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額のみ支給されます。
また、障害手当金の支給を受ける場合、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日までは傷病手当金を受給することはできません。
老齢退職年金を受けている場合
前述の通り、一定の要件を満たせば退職後も傷病手当金を継続受給できますが、老齢退職年金を受給している場合は、傷病手当金を受給することはできません。
ただし、老齢退職年金の支給額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額を受給することが可能です。
労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
労災保険から休業補償給付を受けていた場合や受けている場合、同じ病気や怪我を理由として傷病手当金を受給することはできません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額を受給できます。
出産手当金を同時に受けられるとき
出産手当金の支給を受けている場合も傷病手当金が調整されます。具体的には、出産手当金の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額を受給可能です。
2. 傷病手当金からも社会保険料を天引きすべき?免除すべき?

傷病手当金から社会保険料を天引きする、という表現は厳密には正しくありません。正しくは休業中であっても社会保険料の徴収は発生するというものになります。
休業中は給与が支給されない場合も多いので、その期間の社会保険料の従業員の負担分をどのように従業員から徴収すれば良いのでしょうか。
毎月給料から天引きされるものに雇用保険、所得税、住民税があります。そのうち雇用保険と所得税については、支給される給与に応じて金額が決まるため、給与の支給がなければ徴収は0となります。また、傷病手当金は、課税対象外なので所得税などはかかりません。ただし、住民税についてはこの項目では詳細は割愛しますが、前年度の収入に対して課税されるので社会保険料と同様休業中の天引きの問題が生じます。
しかし、社会保険料は休業していても資格を喪失したわけではないので被保険者である期間は社会保険料の負担が発生します。
極端な話をすれば、人間関係のトラブルなどで従業員が会社に通うことができなくなってしまい、休業したような場合でも社会保険料の支払いは発生します。会社が休業を認めたとしてもそのような状況であれば給料は発生しないでしょう。もちろん、傷病手当金も発生しません。給料が発生していないので所得税や住民税が課税されることはありませんが、社会保険料についてはすでに金額が決定しており、給与に対して課税されるものではないため支払わなくてはいけません。
どのような状況になったとしても、社会保険に加入している限りは社会保険料の支払い義務は発生すると考えておいてください。
2-1. 傷病手当金と社会保険料で相殺は可能?
傷病手当金は、原則、被保険者本人に直接振り込まれます。しかし、被保険者が口座を持っていないなどの理由がある場合は、従業員本人の同意を得た上で、会社の口座を受け取り口座にすることも可能です。そして会社に振り込まれた傷病手当金については、従業員の同意を得た上で、従業員の負担するべき社会保険料や住民税を差引いた後の残額を従業員に給付することができます。
ただし、預かった傷病手当金はあくまで社員のものですので、社会保険料を相殺する場合は社員本人から必ず同意を得る必要があります。
まず当該社員に休職中も社会保険料の支払いが必要になることを説明し、そのうえで傷病手当金との相殺を希望するかどうかを尋ねましょう。
同意を得られた場合は、後のトラブル防止のためにきちんと書面を取り交わしてから、傷病手当金と社会保険料の相殺手続きをおこないます。
2-2. 社会保険料が発生しないケース
基本的には従業員が休業している状態であっても社会保険料は発生しますが、一部例外もあります。産前産後の休業期間や、3歳までの子どもを養育するための育児休業期間については、社会保険料が発生しません。
従業員分はもちろん、会社負担分も発生しないため覚えておきましょう。
3. 傷病手当金から社会保険料を支払う代わりに会社が立て替えることは可能?

休業中の従業員が傷病手当金を受け取っている場合は、傷病手当金から社会保険料を支払うことは可能かもしれません。しかし、病気や怪我の状況次第では、傷病手当金を全額治療費に回さなくてはならず、社会保険料の支払いが難しいというケースもあるかもしれません。
そういった場合は、一時的に会社が立て替えるという方法もあります。しかし、あまり推奨はされません。なぜなら、会社が立て替えた後に社会保険料の支払いをする前に従業員が退職するといった事態が起こる可能性があるからです。従業員と連絡が取れなくなってしまい、社会保険料を回収するだけでかなりの業務負担が発生する可能性もあります。仮に従業員と連絡が取れたとしても従業員が社会保険料の支払いを拒否するかもしれません。
以下、会社が社会保険料を立て替えるときの注意点を紹介します。
3-1. 会社が立て替えるときは立て替え明細を交付すべき
会社が立て替えをおこなう場合は、立て替え明細を添付した社会保険料の支払依頼書を交付して、本人の自筆署名や押印をしてもらうようにしてください。このように何らかの形で確実に支払ってもらえるような対策をしておく必要があります。
万が一、未払いが発生すると訴訟につながるかもしれません。しかし、訴訟をするのはかなりの労力が必要になりますから、そういったリスクを減らすためにも会社が立て替えるのはできれば避けるようにしてください。支払いについてのルールは就業規則で定めておくのが効果的です。
3-2. 退職者から立て替えた社会保険料を支払ってもらえない場合の対応方法
会社が休職中の社員の社会保険料を立て替えたにもかかわらず、社員が立替分の支払いを拒否した場合の対処方法は大きく分けて3つあります。
債務と相殺する
1つ目は、社員に対する債務と相殺する方法です。まれなケースですが、会社が社員に何らかの債務を負っていた場合、社会保険料と相殺することができます。
なお、ここでいう債務には社員に支払う賃金は含まれません。賃金と社会保険料を相殺することは、賃金全額払いの原則に反し、労働基準法違反となりますので注意しましょう。
支払督促をおこなう
2つ目は、支払督促の実行です。裁判所に対して支払督促の申し立てをおこなうと、当該社員に対し、裁判所から社会保険料の未納分を支払うようにという通知が送付されます。
社員が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てがなかった場合、会社は仮執行宣言付支払督促の申し立てをおこなうことが可能です。
仮執行宣言付支払督促に対して異議申し立てがなく、社員が社会保険料の未納分を支払わなかった場合は、社員の財産を調査し特定した後、財産差押えの強制執行の申し立てをおこなえるようになります。
訴訟を起こす
3つ目は訴訟です。前述した支払督促や仮執行宣言付支払督促に対して社員から異議申し立てがおこなわれた場合、訴訟手続きに移行します。
訴訟では社会保険料を立て替え払いした事実や未納の事実を証明する証拠を用意する必要があります。
訴訟にはかなりの手間と時間がかかるため、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
4. 傷病手当金の支給期間も社会保険料の支払いは発生する!

傷病手当金は休業している従業員を守るための制度です。しかし、休業中も社会保険料の支払いは発生するため、徴収もれを防ぐために会社側で何かしらの仕組みを作っておくことが大切です。振込先指定口座は原則申請者本人様口座となります。ただし、相応の事情がある場合には、従業員の同意を得た上で会社の口座に振り込んでもらい、社会保険料などを差し引いた残額を従業員に支給することもできますがあくまで例外的な取扱いになります。トラブルにならないためにもしっかり休業中の社会保険料についての取扱いを決めておきましょう。
また、そのような仕組みを作れば社会保険料の未払いは防げますが、人事や経理担当者の業務は増えます。休業のようなイレギュラーな事態が起こると、対応しなければならない仕事が多くなってしまい、通常の業務に影響が出る可能性もあります。
そういった事態を防ぐために管理システムの導入を検討しましょう。管理システムを導入することでオンライン上でも業務の進捗をすぐに確認できるようになります。業務効率が大幅に上昇し、テレワークでもスムーズに業務を進めることが可能です。
テレワークになるとどうしても業務効率が落ちてしまうと頭を悩ませている企業も多いでしょう。そのような場合は、管理システムを導入して人事や経理担当者の業務効率向上を目指してください。