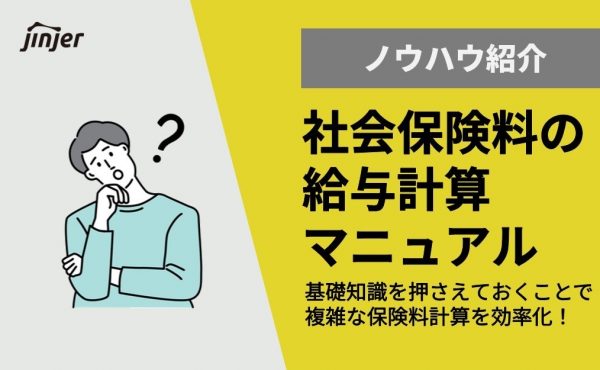賞与は臨時の支給金であり、毎月の給与とは違った方法で所得税を計算します。天引きする項目や所得税率の求め方も異なるため、計算の際には注意しましょう。
賞与は臨時の支給金であり、毎月の給与とは違った方法で所得税を計算します。天引きする項目や所得税率の求め方も異なるため、計算の際には注意しましょう。
今回は、賞与から天引きされる項目や所得税率の求め方、所得税の計算方法について詳しく解説します。
関連記事:給与計算時の所得税の計算方法とは?源泉所得税や控除についても解説
目次
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードの上お役立てください。
1. 賞与から天引きされる所得税や保険料

賞与から天引きされる所得税や保険料は、以下の通りです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 介護保険料(40歳以上の場合)
- 所得税および復興特別所得税
なお、住民税は前年の総所得から算出した税額を、月々の給与から天引きします。賞与からは天引きしないと覚えておきましょう。以下、それぞれの保険料の計算方法について解説します。
1-1. 健康保険料
医療保険の財源となる健康保険料の計算式は「標準賞与額×健康保険料率÷2」です。標準賞与額とは、賞与支給額から1,000円未満を切り捨てした金額のことです。[注1]
たとえば、賞与支給額が60万8,320円の場合、標準賞与額は60万8,000円です。
標準賞与額がわかったら、健康保険料率を確認します。健康保険料率は「協会けんぽ」のホームページに記載されています。都道府県によって利率が異なるので、ホームページ内にある保険料額表を確認してから計算してください。
なお、健康保険料は会社と折半するため、最後に2で割る必要があります。
[注1]厚生年金保険の保険料(3.標準賞与額)|日本年金機構
1-2. 介護保険料(40歳以上の場合)
40歳以上の従業員の場合は、介護保険料の天引きが必要です。「標準賞与額×介護保険料率÷2」の計算式で求められ、介護保険料率は毎年変動します。健康保険料と同様、協会けんぽで介護保険料率を確認してから計算しましょう。[注2]
1-3. 厚生年金保険料
厚生年金保険料は、老齢年金や障害年金などの財源になるものです。「標準賞与額×厚生年金保険料率÷2」で計算します。健康保険料と同様、負担額は会社と折半のため、最後に2で割ります。厚生年金保険料率は一律18.3%です。[注3]
[注3]厚生年金保険料額表|日本年金機構
1-4. 雇用保険料
失業手当をはじめとした給付金の財源となる雇用保険料は「賞与支給額×雇用保険料率」で算出します。これまでの保険料と異なり、賞与支給額そのものを計算に利用するので、誤らないよう気をつけてください。
雇用保険料率は、年度や事業内容によって異なります。令和6年度(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)の雇用保険料率は以下の通りです。[注4]
| 事業の種類 | 4月1日〜3月31日の労働者負担率 |
| 一般事業 | 0.6% |
| 農林水産業・清酒製造事業 | 0.7% |
| 建設業 | 0.7% |
関連記事:雇用保険料の計算方法は?雇用保険の目的や最新の会社負担額を解説
1-5. 所得税および復興特別所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。1年間の所得から所得控除を差し引いた所得に税率が適用されます。
所得税は、所得が多くなるにつれて税額が上がる仕組みです。また扶養人数や医療費、保険料などによって控除金額が変動します。
復興特別所得税は、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地復興を目的とした税金です。所得税額の約2.1%が、復興特別所得税額となります。
復興特別所得税は、制度の特質上、課税対象期間が2013年1月1日から2037年12月31日までに限定されています。
2. 賞与に対する所得税率

賞与に対する所得税率を確定するには「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を使用します。表を使用するには、以下2つの情報が必要です。
- 前月の給与総支給額から社会保険料(健康保険料や介護保険料などの総称)を差し引いた金額
- 扶養人数
まずは、前月の給与総支給額から社会保険料を差し引いてください。たとえば前月の給与総支給額が30万円、社会保険料が5万円の場合「30万円-5万円=25万円」です。扶養人数が1人だと仮定して、25万円の数値と重なる位置を算出率表で確認します。今回の場合、所得税率は「4.084%」だとわかります。
以下は賞与に対する源泉徴収税額の算出率表の一部です。[注5]
| 所得税率 | 扶養人数0人 | 扶養人数1人 | 扶養人数2人 | 扶養人数3人 |
| 0.000% | 6万8,000円未満 | 9万4,000円未満 | 13万3,000円未満 | 17万1,000円未満 |
| 2.042% | 6万8,000円以上7万9,000円未満 | 9万4,000円以上 24万3,000円未満 |
13万3,000円以上26万9,000円未満 | 17万1,000円以上29万5,000円未満 |
| 4.084% | 7万9,000円以上25万2,000円未満 | 24万3,000円以上28万2,000円未満 | 26万9,000円以上31万2,000円未満 | 29万5,000円以上34万5,000円未満 |
| 6.126% | 25万2,000円以上30万円未満 | 28万2,000円以上33万8,000円未満 | 31万2,000円以上36万9,000円未満 | 34万5,000円以上39万8,000円未満 |
| 8.168% | 30万円以上33万4,000円未満 | 33万8,000円以上36万5,000円未満 | 36万9,000円以上39万3,000円未満 | 39万8,000円以上41万7,000円未満 |
このように、社会保険料を差し引いた賞与額や扶養人数によって、所得税率が変動します。
[注5]賞与に対する源泉徴収額の算出率の表(令和6年分)|国税庁
3. 賞与に対する所得税の計算方法

賞与に対する所得税額を計算する手順は、次の通りです。
- 前月の給与総支給額から社会保険料を差し引いて課税所得額を求める
- 課税所得額と扶養人数から所得税率を求める
- 課税所得額と所得税率を乗じて所得税を求める
以下、計算例を挙げながら解説します。
3-1. 前月の給与総支給額から社会保険料を差し引いて課税所得額を求める
課税所得額は、給与総額から社会保険料等控除を差し引いて求められます。賞与の計算に利用するのは、前月の給与総支給額です。前月の給与支給額が40万円、社会保険料が8万円の場合は、課税所得額は32万円です。
3-2. 課税所得額と扶養人数から所得税率を確認する
次に、課税所得額と扶養人数をもとに所得税率を確認します。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を見ながら、当てはまる場所をチェックしてください。課税所得額が32万円、扶養人数が2人と仮定した場合だと、所得税率は「6.126%」です。[注5]
所得税率は従業員ごとに異なるので、計算の都度「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を確認しましょう。
[注5]賞与に対する源泉徴収額の算出率の表(令和6年分)|国税庁
3-3. 課税所得額と所得税率を乗じて所得税を求める
最後に1と2で求めた課税所得額と所得税率を乗じます。今回は課税所得額が32万円、所得税率が6.126%のため「32万円×6.126%=1万9,603円(小数点以下切り捨て)」と計算されます。賞与支給額から源泉徴収する所得税額は、1万9,603円です。
3-4. 前月に給与支給がなかった従業員の所得税額の求め方
手順1において、前月の給与総支給額から所得税率・所得税額を求めると説明しました。しかし、なかには前月の給与支給がない方もいるでしょう。この場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」をもとに所得税を計算します。
まず、賞与支給額から社会保険料を差し引き、賞与の計算期間の月数で割りましょう。
半年に1回の賞与支給の場合は「(賞与支給額-社会保険料)÷6」です。もし半年を超える場合は12で割ります。[注6]
たとえば、賞与額が100万円、社会保険料20万円だとすると、以下の計算になります。
| (100万円-20万円)÷6=13万3,333円(小数点以下は切り捨て) |
次に「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の中から算出された金額に当てはまる税額を探します。13万3,333円で扶養人数が1人の場合は、840円です。[注7]
これは1カ月分の税額なので、×6をすると賞与の所得税額を求められます。
| 840円×6=5,040円 |
賞与支給額100万円、社会保険料20万円で扶養人数が1人の場合の賞与にかかる所得税額は、5,040円だとわかります。
4. 賞与に対する所得税が高くなることもある?
賞与に対する所得税が高くなることはあり得ます。
残業や昇給などで前月の給与額が上がっている場合、賞与の所得税は高くなるでしょう。賞与の所得税は、前月の社会保険料控除の金額と扶養人数によって決まるからです。
ただし、所得税は年収によって最終的な合計額が決まります。そのため、払いすぎた分は年末調整で還付されるケースも多いです。
5. 賞与に対する所得税の計算を効率化するツール
賞与に対する所得税の計算は、エクセルや給与計算ソフトを使うことで、ミスを減らして効率化できます。
5-1. エクセル
計算式が使用できるエクセルは、賞与に対する所得税を計算する際に役立ちます。
計算式を入力したフォーマットを用意すれば、あとは賞与額を入力するだけで、毎回計算をおこなう必要はありません。
ただし、フォーマットとして使用する計算式の設定にはミスが許されません。スキルを持った担当者がいない場合は、給与計算ソフトを使ったほうが無難でしょう。
5-2. 給与計算ソフト
給与計算ソフトはフォーマット作成の手間が不要であるため、誰でもすぐに使い始めることができます。他の業務ソフトとの連携も可能なものが多いため、業務効率化の強い味方にもなるのもメリットです。
6. 賞与に対する所得税率の計算方法を知って正しく天引きしよう!

賞与に対する所得税率を求める場合は、最初に賞与から社会保険料を差し引き、課税対象額を求めましょう。計算後は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」の中から課税対象額と扶養人数が重なる箇所の所得税率を確認します。
従業員によって賞与額や扶養人数が異なるため、所得税率も差があるのが通常です。ミスを防ぐためにも、処理の都度「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」から所得税率を確認し、計算をおこないましょう。
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。
保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」
「保険料の計算が合っているか不安」
「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードの上お役立てください。