
労働基準法では、退職金の支払い義務が定められていません。しかし、退職金を支給することが決まっている場合、労働基準法に基づき、退職金の決定方法や計算方法、支払い方法などを就業規則や雇用契約書に明記しておかなければなりません。この記事では、労働基準法に基づく退職金のルールについてわかりやすく解説します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法に退職金の規定はあるのか?

労働基準法には、退職金の取り決めがありません。そのため、退職金を支払うかどうかは、使用者の裁量で決めることができます。ただし、労働基準法には退職金に関連した条文が少ならからずあります。もしも退職金を支給する場合、労働基準法の規定を正しく守り、労働者に支給しなければ違法になる可能性もあるので注意が必要です。
2. 労働基準法の退職金に関連する条文

労働基準法には、退職金に関係する条文があります。ここでは、労働基準法の退職金に関連する条文について詳しく紹介します。
2-1. 退職金は賃金(労基法第11条)
労働基準法における賃金とは、労働基準法第11条に基づき、労働の対償として使用者から労働者に支払われるすべてのものです。そのため、退職金も労働の対価として支払われるのであれば、賃金に該当することになります。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
関連記事:労働基準法による賃金の定義や支払い方法をわかりやすく解説
2-2. 労働条件の明示義務(労基法第15条)
労働基準法第15条に則り、使用者には労働契約の締結の際、労働者に労働条件通知書を交付し、労働条件を明示する義務があります。退職金を支給する場合、労働基準法施行規則第5条に基づき、次のような事項も、労働条件として明示しなければならないので注意が必要です。
- 退職金を支給する労働者の範囲
- 退職金の決定方法や計算方法、支払い方法
- 退職金の支払い時期
なお、労働条件通知書だけでは労働基準法の要件を満たせても、労働者が労働条件に同意したことを証拠として残せません。そのため、労働条件通知書に加えて、雇用契約書も交付するようにしましょう。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、(省略)、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
(省略)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
引用:労働基準法施行規則第5条一部抜粋|e-Gov
関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!
2-3. 退職金の支払期限(労基法第23条)
労働基準法第23条に則り、退職により労働者から請求された場合、退職金を1週間以内に支給する必要があります。例外として、就業規則で退職金支給日を定めている場合は、それまでに支給すれば良いとされています。
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2-4. 賃金支払いのルール(労基法第24条)
退職金も賃金に該当するため、労働基準法第24条に基づき、通貨で直接労働者に全額を支払う必要があります。家族に支給したり、一部控除したりして支給することは原則認められません。なお、退職金は臨時に支払われる賃金とみなされるので、毎月払いの原則や一定期日払いの原則は、例外として適用されないので注意しましょう。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
毎月払及び一定期日払いの例外(労基法24②但書)
●退職金のような臨時に支払われる賃金
●賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令に定める賃金
2-5. 就業規則(労基法第89条)
労働基準法第89条により、常時労働者数が10人以上の場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。退職金の定めをする場合、次の事項を就業規則に記載しなければなりません。
- 退職金を支給する労働者の範囲
- 退職金の決定方法や計算方法、支払い方法
- 退職金の支払い時期
とくに、退職金の支給対象者は細かく定めておきましょう。雇用形態や勤続年数で区分する場合、従業員が不満を抱かないように設計することが大切です。また、勤続年数に従って退職金が増えていく制度が一般的ですが、どのような退職金の決め方にするかは会社が自由に決められます。そのため、従業員のニーズにあわせて、退職金の決定方法や計算方法も明確に定め、就業規則に明記しておきましょう。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(省略)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2-6. 退職金の請求期限(労基法第115条)
労働基準法第115条に則り、退職金請求権の時効は行使できる時から5年間です。なお、労働基準法第115条には経過措置があり、退職金を除く一般的な賃金の請求権の時効は当面の間3年とされているので注意しましょう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
3. 労働基準法に基づく退職金の決め方

労働基準法には退職金の取り決めがありません。そのため、退職金制度は企業が自由に決められます。退職金の計算方法はいくつかあり、企業が導入している制度によって違いがあります。ここでは、労働基準法に基づく退職金の決め方について詳しく紹介します。
3-1. 退職金の支払い義務が生じるケース
退職金の支払い義務が生じるのは、就業規則に退職金の規定をしているかどうかで決まります。また、就業規則に記載がない場合でも、雇用契約書に退職金を支給する定めをしていれば、労働基準法に基づき、必ず退職金を支給しなければなりません。
また、就業規則や雇用契約書に退職金制度に関する規定がない場合でも、従来から退職金を支給していた実績があり、制度として確立したものとみなされれば、退職金の支払い義務が生じる可能性があります(判例:吉野事件)。このようなトラブルを生まないためにも、退職金制度の有無やその内容については、就業規則や雇用契約書に明記しておくことが大切です。
右認定事実によれば、被告会社東京支店において、正規の退職金規程が制定されていたということはできないが、当初に案として作成・書面化された本件退職金規程に基づいて退職金を支給する実績が積み重ねられることにより、右支給慣行は既に確立したものとなったと認められ、これが被告会社と原告らの雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。
3-2. 退職金の種類と計算方法
退職金制度は、企業の裁量で自由に決められます。退職金制度の種類とその計算方法は、次の通りです。
| 退職金の種類 | 計算方法 |
| 定額制 | 勤続年数に応じて退職金の額を決定する方法。 |
| 退職金共済 | 退職金共済は「掛け金月額×支払った月数」によって決まります。 |
| 確定給付年金 | 確定給付年金も退職金共済と同じく「掛け金月額×支払った月数」によって決まります。 |
| 確定拠出年金 | 確定拠出年金も退職金共済と同じく「掛け金月額×支払った月数」によって決まります。 |
これら以外に、退職金を前払いする方法を採用している企業などもあり、さまざまな退職金制度があります。自社のニーズにあった退職金制度を整備し、正しく退職金を支給しましょう。
3-3. 【ポイント】退職金の税金の計算方法にも注意が必要!
退職金は、給与所得でなく、退職所得に該当します。そのため、通常の給与と違った方法で、所得や税金を計算します。また、退職金を支払う場合、従業員からの「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって源泉徴収のやり方も変わります。退職金の税金の仕組みを正しく理解し、適切に源泉徴収をおこなったうえで、退職金を支給することが大切です。
関連記事:退職金にかかる税金(所得税・住民税)の仕組みや計算方法をわかりやすく解説!
4. 労働基準法に基づく退職金に関する注意点やポイント

退職金の決定や支払いに関しては、いくつか気を付けるべき点があります。ここでは、労働基準法に基づく退職金に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。
4-1. パート・アルバイトに対する退職金の有無を明確にする
パートやアルバイトなどの通常の労働者より時間を短くして働く労働者は、短時間労働者に該当し、パートタイム労働法の適用対象になります。短時間労働者や有期雇用労働者には、パートタイム労働法第6条により、労働条件を明示する際、次の事項も伝えなければなりません。
- 昇給の有無
- 退職金の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
このように、退職金の有無も、必ず労働条件として明示しなければならないので注意しましょう。また、退職金制度を設けている場合、就業規則にもパートやアルバイトに退職金を支給するかどうか明記しておくことが大切です。
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
4-2. 退職金を支払う場合は退職所得の源泉徴収票の交付も必要
所得税法第226条に則り、退職金を支払う場合、給与所得の源泉徴収票だけでなく、退職所得の源泉徴収票も退職後1カ月以内に退職者に交付する必要があります。退職所得の源泉徴収票は、転職先で年末調整を受けるために提出する必要はありませんが、確定申告の際などに必要になる可能性もあるため、適切に保管しておくよう退職者に伝えましょう。
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(省略)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。(省略)
関連記事:退職所得の源泉徴収票とは?書き方や提出期限、確定申告の必要性について解説!
4-3. 退職金を控除できるケースもある
労働基準法の賃金支払いの5原則に基づき、退職金は全額支払わなければなりません。しかし、企業が導入している貸付金制度を労働者が利用し、借入金がある場合は退職金を控除できる可能性があります。ただし、賃金控除協定を締結しているか否かが重要です。賃金控除協定に「退職金支給の際、貸付金残高の有無で控除される」という規定を設けておけば、トラブルを未然に防止することができます。
4-4. 労働基準法に違反すると罰則を受ける
労働基準法には懲役や罰金などの罰則規定が定められています。たとえば、退職金を正しい期日までに支払わなかった場合、違法となります。この場合、労働基準法第120条に則り、30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。また、退職金の未払いに関して請求を受けたら、これに応じる義務もあるので気を付けましょう。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)、第二十三条から第二十七条まで、(省略)の規定に違反した者
5. 労働基準法に基づき退職金を支給するメリット

正しく退職金制度を整備し、労働者に退職金を支給すれば、さまざまなメリットが得られます。ここでは、労働基準法に基づき退職金を支給するメリットについて詳しく紹介します。
5-1. 自社の魅力をアピールできる
コストの負担が大きく退職金制度を用意できない企業も少なくないです。退職金を支給できるということは、財務状況が健全な証であり、応募者に安心感を与えることができます。また、自社のブランド価値の向上にもつながり、ステークホルダーからの信頼が高まる可能性もあります。
5-2. 労働者の退職を抑制できる
退職金の金額は、長く勤めるほど高くなる傾向にあります。これは、退職金が自社に貢献してくれた人を評価するという功労報償的な性格を有するためです。このように、退職金制度は労働者の退職を抑制する効果があり、離職率を減らすためにも役立ちます。
5-3. 労働者に規律を守らせる効果がある
退職金の支給に関して、労働基準法で明確に規定されていないため、企業の裁量で支給対象者や支給金額などを決めることができます。たとえば、懲戒処分として退職金支給なしとすることも可能です(判例:巴屋事件)。このように、退職金制度を上手く活用すれば、労働者に企業の規律を守らせる効果も期待できます。
退職のさいに業務引継ぎを尽さない場合には「円満退職」とせず退職金を支給しない旨の給与規程につき、業務引継ぎが完全に行なわれたものとして、退職金一部不支給分の支払い請求が認容された事例。
5-4. 人材の確保につながる
退職金制度は、会社側だけでなく、従業員側にも多くのメリットがあります。退職金が支給されることで、老後もゆとりを持って生活することが可能です。また、退職所得の計算では、退職所得控除を利用できるので、税金の負担を大きく抑えることができます。このように、退職金制度を用意することで、労働者は安心して長く働き続けられるため、従業員満足度が向上し、人材の定着率も高まります。
6. 労働基準法に基づき退職金を支給するデメリット
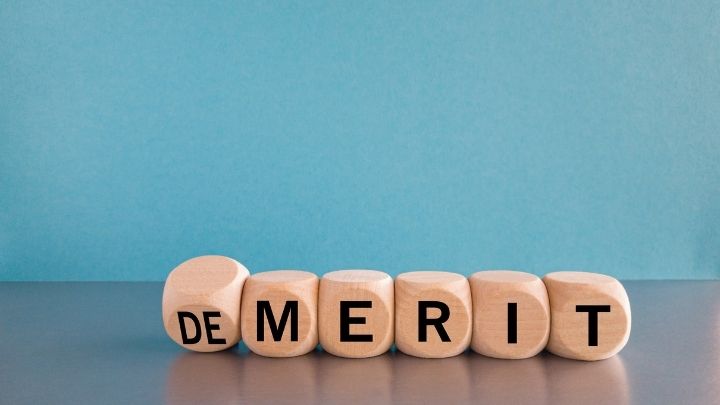
退職金制度には、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、労働基準法に基づき退職金を支給するデメリットについて詳しく紹介します。
6-1. 人件費の負担が大きくなる
退職金を支給するためには、それなりの資金を確保しておかなければなりません。そのため、人件費の負担が大きくなります。また、すぐに退職してしまうのに退職金を支払う場合、コストに見合った効果が得られない恐れもあります。退職金制度を導入する場合、まずは目的を明確にし、支給対象者や支給要件を細かく定義することが大切です。
6-2. 一度導入すると廃止が難しい
既にある退職金制度を廃止する場合、すべての従業員の同意を得たうえで、就業規則を変更する必要があります。労働契約法第9条により、従業員の同意なく、労働者が不利益を被るような就業規則の変更は原則認められません。
このように、退職金制度は一度導入すると、廃止するのが難しいというデメリットがあります。ただし、経営を継続することが困難などの事情があれば、従業員の同意を得なくとも、就業規則の変更により退職金制度を廃止できる可能性もあるので、正しく労働基準法や労働契約法などの法律を理解しておきましょう、
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
6-3. 運用の負担がかかる
退職金制度を導入したら、社会や時代の変化にあわせて、定期的に自社の退職金規定を見直す必要もあります。また、退職者が出たら、退職金に関係する書類のやり取りなど、事務的な負担も増えます。このように、退職金制度を導入する場合、導入時だけでなく、運用の負担もかかります。なお、退職金共済や確定拠出年金といった制度であれば、企業側は掛け金だけを拠出すればよいため、運用の負担を軽減させることが可能です。
7. 労働基準法に基づき退職金を支給する場合は就業規則を整備しよう!

退職金規定は、労働基準法上定める義務はありません。しかし、退職金を支給する場合、就業規則や雇用契約書にその内容をきちんと明記しておかなければ、労使間でトラブルが発生する恐れがあります。退職金制度は自社で設計ができます。労働者のニーズをチェックし、退職金規定を整備することで、従業員満足度の向上や人材の確保などのメリットが得られます。
労働基準法総まとめBOOK









