 労働基準法は、労働者の人権の最低限度を保障するという考え方に基づいて制定されています。しかし、労働基準法における労働者とは、仕事をしているすべての人が該当するわけではありません。この記事では、労働基準法第9条の労働者の定義についてわかりやすく解説します。また、労働者かどうか判断するための基準についても紹介します。
労働基準法は、労働者の人権の最低限度を保障するという考え方に基づいて制定されています。しかし、労働基準法における労働者とは、仕事をしているすべての人が該当するわけではありません。この記事では、労働基準法第9条の労働者の定義についてわかりやすく解説します。また、労働者かどうか判断するための基準についても紹介します。
労働基準法総まとめBOOK
労働基準法の内容を詳細に把握していますか?
人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。
例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。
今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。
労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。
目次
1. 労働基準法第9条「労働者」の定義

労働基準法第1章の各項目には、労働基準法の原則をはじめとした総則が定められています。このうち、労働基準法第9条では労働者の定義が定められています。労働者とは、職種・業種に関係なく、使用者の下で働き賃金を得ている従業員のことです。
なお、対象者が労働基準法上の労働者にあたるかは、労働者性があるかどうかで判断します。労働者性が認められる者に対しては、労働基準法の定めどおりに労務管理をおこなわなければならないので気を付けましょう。
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
2. 労働基準法第9条「労働者」の種類
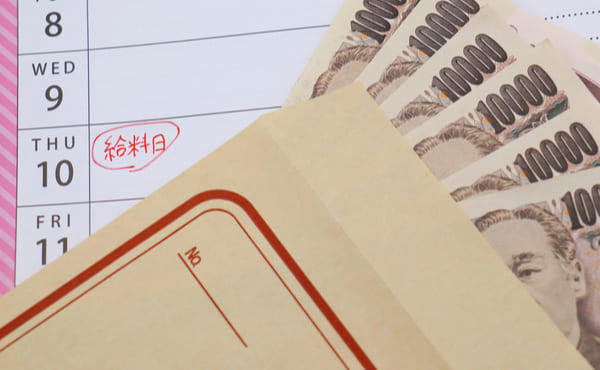
労働基準法第9条の労働者には、どのような人が該当するのでしょうか。ここでは、労働基準法第9条の労働者の種類について詳しく紹介します。
2-1. 正社員
正社員(正規雇用労働者)とは、直接雇用されていて、契約期間の定めがなく、一般的にフルタイムで働く労働者のことです。一方、派遣契約により働く労働者や、契約期間が定められている労働者、短い労働時間で働く労働者などは、非正規雇用労働者とよばれます。
正規雇用と非正規雇用で賞与・手当や福利厚生などの勤務条件を区分している企業もあります。しかし、政府による同一労働同一賃金の導入など、正規雇用と非正規雇用の二極化を緩和する動きも推進されているので留意しておきましょう。
2-2. パートタイム労働者
パートタイム労働者とは、「短時間労働者」「パートタイマー」「アルバイト」と呼ばれることもあり、正社員と比べて、週の所定労働時間が短い労働者のことです。パートタイム労働者は、労働時間が短いだけで、労働基準法第9条の労働者に該当します。そのため、一般の労働者と同様で、休憩時間や有給休暇なども、法律に基づき正しく付与しなければなりません。
また、パートタイム労働者は、労働基準法だけでなく、パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)も適用されます。パートタイマーを雇用する場合、同一労働同一賃金など、パートタイム労働法のルールも遵守しなければならないので注意しましょう。
2-3. 契約社員
契約社員とは、有期労働契約を結ぶ労働者のことです。たとえば、フルタイムで勤務しているけれど、雇用期間が定められている場合は、契約社員にあてはまります。また、期間を定めて働くパートタイマーは、パートタイム労働者と契約社員のどちらにも該当することになります。なお、有期雇用労働者もパートタイム労働法の適用対象になるので注意が必要です。
労働基準法第14条により、契約社員の契約期間の上限は、一部の職種や年齢に該当する労働者を除き3年間です。それ以上の契約期間を定めることはできません。3年を超えて働かせる場合、労働契約の更新手続きが必要です。また、無期転換ルールについても正しく理解しておきましょう。
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
関連記事:雇用契約の更新とは?更新が必要なケースや、対応方法をあわせて解説
2-4. 短時間正社員
短時間正社員とは、次のいずれもの要件を満たし、フルタイムで働く正社員と比較して短い労働時間で働く労働者のことです。
- 期間の定めがない労働契約を結んでいる
- 賃金や手当の計算方法がフルタイムで働く正社員と同様である
近年では、育児や介護と両立して働きたい人や、ワークライフバランスを重視して働きたい人など、さまざまな働き方のニーズがあります。短時間正社員制度を導入すれば、正社員と大きく待遇を変えることなく、多様な人材を確保することが可能です。ただし、短時間正社員のように「正社員」と名が付く場合でも、呼称でなく実態に基づき、パートタイム労働法の適用対象かどうかは判断されるので注意しましょう。
短時間正社員という呼称であっても、その処遇が、正社員としての実態を伴っていない場合には、パートタイム・有期雇用労働法の適用対象となります。
2-5. 日雇労働者
日雇労働者とは、雇用保険法第42条で定められた次のいずれかの条件を満たす労働者のことです。
- 1日単位で働く労働者
- 30日以内の契約期間で働く労働者
なお、上記の条件に該当する場合でも、同一の使用者の下、連続する2カ月のそれぞれの月において18日以上雇用されている労働者や、31日以上継続して雇用されている労働者は、日雇労働者に該当しないので注意が必要です。
日雇労働者も、使用者と雇用契約を結び働く者であるため、労働基準法第9条の労働者に含まれます。日雇労働者は、極めて不安定な就労状態で働くことから、特別で雇用保険できる可能性があります。
(日雇労働者)
第四十二条 この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
一 日々雇用される者
二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
2-6. 派遣労働者
派遣労働者(派遣社員)とは、人材派遣会社(派遣元)と雇用契約を締結したうえで、派遣元と労働者派遣契約を締結している企業(派遣先)に派遣されて働く労働者のことです。派遣社員は派遣元と労働契約を結ぶため、労働基準法第9条の労働者に該当します。また、労働者派遣法第44条に則り、派遣先も労働基準法の一部が適用対象となるので注意しましょう。
(労働基準法の適用に関する特例)
第四十四条 労働基準法第九条に規定する事業の事業主に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者であつて、当該他の事業主に雇用されていないものの派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、(省略)
3. 労働基準法第9条の労働者に含まれない人

正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣社員なども労働基準法第9条の労働者に当てはまります。一方、どのような人が労働者に該当しないのでしょうか。ここでは、労働基準法第9条の労働者に含まれない人について詳しく紹介します。
3-1. 事業主・法人や団体の代表者
労働基準法における労働者とは、企業と雇用契約を結んでいる人や企業から賃金を受け取っている人のことです。企業の経営を担っている事業主、企業の代表者や役員報酬を得ている役員はこれに該当しません。業務執行権や代表権を持っていることや、企業の代表者との従属関係がないことが、労働者の範囲外とするための条件の一つです。
3-2. 個人事業主・フリーランス
個人事業主やフリーランスは、業務委託や業務請負といった契約によって働く者であり、どこかの会社などと労働契約を結び働くわけではありません。使用従属関係が生じないので、労働基準法の労働者に該当しません。そのため、個人事業主・フリーランスは、労働基準法の適用対象外となります。
しかし、形式上業務委託や業務請負という形を取っているものの、実質は雇用に近い状態で仕事をしている場合、労働者とみなされ、労働基準法が適用される可能性もあるので注意が必要です。また、フリーランスの権利や労働環境を守るため、2024年11月からフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されています。
3-3. 家事請負人
家事請負人とは、企業の役員や代表者の家庭において、家族の求めに従って家事一般に従事する者のことです。労働基準法第116条に則り、企業が雇っている家事請負人は労働者の範囲外とみなされます。これは、家庭内のトラブルに関して、政府が監督・規制するのは不適当だという考えに基づいています。
3-4. 事業主の親族
事業主の親族も、家事使用人と同様、労働基準法第116条により、原則として労働者の範囲外とされています。しかし、同居の親族が範囲対象外であるため、同居していない親族であれば、事業主の親族であっても労働者と判断されます。また、同居の親族であっても、ほかの従業員と同じ形で就労しているときには労働者とみなされることもあるので、正しく理解を深めておきましょう。
(適用除外)
第百十六条 (省略)
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
4. 労働基準法第9条の労働者か否かを判断するためのポイント
労働基準法第9条の労働者に該当するかは、労働者性があるかどうかで判断されます。なお、労働者性は一つの要素だけでなく、複数の要素を勘案して総合的に判断されるのが一般的です。ここでは、労働基準法第9条の労働者か否かを判断するためのポイントについて詳しく紹介します。
4-1. 指揮監督下の労働である
労働者性があるか判断するための条件の一つに「指揮監督下の労働であるかどうか」が挙げられます。指揮命令下の労働かどうかは、次のような事項を基に判断されます。
|
事項 |
内容 |
|
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 |
|
|
業務遂行上の指揮監督の有無 |
|
|
拘束性の有無 |
|
|
代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素) |
|
たとえば、働く場所と時間が指定されていて、本人でコントロールできない場合、拘束性があると判断され、指揮監督関係が肯定されやすくなります。
4-2. 報酬の労務対償性がある
労働者性を判断する際は、「指揮監督下の労働であるかどうか」だけでなく、「報酬の労務対償性があるかどうか」も要素の一つになります。つまり、労働の対価として給与・報酬などの賃金が支払われているのであれば、報酬の労務対償性があると判断されます。
たとえば、仕事の出来に関係なく、作業時間のみで金銭の大小が決まる場合、報酬の労務対償性が肯定されやすくなります。一方、単価と件数で報酬を決定する仕組みが採用されている場合、報酬の労務対償性が肯定されることにつながりません。このように、「指揮監督下の労働である」「報酬の労務対償性がある」の両方の条件が満たされる場合、使用従属性があると判断されます。
4-3. その他補強要素
使用従属性が肯定されれば、労働者性があると認められやすくなり、労働基準法第9条の労働者だと判断される可能性が高まります。使用従属性だけで、労働者性を判断するのが難しい場合、次のような要素も考慮して総合的に判断されることになります。
|
事項 |
内容 |
|
事業者性の有無 |
|
|
専属性の程度 |
|
|
その他 |
など |
たとえば、自分で業務に必要となる著しく高額な器具備品などを用意する場合、事業者としての性格が強くなり、労働者性が否定される方向にはたらきます。また、同じような仕事をしている既存の労働者と比べて、著しく高額な報酬を受け取っている場合、労働の対価としての賃金ではなく、事業者に支払う代金とみなされ、労働者性を弱めることにつながります。
5. 労働基準法第9条「労働者」の取り扱いに関する注意点

労働基準法第9条で定められた労働者に該当する人に対しては正しく給与を支払うなど、取り扱いに気を付けなければなりません。ここでは、労働基準法第9条「労働者」の取り扱いに関する注意点について詳しく紹介します。
5-1. 労働の対価としての賃金を正しい方法で支払う
賃金とは、労働の対価として使用者から労働者へ支払われるものです。労働の対償として支給されるのであれば、給料だけでなく、手当やインセンティブなども賃金に該当します。また、賃金の支払いのルールは、労働基準法第24条で明確に定められています。
賃金は、原則として、直接労働者に通貨で全額支払わなければなりません。そのため、家族に支給したり、一部控除したりすることは基本的に認められません。また、賃金は、毎月1回以上期日を定めて支払われなければなりません。3カ月分をまとめて支給するなどは違法になるので注意しましょう。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)
関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介
5-2. 労働時間や休日などのルールを遵守する
労働者には、賃金以外にも、労働基準法に基づきさまざまな規定が適用されます。労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合や、法定休日(1週1日、4週4日)に労働させる場合、事前に36協定の締結・届出が必要です。また、6時間を超えて働かせるのであれば、最低でも休憩時間を45分付与しなければなりません。
さらに、条件を満たす労働者には、年次有給休暇も正しく付与する必要があります。このように、労働者を雇用する場合、使用者は労働基準法のルールをきちんと遵守しなければなりません。法律をよく確認し、定期的に社内制度の見直しをおこなうことが大切です。
5-3. 社会保険の加入義務もチェックする
使用者は、すべての労働者に対して労災保険に加入させる必要があります。また、一定の要件を満たす労働者には、雇用保険や社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)にも加入させなければなりません。労働基準法だけでなく、社会保険の加入義務もきちんとチェックし、正しく社会保険に加入させませしょう。
関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説
5-4. 管理監督者も労働者に該当する
管理監督者でも使用者に雇用されていて、賃金が支払われているのであれば、労働基準法第9条に則り、労働者に該当します。しかし、労働基準法第41条の管理監督者に当てはまる場合、労働時間や休憩、休日といった一部の規定が適用されなくなります。
なお、管理監督者とは「経営者と一体的な立場にある者」のことであり、役職名でなく、実態に基づき判断されます。たとえば、係長や課長という役職に就いていても、適切な権限・賃金が付与されていなければ、「名ばかり管理職」に該当し、一般労働者と同様の労働基準法が適用されることになるので注意しましょう。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(省略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)
(省略)
5-5. 労働者の解雇は簡単にできない
労働者は、労働基準法だけでなく、労働契約法の保護も受けられます。労働契約法第16条により、正当な理由もなく労働者を解雇する場合、解雇権濫用と判断され、その解雇は無効になります。また、正当な理由に基づき労働者を解雇する場合でも、労働基準法第20条に則り、30日以上前に解雇予告をしなければなりません。このように、労働者を一度雇用したら、簡単には解雇できないことを押さえておきましょう。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(省略)
6. 労働基準法第9条「労働者」の定義を正しく理解しよう!

労働基準法第9条では、労働者の定義が明確に定められています。使用者によって雇用されていて、労働の対価として賃金が支払われている人は労働者に該当します。ただし、同居の親族や家事使用人などは、労働基準法の適用対象外になるので注意が必要です。労働者かどうかの判断が難しい場合は、「指揮監督下の労働」「報酬の労務対償性」の観点から使用従属性をチェックし、労働者性があるかどうかを確認することが大切です。
労働基準法総まとめBOOK










