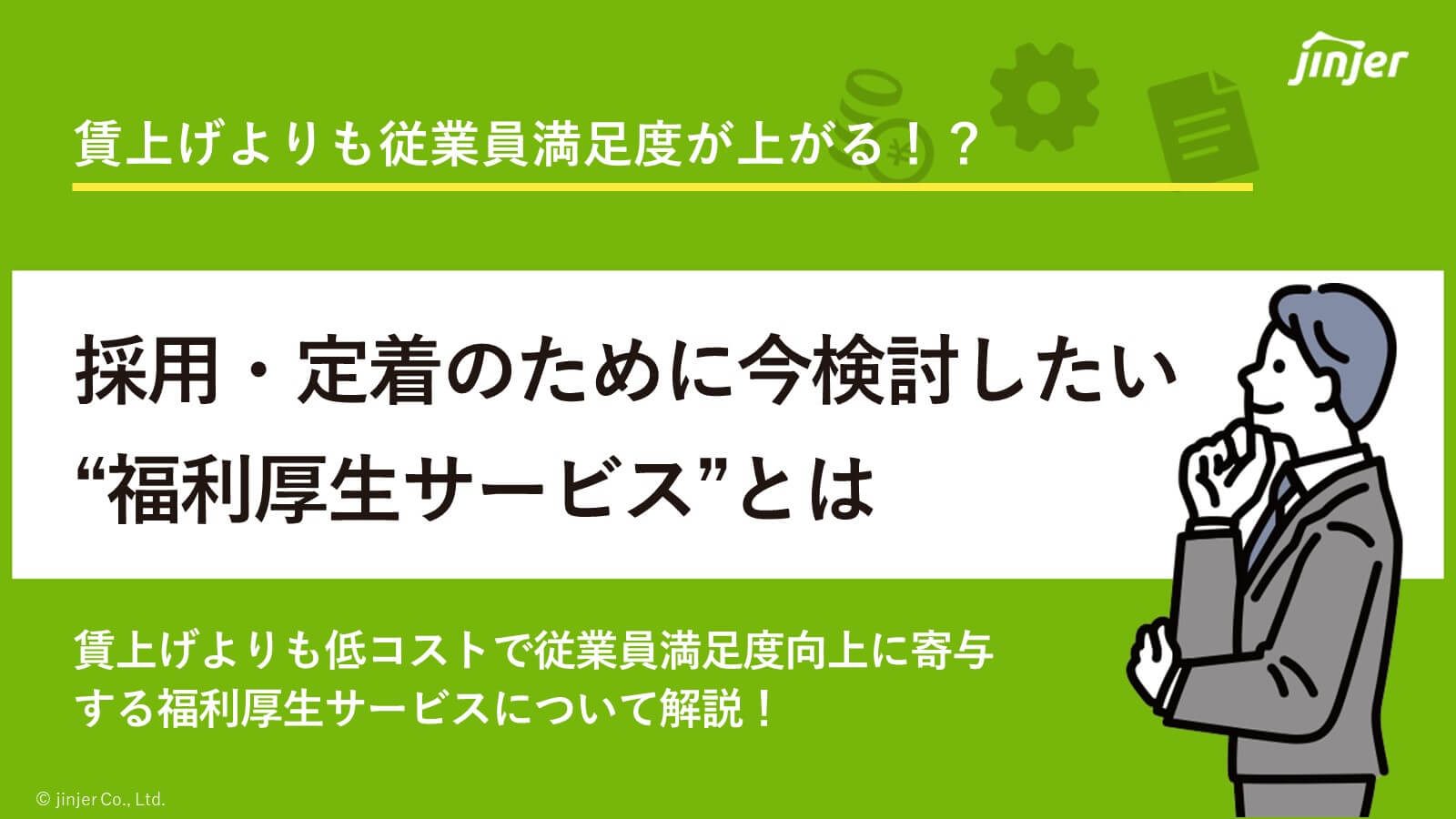「定着率とは?」
「定着率の計算方法とは?」
「定着率を向上させる取り組みを知りたい!」
定着率とは、入社してから所定期間を超えて働いている従業員の割合です。定着率が低いと人材を確保できなかったり、採用コストが増加したりするなど企業側に大きな影響がおよびます。さまざまな損失を回避するために、定着率向上の取り組みを実施することが大切です。
本記事では、定着率の平均値や計算方法などについて詳しく解説します。また人事・採用担当者が実施できる定着率向上の取り組みについても解説するので、ぜひ参考にしてください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 定着率とは

定着率とは、入社してから所定期間を超えて働いている従業員の割合のことです。定着率の数字が高いほど離職する従業員が少なく、働きやすい職場であると判断できます。
働きやすさを重視する求職者の場合、定着率を確認したうえで企業へ応募しているケースも多いです。採用計画に基づいた人数を確保するために、定着率向上の取り組みをおこなう企業が増えています。
1-1. 定着率が重視されている理由
定着率が重視されている理由として、少子高齢化による労働者不足が進んでいることが挙げられます。新しい人材を確保することには限界があるため、企業は今まで以上に既存の従業員の流出を防がなければなりません。
定着率は、従業員の満足度や企業の働きやすさを判断するための指標のひとつです。定着率が高い場合は問題ありませんが、低い場合は社内に何らかの問題があると考えられます。このように定着率を把握することで、社内の課題や解決策を探ろうとする企業が増えてきているのです。
2. 定着率と離職率の違い

定着率と離職率の違いは、割合を算出する際に用いる従業員のステータスです。それぞれの違いについて以下の表にまとめました。
|
定着率 |
入社してから所定期間を超えて働いている従業員の割合 |
|
離職率 |
入社してから所定期間までに離職した従業員の割合 |
定着率は所定期間を超えて働いている従業員の割合である一方、離職率は所定期間に離職した従業員の割合を算出します。定着率が高くなると離職率は下がり、定着率が低くなると離職率は上がるという関係にあります。
離職率に注目する場合は、数値が高くなっているときに注意が必要です。従業員が多く離職している状態であるため、人間関係が悪化していたり、従業員満足度が下がっていたり、何らかの問題がある可能性があります。
3. 定着率の平均値

定着率の平均値は以下の通りです。
- 国内企業の定着率は84.6%
- 大卒の入社3年以内の定着率は65.1%
それぞれの概要について詳しく解説します。
3-1. 国内企業の定着率は84.6%
令和5年雇用動向調査をもとに計算すると、国内企業の定着率は84.6%(離職率は15.4%)でした。令和4年の定着率は85%(離職率は15%)だったため、1年間で0.4%低下しています。
就業形態で比較すると、正社員などを含む一般労働者の定着率は87.9%(離職率は12.1%)、パートタイム労働者の定着率は76.2%(離職率は23.8%)でした。自社における定着率がここで紹介した数値よりも低い場合は、社内に解決すべき問題が潜んでいるかもしれません。
3-2. 大卒の入社3年以内の定着率は65.1%
令和3年3月に大学を卒業した人の場合、入社3年以内の定着率は65.1%(離職率は34.9%)でした。また高卒の場合は61.6%(離職率は38.4%)、短大卒などの場合は55.4%(離職率は44.6%)の定着率です。国内企業の平均値と比較すると、約2割も定着率が低いことが確認できます。
新卒を採用している企業が定着率の向上を図る際は、新卒に対するフォローを充実しなければなりません。以下の記事では若手社員向けの離職防止策について解説しているため、併せて参考にしてください。
【関連記事】「若手社員向けの離職防止策とは?定着率を向上させる取り組み事例を紹介」
参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
4. 定着率の計算方法

定着率の算出方法は以下の2つです。
- 所定期間の在籍人数で算出する方法
- 離職率から算出する方法
それぞれの計算方法について詳しく解説します。
4-1. 所定期間の在籍人数で算出する方法
所定期間の在籍人数で算出する方法は、以下の通りです。算出例として2021年4月入社の人数が120名、2024年3月時点の在籍人数が75名である場合の定着率を算出しました。
|
計算式 |
所定期間の在籍人数 ÷ 所定期間の開始時点の在籍人数 × 100 |
|
算出例 |
75名 ÷ 120名 × 100 = 62.5% |
定着率を算出する際は、中途入社した人数を含まないように注意してください。
4-2. 離職率から算出する方法
定着率は、離職率から算出することも可能です。算出例として2020年4月から2023年4月までの離職率が12%である場合の定着率を算出しました。
|
計算式 |
100(%)− 離職率 |
|
算出例 |
100% − 12% = 88% |
定着率と離職率は対となる指標のため、上記の計算式を用いて算出可能です。
5. 定着率を計算するときのポイント

定着率を計算するときは、以下のようなポイントに注意しましょう。
5-1. 対象とする期間は企業によって異なる
定着率の計算方法や対象期間に関する絶対的なルールはありません。一般的には1年単位で算出することが多いのですが、半年などの短い単位で算出することもあります。逆に3〜5年など、長期的な定着率を調べるケースもあります。企業の目的に応じて、適切な期間を対象として計算しましょう。
5-2. 定着率以外の情報も含めて分析する
算出した定着率をもとに社内の課題を把握しようとするときは、幅広い視点で分析することが大切です。たとえば、定着率が低い数値だったとしても、単純に定年退職が重なっただけかもしれません。
また、家庭の事情など、会社とは関係のない理由で離職する従業員もいるでしょう。数値だけに注目すると、正確な状況を把握できないため、他の情報も含めて分析する必要があります。
5-3. 必要に応じて便利なシステムを導入する
定着率を効率よく算出するためには、便利なシステムを導入するのがおすすめです。人事管理システムなどを活用すれば、現状の従業員数や離職者数などを簡単に把握できます。
定着率の対象期間を決めておけば、数値の推移を楽に比較することも可能です。大きな企業になるほど、従業員数や離職者数を把握するのに時間がかかるため、人事管理システムをうまく活用しましょう。
6. 定着率を高めるメリット

定着率を高めるメリットは以下の4つです。
- 人材を確保しやすくなる
- 採用コストを軽減できる
- 従業員のモチベーションが向上する
- 企業のブランド力が向上する
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
6-1. 人材を確保しやすくなる
定着率を高めるメリットとして、人材を確保しやすくなる点が挙げられます。働きやすい環境や福利厚生が整っていると外部から認識されるため、求人に対する応募数が高まるからです。
採用計画に基づいた人数を採用できると、人手不足の解消につながります。人手不足が解消すると既存従業員の業務負担が軽減し、優秀な人材の離職防止も可能です。
6-2. 採用コストを軽減できる
採用コストを軽減できることも、定着率を高めるメリットです。定着率が高いと離職する従業員が少ないため、新たな人材を採用するためのコストを抑えられます。また採用にかかる時間も削減できるため、別の業務に人員を配置することも可能です。
採用コストを軽減できると従業員の福利厚生を充実でき、従業員満足度の向上も期待できます。また別事業に予算を充てることで、企業の成長につなげることも可能です。
6-3. 従業員のモチベーションが向上する
定着率を高めるためには、ワークライフバランスを整える、ハラスメント対策を徹底するなど、さまざまな取り組みをおこなう必要があります。多くの対策を進めるなかで、人間関係や職場環境が改善されるケースも多いでしょう。
働きやすい職場環境が整うことで従業員の不満が減り、モチベーションが向上することも期待できます。熱意を持って仕事に取り組んでくれるため、生産性アップや顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
6-4. 企業のブランド力が向上する
定着率を高めることは、企業のブランド力向上にもつながります。定着率が高い場合、従業員を大切にしている企業だと認識されるからです。採用活動が効率よく進むだけではなく、投資家からのイメージがよくなり、資金調達がしやすくなるケースもあるでしょう。
7. 定着率が高い会社の特徴

定着率が高い会社の特徴として、以下のようなことが挙げられます。
- 人間関係が良好に保たれている
- 多様な働き方を選択できる
- 評価制度が整っている
それぞれの特徴について簡単に確認しておきましょう。
7-1. 人間関係が良好に保たれている
人間関係が良好であることは、定着率の高い会社に共通する特徴のひとつです。上司と部下が適度にコミュニケーションを取っていたり、チーム内での協力体制が構築されていたりすると、従業員は長く働きたいと考えるでしょう。
逆にコミュニケーションが希薄であったり、足を引っ張り合うような関係性であったりすると、定着率は低下すると考えられます。
7-2. 多様な働き方を選択できる
多様な働き方を選択できることも定着率の高い会社の特徴です。長く働きたいと思っていても、介護や育児、家庭の事情などで離職しなければならないケースもあります。
しかし、リモートワークや時短勤務など、多様な働き方を選択できる仕組みが整っていれば、それぞれの事情に合わせて働けるため定着率が向上するでしょう。
7-3. 評価制度が整っている
定着率の高い会社は、評価制度が整っている傾向があります。客観的な基準がなく、上司の主観で評価されるような制度では、従業員が不満を感じて離職してしまうケースもよくあります。客観的な評価基準があり、努力すれば高い評価を得られるような制度であれば、従業員のモチベーションが高まり、定着率も向上するでしょう。
8. 定着率が低いことによる企業への影響

定着率が低いことによる企業への影響は以下の通りです。
- 人材不足による業務効率の悪化
- 既存従業員の業務意欲の低下
- 採用コストの増加
定着率が低いと離職する従業員が多いため、人材不足によって業務効率が悪化する可能性があります。また人材不足により既存従業員への業務負荷が大きくなると、業務意欲の低下を招くでしょう。
さらに従業員が離職するたびに求人広告や人材紹介サービスを利用すると、採用コストが増加します。採用時にコストをかけすぎると教育や研修に充てられず、十分な人材育成をおこなえません。
従業員が働きやすい環境を整えたり、余計なコストを発生させたりしないためにも、定着率の改善に取り組むことが大切です。
9. 人事・採用担当が取り組むべき定着率を上げる方法

人事・採用担当が取り組むべき定着率を上げる方法として、以下の6つが挙げられます。
- 採用プロセスを改善する
- 人事評価制度を見直す
- 従業員研修を充実させる
- ワークライフバランスを改善する
- 採用時のミスマッチを防止する
- ハラスメント対策を徹底する
それぞれの方法について詳しく解説します。
9-1. 採用プロセスを改善する
従業員の定着率を上げる方法として、採用プロセスを改善する点が挙げられます。採用プロセスとは、採用活動から内定後のフォローまでの過程のことです。
厚生労働省による若年者雇用実態調査では、「労働時間・休日・休暇の条件が合わない」理由で離職した人が30.3%でした。また離職理由として、「人間関係がよくない」と回答した人は26.9%です。
離職を防ぐためには採用前に雇用条件について正しく伝え、内定後フォローの充実を図りましょう。以下の記事ではプロセス別の新卒採用方法についてまとめているため、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】【プロセス別】新卒採用を成功させる方法まとめ|失敗しない新卒採用とは
9-2. 人事評価制度を見直す
人事評価制度を見直すことも、従業員の定着率を上げる方法のひとつです。
従業員が出した成果に対して適切な評価がされていないと、業務意欲の低下を招き、離職する原因につながります。適切な評価をおこなえるように、自社に合う評価制度を取り入れることが大切です。
人事評価制度には業績や能力による評価だけでなく、さまざまな評価手法があります。以下の記事では人事評価制度の基準や導入手順についてまとめているため、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】人事評価制度とは?人事評価制度の仕組みや運用方法を徹底解説
9-3. 従業員研修を充実させる
従業員研修を充実させることも、従業員の定着率を上げる方法です。従業員研修を充実させることで業務に役立つスキルを習得し、業務意欲の向上につながります。
また研修を通して従業員同士の交流を図れるとコミュニケーションが円滑になり、良好な人間関係を構築しやすいです。新入社員・中堅社員などの立場に応じて、適切な研修内容を実施しましょう。
たとえば新入社員の場合はOJTやメンター制度を活用し、先輩社員とコミュニケーションを図りながらスキルを身につけます。中堅社員の場合はOFF-JTを活用し、リーダーシップを身につける研修を取り入れるのがおすすめです。
9-4. ワークライフバランスを改善する
ワークライフバランスを改善することも定着率の向上につながります。やりがいのある仕事でも、残業や休日出勤が多すぎたり休暇を取得しにくかったりすると、プライベートの時間を充実させることができず、離職を考える従業員も出てくるでしょう。
ノー残業デーを設定する、上司が率先して有給休暇を取得するなど、ワークライフバランスを改善できる方法を検討することが大切です。
9-5. 採用時のミスマッチを防止する
定着率を高めるためには、採用時のミスマッチを防止することも重要です。新しい人材を採用したいからといってよい情報ばかりを伝えていると、入社前後のギャップが大きくなり、離職につながる可能性もあります。ミスマッチを防止するためにも、できる限り素直な情報を伝えるようにしましょう。
9-6. ハラスメント対策を徹底する
ハラスメント対策を徹底することも定着率の向上につながります。社内でパワハラやセクハラが横行していると、従業員が肉体的・精神的な苦痛を感じ、離職を考えてしまうでしょう。無意識にハラスメント行為をしているケースもあるため、研修をおこない、従業員の意識を高めることも必要です。
10. 定着率を高めて企業のブランド力を向上させよう!

今回は、定着率の意味や注目されている理由、定着率を高めるための対策などを紹介しました。定着率が低いことは、従業員がすぐに離職していることを意味するため、社内に何らかの問題が潜んでいるかもしれません。放置しておくと優秀な人材の流出が進んだり、企業のイメージが悪化したりする可能性もあるため、早急に対策を講じることが必要です。
定着率を高めるためには、評価プロセスや人事評価制度を見直すこと、ワークライフバランスを改善することなどを検討しましょう。ハラスメント対策を徹底して、働きやすい環境を整えることも重要です。まずは自社の定着率を算出して、適切な対策を検討していきましょう。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。