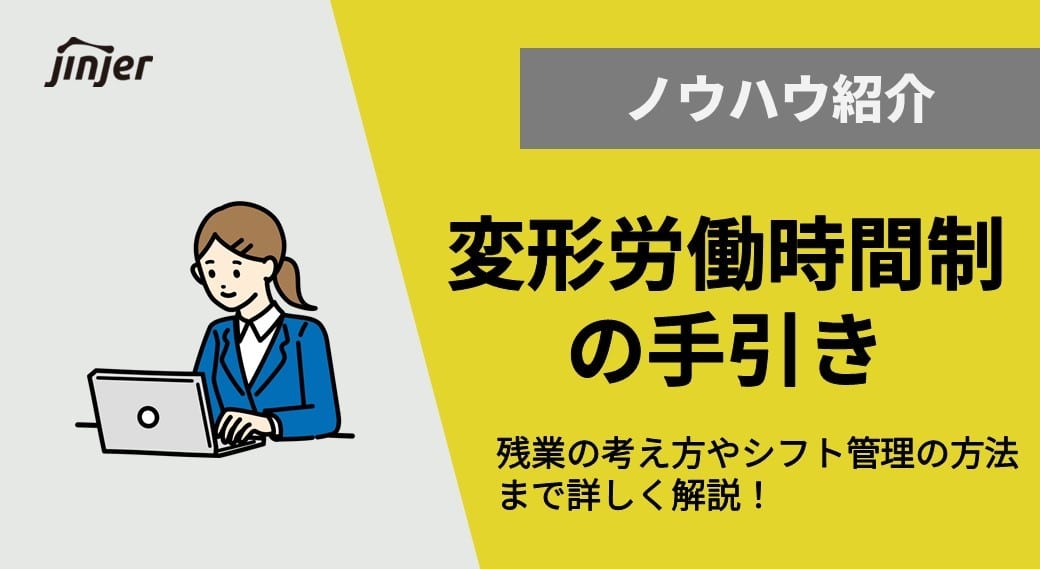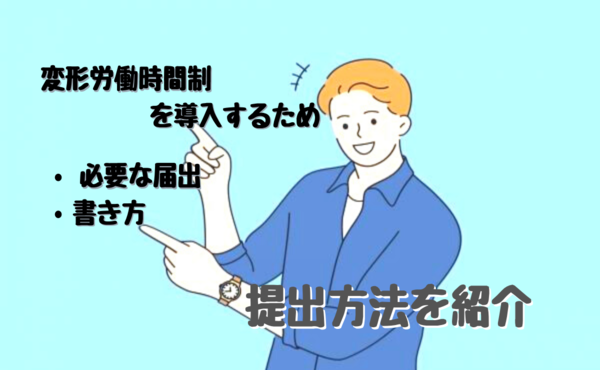 変形時間労働制の導入は、使用者の一存でできるものではありません。労使間の協議に加えて、労働基準監督署への届出が必要なケースがあります。
変形時間労働制の導入は、使用者の一存でできるものではありません。労使間の協議に加えて、労働基準監督署への届出が必要なケースがあります。
トラブルを防ぐためにも、必要な届出を理解しておきましょう。書類作成をスムーズにするための、書き方や提出方法をお話します。
関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制を採用事例で具体的に詳しく紹介
変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 変形労働時間制の導入には届出が必要
 まずは変形時間労働制の種類と、届出が必要なケースについて解説します。期間によって違いがありますので、ご注意ください。
まずは変形時間労働制の種類と、届出が必要なケースについて解説します。期間によって違いがありますので、ご注意ください。
1-1.届出が必要な変形時間労働制の種類
変形時間労働制には4つの種類があります。
- 1年単位の変形時間労働制
- 1ヶ月単位の変形時間労働制
- 1週間単位の変形時間労働制
- フレックスタイム制
このうち、届出が必須となのは「1年単位の変形時間労働制」「精算期間が1ヶ月以上のフレックスタイム制」です。
ただし、その他の変形時間労働制も、労働時間などを使用者が自由に決めてよいというわけではありません。労働者の代表者と協議したうえでの労使協定の作成や、就業規則によるルールの設定が必要です。
関連記事:1年単位の変形労働時間制についてメリット・デメリットを徹底解説
1-2. 変形労働時間制の届出義務を怠る労働基準法違反になる
労働基準監督署への届出が必要な変形時間労働制を導入しているにも関わらず、届出を怠ると労働基準法違反になります。
罰金30万円以下の罰則も定められており、違反が発覚した場合は、社会的な信頼を失うかもしれません。
知らなかった、うっかりしていた、では許されませんので、変形時間労働制を導入する際は届出のことをしっかりと覚えておきましょう。
2. 変形労働時間制の届出様式や必要なもの
 変形時間労働制の届出を行う際は、以下の書類が必要です。ここからは、1年単位の変形時間労働制を導入すると仮定して解説を行いますが、1ヶ月単位の変形時間労働制やフレックスタイム制の導入の場合も大きな違いはありません。
変形時間労働制の届出を行う際は、以下の書類が必要です。ここからは、1年単位の変形時間労働制を導入すると仮定して解説を行いますが、1ヶ月単位の変形時間労働制やフレックスタイム制の導入の場合も大きな違いはありません。
- 1年単位の変形時間労働制に関連する協定届
- 労使協定書
- 変形時間労働制期間中の労働日・労働時間が分かる勤務カレンダー
- 労働者代表の意見書を添付した就業規則(就業規則に変更がある場合のみ)
1年単位の変形時間労働制に関連する協定届は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーより入手可能です。その他の様式も準備されていますので、窓口に受け取りに行く手間を省けます。
変形時間労働制に関連する協定届以外の書類には、特に決まった形式はありません。協定の内容と、労働時間や日数が分かるものであれば大丈夫です。
いずれの書類も労働基準監督署への提出用と、会社控用が必要です。それぞれ2部ずつ用意しましょう。
3. 労働基準監督署長に変形労働時間制を届け出る方法
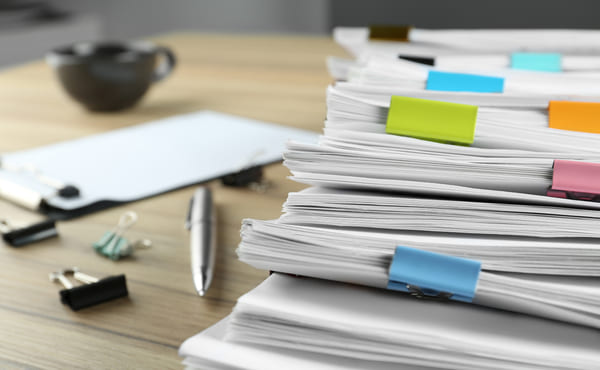 1年単位の変形時間労働制協定届の書き方と提出方法を解説します。その他の変形時間労働制の届出を行う際も手続きはほぼ変わりません。
1年単位の変形時間労働制協定届の書き方と提出方法を解説します。その他の変形時間労働制の届出を行う際も手続きはほぼ変わりません。
3-1. 1年単位の変形労働時間制に関する協定届の書き方
1年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入項目の中から、複雑な部分を抜粋して解説します。
|
事業の名称 |
複数の事業場がある場合は、会社名に加えて営業所や工場名など出先機関名まで記入します。 例:〇〇株式会社 〇〇営業所 |
|
労働者数 |
役員以外の人数を記載します。パートやアルバイトを含む非正規雇用の労働者も、雇用契約を結んでいる場合は人数に数えなくてはいけません。 |
|
対象期間及び特定期間 |
対象期間:1年(〇年〇月〇日) 特定期間:〇年〇月〇日~〇年〇月〇日 のようにに分けて記載します。 |
|
対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日 |
協定届の裏面を参考にして記載します。 |
|
協定の有効期間 |
〇年〇月〇日から1年間 のように記載します。 |
|
労働時間が最も長い日の労働時間数 |
1日の労働時間の限度である10時間以内で指定します。 |
|
労働時間が最も長い週の労働時間数 |
1週間の労働時間の限度である52時間以内で指定します。 |
|
労働時間が 48 時間を超える週の最長連続週数 |
連続週数の限度である3週間以内で指定します。 |
|
対象期間中の最も長い連続労働日数 |
連続労働日数の限度である6日以内で指定します。 |
|
対象期間中の労働時間が 48 時間を超える週数 |
起算日から3ヶ月毎に期間を区切り、その期間内で1周48時間を超える週の初日の数が3日以内でなければいけません。 |
|
特定期間中の最も長い連続労働日数 |
休日は最低でも1週間に1日必要であるため、連続労働日数は12日以内でなければいけません。 |
|
旧協定に関する内容 |
過去に変形時間労働制の労使協定を締結している場合は、その内容を記載します。 |
|
協定の成立年月日 |
有効期間の初日よりも前の日付に設立させる必要があります。 |
変形時間労働制の協定届は、法令で定められている時間や日数制限を守って作成しなければいけません。
また、枠外にも確認すべき項目があるので、チェックボックスや押印、署名など忘れずにおこないましょう。1箇所でも不備があると受理されません。
3-2. 届出先は管轄の労働基準監督署長
必要な書類を揃えたら、変形時間労働制を実施する事業場を管轄する労働基準監督署長へ届出をおこないます。窓口による提出のほか、郵送やe-Govによる電子申請も可能です。
近年は新型コロナウィルスの感染防止のため、郵送や電子申請が強く推奨されています。
また、変形時間労働制の導入によって残業・休日出勤などが生じる可能性がある場合は、別途36協定も必要です。
変形時間労働制を導入すると、ほとんどの場合残業や休日出勤が発生するため、36協定も同時に結びます。届出が終わっていない場合は、その他の労使協定も合わせて届出をおこなうとよいでしょう。
届出が終わっていない場合は、その他の労使協定も合わせて届出を行うとよいでしょう。このように、変形労働時間制を導入する際には導入前から届出を提出するまでおこなうべきことがいくつかあります。当サイトでは、変形労働時間制を導入するにあたって企業のご担当者が対応すべきことをまとめた資料を無料で配布しております。導入を検討中のご担当者様はこちらからダウンロードしてご活用ください。
4. 変形労働時間制の届出をする際の注意点
 変形時間労働制の届出は難しいものではありません。しかし、以下の点には注意しておきましょう。
変形時間労働制の届出は難しいものではありません。しかし、以下の点には注意しておきましょう。
4-1. 就業規則による規定が必要
変形時間労働制の届出を行う場合でも、就業規則による規定は必要です。途中から変形時間労働制を導入する場合は、就業規則の変更も必要になりますので、労使間で協議をしっかりと重ねたうえで取り決め、改めて周知を行うようにしましょう。
なお、就業規則には以下のような内容を規定する必要があります。
- 対象となる期間
- 対象となる労働者の範囲
- 変形期間の起算日
- 変形期間を平均した際、労働時間が法定労働時間を超えないことの定め
- 変形期間中の各日および各週の労働時間
- 各労働日の始業・終業時刻
4-2. 従業員数が10人未満なら届出不要だが、種類によっては要提出!
就業規則の届出は、労働者数が10人未満の事業場では必要ありません。しかし、1年単位の変形時間労働制を導入する場合は、たとえ従業員数が10人未満でも届出が必要です。誤解しやすい部分ですので注意しましょう。
4-3. 労使協定の締結が必要
変形労働時間制を1年単位で導入する場合は、労使協定の締結も必要です。労使協定で定める項目は以下のようになります。
- 対象の労働者
- 変形の対象期間
- 変形期間の起算日
- 特定期間
- 変形期間中の各日および各週の労働時間
- 労使協定の有効期限
1カ月単位の変更労働時間制を採用する企業の中には、就業規則の代わりに労使協定に必要事項を記入して締結することもあります。しかし、労使協定だけでは、変形労働時間制で働くことを従業員に義務づけることはできません。
会社のルールに従って労働してもらうためには、就業規則に規定を記載して従業員に周知する必要があります。
変形労働時間制を1年単位で導入する場合は、労使協定の締結も必要です。労使協定で定める項目は以下のようになります。
- 対象の労働者
- 変形の対象期間
- 変形期間の起算日
- 特定期間
- 変形期間中の各日および各週の労働時間
- 労使協定の有効期限
1カ月単位の変更労働時間制を採用する企業の中には、就業規則の代わりに労使協定に必要事項を記入して締結することもあります。しかし、労使協定だけでは、変形労働時間制で働くことを従業員に義務づけることはできません。
会社のルールに従って労働してもらうためには、就業規則に規定を記載して従業員に周知する必要があります。
4-4. 1カ月単位の変形労働時間制の届出方法
1カ月単位の変形労働時間制の届出に必要なものは以下の通りです。
- 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労使協定もしくは就業規則
- 対象期間中の労働日・労働時間がわかる勤務スケジュール表
1カ月単位の変形労働時間制は、1年単位の変形労働時間制とは違い労使協定を締結する必要がありません。そのため、届出に必要なものの1つである労使協定は就業規則でも代用可能です。
なお、就業規則に勤務スケジュールの記載をした場合は、従業員の労働日・労働期間がわかるスケジュールの提出も必要になります。
1カ月単位の変形労働時間制の届出に必要なものは以下の通りです。
- 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労使協定もしくは就業規則
- 対象期間中の労働日・労働時間がわかる勤務スケジュール表
1カ月単位の変形労働時間制は、1年単位の変形労働時間制とは違い労使協定を締結する必要がありません。そのため、届出に必要なものの1つである労使協定は就業規則でも代用可能です。
なお、就業規則に勤務スケジュールの記載をした場合は、従業員の労働日・労働期間がわかるスケジュールの提出も必要になります。
4-5. 毎年届出をする必要がある
変形時間労働制の届出は、1年ごとに届出をする必要があります。労働時間や就業規則に変更がない場合でも、変形時間労働制を継続する限り必要ですので、忘れないようにしましょう。
変形時間労働制と一緒に締結することが一般的な36協定も、毎年届出が必要です。どちらも届出を忘れると法定時間外の労働が違法になってしまうため、あらかじめ手続きの日程を定めておくとよいでしょう。
5. 1年単位の変形時間労働制を導入する場合は届出が必要
 1年単位の変形時間労働制を導入する際は、どのような企業であっても必ず届出が必要です。また、1カ月単位制を導入する場合は、1年単位制と届出方法がやや異なるので注意しましょう。
1年単位の変形時間労働制を導入する際は、どのような企業であっても必ず届出が必要です。また、1カ月単位制を導入する場合は、1年単位制と届出方法がやや異なるので注意しましょう。
勤務カレンダーや協定書の作成は不慣れだと非常に時間がかかってしまうため、管理システムや外部委託で勤怠管理をしておくのがおすすめです。
書類作成は人がおこなう必要がありますが、記載する情報がデータ化されていれば、事務作業にかかる手間を大幅に削減できます。
変形労働時間制を導入する場合は、届出などにかかる手間も考慮して管理方法の見直しもおこないましょう。
変形労働時間制は通常の労働形態と異なる部分が多く、労働時間・残業の考え方やシフト管理の方法など、複雑で理解が難しいとお悩みではありませんか?
そのような方に向け、当サイトでは変形労働時間制の基本やシフト管理についてわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
「変形労働時間制を正確に理解したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。