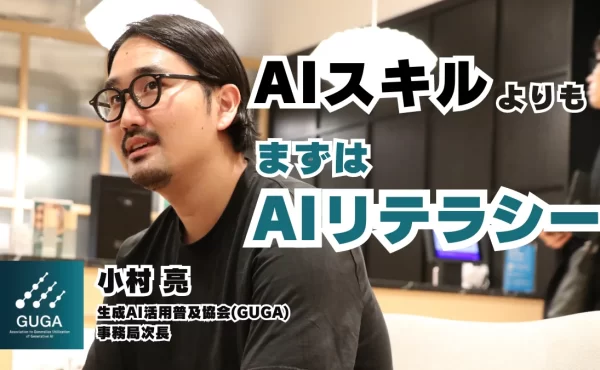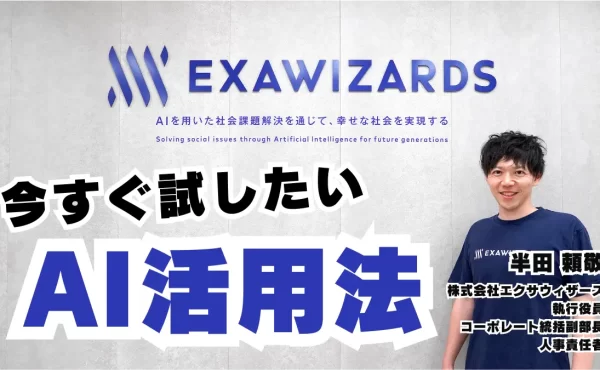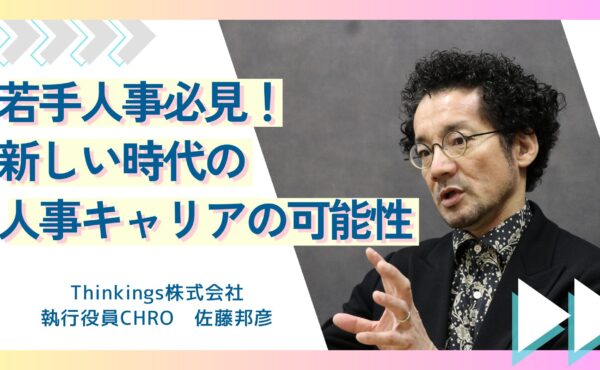今回は東南アジア最大のオンラインゲームカンパニーGarena(SeaGroup)に「成長し続けるための組織づくり」について取材。いまやゲーム好きでは知らない人はいないほどの有名企業Garenaですが、ビジネスの裏側について語られることは多くありません。
GarenaはSeaグループに所属しており、Seaグループは他にもタイで有名なオンラインショッピングShopeeや決済サービスAir payなどの事業を展開しています。
HRNOTE.asia編集部はGarena Thailand人事部部長のTopさんにお話を伺いました。

Ratthawut Suwanila | People Manager at Garena Thailand
【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』
 「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。
「スタートアップ精神」を維持し続ける

Q. 企業が成長するために意識しているマネジメントについて教えてください。
Topさん:私たちがマネジメントについて重視しているポイントは2つあり、1つめは、スタートアップ精神です。Garenaは成長し企業規模も大きくなりましたが、今でも私たちの根底にあるものはスタートアップ精神だと思っています。
現在のような規模に成長する前は、私たちもスタートアップと呼ばれるような会社規模でした。しかし企業の規模が変わっても、この精神を忘れなかったからこそ成長が維持できており、企業がどんな状態になってもスタートアップ精神は忘れてはいけないと思っています。
Q. Garenaにとってスタートアップ精神とは何でしょうか。
Topさん:従業員がオーナーシップを持ち、常に新しいものごとに挑戦することです。
このスタートアップ精神を維持するためには適切な企業文化の醸成や社内制度が必要だと思います。そこで私たちはスタートアップと大企業の特徴をそれぞれ組み合わせた組織づくりを意識しています。
まずスタートアップの特徴の一つでもある、「オーナーシップを与えること」を意識しているので、従業員は手を上げればすぐに新しい仕事に取り組むことができますし、もちろん失敗してもカバーできる組織体制を構築していいます。
組織全体としても仕事を早く進めることができますが、企業規模が大きくなった今では、誰もが好きな仕事をできるというわけではありません。
そこで我々は「centralization(集中)」と「decentralization(分散)」を意識した組織を作っています。
「centralization」では、事業をすすめる上で私たちは何を実現したいのか、集中するべきことを明確にします。私たちが実現したいことを明確にし、方向性や目標を決めれば、ぶれることなく決めた道に対して進むことができます。
2つ目の「decentralization」では、組織内の権限が一箇所に集中しないように従業員に裁量を与え、権限を分散しています。
例えば東南アジア最大のeSportsイベント『Garena Worldプロジェクト』では、経営陣側で達成すべき目標数値や方向性などを設定します。これは先ほど話した「centralization」にあたります。
目標数値や方向性を設定した後は、実際に業務を遂行する従業員に共有し、彼らが責任をもって企画から実行までをおこなっていただきます。これが「decentralization(分散)」ですね。
先ほど決めた方向性を共有し開発チームにまかせると、彼らは自発的に計画をたて、業務を分類し、他メンバーのアサインなど、目標達成するためにかなりの熱意をもって取り組んでくれます。
Garena Worldのような大規模プロジェクトであれば、一般的にリスク回避のため全プロセスを経営陣やマネジメント側だけで考えていますが、私たちはクリエイティビティを常に必要とする会社です。経営陣が求めている大枠のビジョンや目標、方向性だけを伝え、ミッションを与えられた彼らは何をすべきか自ら考え、自走して動いてもらいます。これがマネジメントで重視している1つ目のポイントですね。

Q.従業員のマネジメントで2つ目に大切にしていることはなんでしょうか。
Topさん:2つめは、私たちは以下のようなコアバリューを大切にしています。
-「we serve」ホスピタリティをもつこと
-「we run」速く物事を進めること
-「we adapt」変化に適応すること
-「we commit」責任を持つこと
-「we stay humble」いつも謙虚であること
私たちは全従業員が素晴らしい才能を持っている一方で、完璧な人などいないという考えを持っているので、私たちはお互いから学び成長することを重視しています。
また従業員に対して積極的に投資することも意識しており、単に従業員の教育だけでなく職場の環境を整備することも一つの投資になりますし、それらが従業員を大切にすることに繋がります。
従業員にオーナーシップを与えながらも、働きやすい環境を整え、高い成果を出せる組織作りを意識していますね。
スタートアップ精神を重視するからこそ、失敗には寛容

Q.オーナーシップを与えることで成功した事例はありますか?
Topさん:基本的に成功した事例の方が多いですが、うまくいかなかった事例もありますので、今回はそちらの話をしますね。
以前、Seagroupではフードデリバリーサービス「ナウデリバリー」を展開していました。
2017年12月、担当者3名によってプロジェクトが始まり、第1四半期には人員が200人に増員していました。
すぐにでも事業拡大、マーケットシェアを獲得したいと考えており、目標達成するためにどのような人材を採用するかを考えていました。
一時ナウデリバリーはGrabfoodやLINE MANと並んでトップ3のフードデリバリーサービスでしたが、あらゆる施策などを試しているうちに市場はレッドオーシャンになってきたんです。
事業に多額の投資をしましたが、なかなか目標に到達できないという状態が続き、結果的に、Seaグループはフードデリバリーから撤退することになりました。
企業側が撤退の決断をしたとはいえ、その事業で従事してくれた従業員をそのままにしておくわけにはいかないですよね。引き続き他の事業で働きたいという意志があれば他の部署への異動を提案しました。
彼らが目指す方向性にマッチしていなければ異動は実現できないので、もちろん一度面談を組みますが、最終的には多くの従業員が社内に残ってくれました。
その後、彼らからはフードデリバリー事業での失敗や経験を次の仕事で活かしており、挑戦があるからこそ失敗も経験しますが、それだけ従業員は成長すると考えています。
また挑戦する企業文化を作るためには、同時に従業員のフォロー体制を整えることも重要だと思っています。
Q.従業員と良い関係を構築する方法はありますか?
Topさん:私たちの会社では若い世代の社員が多いのですが、まずは彼らが何を求めているのかを知る必要があります。
いまの若い世代はお金をモチベーションに働かなくなった世代だと思っています。お金よりも経験を求めている傾向にあるので、彼らに自分の力で試す機会を意識的に与えています。
それと同時に成功した際は、周りにいる社員が彼らの努力を称賛し、自分の功績が認識されている実感を生むような環境づくりを意識しています。
しかし、ここで伝えたいのはただ注目される存在にしたいというわけではなく、努力し認められたときに称賛する文化を作りたいといった思いが強く、従業員が大事にされている実感を生み出すことが重要だと思っています。
Q.称賛文化も成果を出す上で重要になりますね。
他に環境づくりで意識していることはありますか?
Topさん:職場環境を整備することも重要視しています。例えば職場では従業員のためにフリーランチやお菓子などを用意します。
それは会社が働くためだけの空間ではなく、それ以上に価値のある空間だと私たちは考えているからです。
従業員はオフィスで膨大な時間を過ごすわけですから、職場の雰囲気は常に快適でなければなりません。
彼らが仕事から疲れた際にはお菓子を用意するなどして従業員がリラックスできる快適な環境づくりを意識しています。
また、従業員たちからあがってくる意見も常に尊重しています。もちろん従業員の意見だけで全て判断するわけではなく、企業活動に支障が生まれないかといった観点からも考え、実際にやるべきか判断します。
ほかにも予算の兼ね合いなどもありますが、我々が一方的に会社の規則を決め、それを従業員に押し付けることはベストではないと思っています。
採用で重視する「従業員と企業文化のフィット感」

Q.採用する際はどのような点を意識していますか?
Topさん:二つ重視していることがあります。一つ目は当たり前ですがスキルや専門性です。
まずは任せられる仕事の責任を果たせるかどうかが重要になります。一方で私たちは求職者が過去に取得した資格などはあまり気にしていません。また仕事とは関連しない学歴だとしても、成果を出す人材であれば採用することもあります。
2つ目はカルチャーフィットです。もし、企業と相性が合わない人を無理矢理採用したところで、長期的に見てお互いが幸せではなくなります。先ほども触れた5つの「core value」に共感できる方を採用するようにしています。
Q.「ゲーム好き」は採用において重視していますか。
Topさん:確かに面接では「普段ゲームで遊びますか」と聞くようにしていますね。
「はい」と面接で答えた方の中にはeSportイベントのリーダーを担当している人もいます。
彼が入社する前は、シューティングゲームの国内チャンピオンでしたが、彼はゲームへのパッションがあると同時に仕事もできる人材でした。
一方で「ゲームをしない」と答える方も少なくありません。ただ同時にゲーム業界のビジネスに興味がある理由を面接で答える方も多く、そういう点もチェックしていますし、他にも企業文化にフィットしているかどうかが重要であると思っています。
Garenaでは「ゲーム好きかどうか」、Shopeeでは「オンラインショッグに興味があるかどうか」といった質問を求職者によく投げかけますが、「好きではない」「興味がない」といった返答次第で不採用にすることはありません。
多くの企業の人事担当者は、自社サービスに関連する領域に興味がない求職者がいた場合、「自社にあわないのでは」と思うかもしれません。そこで判断せず、違う観点から求職者の方について理解し、自社の企業文化にマッチしているかを見極めることも重要だと思いますね。
Q.なかには「好きなゲームの開発チームで働きたい」という方もいますよね?
Topさん:そうですね。もし偶然にも彼らが夢中になっているゲームを、自分の仕事にすることができれば幸運ですよね。そうなると毎日仕事にコミットできるかもしれませんが、 好きなことを仕事にする際に注意する必要があります。
例えば、自分が気に入っているゲームに夢中になりすぎる一方で、柔軟性がないと仕事に影響が生まれます。確かに一つのゲームに集中することで成長する部分もあると思いますが、ゲーム業界ではプロダクトのライフサイクルが短いといった特徴があります。
開発したゲームの中でも短期で終わるプロジェクトがあるので、常に新しいゲームにも挑戦するように従業員には求めています。
Q.多くの領域での経験を通して成長を促しているんですね。
Topさん : 我々は「担当しているゲームの運営が終わる=その会社での仕事も終わる」と捉えてほしくないですね。
中にはそういう考えを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
せっかくの成長機会を逃してしまうことにもなるので、あらゆるゲームを通して多様なスキルを身に着けてほしいと彼らに伝えます。ただ、新しい領域のゲーム開発を担当するか否かは最終的には彼ら次第ですが。
個人的な意見としては、新しい領域にも興味を持たなければ行けないと思っています。
入社した際に担当しているゲームに興味を持つことも重要ですが、長い目でキャリアを考えた際に、1つのゲームに集中するだけでなく他の領域にも興味が持てるようにマインドを変えていく必要がありますね。

Q.ゲーム企業である一方「グローバル」というイメージもあるGarenaですが、
外国人従業員は採用していますか?
Topさん : タイ国内ではタイ人スタッフ中心に採用しています。私たちはローカライゼーション(Localization)を重視しており、現地のスタッフが一番自分の国・文化、人を知っていると考えているからです。
この考え方の徹底がアジアにおけるSea Groupの成功要因の一つともいえます。同じ地域であっても、各国の文化はかなり違います。
例えばタイとベトナムはよく周りの人から「似ている」と言われますが、文化面や習慣など取ってみると、似ていないこともあります。またシンガポールとマレーシアの場合でも、隣同士の国ですが完璧に同じであるとはいえません。
グローバル企業として各国で成功するならば、現地の方を採用することが成功の近道だと思います。
一方で、人材育成の観点で国際的な働き方も推奨しています。例えばシンガポールにある本社では、中国の開発者と連携しなければいけません。なので従業員には一度中国で働いてみてはどうかと奨めることもあります。
しかし基本的には、現地のスタッフの採用し、協力しながら事業を進める姿勢は変わりませんね。
Q.タイ企業がグローバルで活躍するためには何が必要でしょうか?
Topさん : タイ人のポテンシャルで見ると、アジアだけでなく他国と比べても負けないと思っています。特に若い世代などテクノロジーに慣れ親しんだ世代を見ると、タイ人は物事を早く考える傾向にあると思っています。
また最近ではタイ人の中でもスタートアップを立ち上げたいと考える人は年々増えています。しかしユニコーンのような企業が生まれない理由としては、タイのスタートアップは、最初からタイ国内のマーケットだけを見ている点にあると思います。
近隣の国、例えばインドネシアではユニコーンがいくつか生まれていますよね。その理由としては、スタートアップを立ち上げた時から常にグローバルを視野に入れているからだと思います。
他の地域にあったマーケティングや事業プランを立ち上げ当初から考えている点のおいては、国内マーケットに限定して戦略を練る場合と比べて、生まれる結果が大きく違ってくるのではないでしょうか。

タイのスタートアップでは、タイ国内でできることだけを考え、ほかをあまり深く考えずに始める傾向にあります。タイ国内だけにフォーカスを当てていれば問題ないのですが、仮に海外へ展開するとなると事業プランを作り直す必要なども生まれますよね。
世界を見据えたときに計画は変わりますし、直面する問題も変わってくるので簡単なことではありません。解決策も違います。ただ同時にビジネスが成長する規模感も変わってくるでしょう。
タイはかなり快適な国ですよね。自然災害もなく快適に住むことができます。タイに住む方も親切な人は多いですからね。
ただ、その環境が時にコンフォートゾーンから離れられないことにもつながっているかもしれませんし、それが海外へ展開することを阻害しているかもしれません。なので個人的にはもう少し外へ出て知識・経験を得るという行動を取ったほうがいいと思います。
近い未来にグローバルにおいて他国の国に負けないためには、国内だけでなく、いかにグローバルな視点で物事を見ることができるかが重要ではないかと思います。
私も人事としてグローバルに活躍できる人材が生まれるよう日々尽力していきたいと思います。

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』
 「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。