 会社にとって、従業員がどれだけ自社に愛着を持っているか、業務に対してモチベーションを維持しているかは重要な要素です。これらが低いと従業員の離職率が高まり、生産性が低下してしまう恐れがあります。
会社にとって、従業員がどれだけ自社に愛着を持っているか、業務に対してモチベーションを維持しているかは重要な要素です。これらが低いと従業員の離職率が高まり、生産性が低下してしまう恐れがあります。
上記のような問題を解決するために役立つのが組織サーベイです。今回は、従業員の離職率低下や生産性向上などの効果が期待できる組織サーベイについて解説します。
目次
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 組織サーベイとは?

まずは、組織サーベイの概要について確認しておきましょう。
1-1. 組織サーベイとは「組織の見えない部分」を調査すること
組織サーベイとは、会社のような「組織」の状態を測ることを意味します。具体的には、従業員の会社に対する愛着やモチベーションの調査です。
組織サーベイを実施する目的は、組織の状況を可視化して課題を解消することです。組織には、「見える(見えやすい)部分」と「見えない(見えにくい)部分」の2つの側面があるとされています。組織サーベイは、この見えない部分の現状を確認するためにおこなう調査です。
1-2. 組織サーベイが注目されている理由
日本は少子高齢化が進み、働き手の減少が予想されます。内閣府の『令和6年版高齢社会白書』のなかで、日本の生産年齢人口(15~64歳)は、2030年には7,076万人、2070年には4,535万人まで減少すると発表されました。[注1]
生産年齢人口のピークであった1995年の約8,700万人と比較すると、大きく減少してしまうことがわかります。[注2]
さらに働き方が多様化していることで、定年まで特定の企業に属すというケースへ減少傾向にあります。このように、働き手が不足し、働き方が多様化する時代においては、組織サーベイを活用することで組織の状況を定期的に確認してマネジメントすることが求められているのです。
[注1]令和6年版高齢社会白書|内閣府
[注2]平成29年度(2017年度)の中小企業の動向|中小企業庁
1-3. サーベイとリサーチの違い
サーベイもリサーチも「調査」という意味をもっていますが、使われる場面が若干異なります。リサーチは、研究やマーケティングなどの分野で用いられるのが一般的です。
論文や文献、数値データなどをもとに、対象となる物事について具体的に把握しようする行為がリサーチといえるでしょう。一方のサーベイは、物事や組織の状態を幅広く把握しようとする行為といえます。
2. 組織サーベイを実施するメリット

組織サーベイを実施することで得られるメリットとして、従業員の離職防止や生産性の向上が挙げられます。ここでは、組織サーベイのメリットについて詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
2-1. 見えにくい課題を発見できる
見えにくい課題を発見できることは、組織サーベイを実施する大きなメリットです。社内の設備が整っていないなど、物理的な課題を把握することは比較的簡単ですが、従業員が感じている不満などは、目に見えにくいため簡単には発見できません。従業員サーベイを通して見えにくい課題を発見できれば、すぐに解決策を立案し、状況を改善することができます。
2-2. 従業員の離職を防止できる
組織サーベイによって従業員の会社に対する愛着、モチベーションを可視化することで、従業員の離職の防止につながります。組織サーベイで従業員がなぜ離職を検討しているかを把握できるため、その問題と課題を解消できます。
2-3. 従業員の生産性を向上できる
組織サーベイは、従業員の生産性向上にもつながります。組織サーベイによって従業員のモチベーションが低下している原因が判明すれば、解決策を講じることでモチベーションの向上が期待できます。解決策によって従業員のモチベーションが向上することで、生産性の向上にもつながるでしょう。
3. 組織サーベイを実施するデメリット
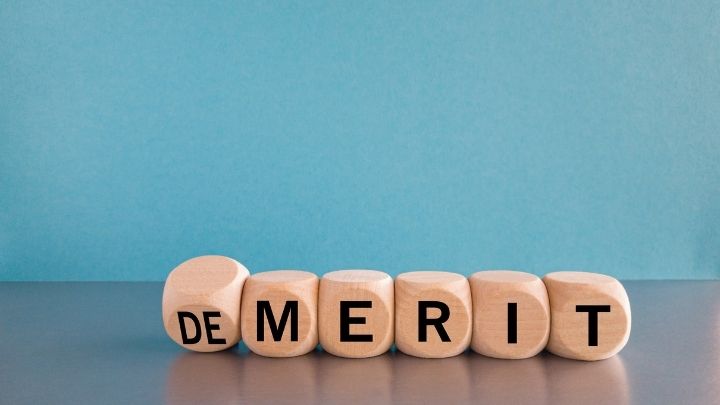
さまざまなメリットが存在する一方で、以下のようなデメリットもあります。
3-1. 組織サーベイの実施が従業員の負担になってしまう
組織サーベイを実施するためには、従業員はいくつかの質問に回答する必要があります。従業員は普段の業務の合間をぬって回答するため、サーベイ実施を負担に感じてしまうかもしれません。
また、組織サーベイのための質問回答によって業務に遅れが出てしまう可能性も考えられます。遅れが出てしまった業務を取り戻すために、時間外労働が発生してしまう可能性もあるでしょう。そのため、組織サーベイを実施するタイミングは繁忙期を避けるなど、従業員への配慮も忘れてはいけません。
3-2. コストがかかる
ある程度のコストがかかることも組織サーベイのデメリットです。調査を外部に委託したり、システムを活用したりする場合は、外注費やシステム利用料などが発生します。
社内で実施する場合は担当者の業務が増えてしまうため、残業代が発生するケースもあるでしょう。組織サーベイを実施するときは、予算内に収まるか事前に検討しておくことが大切です。
4. 組織サーベイの種類

組織サーベイには2つの代表的な種類があります。
| 種類 | 概要や特徴 |
| 従業員満足度調査(ES調査) |
|
| エンゲージメントサーベイ |
|
以前の組織サーベイは、従業員満足度調査が主流でした。しかし、最近はエンゲージメントサーベイに移行しつつあります。組織への貢献度を重視する企業が増え、その調査に対応できるのがエンゲージメントサーベイだからです。
これから組織サーベイを取り入れる場合は、エンゲージメントサーベイを検討するとよいでしょう。
5. 組織サーベイの実施手順

組織サーベイを実施する手順は次の通りです。
- 会社や従業員が抱えている課題が何かを分析する
- 質問内容を設定する
- サーベイの手法やツールを検討する
- 結果を分析する
- 改善策を立案する
各手順を押さえたうえで、組織サーベイを実施しましょう。
5-1. 会社や従業員が抱えている課題が何かを分析する
組織サーベイを実施するためには、まず会社や従業員がどのような課題を抱えていて、何が原因なのかを分析しなくてはなりません。たとえば、退職者が増加しているという課題があるとした場合、その原因は職場でのコミュニケーション不足といったように分析します。この課題と分析結果を基に質問項目を設定していきます。
5-2. 質問内容を設定する
課題や分析結果を基に質問を設定します。質問を設定する際は、課題、分析結果を基に、調査となる対象、調査の頻度、質問の量などを調整しましょう。
なお、具体的な質問項目は後ほど解説します。
5-3. サーベイの手法やツールを検討する
そして最後に、サーベイを短いスパンで繰り返し実施するパルスサーベイにするか、適したツールはあるかなどを検討します。パルスサーベイは少ないタイムラグで従業員の状況を把握できる一方、実施頻度が高いため、従業員の負担軽減を考慮する必要があります。
また、組織サーベイの実施方法は、以下のいずれかから選択しましょう。
| 種類 | 概要や注意点 |
| オープンアンケート |
|
| クローズドアンケート |
|
5-4. 結果を分析する
組織サーベイを実施したら、結果を集計して分析することが大切です。全体の平均値を算出したり、回答の分布を確認したりして、従業員が考えていることや解決すべき課題を把握しましょう。結果をしっかりと分析することで、適切な改善策の立案につながります。
5-5. 改善策を立案する
組織サーベイを実施するだけでは意味がありません。分析結果をもとにして改善策を立案しましょう。従業員が不満を感じている部分については、とくに制度や仕組みの見直しが必要です。放置しておくとモチベーションが低下し、離職する従業員が増える可能性もあるため、早めに対策しましょう。
また、正しい方法で組織サーベイを実施しても、その後どのように分析をして、どのように改善につなげれば良いのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「従業員満足度のハンドブック」という資料を無料配布しています。調査後の分析やその後の改善の施策についても解説しており、サーベイ後の運用をトラブルなく進められる参考資料としてご活用いただけます。 興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
6. 組織サーベイで適切な質問項目を設定するには
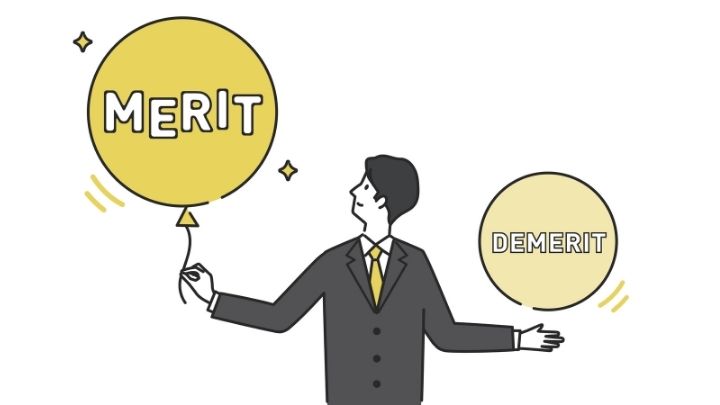
組織サーベイを実施するにあたって、最も重要なポイントは質問項目の設定です。会社にとって本当に必要な情報を引き出すために、的を得た質問を設定するよう心がけましょう。
なお、参考として、組織サーベイを実施する目的別に最適な質問項目の概要を以下の表で紹介します。
| カテゴリ | 項目 | 概要 |
| 進化し続ける組織 | 組織活性 | ビジョンの共有度、関係性の質、相互成長できる支援の有無 |
| 新たな価値の創造 |
パフォーマンス、改善行動、創造性の発揮度 |
|
| 社会への貢献度実感 |
コンプライアンスの遵守、会社。顧客への貢献実感 |
|
| 学び続ける人材 | 成長したい意欲 | 成長への意欲、主体性、モチベーション |
| 成長している実感 | キャリア構築実感、成長実感、能力活用実感 | |
| 満足度・やりがい | 就業満足度、就業継続意向、ワーク・エンゲージメント | |
| 働き続けられる職場 | 仕事の効率性 | 残業体質、業務効率実感 |
| 働きやすさ |
多様性許容度、評価や昇給・昇進の公平性、心理的安全性 |
|
| ストレス度 | ストレス度 |
組織サーベイの質問項目は、より具体的に設定することが大切です。なぜなら、サーベイは設問として聞いたことしかわからないためです。
また、結果を分析し改善策を講じるために、原因となる要素が探せるよう網羅性を意識しましょう。
このように、組織サーベイにおいて質問項目の設定はとても重要です。一から質問を検討・設定するのは困難であり、的外れな質問になってしまえば実施しても効果を得られません。
組織サーベイを実施する場合は、あわせてツールの導入も検討するとよいでしょう。
7. 組織サーベイを実施するときのポイント

組織サーベイを実施するときは、従業員、経営陣それぞれの理解を得ておきます。また、特定の部署で成功例を作ってから全体の改革に臨むのがおすすめです。組織サーベイで集めた従業員の回答は分析して、施策に活かすようにしましょう。
7-1. 従業員の理解を得てから実施する
組織サーベイを実施する際は、従業員の了承を得ておきましょう。先述の通り、組織サーベイの実施は従業員の負担になってしまう可能性があります。また、回答内容がどのように使われるかを従業員に伝えないと、不信感を抱かれてしまうかもしれません。
そのため、組織サーベイを実施する際は事前に従業員の理解を得ておきましょう。
7-2. 経営陣の理解を得ておく
組織サーベイによって社内の問題点や課題を解決するためには、経営陣の協力が欠かせません。そのため、組織サーベイを実施するうえでは経営陣の理解も得ることが大切です。経営陣の理解を得るためには、組織サーベイの成功事例などを提示するとよいでしょう。
7-3. 特定の部署で成功例を作る
まずは組織サーベイによって、特定の部署の成功例を作っておきましょう。いきなり組織サーベイで会社全体を改善するのではなく、特定の部署で成功例を作ることで、他の部署でも積極的に改善に取り組めるでしょう。
7-4. 適切な頻度で実施する
組織サーベイは1回で終わらせず、適切な頻度で繰り返し実施する必要があります。何度か実施することで、対策の効果や従業員の変化を把握できるからです。組織サーベイの目的によっても異なりますが、1週間に1回、1カ月に1回など、適切なタイミングで実施しましょう。
7-5. 改善策を講じる
組織サーベイで集めた従業員の回答を基に改善策を講じるようにしましょう。ただ従業員に回答してもらうだけでは、負担を背負わせてしまうだけで何も改善がされません。そのため、組織サーベイで得た情報を基に、会社が抱えている問題点の改善策を講じるようにしましょう。
7-6. 結果を開示する
組織サーベイを実施した場合は、その結果を従業員に周知しましょう。その際、調査に協力してくれたことに対するお礼の文面も含めることが大切です。
また、開示する情報はそれほど詳細なものでなくて構いません。組織サーベイの結果は部署・個人の優劣をつけるためのものではないため、現時点における情報を大まかに伝えれば問題ないでしょう。
8. 【厳選7社】組織サーベイツールの比較

組織サーベイを自社で一からおこなうことは大きな負担となります。そこで活用したいのが組織サーベイツールです。
ここでは、組織サーベイに活用すべきツールを7社厳選して紹介します。
8-1. 組織サーベイツールとは?
組織サーベイツールとは、社内でおこなう調査を効率化できるシステムです。質問項目を作成して配信することで、従業員はシステム上で回答できます。紙のアンケート用紙を印刷したり配布したりする手間を省けるため、調査を効率よく実施できるでしょう。
8-2. 【比較表】組織サーベイツールの特徴と料金
組織サーベイツールは、その特徴から以下の4つに分類されます。
- 定点観測をしながら組織の課題を解決できるタイプ
- 人事施策を含めて組織改善を図るタイプ
- 離職防止に着目したタイプ
- メンタル面を解決できるタイプ
それぞれのタイプ別に、おすすめのツールを紹介します。
8-2-1. 定点観測をしながら組織の課題を解決できるタイプ
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|
ラフールサーベイ (株式会社ラフール) |
|
月額400円/1人 |
|
webox (株式会社アトラエ) |
|
月額300円/1人 |
8-2-2. 人事施策を含めて組織改善を図るタイプ
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|
カオナビ (株式会社カオナビ) |
|
要問い合わせ |
|
ミイダス (株式会社ミイダス) |
|
要問い合わせ |
8-2-3. 離職防止に着目したタイプ
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|
PULSE AI (株式会社ジャンプスタートパートナーズ) |
|
月額200円/1人 |
|
ハタラクカテ (株式会社OKAN) |
|
月額167円/1人 |
8-2-4. メンタル面を解決できるタイプ
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|
ジンジャー人事労務(サーベイ) (jinjer株式会社) |
|
月額500円/1人 |
9. 組織サーベイツールを選ぶ際のポイント

組織サーベイツールを選ぶときは、以下のようなポイントに注意しましょう。
9-1. コスト
組織サーベイツールを選ぶときは、コストを比較しておきましょう。ツールを導入すると、初期費用や月額費用が発生します。組織サーベイは繰り返しおこなうのが一般的であるため、コストも長期的に発生します。高額なツールを導入すると長期的に利用できなくなるケースもあるため、予算に合っているか確認しておきましょう。
9-2. 使いやすさ
使いやすさも重要なチェックポイントです。質問を作成する担当者だけではなく、質問に回答する従業員にとっても使いやすいツールを選ぶとよいでしょう。簡単に質問を作成できるか、回答の手間はかからないかなど、さまざまな視点からチェックすることが大切です。
9-3. 希望する診断が可能か
多くのツールは調査項目のテンプレートを搭載しています。しかし、その範囲や度合いはツールによって異なるため、分析が必要な項目を調査できるテンプレートが備わっているか確認しましょう。なかには、オリジナルの調査項目を持つツールなどもあるため、比較して見極めることが大切です。
なお、「ジンジャー人事労務(サーベイ)」のように、自由にコメントできる機能を備えたタイプなら、より従業員のリアルな声を聞くことができ、問題の把握・改善に大いに役立つでしょう。
9-4. 分析機能の質
アンケート結果を集約したものの、その後の分析が思うように進まないケースも珍しくありません。このような場合に備え、分析機能の質が高いツールを選ぶことが大切です。
業界平均値と比べた自社のコンディション状態の善し悪しや、離職を考えていそうな従業員がいるかなどを可視化できるツールもあります。
まずは、自社が組織サーベイツールで調査したい内容を明確にし、それに対応する分析機能を持つツールを選ぶとよいでしょう。
9-5. 改善策の提案の有無
調査結果をもとに課題が明らかになっても、具体的な改善策を見い出せないケースもあります。そこで活用すべきは、組織改善に向けたアクションまで支援してくれるツールです。
課題を見つけたら終わりではなく、組織の改善までサポートしてくれるツールを選べば、スムーズな改善につながるでしょう。
10. 組織サーベイを実施して従業員の離職率低下や生産性向上につなげよう

今回は、組織サーベイの意味や実施するときのポイントを解説しました。組織サーベイは、従業員の会社に対する愛着やモチベーションを数値化する調査です。組織サーベイを実施することで、従業員の離職率低下や生産性の向上が期待できます。組織サーベイを実施するうえでは、従業員や経営陣の理解を得ておくことが大切です。
組織サーベイはポイントを押さえて実施し、従業員の離職率低下や生産性向上につなげましょう。また、ツールを活用し、効率的かつ正確性の高い調査をおこない、最適な改善策を講じて組織の改革につなげましょう。
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。









