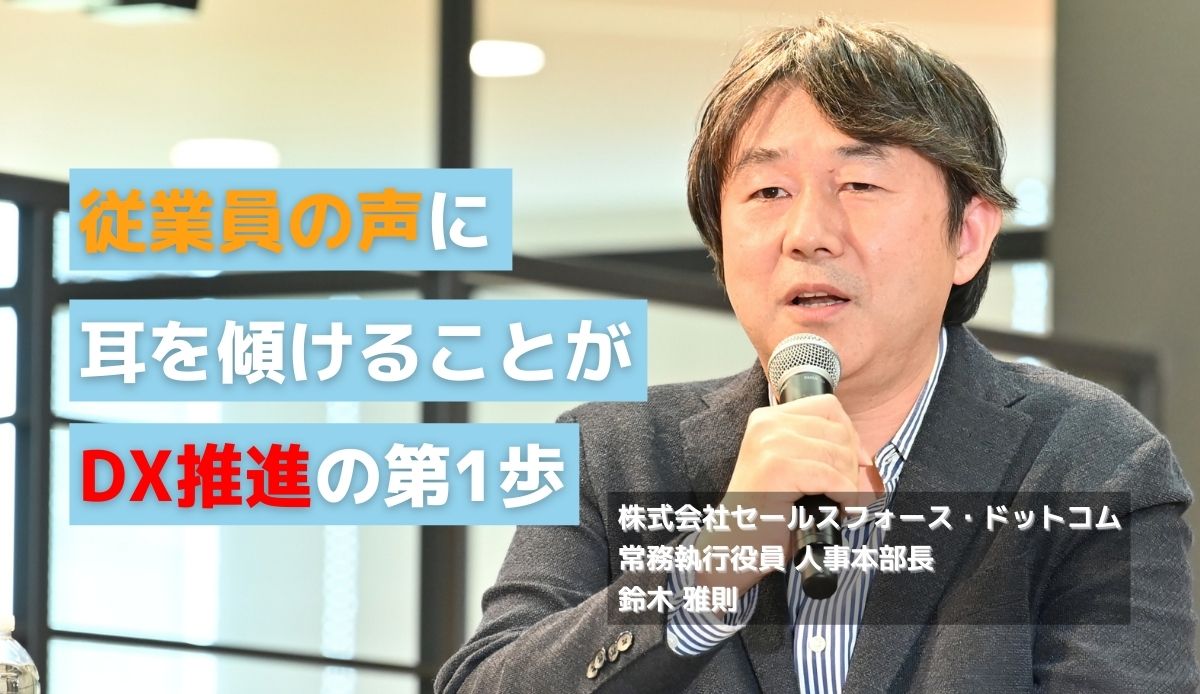
近年、人事領域でもさまざまなテクノロジーの普及が進んでいます。
しかし、「ツールを導入しただけで運用しきれていない」「なかなか社内のDXが進まない」と悩んでいる企業の人事担当者や経営者の方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回、複数の外資系企業で採用から人材開発まで担当し、現在はセールスフォース・ドットコム(以下、セールスフォース)で人事本部長を務める鈴木さんに、『人事領域でDX化を推し進める方法』についてお話を伺いました。
実際にセールスフォース内でも実践されている「人事×テクノロジー」の人事施策について、および社内のDX化における大切なマインドセットについて、事例とともにご紹介します。

【人物紹介】鈴木雅則|株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員 人事本部長
(米)コーネル大学院 人材マネジメント・組織行動学修士。2003-2011年の8年間、GEとGoogleにて採用・リーダーシップ開発業務などに携わる。2011年よりコンサルタントとして独立、執筆活動や企業向け研修などを行う。(著書:「リーダーは弱みを 見せろ」光文社新書)
2013年よりリクルーティングディレクターとしてQVCに入社後、米国本社にてグローバル人材開発チームをリード。帰国後はHRディレクターアジアを務める。その後BMWにて人事部長を経験後、2019年2月より現職。
目次
「人事×テクノロジー活用」セールスフォースでは、どのような施策を実践しているのか?

ーまず、セールスフォース様で実践されている「人事×テクノロジー活用」の施策について教えてください。

まず、当社がテクノロジーを活用した人事施策をおこなう上で大事にしている考え方について、ご紹介します。
大前提として、弊社ではテクノロジー活用のみに注力しているわけではありません。
その周囲にある従業員エンゲージメントの向上や組織カルチャーの構築についてバランスよく見ていくための手段として、テクノロジーを活用するべきであると考えています。
セールスフォースはCRMを提供する会社であり、これまでに多くのエンドユーザーとの信頼関係を構築してきました。
そして、このようなことに重きを置く中で、目指すべきビジネスモデルや会社の思想を成り立たせるためには、ハード面とソフト面が両立しなければならないという考えを根底に持っています。
そのため、セールスフォースの人事施策も、
- 「人事担当者のお客様は誰か?」と考えた際に、その中心にいるのは従業員である
- 従業員は、普段の生活で自社のシステムだけを使用しているのではなく、他社のサービスも活用している
- テクノロジーを活用して、いかにEX(従業員体験)を向上できるかが大事である
という考えのもと、様々な施策に落とし込んで実施するようにしています。
セールスフォースが実践する具体的な人事施策

セールスフォースがテクノロジーを活用して具体的に人事施策として実施していることは、様々ありますが、ここでは次の2つを紹介します。
②コンシェルジュ
それぞれ、具体的ににご紹介していきます。
①オンボーディングの自動化
セールスフォースでもテクノロジーの施策を実施する以前までは、入社手続や書類手配、コンプライアンス、IT関連の手続などに多くの時間を費やしていました。
せっかく入社いただいたにも関わらず、その入社前後の従業員体験があまり良い状態とは言えず、これは大きな課題であると考えていました。
そこで、Salesforce Marketing Cloud(オートメーションテクノロジー)等の自社製品を活用し、入社前の段階で「名前」「住所」「連絡先」といった基本的な情報から、「どのようなPCが欲しいか」「携帯は必要か」といった働く上で必要な情報までスムーズに収集することができるような仕組み作りを実施しました。
これにより、人事担当者の属人的な情報収集による質問漏れを防ぐこともでき、また、従業員が似たような書類に繰り返し住所や名前を記載する手間も削減することができました。
また、ジャーニーメールを年に20回ほどにわけて自動配信することで、必要なタイミングに従業員に適切な情報を届けることができるようになりました。
・入社3カ月頃に「もうすぐ目標達成に関する面談を実施します」といった通知を実施する
・適切なタイミングで「福利厚生の申込時期となりました」といった通知を送付する
など
入社直後の1日~2日で詰め込んでいた情報を体系的に分散して送付することで、1度に提供する情報量をコントロールした結果、メールの開封率は平均して90%となっています。
また、人事に対する新入・中途社員からの質問メール数も導入前と比べて約30%削減できています。
②コンシェルジュ
2つ目の「人事×テクノロジー」の取り組みとしては、自社サービスのコンシェルジュの活用事例があります。
コンシェルジュとは、管理画面の検索窓で会社や人事制度に関して気になる情報を検索すれば、いつでも欲しい情報を得られるサービスです。
Googleの検索と同じようなシンプルな検索窓で親しみやすく、検索した記事を読んだ後は、その情報が役立ったかどうか従業員視点で評価することができます。
記事に対する評価は、バックエンド側で蓄積されるため、コンシェルジュ内の記事内容や検索性の改善にもつながります。
また、どうしても検索した記事だけでは悩みが解決しなかった場合、チケットをあげて担当者に質問したり、対応を依頼したりすることも可能です。
一般的なイントラネットでは、情報を探すことに苦労したり、担当者がわからず社内やコールセンターなどあちこちに質問して、たらい回しにされたりするケースも多いことでしょう。
コンシェルジュは、このような社内の情報収集に関する非効率な体験を改善するためのものです。
テクノロジーの活用が、従業員エンゲージメントの向上に繋がるように

セールスフォースでは、この他にも従業員の声を拾い、施策につなげるために、年に2回、社員向けのアンケートを実施しています。
このアンケート結果は全社員に公開され、マネージャーやリーダーの名前ごとにスコアを検索したり、個別のスコアを体系的に分析したりして従業員のエンゲージメントを可視化できるようになっています。
これらのデータから、カルチャーやコアバリューの体現度を客観的に測り、人事施策を企画する際の参考にしています。
ーテクノロジーを活用した施策を実施する上で大事にしていることはありますか。
今回ご紹介した以外にも、数多くのテクノロジーツールを活用していますが、ここで伝えたいことは、私たちはデータドリブンでの意思決定を実行するためにテクノロジーを活用しているということです。
そして、これに加えて、社内外での言行不一致やコミュニケーションのギャップが起きないように注視している会社だとも思っています。
日々、新しいiPhoneのアプリがリリースされ、便利なサービスが世に溢れていくにも関わらず、企業と従業員とのコミュニケーションに使用するテクノロジーが進化しなければ、必然的に従業員の満足度は下がってしまいます。
特に、私たちはCRMという企業と顧客との信頼関係の構築を支援するテクノロジーを提供している会社であるので、社内も同等ないし、それ以上のテクノロジー活用を提供しなければならないと考えているのです。
そのため、テクノロジーを活用する際は、単なるデータの整理としてではなく、エンゲージメントの高い従業員がより自分らしく働くことのできる環境を整えることを目的として実施することを大事にしています。
いきなりテクノロジーを活用するのではなく、しっかり目標を設定して、会社と従業員の信頼関係がしっかり構築されている心理的安全性の高い職場づくりを意識することが重要だと考えています。
「なぜ日本企業ではなかなか進まないのか?」人事領域におけるDX化の現状

ー多くの外資系企業でのキャリアを持つ鈴木さんから見て、日本の人事領域におけるDX化の現状をどのように受け止めていますか。

海外と比較すると「日本企業の多くが人事領域のDX化が進んでいないのでは」という意見もあると思います。しかし、もちろん外資系企業の中でもDX化が進んでいない会社もあり、必ずしも日本企業に限った話ではないと考えています。
そもそも、テクノロジー活用を進めることは、企業にとってある意味では「投資」ですよね。
企業は、顧客がサービスを利用してくれた利益で成り立つので、お客様に提供する「サービス」のDXに投資することは、会社の利益に直結すると考え積極的になる場合が多いでしょう。
しかし、その一方で、従業員に対するDXには全く投資しない会社もあります。使いづらいイントラネットや勤怠管理システムなど、社内のシステムに還元せずにほったらかしのままのケースも少なくはないでしょう。
ーなぜ、多くの企業が社内のテクノロジー活用を推進することができないでいるのでしょうか?
表面上にある様々な課題を突き詰めていくと、結局は各企業のフィロソフィーの問題にたどり着くのではないかと思っています。
私たちセールスフォースでは、従業員に投資することでお客様へのサービスの質が高まると考えており、お客様向けのサービスへの投資と従業員向けの投資は両輪で動かすべきと考えているため、どちらか一方のDX化に取り組んでも意味がないと思っています。
そして、このようなカルチャーを持つ企業であれば、従業員に投資することは当たり前のこととして、テクノロジーの活用にも積極的になっているように思います。
しかし、実態として外側(顧客側)ばかりにフォーカスしている会社も多いのではないかと見ています。
ーそれでは、社内でのテクノロジーの活用や、従業員に還元するためのDXを推し進めるためには、どのようにすれば良いのでしょうか。
繰り返しになりますが、社内のDX化が進まない要因は、テクノロジーツールの機能面ではなく、社内カルチャーにあると考えています。
多くの人が活用しているSlackやGmailなどのツールはかなり使い勝手がいいですし、アレクサのような音声テクノロジーサービスや、SNSなどを全く使えない方は、あまりいないでしょう。
これだけ便利なテクノロジーがあるにも関わらず、社内で浸透しないのは、従業員の今までの働き方や考え方、マインドセットにボトルネックがあるのではないでしょうか。
もちろん、これだけ意識してテクノロジー活用を進めている私たちでさえ、従業員からお叱りの声を受けることがあります。日常的に、便利なテクノロジーに触れている従業員から見ると、会社の提供するシステムが全然物足りないと感じてしまうのです。
しかし、全てを従業員の求めるレベルで提供できなかったとしても、できるだけ寄り添って声を拾っていくのが大切でしょう。
人事領域のDXは「データ収集」と「目標設計」から

ー人事領域におけるDXを実践する場合、まず何から始めたらいいのでしょうか?

まずは、従業員の声に耳を傾けることが非常に大事だと思います。
セールスフォースでは、社内でのさまざまな意思決定をおこなうために、頻繫にアンケートを実施しています。最近のテーマとしては、たとえば「コロナ後の働き方」に関して声を集めました。
海外を含めて多様なバックグラウンドの方が働いているので、「週にどのくらい働きたいか」「オフィスを今後どのように活用したいのか」など複数の質問をしてデータを参照します。また、同時に実際の行動面もチェックするよう意識しています。
従業員の行動面を観察すると、この1年半の出社率は平均約3%ほどでした。
しかしアンケートの声を聞くと、「オフィスを完全になくすのはやめてほしい」「オフィスならではの従業員のつながり、コラボレーションが大事」という意見もあります。
このような事実ベースの行動とリアルな声をあわせて、意思決定の判断材料として確認することが大切です。
中には、「従業員サーベイをやっても、結局会社として何もできないから意味がない」といった意見もまれに耳にします。しかし、人事側から何もアクションをしないのではなく、上がってきた声について「今はこういった理由で実現できないが、このタイミングでは実行します」と丁寧に説明するだけでも随分違います。
「どうせできないから聞かない」ではなく、「しっかり声を拾って向き合い続ける」ことが重要です。
そして、決してトップダウンで意思決定はせず、定期的に声を拾い、行動データをとり、少しずつ検証を進めていくのが人事の役割だと考えています。
また、繰り返しになりますが、テクノロジーを実際に活用する前に、しっかりとした目標設定をすることも非常に重要です。
ただやみくもに「DX推進」を掲げるのではなく、テクノロジーを使ってどのような目標を達成するのか、テクノロジーを活用すると従業員の働き方はどう変わるのかなど、事前にしっかり明確化することが大事でしょう。
しっかり目的を捉え、テクノロジーを手段の1つと認識しないと失敗してしまうと思います。
ーデータやテクノロジーを活用して人事施策を実施する上で、人事に必要な知識やスタンスはありますか?
まず、人事部門の人間が、テクノロジーそのものへの理解を深める必要は確実にあります。
この10年~15年で人事職に求められる要素は大きく変化し、現代の人事には労務や事務処理を中心とした業務だけではなく、テクノロジーやデータを活用したマーケティング寄りの業務も必要になってきました。
人事業務をデータドリブンで進めることで、人事の側面からビジネスにどういったインパクトを与えることができるのか、よりビジネスに直結した視点が必要となっています。
そのため、人事畑で長年の実務経験をしてきた人だけでなく、ビジネスセンスがあってマーケティング知識やデータまわりの活用に長けていて、かつ従業員や組織に関心が強いタイプの人材のが活躍できる場が増えつつあります。
また、テクノロジーの活用は、これまで人事担当者の「勘」で業務を進めていた場合と異なり、「データ」をもとにした意思決定をすることができるようになりました。
たとえば「コロナ禍でどうしていくべきか」と働き方に関する議論があったときに、「恐らく現場のリーダーはこう考えているだろう」と勘で動き、トップダウンの人事施策を実施するのはかなり危険でしょう。
しかし、実際にアンケートを取ってみることで「ハイブリッド型で働きたい」「こういうときは在宅で働きたい」とさまざまな意見に触れることができます。
もちろん、勘は正しいこともありますが、間違う可能性もかなり高いはずです。環境変化が激しい中で、さまざまな角度からデータを取得し検証しない限り、これからの組織運営の成功は難しいと思います。
最後に
ーこれから人事領域でテクノロジーを活用していくことを考えている方々にメッセージをお願いします。

現在の日本にも優秀な人事担当者の方はたくさんいると思いますし、様々な外国企業の人事と交流をしていても、日本の人事担当者が他国より劣っていると感じたことは決してありません。
しかし、日本では集団の中で個人の力を上手く引き出せていない人事担当者が多くいるように思います。日本全体の風土として、場の空気を読み合ってしまう人が多いことも要因の1つでしょう。
せっかく優秀な人が集まっているのにも関わらず、組織という集団に入った途端に、空気を読み合い過ぎて、1人ひとりの個性が埋もれてしまうのは、非常にもったいないと思いますし、これからは、年齢にかかわらず、能力のある人材がきちんと発掘され、年功序列に依存せずに正しく評価されていく体制を作っていくことが重要ではないでしょうか。
セールスフォースでは、現在、全社一丸となってポストコロナの働き方であるハイブリッドワークを機能させることに注力をしており、どこからでも、柔軟に企業活動に参加して成果を出せるような環境づくり、そのためにテクノロジーの活用に取り組んでいこうと考えています。
ダイバーシティの考え方が世界的に広がり、働き方を含めた多様性が増す中で、組織に対する遠心力が高まるのは必然です。しかし、多様性、柔軟性を認める一方で、子育てや介護などの問題も発生してくるので、それぞれの細やかなケアも重要な課題となります。
多様性を追求しても、カルチャーや一体感が失われないようバランスをとりながら、セールスフォースならではの組織らしさを守っていきたいと思います。当社の事例が他の企業が変革を図る上での参考になればと思っています。







