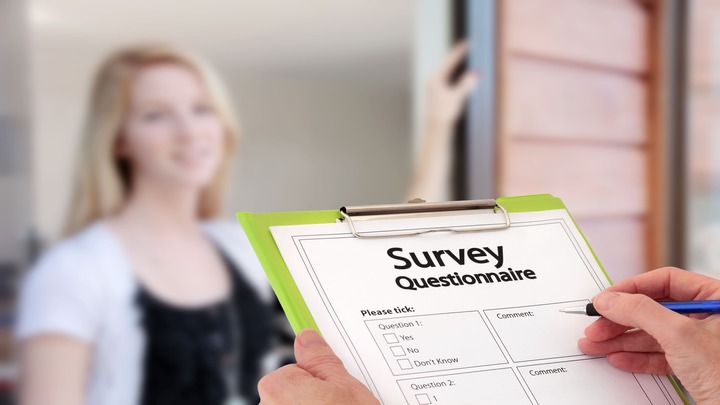 会社にとって従業員は大切な資源です。とくに少子高齢化が進み、働き手の減少が予想される今後は、従業員はより貴重な存在となるでしょう。しかし、会社の状況によって従業員が定着しない、従業員の生産性が低いといった課題が考えられます。従業員の定着率や生産性を向上させるために役立つのが、従業員サーベイです。
会社にとって従業員は大切な資源です。とくに少子高齢化が進み、働き手の減少が予想される今後は、従業員はより貴重な存在となるでしょう。しかし、会社の状況によって従業員が定着しない、従業員の生産性が低いといった課題が考えられます。従業員の定着率や生産性を向上させるために役立つのが、従業員サーベイです。
そこで今回は、従業員サーベイについて解説します。従業員サーベイの種類や実施方法について詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 従業員サーベイとは?
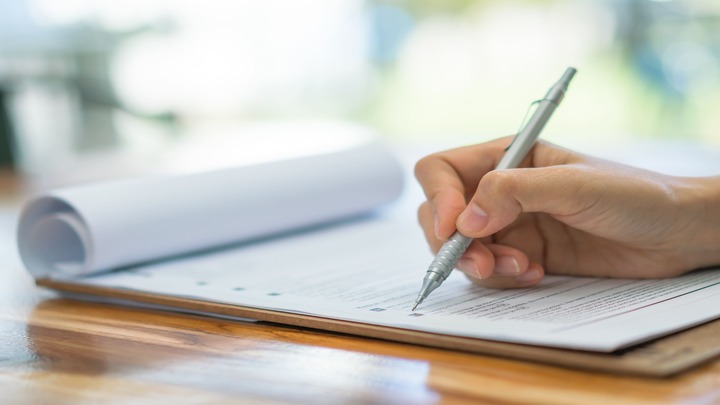
従業員サーベイとは、従業員が自分の勤務する会社に対して、どのように感じているかを総合的に測る調査です。具体的には、会社内の人間関係や環境などについての質問項目を用意して、従業員がどのように満足しているか、あるいは不満を抱いているかを確認します。
従業員サーベイを実施する前に、目的や一般的な調査項目を把握しておきましょう。
1-1. 従業員サーベイの目的
従業員サーベイを実施する大きな目的は組織の改善です。従業員サーベイを通して明らかになった課題を解決することで、従業員のモチベーション向上を図り、組織力を強化します。感覚的なヒアリングとは異なり、アンケート結果などをもとに現状を数値化して把握できるため、具体的な改善案を立てることができるでしょう。
優秀な人材の流出を防止することも従業員サーベイの目的のひとつです。多くの従業員が不満を抱いている点を改善すれば、転職を考える従業員を減らすことができます。その結果、無駄な採用コストを削減できるのはもちろん、自社のアピールポイントが増えるため新規の採用活動にも役立つでしょう。
1-2. 従業員サーベイにおける調査項目
従業員サーベイでは、会社に対する感じ方を包括的に調査します。具体的には、以下のような項目を準備しましょう。
- 勤務条件
- 職場環境
- 人間関係
- 給与・賞与
- 休暇
- 福利厚生
- やりがい
- 愛着
ただし、調査項目に関する絶対的なルールはありません。自社の目的に合わせて最適な調査項目を設定することが大切です。
1-3. 従業員サーベイの実施タイミング
従業員サーベイの実施タイミングは、目的や調査の方法などによって異なります。たとえば、長期的な目線で従業員の変化を把握したい場合は、1年に1回などのスパンで実施するとよいでしょう。
逆にリアルタイムで状況を把握したい場合は、1週間に1回、1カ月に1回という短いスパンで実施することも可能です。さまざまな調査方法があるため、目的を明確にしたうえで最適な方法を選択しましょう。
1-4. 従業員サーベイと従業員満足度調査の違い
従業員サーベイと似た言葉として、従業員満足度調査が挙げられます。従業員満足度調査とは、職場環境や労働条件に対する満足度を把握する調査のことです。
一方の従業員サーベイとは、従業員に対して実施する調査の総称であるため、従業員満足度調査より広い概念であるといえるでしょう。従業員サーベイでは、満足度だけではなく、仕事に対するやりがいや企業に対する愛着など、幅広い内容を調査します。
2. 従業員サーベイに注目が集まっている背景

従業員サーベイを実施する企業が増えてきた背景としては、以下のようなことが挙げられます。
2-1. 人材の確保が難しくなった
人材の流動化が進んだことにより、自社に人材を定着させることは企業の大きな課題となっています。優秀な人材の流出を防止しなければ、事業を継続的に発展させることはできません。
そこで従業員サーベイを実施して、従業員が感じている不満や組織の課題を把握し、環境改善に取り組む企業が増えてきたのです。さまざまな種類のサーベイを通して従業員のモチベーションやエンゲージメントを把握し、適切な対策を立てることで、優秀な人材の定着率を高めていきましょう。
2-2. 気軽に調査を実施できるようになった
気軽に調査を実施できるようになったことも、従業員サーベイをおこなう企業が増えた理由のひとつです。以前は紙のアンケートを作成して配布したり、従業員へ直接ヒアリングしたりするなど、調査の手間がかかっていました。
しかし現在は、オンラインで簡単に調査を実施できるツールも多く開発されているため、アンケートを配布したり回収したりする手間はかかりません。結果を自動的に集計し、グラフ化できるツールもあるため、うまく活用することで効率よく従業員の情報を把握できるでしょう。
2-3. 精度の高い調査が可能になった
精度の高い調査が可能になったことも、従業員サーベイが注目されている理由のひとつです。調査ツールを活用することで、回答率を高められるのはもちろん、簡単にデータを分析できるようにもなりました。専門知識がなくてもデータをさまざまな視点から分析できるため、従業員サーベイを実施する企業が増えてきたのです。
3. 従業員サーベイの種類

従業員サーベイの「サーベイ」とは、対象となる物事の全体像を把握するための調査のことです。ここでは、企業が取り組むべき従業員サーベイの種類を紹介します。
3-1. 従業員の意欲の引き上げが期待できる「モラールサーベイ」
モラールサーベイは、従業員が会社や組織の目標達成のために、どれだけ意欲をもって臨んでいるかを測ります。会社や組織が目標を達成するためには、従業員の意欲や積極性は欠かせません。そのため、モラールサーベイによって従業員の意欲を測り対策を講じることで、目標達成に必要な従業員の意欲引き上げが期待できます。意欲のある従業員は生産性が高く、さらに会社に定着する可能性も高いといえます。
3-2. 簡単なチェックを短期間に繰り返す「パルスサーベイ」
パルスサーベイは5分ほどで回答できる簡単な質問で、従業員の意識やどのような状態にあるかを把握します。パルスサーベイの特徴は実施するスパンです。エンゲージメントサーベイやモラールサーベイは年に1回もしくは数カ月に1回実施するのに対して、パルスサーベイは数日に1回、週に1回、月に1回といったように短いスパンで実施します。短期間でサーベイを実行することで、従業員の変化を少ないタイムラグで確認できます。
3-3. 従業員の自社への愛着を測る「エンゲージメントサーベイ」
エンゲージメントサーベイは、従業員が持つ自社への愛着や貢献する姿勢を測ります。従業員が自社に愛着や貢献しようとする姿勢を持っていれば、生産性の向上や離職率の低下につながります。エンゲージメントが低い場合は、従業員が愛着を持ってくれるよう、何らかの対策を講じなければなりません。
3-4. チーム全体の情報を集める「組織サーベイ」
組織サーベイとは、チーム全体の状況を把握するための調査です。チームに所属する従業員に対してアンケート調査を実施して、組織としての成果や課題などを探ります。組織サーベイを通して理想と現実のギャップを明確にすることで、適切な対策を立て、目標達成を図ることが可能です。
4. 従業員サーベイのメリット

従業員サーベイを実施することで、業務効率化や定着率の向上につながります。ここでは、従業員サーベイのメリットについて詳しく確認しておきましょう。
4-1. 会社が抱える課題を解決して業務を効率化できる
従業員サーベイによって従業員の意見を集めることで、従業員が感じている会社の問題点や課題を把握できます。結果をもとに解決策を講じることで、スムーズに課題を解決できるでしょう。
従業員が抱える問題が解消されることで、業務の効率化や生産性の向上につながります。
4-2. 従業員が納得して働ける環境をつくれる
従業員サーベイで得た意見をもとに、会社の方針や方向性を決められます。従業員の意見を反映することで、従業員が納得して働ける環境をつくることができるでしょう。従業員が納得して働ける環境があれば、離職率低下が期待でき、優秀な人材の流出を防げます。
4-3. 曖昧な情報を数値化して分析できる
従業員サーベイを実施することで、曖昧な情報を数値化して分析できます。従業員のモチベーションやエンゲージメントなどは目に見えにくいため、なかなか把握することができません。
そこで従業員サーベイを実施すれば、状況を数値化して把握できます。結果を簡単にグラフ化してくれるツールもあるため、分析の手間もかからないでしょう。
5. 従業員サーベイのデメリット
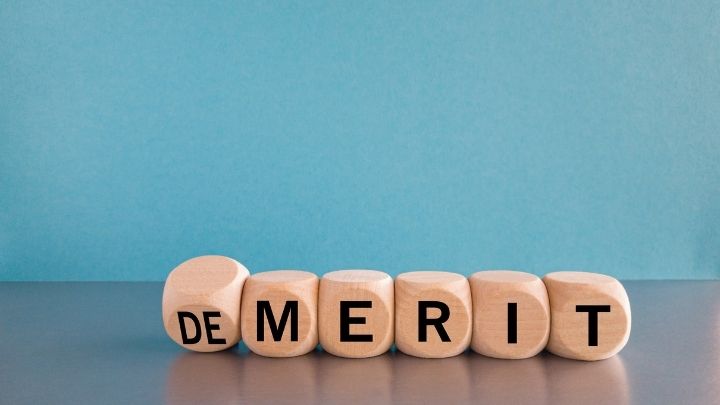
さまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあるため注意しましょう。
5-1. 実施にコストがかかる
従業員サーベイを実施するためには質問の作成や集計、分析に人的コストが発生してしまいます。さらには質問を回答する側である従業員の時間も割いてしまうため、生産性の低下が危惧されます。
5-2. 従業員の不信感が増大してしまう可能性がある
初めて従業員サーベイを実施するとなると、従業員は回答結果がどのように活用されるか不安になってしまうかもしれません。場合によっては自分の回答が他の従業員に伝わってしまうのではないか、という不安を感じる従業員もいるでしょう。
また、せっかく回答したのにも関わらず意見が反映されなければ、従業員の不信感増大につながってしまう恐れもあります。
5-3. 実施しすぎると現場が混乱する
従業員サーベイは、適切な頻度で実施するようにしましょう。あまりに頻繁に実施すると、回答する側の負担が増えるだけではなく、集計や分析の手間もかかってしまいます。集計・分析すべき情報が多すぎて混乱する可能性もあるでしょう。従業員サーベイを実施するなら、実施する頻度とタイミングをしっかりと検討することが重要です。
また、いざ従業員サーベイを策定しようと考えても、何から初めて良いかわからず困っている方も多いでしょう。そのような方に向けて当サイトでは「従業員満足度のハンドブック」という資料を無料配布しております。本資料では、そもそものサーベイの種類や、サーベイの策定から調査、運用までこれひとつですべて学べる資料になっています。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
6. 従業員サーベイを実施するときの流れ

従業員サーベイを実施するときは、以下のような流れで進めましょう。
6-1. 質問項目を検討する
従業員サーベイを実施するときは、質問項目を決める必要があります。ただし、適当に質問項目を決めると、求める回答を得られなかったり、組織の課題を正確に把握できなかったりするため注意しなければなりません。
まずは従業員サーベイを実施する目的を明確にしたうえで、質問項目を決めることが大切です。従業員のモチベーションを把握したい、労働条件や職場環境に対する不満を確認したいなど、調査の目的に合わせて質問内容を決定しましょう。
6-2. アンケートを配布して意見を集める
質問項目が準備できたら、従業員へアンケートを配布しましょう。紙のアンケート用紙を配布する方法もありますが、オンラインでアンケートを実施できるシステムを利用するのもおすすめです。システムを活用すれば、ペーパーレス化を図れるのはもちろん、配布・回収や集計の手間を省くことができます。
また、アンケートの回収率を高めるためには、回答期日を設け、定期的にリマインドすることが大切です。忙しくてアンケートに答えるのを忘れているケースもあるため、上司やチームリーダーから呼びかけてもらうとよいでしょう。
6-3. アンケート結果をもとに課題を把握する
アンケートを回収したら、結果を集計して分析することが重要です。また、過去のデータと比較することで、従業員の満足度やモチベーションがどのように変化しているかを把握できます。
さらに、アンケート結果から課題を抽出し、解決策を検討しましょう。今まで実施してきた対策で問題ないのか、新しい対応策を立案すべきなのか、できる限り早い段階で決定して次のプロセスへ進むことが大切です。
7. 従業員サーベイツールとは?

従業員サーベイツールとは、働き方や職場環境に関する調査を実施するためのツールです。さまざまな質問内容を作成して配信することで、従業員の状況を的確に把握できます。従業員サーベイツールを活用することには、以下のようなメリットがあります。
7-1. 配布や集計を効率化できる
従業員サーベイツールを活用することで、アンケートを作成して配布したり、回収して集計したりする手間を削減できます。システム上で質問を作成できるのはもちろん、従業員もシステム上で簡単に回答することが可能です。回答する側も集計する側も楽に作業できるため、効率よく調査を実施できるでしょう。
7-2. ペーパーレス化を実現できる
ペーパーレス化を実現できることも従業員サーベイツールのメリットです。紙のアンケート用紙を準備する必要がなくなるため、印刷代を削減できます。また、アンケート用紙を回収する手間がなくなる、用紙を保管するスペースが不要になるなどのメリットもあります。
8. 従業員サーベイを実施するときの注意点

従業員サーベイは従業員からの回答が集まらなければ、効果が期待できません。従業員からの回答を集めるためには、従業員サーベイ実施の目的や情報の取り扱いについて事前に伝えておきましょう。また、従業員サーベイの精度を高めるために質問内容も十分な検討が必要です。
8-1. 従業員サーベイ実施の目的を伝えておく
従業員サーベイを実施するときは「なぜ実施するか」という目的を伝えておきましょう。従業員に目的も伝えずに質問への回答を依頼してしまうと、不信感を抱かれるかもしれません。
従業員の不信感を和らげるためには、知り得た情報の取り扱いについても伝えておくことが大切です。従業員サーベイのためにしか使用せず、閲覧者も限られていることを伝えることで、従業員の不安をさらに緩和できます。
8-2. 従業員が回答しやすくする
従業員が回答しやすくするような質問にすることも重要です。記述式のアンケートにすると、回答を考えたり記載したりすることが面倒に感じられ、うまく回答が集まらないケースもあります。選択式の質問にするなど、できる限り簡単に回答できるように配慮しましょう。
8-3. 従業員サーベイの対象とする従業員に網羅性をもたせる
従業員サーベイは、多くの従業員を対象とする必要があります。たとえば正社員だけを対象とする、管理職だけを対象とするといったように、対象を限定してしまうと正確な結果が集められません。対象を限定すると、上がってくる回答も限定的になってしまうため、対象となっていない従業員の課題や問題点を解決できないでしょう。
8-4. 質問は現状の課題に則した内容にする
従業員サーベイで用いる質問は、現状の課題に則した内容にします。一般的な質問だけでは、自社の問題点や課題の解消にはつながりづらいでしょう。自社の問題点や課題に則した仮説を立てて、質問を用意することが大切です。
8-5. 回答結果を分析して施策を講じる
従業員サーベイは、質問に回答してもらうだけでは問題解決につながりません。従業員の回答を分析して、課題や問題解消のための施策を講じることで、従業員の生産性や定着率向上につながります。
施策を講じないことは、従業員の生産性や定着率が向上しないだけではありません。何も施策が講じられないと、時間を割いて回答した従業員が不信感を抱いてしまう恐れがあります。従業員が不信感を抱いてしまうと生産性や定着率の向上ではなく、低下につながりかねません。
8-6. 分析結果を公表する
分析結果を従業員へ公表することも大切です。結果を非公開にしたり、改善策を検討しなかったりすると、次の調査に協力する気持ちが失われてしまいます。継続的な調査を実施するためにも、結果を公表するようにしましょう。
9. 従業員サーベイを活用して生産性や定着率の向上につなげよう

従業員サーベイを実施することで、従業員の会社に対する満足度やモチベーションを数値化できます。この結果で明らかになった課題や問題に対する施策を講じることで、従業員が働きやすい環境を整えることが可能です。その結果、従業員の生産性や定着率の向上につながります。
従業員サーベイを実施する際は、従業員に実施の目的や情報の管理方法を伝えるのに加えて、多くの従業員を対象としましょう。また、質問は自社の問題点や課題に則した内容にすることが大切です。従業員サーベイ実施のポイントを押さえて、従業員の生産性、定着率向上につなげましょう。
人材不足が課題の昨今、職場定着率の低さ・若年層の早期退職は深刻な問題です。
このようなケースに該当する企業において、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
この解決方法として、職場改善を目的とした従業員のモチベーション管理の仕組みを積極的に取り入れる企業が増えており、従業員満足度の調査ツールが注目を集めています。
当サイトでは、「モチベーション管理において、まず何から始めていいのかわからない」「具体的にどのような分析・活用をすべきなのか知りたい」という人事担当者の方に向けて「従業員満足度調査のハンドブック」を無料配布しています。
ツールの選び方から調査方法、結果の活用方法までわかりやすく解説していますので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方はこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。









