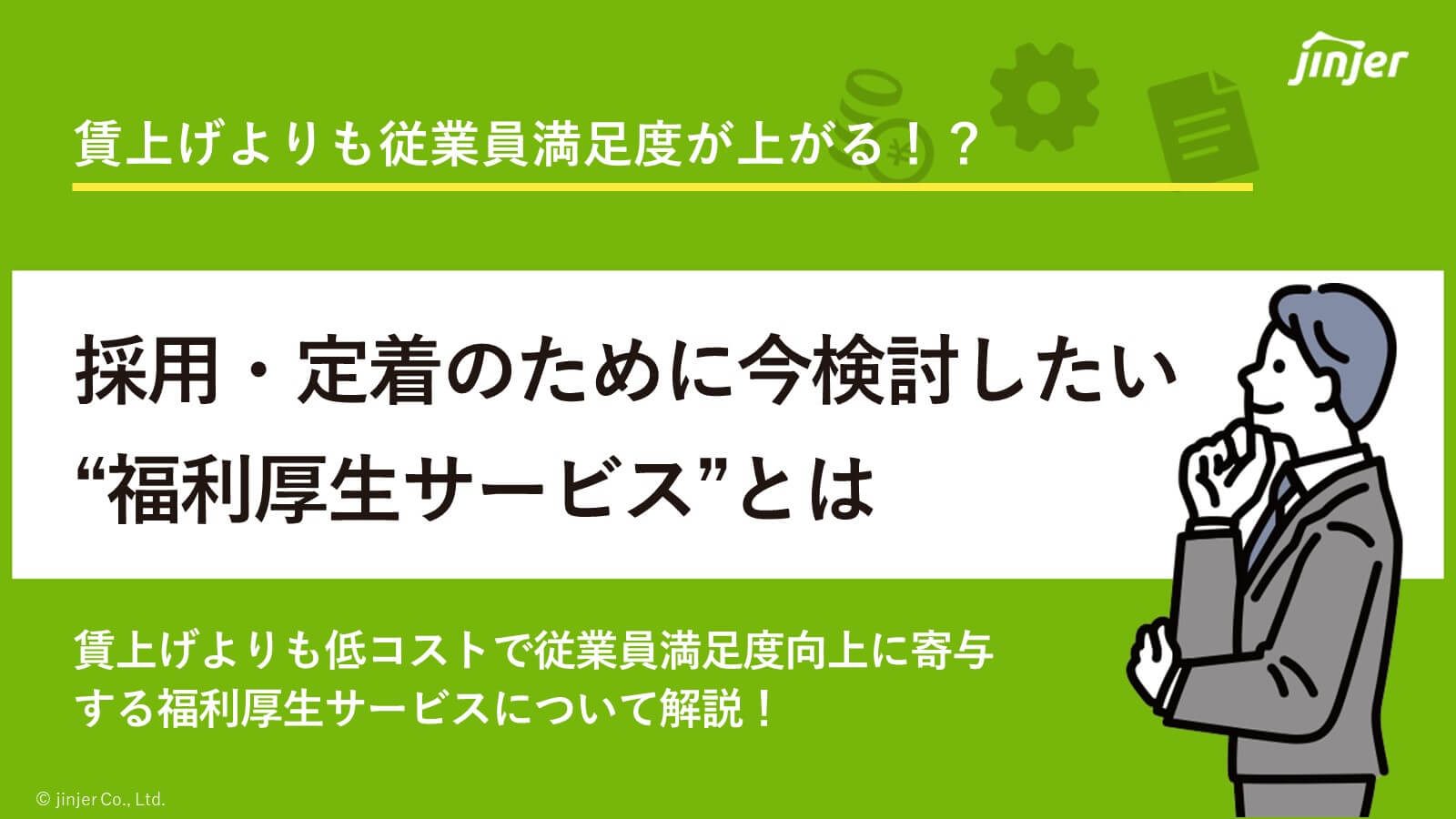「ベースアップを実施している企業の現状を知りたい」とお考えの方も多いでしょう。ベースアップとは、労働組合と経営側との交渉を通じて基本給を一律に引き上げることです。
役職や勤続年数に関係なく全社員に適用されるのが特徴で、物価上昇への対応と従業員のモチベーションアップが主な目的です。本記事では、ベースアップの基本的な概要や、ベースアップ率の計算方法について解説します。実施する際の注意点も紹介しているので、ベースアップを検討している場合はぜひ参考にしてください。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. ベースアップとは

ベースアップとは、会社全体の賃金水準を一律に増額することです。「ベア」とも呼ばれており、基本給などをベースに全社員の賃金が一律でアップします。
役職や勤務年数、成績に関係なく、全社員に適用されるのが特徴です。一般的には春季闘争といわれる、労働組合が毎年春に実施する賃上げ要求を中心とする闘争にてベースアップを交渉します。
一定の金額をアップする、一定の割合で増額するなど、いくつかの方法があります。具体的な方法については、後ほど詳しく解説しますのでチェックしておきましょう。
1-1. ベースアップを実施する目的
社員に対して経営者がベースアップを実施する目的は、以下の通りです。
- 社員の生活水準を担保するため
- 社員のモチベーションアップさせるため
- ベースアップが導入されていることをPRして採用力を強化するため
ベースアップの実施は法律で決められているわけではないため、実施するかどうかは企業に委ねられます。昇給額も企業で自由に設定可能です。
春季闘争の内容や業績などを考慮しながら、ベースアップを実施するかどうか慎重に判断しましょう。
2. ベースアップと定期昇給との違い

ベースアップと定期昇給の違いは以下の通りです。
|
ベースアップ |
定期昇給 |
|
・全社員の賃金水準を一律に引き上げる ・年齢や成績、勤続年数関係なく、会社の成果などに応じて全社員の給与を一律で増額する仕組み |
・勤続年数や成績に応じて一定のタイミングで昇給する ・個人の年齢や勤続年数、仕事の業績に応じて昇給する仕組み |
ベースアップと定期昇給の大きな違いは、昇給の対象が会社全体になるか個人になるかです。ベースアップは会社全体で賃金を一律に底上げします。一方で定期昇給は、個人の成果や勤続年数によって賃金がアップする仕組みです。
定期昇給は個人の評価で決まるので、必ずしも昇給されるわけではありません。ベースアップは、年齢や成績、勤続年数関係なく必ず増額します。
2-1. ベースアップと賃上げの違い
ベースアップと似た言葉として「賃上げ」がありますが、両者の意味は異なります。賃上げとは、社員に支払う賃金を引き上げることです。つまり、ベースアップや定期昇給は、賃上げの方法のひとつといえるでしょう。
2-2. ベースアップと賞与の違い
賞与とは、会社の業績や社員の成果などに応じて、臨時的に支給するものです。支給するかどうかは状況によって異なり、その額も毎回変動するケースが多いでしょう。
ベースアップは毎月の給与を一律で増額することであるため、賞与とは異なります。ただし、賞与額を「給与の3カ月分」などと設定している場合は、ベースアップによって賞与額が増えるケースもあります。
3. ベースアップを実施している企業の現状

労働組合との交渉を経て、8割以上の企業が賃上げを実施しています。人材確保や社員の待遇改善のために、賃上げの実施を避けられないのが現状です。
産業別に見た実施率は以下のようになりました。
- 製造業:89.6%
- 運輸業:88.9%
- 建設業:88.6%
- 卸売業:87.7%
- 農・林・漁・鉱業:85.9%
- 金融・保険業:82.6%
- 小売業:80.4%
- 情報通信業:72.1%
- 不動産業:62.9%
多くの業界で8割以上の実施率を記録したのに対し、不動産業における実施率は約6割という結果になりました。業界によって、ベースアップの実施率は大きく異なることがわかります。
また、賃上げを実現している企業のほとんどが大手です。資本金が1億円以下の中小企業は、賃上げは難しいと回答している企業も多く存在しています。
ベースアップを実施している企業は増加傾向にありますが、中小企業を中心に賃上げを実現できない企業も存在するのが実情です。
参考:2024年度の「賃上げ」率 最多は「5%以上6%未満」 実施率は84.2%、中小企業は「賃上げ疲れ」も|株式会社東京商工リサーチ
3-1. ベースアップを実施するかどうかは景気による
ベースアップを実施するかどうかは、会社の業績だけではなく、業界全体の景気にもよります。高度経済成長期には多くの企業が積極的にベースアップを実施していましたが、2000年以降はデフレのためにベースアップを見送る企業が増えました。
ベースアップを実施すると残業手当や保険料なども増えてしまうため、企業の負担も大きくなってしまいます。社員の待遇を改善したいと思っていても、実際のところベースアップを実施するのが難しい企業も多いのです。
3-2. 管理職もベースアップの対象になる
管理職もベースアップの対象になります。厚生労働省の調査によると、管理職に対して「ベアを行った・行う」と回答した企業の割合は47.0%でした。一方、一般職に対して「ベアを行った・行う」と回答した企業の割合は52.1%でした。
一般職の実施割合よりは低いものの、約5割の企業は管理職もベースアップの対象としていることがわかります。
参考:令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況|厚生労働省
4. ベースアップの2つの種類

ベースアップの種類には、以下の2つがあります。
- 一定の金額
- 一定の割合
それぞれ社員の給与に与える影響が異なります。ベースアップを検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
4-1. 一定の金額
ベースアップには一定の金額を支給する方法があります。基本給に対して、全員に同じ金額を上乗せする方法です。
一定の金額を支給するケースでは、給与が高い人は昇給率が下がり、低い人は高くなります。
たとえば、一定の金額2万円を一律で支給した際の、昇給後の給与は以下の通りです。
- 基本給25万円の場合:25万円 + 2万円 = 27万円
- 基本給50万円の場合:50万円 + 2万円 = 52万円
勤続年数や役職など、ベースとなる基本給は社員によって異なります。しかし昇給額は同じになるため、給与が低い人と高い人の格差が大きくなりにくいです。
4-2. 一定の割合
一定の割合で昇給するベースアップ方法もあります。一定の割合での昇給は、基本給に昇給率を乗じて計算する方法です。
たとえば、一定の割合7%が一律で適用されたケースでは、昇給後の賃金は以下のようになります。
- 基本給25万円の場合:25万円 × 1.07 = 26万7,500円
- 基本給50万円の場合:50万円 × 1.07 = 53万5,000円
基本給25万と50万円では、昇給額に1万7,500円の差がありました。一定の割合でのベースアップは賃金が高い人の昇給率が高くなるため、低い人との差が大きくなりやすいのが特徴です。
5. ベースアップの実施方法

ベースアップを実施する際は、賃金表の改訂をおこないます。賃金表とは、勤続年数や等級ごとに給与を記載した表のことです。
ベースアップを実施するときは、賃金表に記載されている基本給をもとに、昇給額もしくは昇給率を反映します。賃金表には、ベースアップによって上がった基本給を記載しましょう。
賃金表を改訂すると就業規則や労働協約が変更になります。変更の際には、過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。
また、所轄の労働基準監督に変更の旨を届け出る必要もあります。さらに、ベースアップにより基本給の額が変更したことを社員に周知しましょう。
6. ベースアップ率の計算方法

ベースアップ率の計算方法は以下の通りです。
昇給額 ÷ 基本給 = ベースアップ率
たとえば月給50万円で、昇給額が2万円だったケースでのベースアップ率は以下の通りです。
2万円 ÷ 50万円 = 0.04(4%)
逆に、ベースアップ率から昇給額を求めたい場合は以下のように計算しましょう。
- 月給30万円の場合:30万円 × 0.04 = 1.2万円
- 月給50万円の場合:50万円 × 0.04 = 2万円
ベースアップで重要なのは、昇給額ではなく昇給率です。年々昇給率が伸びていれば、企業の将来性や成長率もアップしているといえるでしょう。
昇給率が低いままだと、勤続年数が長くても賃金が上がりにくいため、社員の離職につながります。ベースアップ率を算出して把握することで、企業の将来性や事業内容を考え直すきっかけになるでしょう。
7. ベースアップを実施する際の4つの注意点

ベースアップを実施する際は、以下のような点に注意しましょう。
- 実施するかどうか慎重に判断する
- 経営方針と一致させる
- 同一労働同一賃金を意識する
- 賃金を引き上げる際は社員の同意が必要になる
ベースアップを実施する前に必ず目を通しておきましょう。
7-1. 実施するかどうか慎重に判断する
ベースアップを実施するかどうかは、慎重に判断しましょう。一律に給与水準が上がり、人件費が大幅に増えるためです。
ベースアップの実施は、会社の義務ではありません。業績が悪かったり赤字になる可能性があったりした場合は、実施を見送る判断も必要です。
またベースアップは、結果を出している社員も出していない社員も同様にベースアップするため、不満が出る可能性があります。
新卒社員の基本給をベースアップするケースでは、既存の社員の基本給を上回らないように配慮も必要です。会社の状況や同業者の動向を把握して、実施するかどうかを慎重に判断しましょう。
7-2. 経営方針と一致させる
ベースアップを実施するときは、経営方針と一致させることが重要です。将来的に事業をどのように展開していくか、どのように人材を確保していくかなど、さまざまな視点からベースアップ実施の是非を検討しましょう。
経営方針によっては、ベースアップではなく、他の対応が適切な場合もあります。定期昇給や賞与の支給なども含め、さまざまな選択肢のなかから最適な方法を選びましょう。
7-3. 同一労働同一賃金を意識する
ベースアップを実施するときは、同一労働同一賃金を意識しなければなりません。同一労働同一賃金とは、同じ内容の仕事をしているなら、雇用形態に関わらず、同じ待遇にすべきという考え方です。
正社員のみを対象としてベースアップを実施することもあるかもしれませんが、契約社員も同じ内容の仕事をしている場合は、同様にベースアップを検討すべきでしょう。不合理な待遇差をなくすよう、企業には仕組みを改善することが求められています。
7-4. 賃金を引き下げる際は社員の同意が必要になる
ベースアップを実施した後に、賃金の引き下げを検討する場合は社員の同意が必要です。賃金の引き下げは労働条件の不利益変更に該当するため、すべての労働者から個別に同意を得なければなりません。
労働条件の不利益変更とは、給与などの労働条件を社員にとって不利な内容に変更することです。基本的に会社は一方的に変更できません。
しかし労働者が受ける不利益の程度や変更する必要性があるケースでは、合理的な変更とみなされる場合もあります。
すべての社員から賃金引き下げの同意を得るのは、簡単なことではありません。会社はベースアップの実施について、慎重に判断する必要があります。
8. ベースアップを実施して待遇を改善しよう!

今回は、ベースアップの意味や目的、実施方法などについて解説しました。ベースアップを実施すると、社員のモチベーションアップや定着率の向上を期待できますが、社員の給与が一律に増加するため企業の負担は大きくなります。一度引き上げた賃金を下げることは難しいため、ベースアップを実施するかどうかは慎重に判断しなければなりません。経営方針や企業の業績なども考慮しながら、他の方法も含めてしっかりと検討しましょう。
また、実際にベースアップをおこなう際は、賃金表の改訂をおこないます。賃金表に記載されている基本給を確認して、昇給額や昇給率を反映させましょう。正しい方法でベースアップを実施して、社員の待遇を改善していくことが大切です。
福利厚生を充実させることは採用・定着にもつながるため重要ですが、よく手段としてとられる賃上げよりも低コストで従業員満足度をあげられる福利厚生サービスがあることをご存知でしょうか。
当サイトでは、賃上げが従業員満足度の向上につながりにくい理由や、低コストで始められる福利厚生サービスがどのようなものかを解説した資料を無料で配布しております。
限られた予算で福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めたい方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。